VIDEO
2023年4月11日 公開 ChatGPTは教育の敵か、味方か?
2023年、最も注目を集めるのは生成AI「ChatGPT」です。調査、分析、作文などビジネスシーンで活用されるChatGPTですが、教育現場での活用も期待されています。しかし米国ではChatGPTに対して「学校教育が機能しなくなる」と危惧しする声が多く、すでに一部の学校では学生に利用を制限しているほどです。
子どもの思考力の低下や有害な情報の提供などさまざまなリスクが懸念されていますが、これからのデジタル教育について考えた時、ChatGPTは我々にとって敵なのか、味方なのか?子どもたちの教育はどう変わるべきか?専門家と有識者を交え、徹底討論します。
<ゲスト>
宮田裕章(慶応義塾大学医学部 教授)
大柴行人(Robust Intelligence 共同創業者)
中室牧子 (教育経済学者/慶應義塾大学総合政策学部 教授)
佐藤亮子(子ども4人を全員東大理Ⅲに合格させたスーパーママ)
子どもの思考力の低下や有害な情報の提供などさまざまなリスクが懸念されていますが、これからのデジタル教育について考えた時、ChatGPTは我々にとって敵なのか、味方なのか?子どもたちの教育はどう変わるべきか?専門家と有識者を交え、徹底討論します。
<ゲスト>
宮田裕章(慶応義塾大学医学部 教授)
大柴行人(Robust Intelligence 共同創業者)
中室牧子 (教育経済学者/慶應義塾大学総合政策学部 教授)
佐藤亮子(子ども4人を全員東大理Ⅲに合格させたスーパーママ)
出演者:
人気 Picker
AIと教育の議論って、How toの話が先に進みがちなのですが、そもそもの社会変化・求める人材像の変化・基礎学力の定義の変化あたりが本質と考えています。
古い社会観・人材観・能力観でAI☓教育を考えると、AIって邪魔者なんですよね。これまでの教育システム(特に評価)が機能しなくなるからです。
途中で佐藤ママの意見に対して、宮田先生が今の受験にとってはChatGPTは敵と言ってるあたりの議論ですね。
既存の教育を変えずにChatGPT にどう活用するかではなく、ChatGPTはじめAI前提の社会の中で教育がどう変わるのか。そこを議論したいですね。
次回あれば是非呼んでください笑
古い社会観・人材観・能力観でAI☓教育を考えると、AIって邪魔者なんですよね。これまでの教育システム(特に評価)が機能しなくなるからです。
途中で佐藤ママの意見に対して、宮田先生が今の受験にとってはChatGPTは敵と言ってるあたりの議論ですね。
既存の教育を変えずにChatGPT にどう活用するかではなく、ChatGPTはじめAI前提の社会の中で教育がどう変わるのか。そこを議論したいですね。
次回あれば是非呼んでください笑
- いいね14
昨今何かと話題になっているchatGPTですが、こう言った議論も刻一刻とテクノロジーの発展によって変貌を遂げ続けています。
大学で今自然言語処理を学習しており、こう言ったものを学習し再現していく試みも個人的にはとても面白く感じていますが、最近の発展の速度には驚かされることばかりです。1ヶ月以上前の論文でさえ、もう「古い論文」として捉えられてしまうなど、他の分野でなかなか例を見ないのではないでしょうか。
大学で今自然言語処理を学習しており、こう言ったものを学習し再現していく試みも個人的にはとても面白く感じていますが、最近の発展の速度には驚かされることばかりです。1ヶ月以上前の論文でさえ、もう「古い論文」として捉えられてしまうなど、他の分野でなかなか例を見ないのではないでしょうか。
- いいね22
こういう新しい道具が出てきた時に、遠ざける、害がないか様子を見るというのは、毎回見られる対応ですが、子供を完全に隔離するなんてことは本当にそんなことが現実的に可能なのでしょうか?家族だけで無人島で暮らすんですかね?
番組の議論のように国内外の一部の大学が既に方針を出しているように、使い方や、活用方法、利用して作ったものの取り扱いを決めていくことが重要かと思います。
ITテクノロジーの害みたいなことはしばしばクローズアップされますが、今の子供の方が世界中で起こっていることをタイムリーに理解していますし、より多くのことを知っていますし、自分の意見を発表したり表現したりする能力も高く、よりレベルが高い教育を受けているように思います。その辺りは、無駄に手書きの書類の作成に時間がかかったり、情報の送受信に膨大な時間をかけていた時代と比べて生産性が上がっているビジネスと同じでIT技術の進歩のデメリットを探して導入を遅らせることは迷信に近い妄想と言っても良いと思います。
そもそも、「子供を大学に合格させた」って親側のブランドや教育に関するオーソリティーになるんですかね?そもそも大学に受かった時点では何かを成し遂げたには程遠いですし、大前提として、大学生になるにあたって親の影響は小さいのではないでしょうか。大学生になるまで親がかりというのは子供が自立していないということなのではと逆に心配になります。
番組の議論のように国内外の一部の大学が既に方針を出しているように、使い方や、活用方法、利用して作ったものの取り扱いを決めていくことが重要かと思います。
ITテクノロジーの害みたいなことはしばしばクローズアップされますが、今の子供の方が世界中で起こっていることをタイムリーに理解していますし、より多くのことを知っていますし、自分の意見を発表したり表現したりする能力も高く、よりレベルが高い教育を受けているように思います。その辺りは、無駄に手書きの書類の作成に時間がかかったり、情報の送受信に膨大な時間をかけていた時代と比べて生産性が上がっているビジネスと同じでIT技術の進歩のデメリットを探して導入を遅らせることは迷信に近い妄想と言っても良いと思います。
そもそも、「子供を大学に合格させた」って親側のブランドや教育に関するオーソリティーになるんですかね?そもそも大学に受かった時点では何かを成し遂げたには程遠いですし、大前提として、大学生になるにあたって親の影響は小さいのではないでしょうか。大学生になるまで親がかりというのは子供が自立していないということなのではと逆に心配になります。
- いいね15
考えないといけないことが多々あるなと感じました。
コロナ禍にNPと出会って、このままではまずい、勉強、学び直しせねば、と思い、個人授業を受けたり、自身で書籍を買い読み漁り、YouTubeを倍速で観て、今があるのですが、特に書籍を読む時に感じる感動、納得、うなづき、なるほどと独り言を言う動作が失われる可能性があるな、と感じました。感性、琴線、そういった「ヒト」独自のアナログですが、胸が熱くなる瞬間が、時短、圧縮、要約などで失われるのは改めてどうなんだろうか、と考えさせられました。教育のシーンでは取り扱い注意ですし、逆にますます人らしさが問われる時代になるのかなとも思いました。貴重な回でした、できるだけあらゆる世代に人に観ていただきたいですし、そこからどう向き合っていくべきかというこれからの倫理面においても考えさせられました。
コロナ禍にNPと出会って、このままではまずい、勉強、学び直しせねば、と思い、個人授業を受けたり、自身で書籍を買い読み漁り、YouTubeを倍速で観て、今があるのですが、特に書籍を読む時に感じる感動、納得、うなづき、なるほどと独り言を言う動作が失われる可能性があるな、と感じました。感性、琴線、そういった「ヒト」独自のアナログですが、胸が熱くなる瞬間が、時短、圧縮、要約などで失われるのは改めてどうなんだろうか、と考えさせられました。教育のシーンでは取り扱い注意ですし、逆にますます人らしさが問われる時代になるのかなとも思いました。貴重な回でした、できるだけあらゆる世代に人に観ていただきたいですし、そこからどう向き合っていくべきかというこれからの倫理面においても考えさせられました。
- いいね11
ChatGPTはテストの形を大きく変えるが、最終的には口頭審問になるのでは?との意見がありましたが、頭に詰め込んだ情報でいかに戦えるか?という旧来の価値観の延長なので、アイディアとしては実現しないのではと思います。
良くも悪くもこれからはAIをいかに使いこなして前に進むかが仕事でも重要です。
学生の論文はChatGTPで楽になり知的レベルを測り辛くなった話が出てきましたが、机上の調査やあるべき論の精査は数日くらいでまとめることができるようになるので、その結論を実社会でどの程度、どう試して、どの程度の社会へ良い影響を及ぼせたかを定量的・定性的に示すような形にすべきでは?と思いました。
現時点でのChatGPTの欠点の一つは、体や感覚器官がないことなので、論より証拠で、机上の話を実行する部分のスピード感やアグレッシブさ(影響力のある人・キーマンとの人間関係の作り方)など、今まであまり求められなかった部分をはかる試験にすると、いいのではないでしょうか。
今回の論客がどの程度、社会人代表と言えるのか?はやや疑問が残りますが、AIがいる世界で社会人生活を送る中では、ルーティンワークはAIに任せ、実行過程のスピード感や人間関係構築スキルは役に立ちますし、先生としても評価できない問題をクリアでき、社会もどんどん好回転していくように思います。
良くも悪くもこれからはAIをいかに使いこなして前に進むかが仕事でも重要です。
学生の論文はChatGTPで楽になり知的レベルを測り辛くなった話が出てきましたが、机上の調査やあるべき論の精査は数日くらいでまとめることができるようになるので、その結論を実社会でどの程度、どう試して、どの程度の社会へ良い影響を及ぼせたかを定量的・定性的に示すような形にすべきでは?と思いました。
現時点でのChatGPTの欠点の一つは、体や感覚器官がないことなので、論より証拠で、机上の話を実行する部分のスピード感やアグレッシブさ(影響力のある人・キーマンとの人間関係の作り方)など、今まであまり求められなかった部分をはかる試験にすると、いいのではないでしょうか。
今回の論客がどの程度、社会人代表と言えるのか?はやや疑問が残りますが、AIがいる世界で社会人生活を送る中では、ルーティンワークはAIに任せ、実行過程のスピード感や人間関係構築スキルは役に立ちますし、先生としても評価できない問題をクリアでき、社会もどんどん好回転していくように思います。
- いいね3
基本的には、「触ってもいいけど使い方を考えろ」が現時点での着地点かと思います。本学でも注意は出されてますが、その流れにはなってます。
https://www.uec.ac.jp/news/announcement/2023/20230421_5328.html
一律禁止は「使わければ問題起きない」という思考停止になってる気もします。かつてのスマホ、携帯、インターネット、バイクと同じ扱いかな。
https://www.uec.ac.jp/news/announcement/2023/20230421_5328.html
一律禁止は「使わければ問題起きない」という思考停止になってる気もします。かつてのスマホ、携帯、インターネット、バイクと同じ扱いかな。
- いいね1


 オリジナル動画・記事が見放題
オリジナル動画・記事が見放題




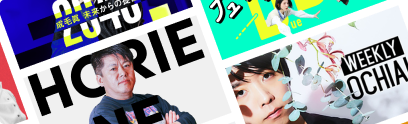



























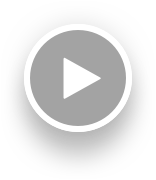

























ライブコメントを表示