ホーム
9フォロー
176フォロワー
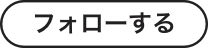
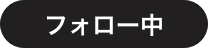
国立大の財務状況「もう限界です」 国大協が異例の声明
榮 義博日本証券アナリスト協会認定アナリストCMA
何を言ってるのかまったくわかりませんね。協会加盟の国立大学が80校、大学の裁量で標準額から引き上げている大学がわずか7校なのですから限界であるはずがありません。圧倒的多数が標準額に設定しているのであれば、現在の標準額や運営費交付金の水準は適正ということでしょう。
大学が与えられた裁量を行使せずに怠慢な状態にあるというのであれば、まずはその部分にメスを入れるべきです。学長などの役職者を更迭して再起を図るべきでしょう。そうした部分にこそ、国ひいては国民の関与がなされるべきであり、現行法上難しいのであれば、法改正すべきかと思います。
大学は自身のサービスの価値や提供コストに基づいて料金を設定する。その上で、学生側の負担が世帯所得に対して過大となる問題が生じて、社会全体として教育の機会の提供に支障が出るのであれば、その時こそ学生に対する支援策拡充を国として行うべきであり、運営費交付金の増額を求めるのは筋違いです。
一方、研究に対しては、将来を見据えて国としてしっかりと投資すべきですが、これは国立大学に限ったことではないので、本件とは別問題だと思います。
「ラインモ」が最安値プラン 10ギガ以下、乗り換え狙う
榮 義博日本証券アナリスト協会認定アナリストCMA
「データ容量10ギガバイト以下では携帯大手で最安値になるといい」
たしかに間違いではないのですが、苦笑いしかありません。月額制のみを比較対象としてpovoを比較対象から外した形ですね。
povoの場合、300GB(365日有効)で24800円なので月換算だと25GBで2066円です。たしかにpovoだと月換算でも10ギガバイト超なので、「10 ギガバイト以下として設定された価格」では最安値になるのでしょうが…
ちなみに楽天モバイルは3GB-20GBで2178円なので、こちらは一応は3GB-10GBにおいて楽天モバイルよりLINEMOの新プランの方が安くなっています。
「うまずして何が女性か」発言 上川外相が撤回「真意と違う形」
榮 義博日本証券アナリスト協会認定アナリストCMA
部分的な報道しかされていなかったので悪意ある切り取り報道かと思うも発言内容を確認してみるとそうでもなく、確かに流れの中で出産についても触れていますし、上川大臣には産まない男性と産む女性という分類しか念頭になかったことが伺えます。
発言趣旨を確認する習慣と読解力は大事だなと思いました。
例えば、候補者が女性がより活躍できる社会の実現のために尽力してきたとか、女性一般の問題意識に近い政策を掲げてるとか、そういった点(もしあれば)に触れた流れでの発言であればまた違った意味合いになりますが…
まあそうだとしても、「この人を当選させなくてなにが保守(リベラル)か」とか考え方などでの分類なら分類者の主観が入り込む余地があるのでわかりますが、女性という先天的な特性にフォーカスして「この人を当選させなくてなにが女性か」と言われても、理解に苦しみます。地域全体のことより先天的属性に対する利益誘導を図りますと言っているようなもので…
【追記】
発言趣旨をわかりやすくかつ正確に書くと次の通りかと思います。
男性にはわからないだろうが、女性が経験する出産の苦しみは本当にすごい。その苦しい出産をするべき女性というパワーある存在であるべきなのだから、この苦しい県知事選でこの候補者を新たな県知事として誕生させられないようでは出産できるパワーがあるとは言えないので女性とは言えない(女性として備えるべき価値を有していない)。
前澤友作さんがメタ社とFacebook日本法人を提訴 なりすまし広告めぐり 請求額は1円「まずは違法なのかはっきりさせたい」東京地裁
榮 義博日本証券アナリスト協会認定アナリストCMA
よくわかりませんが、1円訴訟であれば、FB側は無視するのがいちばん効率的ではないでしょうか?
徹底的に争って万が一敗訴した場合、FB側はすべての広告に対して注意を払う責任が生じてきます。無視した場合、争点に対する司法の明確な結論が出ませんので、仮に敗訴しても判決文に含まれる前澤氏関連の広告のみに注意を払えば済むでしょう。
本当に「違法なのかはっきりさせたい」のであれば、それなりの訴額を提示して相手方を訴訟の場に引きずり出す必要があるように思います。穿った見方かもしれませんが、前澤氏は、自身に勝算が薄いことを見越して、不戦勝を狙った1円訴訟に舵を切ったように感じます。が、どうなんでしょう?
なぜマックで“客への反撃”が増えているのか いまだ続ける「スマイル0円」との関係
榮 義博日本証券アナリスト協会認定アナリストCMA
多くの方が勘違いしているところですが、「カスハラ客」がいるわけでも「逆カスハラスタッフ」がいるわけでもありません。ならず者がいて、これがこれまでは「お客様は神様」を錦の御旗に客側として横暴を極めていたところ、今度は「カスハラ」を錦の御旗にスタッフ側として横暴が増えつつある、という構造です。
Xではより顕著に現れています。
例えば、「汚客様報告会」なるタグをつけて「カスハラ」などの体験をポストしている店員たちがいますが、その中にはスタッフ側に問題のあるケースが多く含まれています。
また、2024年問題が騒がれた物流業界で言えば、某宅配業者の現役ドライバーを名乗るひろい氏@hiroyzeroは、業界や会社の方針など対する不満をお客様の問題の形にして、お客様とのやり取りをポストして悪態をついているのですが、底辺層から一定の支持を集めています。
こうした人は、スタッフ側にいる時はスタッフとして横暴を働き、客側にいる時は客として横暴を働く人たちです。
会社は、この事実を認識して、カスタマーハラスメントに対してより明確な方針を打ち出す必要があるでしょう。従業員に判断を任せてはいけません。ハラスメントであるか否か判断できる人材は限られており、また従業員にはならず者が混在しているからです。組織的にカスタマーハラスメントの該当性を判断し、その判断に基づいて対応する方針でなければなりません。
先日、キャンドゥに立ち寄った際に目に入ってきた方針には驚きを隠せませんでした。そこにはこう書かれていました。
「万が一、お客さまからこれらの行為を受けた際は、従業員が、本社や警察等へ報告・相談することを定めており、ハラスメントとして組織的に対応いたします。」
これでは、一従業員の判断で警察等に相談するかのような方針となってしまい、組織的な対応とは到底言えません。「逆カスハラ」を蔓延させる温床となってしまうでしょう。
店舗スタッフvs客、のみならず、自動車vs自転車・歩行者などなど、さまざまな対立がSNSの普及とともに先鋭化してきましたが、そうした立場の間での対立ではなく、一般人vsならず者の対立であるとしっかり意識し、一般人が一致団結してならず者に「錦の御旗」を与えないように対処し、ならず者に対して勝利をおさめなければなりません。
1ドル160円突破に大慌てでも…日銀「2度の為替介入」は戦略的に凄かったと言えるワケ
榮 義博日本証券アナリスト協会認定アナリストCMA
記事のような戦術的な意図があったかどうか定かではありませんが、マーケットには介入後に上がった円を売って儲けようと狙う向きはありましたので、この「一連の1回の介入」において断続的に円買い介入を実施したことは、今後の介入に対する投機筋の出方に一定の影響をもたらすかとは思います。
ただ、財務省の主たる意図は別のところにあったでしょう。
変動相場制度には、みなさんご存知の通り、自由変動相場制度と管理変動相場制度があります。IMFの最新の報告書では、全加盟国の2割に満たない31の国・経済通貨同盟が自由変動相場制度を採用しており、日本はアジア唯一の自由変動相場制度採用国となっています。そして、IMFに自由変動相場制度と分類されるには、為替介入は6ヶ月で3回(3営業日以内に行われる介入は一連のものとして1回とカウント)までとなっています。
すなわち、5/2の介入は4/29とあわせて1回とカウントされるために必要性の薄い場面で行ったものであり、「今後半年のために残り2回を温存したい」という財務省の不安の現れと言えます。そして、「必要とあれば自由変動相場制度からのテクニカルな離脱も辞さない」という覚悟ができていないことの現れでもあります。
こうした示唆をマーケットに与えてしまった点において、今回の介入は大失敗と言えるでしょう。
電車内で「前リュック」はマナー違反なのか 鉄道会社も配慮する“リュックは前に抱えるな派”の言い分
榮 義博日本証券アナリスト協会認定アナリストCMA
ちゃんと様々な状況をシミュレーションして検証すれば、「前リュックより後ろリュックの方が合理的(ただし、座席前の吊り革下は前リュックの方が合理的)」という結果が出るかと思いますが、どうも「わざわざ前リュックにして気遣ってる」というアピール性が世論を掴んでしまっているように感じます。
特に肥満者の前リュックほど迷惑かつ非合理的なものはないでしょう。解雇事由にしても良いくらいです(半分冗談です)。
荷物は状況に応じてより適切な位置があるかと思います。思考力を働かせて状況に対応して欲しいものですが、大衆相手となるとそうもいかないのがもどかしいところ。そして、下手にアナウンスすると、トラブルが生じかねません。
迷惑にならない可能性が高いのは、鉄道会社がアナウンスしている通り、「手で下げて持つ」「荷物置きを利用する」の2つしかないので、それを指針としながら他を排除しないアナウンスは適切かと思います。
全体の4割超の744自治体が「消滅可能性」 東京都豊島区は脱却も「ブラックホール型」に分類
榮 義博日本証券アナリスト協会認定アナリストCMA
民間団体の発表とはいえ、いつまでこのような無意味な「指標」を議論(?)しているのでしょう。江戸時代じゃあるまいし、居住移転の自由は保障されています。
水に一滴のインクを垂らすと拡散しますが、インクが消えるわけではありません。地域人口についても同様。拡散しただけでは限度があり、人は消えません。
「30年間で子供を産む中心の年代となる20~39歳の女性が半数以下となる」自治体を「消滅可能性自治体」としているわけですが、40歳で転居できなくなるわけでもなく、人口流出入は起こるわけですから、極めてナンセンスな話です。
極端な話、女子大の移転誘致と職住近接型の風俗店の誘致を行えば一挙に解消するわけですが、これがこの文脈で言う「消滅」を回避したことになるでしょうか?
独身女性に好まれる土地と若年夫婦の家庭に好まれる土地も違うでしょう。また、子供の成長段階によっても好まれる土地は異なるでしょう。にも関わらず、なんらの示唆も生まない「消滅可能性自治体」などというものをことさら報道することは、自治体の政策に悪影響すら与えかねない、害悪でしかない行為だと思います。
議論すべきは、自由な居住移転の自由が制限される国境を境とした内側全体、つまり日本国内全体における出産可能年齢にある女性の減少と低水準の出生率です。
新生Vポイント、2日目も不具合--「アプリが開かない」などの投稿相次ぐ
榮 義博日本証券アナリスト協会認定アナリストCMA
両ポイントは統合したのではなく、Vポイント(CCC) とVポイント(SMBC) は併存しています。下記のような処理になっているはずで、各々の処理はさまざまなサービスで実装されていると思うので、システム構築は比較的簡単なものに素人目には見えるのですが、昨日のITエンジニアさんのコメントにあったように経験者少なく難しいものなのでしょうか?会社の規模とかユーザー数とかはシステム構築の難易度にはまったく影響しないと思うのですが??手作業じゃあるまいし…
ID連携されたら…
◻︎2つのアカウントを紐付けて、Vポイント(SMBC)をVポイント(CCC)にポイント交換
◻︎Vポイント(SMBC)特典を利用する際にVポイント(CCC)からVポイント(SMBC)にポイント交換
◻︎相互のポイント交換に係る経理処理
◻︎自社製・他社製アプリにVポイント(CCC)を連携表示
新生Vポイント誕生、競争激化へ Tポイント統合、利用者囲い込み
榮 義博日本証券アナリスト協会認定アナリストCMA
記事中、「Tポイントは名称がなくなるが、既存のポイントはそのまま使えて、手続きをすれば新生Vポイントに合算もできる。」とありますが、間違いかと思います。新生VポイントはTポイント(下記のポイント機能①)です。運営会社は引き続きCCCグループです。
非常にわかりにくいので、まとめてみます。
【ポイント機能】
①Vポイント(旧名称Tポイント):CCCMKHDが運営▶︎いわゆる新Vポイント
②Vポイント(旧名称Vポイント):三井住友カードが運営
両ポイントはID連携することでVポイント(旧名称Tポイント)として合算
※CCCNKHD(CCC60%・SMBCグループ40%)
【決済機能】
VポイントPay:三井住友カードが運営
アプリとID連携したVポイント(旧Tポイント)又はVポイント(旧Vポイント)からチャージ可
ちなみに、ID連携した会員がVポイントを三井住友カード側の特典に交換する場合、契約上・システム上は、Vポイント(旧名称:Tポイント)からVポイント(旧名称:Vポイント)に一度ポイント交換した上で特典に交換することとなります。
「東京の概念的な範囲」を可視化した地図が話題に 東京に侵食されている地域に思わず納得
榮 義博日本証券アナリスト協会認定アナリストCMA
東京は、見る人の地域性が影響する概念、かつ同じ人でも強弱感のある段階的な概念だと思います。ただ、中心は山手線と中央線で囲まれた地域とその周縁地域である点では共通認識があり、意思疎通にも特段困らないのではないかと思います。
一方、横浜への見方は、地域性が大きく影響します。神奈川県出身者から見た横浜は、東京に至る経路の主要駅としての横浜(横浜駅及びその周辺部)、県外の方から見た横浜は観光地としての横浜(みなとみらいや中華街)でしょう。県外の人は横浜を憧れの対象と見る面がありますが、県内の人にとってはスルーされる一経由地にすぎません。このため、「横浜で遊ぶ」と言った場合など、神奈川県民か否かで語感がかなり変わってきます(県内の人にとっては、「遊びに『出かける』」というより「近場で済ませる」と言った感じ)。
なお、記事で挙げられた地図は、施設名などを拾っているので、そのターゲットとなる地方の方々の「東京」が反映されたものになっているのではないかと思います。
地域名に対する見方、いろいろな切り口でまとめてみると面白そうですね。
【求人】金融業界の常識を変える、顧客ファースト型資産運用アドバイザー
榮 義博日本証券アナリスト協会認定アナリストCMA
IFAは、証券会社の営業方針やノルマからは解放されますが、決してすべてが中立というわけではありません。
まず、「どこから報酬を受け取ってるか」という点が大変重要です。
アメリカのIFAは、相談料や運用資産規模に応じた手数料など、主たる報酬は顧客から資産フィーとして受け取っています。アメリカのIFAには、日本のIFA(金融商品仲介業)に類似するブローカー・ディーラー登録、投資顧問業者(RIA)登録、この2種類があります(両方に登録したハイブリッドも可)。前者が主としてコミッション型、後者が主として資産フィー型の体系となりますが、近年ではこの登録者数でも後者が前者を上回っています。利益相反の可能性を抑制でき、「顧客の最善の利益」を追求できるためです。
一方、日本のIFAの場合、提携する仲介先の証券会社などから受け取る販売手数料などのコミッションが報酬の大部分を占めています。
このため、日本のIFAは、アメリカで医者・弁護士と並んで重用されると言われるIFAとはまったく別物と言えます。
次に個々のIFAの方針を見る上で社員の報酬体系は欠かせません。
リンク先を含めてざっと見たところ報酬に関する具体的な記載がなかったので求人情報を検索してみたところ、「成果に応じて正当にインセンティブを支給します!」「賞与は売り上げに応じて支給」とありました。本来、多角的に評価・検討されるべき賞与すら売り上げに応じるのですから、インセンティブも売り上げに応じるのでしょう。会社HPには相談料は無料との記載もあります。つまり、利益相反が生じやすい仲介先からの報酬などのコミッションが直結する報酬体系となっていることがわかります。
米国のIFAを引き合いとして日本のIFA(金融商品仲介業者)の中立・信頼を謳うものをたびたび見かけますが、「ミニ証券会社」と捉えて差し支えのない事業者も多いと思いますので、その会社がどこから報酬受け取り、どのように報酬分配しているのか、必ずチェックするようにしましょう。
Z世代に人気の資産運用、第1位は「NISA」 Z世代の投資家の4割が「毎月5万円以上」投資していることが明らかに
榮 義博日本証券アナリスト協会認定アナリストCMA
NISAは制度であり金融商品でないことは皆さんご指摘の通りですが、「あてはまるものを全て」なので調査結果自体には影響ないかと思います。
ここでこの調査結果を額面通りに受け取ると、NISA利用者のうち少なくとも35%以上もの方々がつみたて投資枠(金融庁の基準を満たした投資信託に投資対象を限定した非課税投資枠)を利用していないこととなります。
【計算式】
投資信託13.5%÷NISA21.0%≒64.3%
▶︎NISA利用者のうち、NISA内で投資信託に投資している人は最大で64.3%
※NISA内とは、つみたて投資枠に限らず、成長投資枠も含む
また成長投資枠でさえ、投資信託以外の投資対象は現物株式とETN(上場投資証券)に限定されます。ETF(上場投資信託)もREIT(不動産投資信託)も投資信託です。
これだけ低い利用率はなかなか考えにくいので、この結果から想像できることは、「多くの方々が投資信託に投資していると認識せずに投資信託に投資しているのだろう」という点です。
「長期積立分散投資」などと称して、あたかも金利収入のごとく得られるかのように語り、NISAを利用してeMAXIS Slimの全世界株式(通称オルカン)や米国株式(S&P500)に投資させようとする向きが散見されます。こうした手口に引っかかって、投資信託のリスクどころか投資信託に投資していることすら認識していないのでしょう。
投資者保護の観点からは大変懸念される事態だと思います。

NORMAL











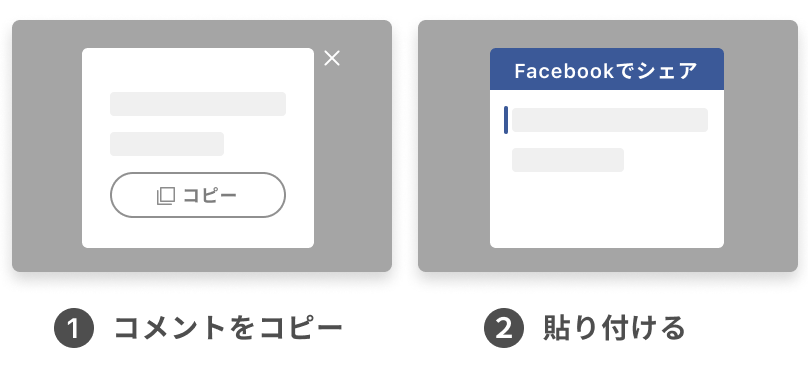

投稿したコメント