VIDEO
2023年10月14日 公開 人気 Picker
テーマが広くとても知的好奇心が刺激され為になります。ただ、円相場については、以下のように思います。海外でよく日本人はNATOと言われます。No Action Talk Only、口ばかりで行動を伴わないこという意味です。つまり評論家です。日本は本当に評論家大国です。しかし、評論家が本当の専門家かというと違います。では専門家とは何か。本当にポジションを張って、結果が損益の数字で見える人です。この種の人こそ、喋らせると本当に面白い。出羽守になってはいけませんが、欧米のメディアはこういう専門家しか出てこないと思います。ここが日本と海外のメディアの顕著な違いだと思います。この差がどこから来るかと言うと、日本では権威がや肩書がモノをいいます。一方、欧米は稼いだ人、実績を出した人が偉い、と評価の基準が明快だからだと思います。
- いいね199
エンタメとして面白い、がそれ故にあえて極端に対立軸を作ってるがゆえミスリーディングなところもあるので、そこは解説が必要でしょう。
まず量的金融緩和/引締政策(QE/QT)というものはどの国でもやっている極々基本的な中央銀行の仕事であるところ、何か特別な事のように印象付けられている点に注意。実際はむしろ日本だけが異常に「やらな過ぎ」だったのを安倍、黒田レジームになりようやく始めたというのがデータを見れば一目瞭然のファクト。次にリフレ(派)という言葉、日本ではその言葉が極端な意味を持つようになってしまった。いくら刷っても財政破綻はしない、くらいまで極端に。そして動画で何度もリフレ派という言葉を使っているが、量的緩和が有効だと主張してる人即リフレ派では実際は全く無いし、そもそも量的緩和の効果が全く無いと言っている方もインタビューの中ですらいなかった。ただ効果の程度や効く先や論拠の違いだろう。それをリフレ派とそうじゃない人で対立軸を作り、前者がマリノリティーだ馬鹿だと印象付けられてしまっている。ならば米英はじめ世界の金融政策当局者、バーナンキ含め全員がリフレ派でマイノリティで馬鹿だ、という事になるでしょう。
まず量的金融緩和/引締政策(QE/QT)というものはどの国でもやっている極々基本的な中央銀行の仕事であるところ、何か特別な事のように印象付けられている点に注意。実際はむしろ日本だけが異常に「やらな過ぎ」だったのを安倍、黒田レジームになりようやく始めたというのがデータを見れば一目瞭然のファクト。次にリフレ(派)という言葉、日本ではその言葉が極端な意味を持つようになってしまった。いくら刷っても財政破綻はしない、くらいまで極端に。そして動画で何度もリフレ派という言葉を使っているが、量的緩和が有効だと主張してる人即リフレ派では実際は全く無いし、そもそも量的緩和の効果が全く無いと言っている方もインタビューの中ですらいなかった。ただ効果の程度や効く先や論拠の違いだろう。それをリフレ派とそうじゃない人で対立軸を作り、前者がマリノリティーだ馬鹿だと印象付けられてしまっている。ならば米英はじめ世界の金融政策当局者、バーナンキ含め全員がリフレ派でマイノリティで馬鹿だ、という事になるでしょう。
- いいね204
めちゃめちゃ面白かった。こういう取り上げ方と取材の仕方が、NewsPicksの経済メディアとしての真骨頂だと思う。こういうの、金融政策に限った話ではなくて、他のいろんな政策でも実はごろごろ出てくるんです。あと、企業経営も同じ。当局や企業から正式にリリースされてくる推敲されまくったメモを取り上げて短い記事にするだけでなく、そのプロセスとか、「誰が、いつ、何をしたから、こうなった」というのを党利党略に基づいて掘り返して批判の材料にするのでなく、純粋に一つのエンタメとして切り出してくる、というのはこれまでのメディアがやってこなかった未開拓領域。そういうものを見たいというコンテンツに対するニーズはかなりあると思う。NewsPicksには、既存メディアがやってこなかったそいいう領域の開拓を期待したい。
- いいね71
アベノミクスが始まるかなり前の2010年のことですが、岩田規久男先生が「経済学的思考のすすめ」という本を書き、辛坊兄弟の「日本経済の真実」を徹底的にこき下ろして下さいました。私らの本を批判するために出されたような本で、面倒なので敢えて数えてもいませんが、辛坊兄弟という名が繰り返し出て来ます。一言で言うと、こんな素人経済学を読んだら国民がバカになるとのご主張でした。高名な先生にそこまでして頂いたことを、大いに名誉に感じています。(^_-)-☆
当時、発表の場をさして持たなかった私には反論する術もなく、反論する気も無かったですが、言いたいことは言っておこうとアメブロに一文を書きました。題して「非経済学的思考のすすめ」です。アベノミクスの壮大な社会実験と円安・インフレ、そしてその結果、かつて歯牙にもかけなかった韓国や台湾に賃金で抜かれるほどの停滞を経験するに及び、私は間違ってはいなかったと改めて思っています。もう更新していないブログですが、お暇なら・・・ 2010年に書いた一文です f(^^;
https://ameblo.jp/saki--san/entry-11132924091.html
当時、発表の場をさして持たなかった私には反論する術もなく、反論する気も無かったですが、言いたいことは言っておこうとアメブロに一文を書きました。題して「非経済学的思考のすすめ」です。アベノミクスの壮大な社会実験と円安・インフレ、そしてその結果、かつて歯牙にもかけなかった韓国や台湾に賃金で抜かれるほどの停滞を経験するに及び、私は間違ってはいなかったと改めて思っています。もう更新していないブログですが、お暇なら・・・ 2010年に書いた一文です f(^^;
https://ameblo.jp/saki--san/entry-11132924091.html
- いいね54
どれもそれぞれから見た真実だし、Shy Trump(隠れトランプ)を思い出すし、人間くさいなーと思う。また不謹慎だが面白かった。
マクロ経済に関わらず、社会は相互に影響しあうから複雑。ただ、それらを考慮しきれないから、理論は単純化する。一方で、単純化の過程は捨象があり、それと前提が揃うことが重要。
経済は「期待」が重要、というのは、どの方にも通じたコンセンサス。ただ、誰(資本市場・家計、日本人・外国人)の部分への前提と、理論や結果がでた経済環境が違うのに、前提を揃えずそれぞれの世界の話をされている。
自分は動画にある
①量は一定影響する(金利も)
②賃上げがなかったのがマイナスだった
③消費増税はマイナスだった
をいずれもそうだと思っている。家計が実質所得にポジティブと感じる循環の手前まで行ったが、②・③でとん挫し、長期のデフレ期待を変えられず、異次元緩和という「舞台装置」をそのままにせざるを得ない状態になってしまったと捉えている。
①の量に関しては、日本だけでなく世界との相対感。今の円安も日本が低金利で海外、特に米国が利上げし、金利差が拡大した(金利差だけではないし、動画で出てきたサービス収支赤字なども当然ある)。
白川氏の時代は、金融危機の中で、海外は利下げするが日本は元々金利が低く利下げ余地がなく金利差が縮小、また米国はじめ量的緩和を組み合わせた、相対的な金利・量の緩和度で劣位に立っていた時代。
黒田氏の時代は、日本の緩和拡大に加え、米国は緩和が横ばい~縮小し利上げという外部環境の違いがあり、効果も変わる。
そのなかで、論者同士がお互いに知的誠実性がない、と感情的だったのは、人間くさいし残念でもあった。
経済は期待が影響することは全員のコンセンサス。また人の期待は一様でないことも理解されているだろうが、それぞれが主張する理論の最も単純な部分に帰着し執着されているのが、エリート的。市井に影響する部分・現実の多様性をあえて見ない、エリーティズムとそこに起因する感情・プライドを組み合わせ、隠れトランプに似ていると思った。
個人的には、当事者以外のフラットな方に白・黒日銀両方の時代を、環境の違いも踏まえて解説してほしい。
この動画は当事者の感情面という事実を浮き彫りにした価値はある一方で、少しセンセーショナル。抑制的な情報との組み合わせも重要だと思う。
マクロ経済に関わらず、社会は相互に影響しあうから複雑。ただ、それらを考慮しきれないから、理論は単純化する。一方で、単純化の過程は捨象があり、それと前提が揃うことが重要。
経済は「期待」が重要、というのは、どの方にも通じたコンセンサス。ただ、誰(資本市場・家計、日本人・外国人)の部分への前提と、理論や結果がでた経済環境が違うのに、前提を揃えずそれぞれの世界の話をされている。
自分は動画にある
①量は一定影響する(金利も)
②賃上げがなかったのがマイナスだった
③消費増税はマイナスだった
をいずれもそうだと思っている。家計が実質所得にポジティブと感じる循環の手前まで行ったが、②・③でとん挫し、長期のデフレ期待を変えられず、異次元緩和という「舞台装置」をそのままにせざるを得ない状態になってしまったと捉えている。
①の量に関しては、日本だけでなく世界との相対感。今の円安も日本が低金利で海外、特に米国が利上げし、金利差が拡大した(金利差だけではないし、動画で出てきたサービス収支赤字なども当然ある)。
白川氏の時代は、金融危機の中で、海外は利下げするが日本は元々金利が低く利下げ余地がなく金利差が縮小、また米国はじめ量的緩和を組み合わせた、相対的な金利・量の緩和度で劣位に立っていた時代。
黒田氏の時代は、日本の緩和拡大に加え、米国は緩和が横ばい~縮小し利上げという外部環境の違いがあり、効果も変わる。
そのなかで、論者同士がお互いに知的誠実性がない、と感情的だったのは、人間くさいし残念でもあった。
経済は期待が影響することは全員のコンセンサス。また人の期待は一様でないことも理解されているだろうが、それぞれが主張する理論の最も単純な部分に帰着し執着されているのが、エリート的。市井に影響する部分・現実の多様性をあえて見ない、エリーティズムとそこに起因する感情・プライドを組み合わせ、隠れトランプに似ていると思った。
個人的には、当事者以外のフラットな方に白・黒日銀両方の時代を、環境の違いも踏まえて解説してほしい。
この動画は当事者の感情面という事実を浮き彫りにした価値はある一方で、少しセンセーショナル。抑制的な情報との組み合わせも重要だと思う。
- いいね67
想像以上に断言していてびっくりしました。そして、さらに想像以上だったのが、日本最強クラスの頭脳集団をもってしてもみなさん全く違う論理を持ち出してくるところ。これだけ違う意見が出てきたら総裁はまとめるの大変ですね
- いいね35


 オリジナル動画・記事が見放題
オリジナル動画・記事が見放題




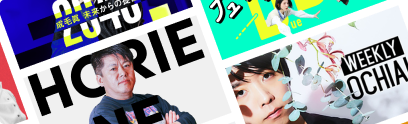



























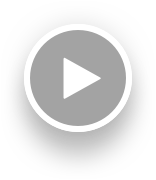

















ライブコメントを表示