Vol.4 『エネルギーをめぐる旅』/私たちは何のために急いで生きるのか?
当事者こそ哲学せよ
いぬ山:さて、あっという間に連載4回目になりましたね。どうですか?この連載の筆の進み具合は?
荒木:いやこれが本当に不思議なくらい滑らかで。他の執筆作業もいくつか同時並行で回しながらやっているのですが、このトピックスはそれほどエネルギーを消費せずに書くことができています。
ー省エネ執筆ですか。
荒木:はい。今もう一方で執筆しているものは、がっつりリサーチから始まり、仮説を組み立てて、検証しながら最後にストーリーで起承転結を作る、ということをやっているんです。すでに執筆した『世界「倒産」図鑑』や『世界「失敗」製品図鑑』もそうだったのですが、やはりそのタイプの執筆は大変しんどい。なかなか読者にとっての面白ポイントが見つからずに、ひたすら時間を浪費することもあります。
ー時間をかければアウトプットが出るわけでない、というのが厳しいですね。
荒木:そうなんです。やっぱり一つのアウトプットに対して、どれくらいの時間がかかったのか、というのは、全ての仕事に共通する一つの基準だと思うのですが、その時間効率が書き物の種類によって全く異なるんですよね。
ーその辺の構造を明らかにして、全ての書き物は省エネで行きたいですよね。
荒木:まさに。で、今日はその「エネルギー」という話の延長で、先日面白い本を読んだので、早速その本の紹介から行きたいと思います。
ーエネルギーはまた最近のホットイシューでもありますね。では、どの本になりますか?
荒木:今回は、『エネルギーをめぐる旅』という本です。2021年8月に出たので、まだ新しい本です。エネルギーの歴史が書かれているのですが、単なる歴史ではなく、エネルギーそのものを抽象化して哲学的に考えるアプローチなんですよね。
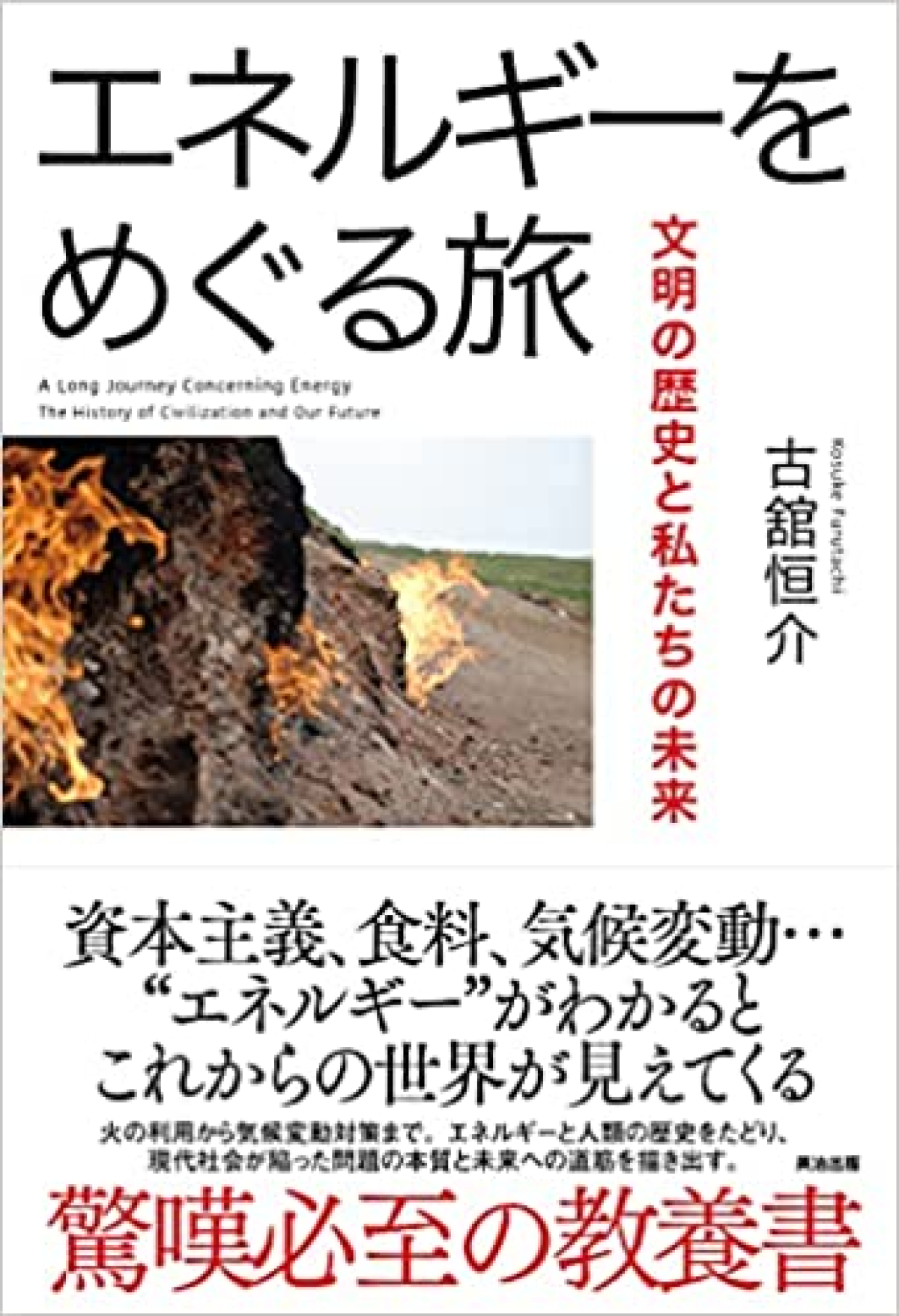
ーほう、なんか面白そうな。あれ、でも、著者の古舘恒介さんって方は、JX石油開発の現役技術管理部長なんですね?
荒木:そうなんですよ。それがまた面白いところで。業界の当事者がその対象物を哲学して書物にする、というのはなかなかできることではないです。
ー当事者だからこそ、具体的なところに目がいっちゃいますし、会社の都合とかもあるでしょうし。
荒木:そうなんですよね。だからこそ、何よりも「当事者が哲学する」というこの知的な態度に刺激を受けました。
ー例えば出版業界にいたとしたら、業界の具体的なルールとか慣行とかにやたら詳しくなるのは当然ですが、「人はなぜ本を読むのか?」とか「人はなぜ学ぶのか?」といった抽象的な問いは結構疎かになってしまいますからね。
荒木:まさに。その辺の哲学的な思考というのは、短期的な「仕事ができる」という評価からは切り離されているので、どうしても二の次になってしまう構図があると思います。でも、この本を読んで、改めてその重要さに気づきました。
エネルギー消費の理由は私たちが持つ「時間短縮」欲求にあり
ーなるほど。では、この本からの一節をご紹介ください。
荒木:はい。まさにその哲学的な箇所を引用したいと思います。
人類はなぜエネルギー消費量を増やしてきたのでしょうか。第一部でみてきたように、火の利用に始まる五段階にわたるエネルギー革命を通じて、人類はエネルギー消費量を劇的に増やしてきました。実はそれぞれの過程には共通することがあると、私は考えています。キーワードは「時間の短縮」です。第2部 第3章 エネルギーの流れが創り出すもの P.246
ーふむ。エネルギー消費の理由は「時間の短縮」…ですか。
荒木:そうなんです。例えば、人類の歴史を振り返ってみると、火の活用というのは大きなエネルギー革命だったのですが、火を使うことによって大きな時間短縮につながっています。
ーん?何の時間短縮でしょう?
荒木:それは、消化ですね。火に通すから、一気に消化時間が短縮できるのです。野生のチンパンジーは消化に1日当たり6時間くらいかかると書かれています。それと比べて、人間は圧倒的に消化にかける時間が短い。だから、私たちはその残りの時間で色々なことができるわけです。
ーなるほど、エネルギーによって時間が短縮されていく。いや、私たちが時間を短縮したいと思うから、火というエネルギーを活用する、ということですね。
荒木:はい、その通りです。そして、その「時間短縮」という補助線が、これからの問題解決に重要になってくるのです。
言うまでもなく、私たちはこれから増大していくエネルギー需要の問題をどう解決するか、という問いに向き合わなくてなりません。そのために、新たな代替技術に投資するとかいろいろな可能性があるのですが、その手段検討の前に、もっと根本的な部分、つまり「私たちがなぜエネルギー消費をするのか」という点から考察する必要があるのです。
ーなるほど。ということは、エネルギー問題を解決しようとするのであれば、自分たちが持つ「時間短縮への欲求」を自覚し、それをどうにかできないか、からまず検討しろ…と。
荒木:そうなんです。別の言い方をすれば、「その時間短縮は本当に必要か?」「限られたエネルギーを消費してまで時間短縮したいのか?」「そこで余った時間を何に使いたいのか?」という問いかけなのです。
ーうーん。それはなかなか難しい問いですね。そこまでしてやりたいことがあるか、と言えば、別にあるわけでもない。しかし、今まで時間短縮レースをダッシュで駆け抜けてきたので、「立ち止まることは悪」だという感覚もあります。
荒木:確かに。しかし、焦る理由がないのに焦っている。そんな姿も滑稽ですよね。私たち人類は、「無」に向かってダッシュをしているとも言えるのかもしれません。

エネルギー問題とは、「私たちの生き方問題」である
荒木:最後に、もう一節、最終章から引用しておきましょう。
エネルギー問題を考えると言うことは、つまるところ、「私たちはいかに生きるべきか」という哲学を考えるということなのです。
私たちひとりひとりが幸せな人生を送るためには、何をすべきか。改めて、心の声を聞いてみませんか。第4部 第3章 私たちにできること P.380
ー心の声ですか。確かに、今までダッシュしてきたと言いましたが、心の声を聞く余裕はなかったですね。そんなことしていたらレースに遅れちゃいますから。
荒木:はい、そうでしょう。僕もそうです。でも、そのレースって一体何のレースなんでしょうね?みんな走っているから自分も走っている、ってこと、ありませんか?もしそうだとしたら、一旦心の声を聞いてみるのも大事だと思います。
ーなるほど。エネルギー問題は生き方問題そのものですね…。
荒木:かつてセネカは『生の短さについて』にてこう語っています。
生きることは生涯をかけて学ぶべきことである。そして、おそらくそれ以上に不思議に思われるであろうが、生涯をかけて学ぶべきは死ぬことである。『生の短さについて』P.22
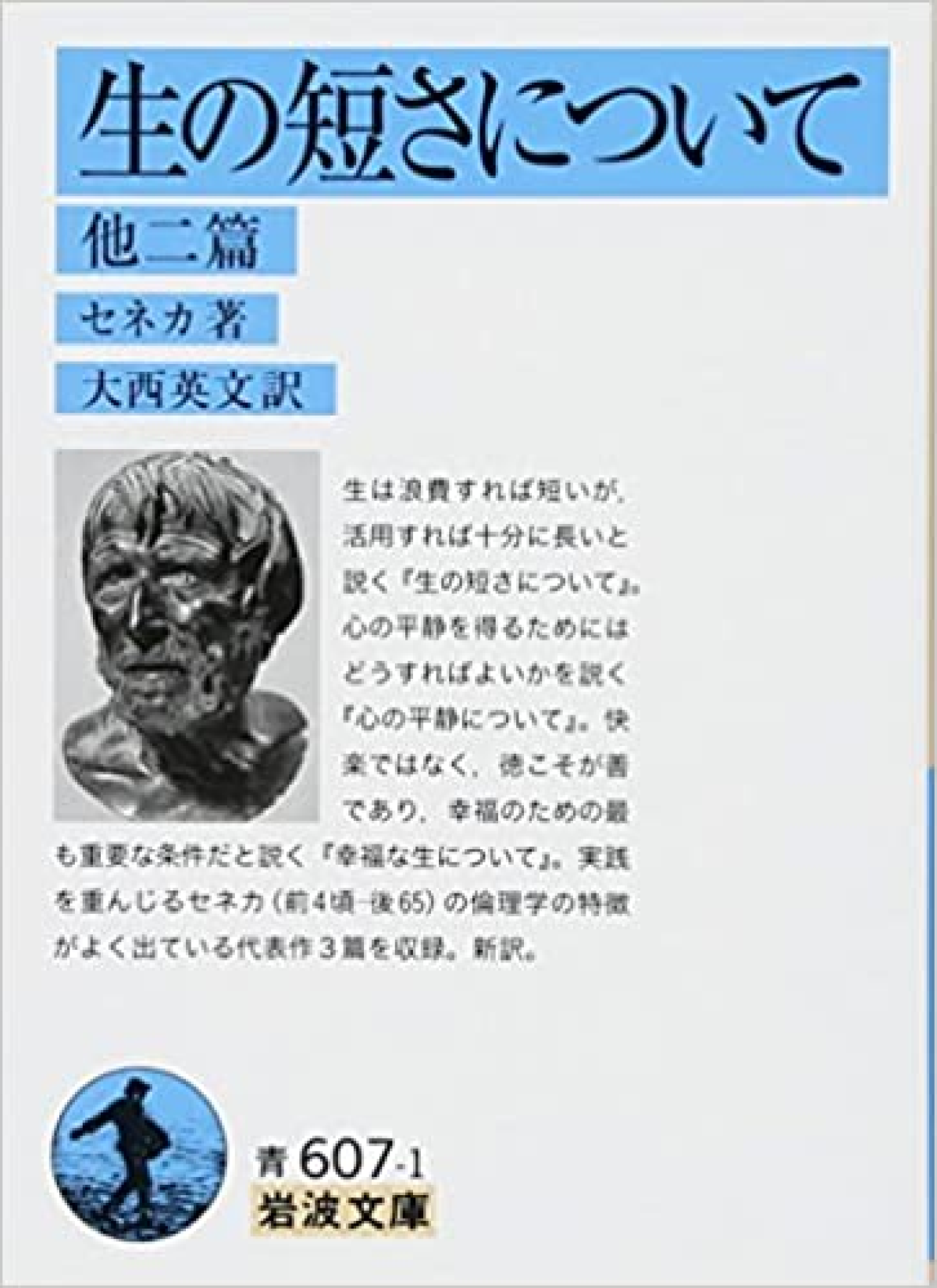
ーむむ。セネカですか。2000年前の言葉だけに、その間私たち人類が生きることに対する学びを怠っていたからこそ、エネルギー問題が起きてしまったと読み取れなくもありません。
荒木:まあ流石にそこまで考えていたとは思えませんが、エネルギーというのはかくも哲学的な問いなんですよね。
ーところで、荒木さんは、もし執筆の時間を短縮できるテクノロジーが出たとしたら、お金を出しますか?
荒木:うう……。それはぜひ買いたい。でも、そのテクノロジーにはエネルギーが必要となり、そのエネルギーを消費してまで時間短縮したいのか、時間短縮して余った時間を何に使うのか、と言われると…めっちゃ悩む!
ーしかも、そのテクノロジーをみんなが買っていて、「半分の時間で書けるようになった!」なんて声がSNSで上がっていたら…
荒木:絶対買う!
ーそれ、深く考えずにみんなと一緒にダッシュしちゃってるじゃん(笑)
今回の一節
人類はなぜエネルギー消費量を増やしてきたのでしょうか。第一部でみてきたように、火の利用に始まる五段階にわたるエネルギー革命を通じて、人類はエネルギー消費量を劇的に増やしてきました。実はそれぞれの過程には共通することがあると、私は考えています。キーワードは「時間の短縮」です。『エネルギーをめぐる旅』古舘恒介/英治出版 第2部 第3章 エネルギーの流れが創り出すもの P.246
エネルギー問題を考えると言うことは、つまるところ、「私たちはいかに生きるべきか」という哲学を考えるということなのです。私たちひとりひとりが幸せな人生を送るためには、何をすべきか。改めて、心の声を聞いてみませんか。『エネルギーをめぐる旅』古舘恒介/英治出版 第4部 第3章 私たちにできること P.380
生きることは生涯をかけて学ぶべきことである。そして、おそらくそれ以上に不思議に思われるであろうが、生涯をかけて学ぶべきは死ぬことである。『生の短さについて』セネカ/岩波文庫 P.22
更新の通知を受け取りましょう
























投稿したコメント