いつもお世話になっておりませんのに?:ビジネスと世間とホラー
ビジネスシーンで出会う「呪い」的なものはありませんか?大学教員といえば、毎日好きなことばかりしていてビジネスとは無縁と思われるかもしれません。が、悲しいことに、会議や事務作業、メールのやりとりといった仕事に多くの時間は割かれています。
その証拠に。わたしのPCのキーボードの「い」を押すと、次の予測が一番にでてきます——「いつもお世話になっております。」「こ」を押せば、「今後ともよろしくお願いいたします。」
予測変換ぐらいでビジネスパーソンづらをしていたら怒られるかもしれません。でも、これらの表現は日本のビジネスを含むあらゆる場面で重要な役割を果たします。
実際にお世話になっていようがいまいが、ヨロシクしたかろうがしたくなかろうが、わたしの心情に関わらず(本当にヨロシクと思っていることもあります)、キーボードは、半ば自動的にこれらの言葉を提案し、入力していくのです。
みなさんは「いつもお世話に…」の返事に「わたしがいつあなたのお世話をしたでしょうか?」とは書かないですよね。「今後とも…」に対して「今後というのは具体的にはいつまででしょうか?」とも書きません。なぜ、私たちはこうは聞き返さずに平気でいるのでしょうか。
以前のトピックスで、“意味なき意味”を持つ「あいさつ」について取り上げました。人類は沈黙という「魔」を追い払うために、大して意味のない言葉のやりとりをしているというお話でした。
今回は、ビジネスでもよく使われる「いつも」「今後」という“意味なき言葉の意味”について考えてみたいと思います。
「いつも」の恐怖——正体不明のXからのまなざし
「いつも綺麗にご利用いただきありがとうございます。」
「はじめて」入ったはずの店のトイレでこの張り紙を目にすると、わたしはもうクラクラしてしまいます。…わたしはもう絶対にここを汚せない。はじめて入ったこの店の見知らぬ存在Xは、「あなたはここを汚さないナイスな人間ですよね?知ってますよ」と語りかけている。わたしの未来はもう決められている。Xの期待を裏切ることはできない。
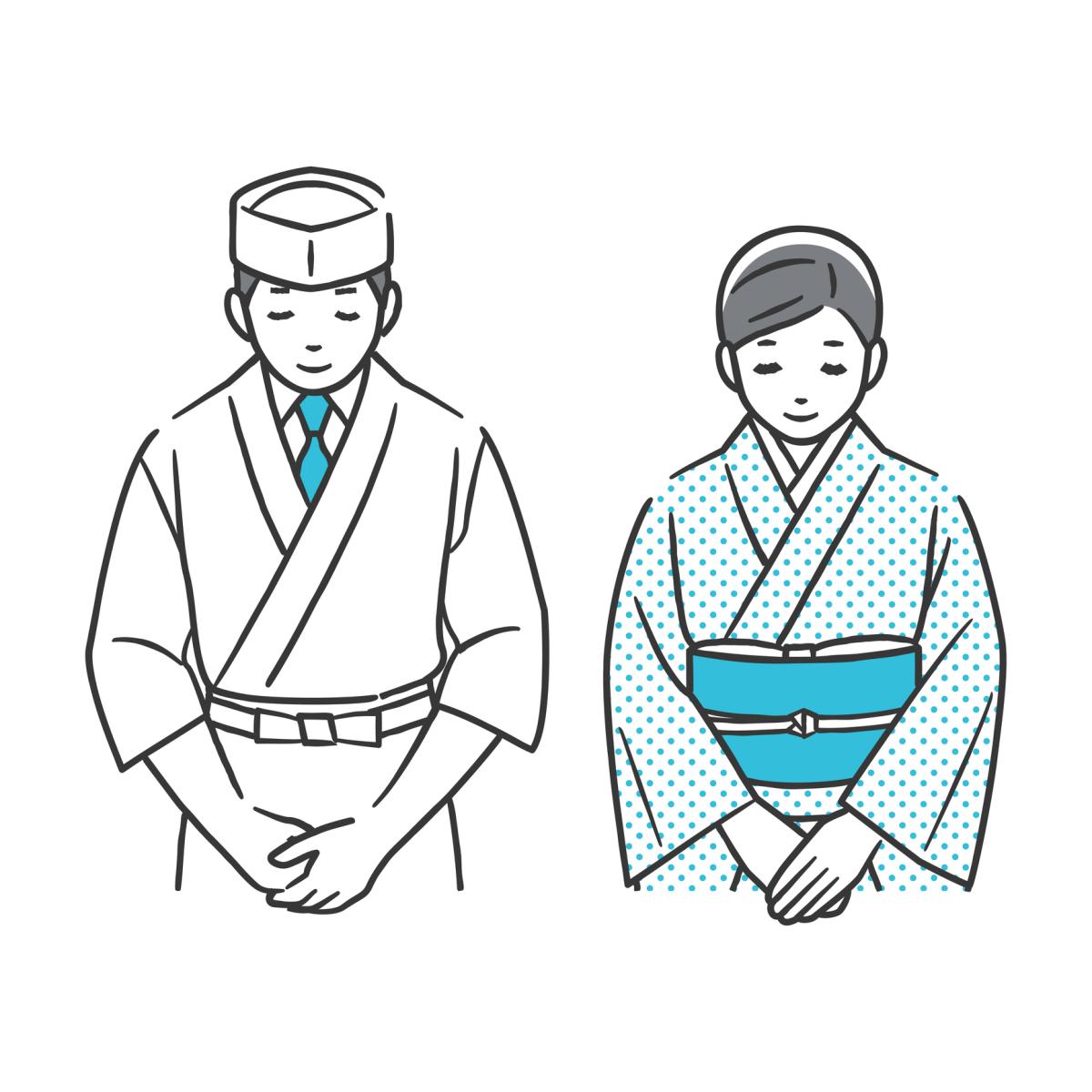
これは「汚さないでください」というお願いではありません。「あなたのことは全然知りませんが、当たり前のことを当たり前にしてくれる人でいてくれてありがとうございます」…「わたし」という人間をがんじがらめにするこの圧。この空気。はじめて出会うはずなのに、私たちのことを知っているがごとくふるまい、私たちの言動を制限するXとはいったい誰なのでしょうか?正体不明のX、これを私たちは「世間」と呼びます。
社会ではなく世間——関係を強制する
世間とは何でしょうか?
「世間知らず」「世間体が悪い」「そうは世間が許さない」。
どうも、世間とはネガティブな言葉と相性が良いようです。これは私たちがいかに世間なるものと苦しんで付き合っているかを物語ります。
世間と似た言葉に「社会」があります。今では当然のように使われますが、「社会」は日本ではなじみのない考えとして、割と最近になって入ってきたものです。「社会」は明治時代の1877年にsocietyの訳語として登場しました。また、社会を構成する「個人」という考えも、同じ頃にindividualの訳語として入ってきました(阿部1995:174-176)。

西欧社会で尊厳を持つ独立したものとして「個人」が登場したのが12世紀とされています(*1)。800年以上の歴史を持つ西欧の「社会」・「個人」に対し、日本ではそれが輸入されてまだ150年足らず。対し、「世間」は万葉集にも世間(よのなか)として登場します。つまり、「世間」は1200年以上も前から存在してきた世界の捉え方です。
現代日本で私たちが使う「社会」や「個人」は、西欧の前でも、世間の前でも、生まれたての赤子同然の、まだヨチヨチ歩きをしている考え方なのです。 世間の前では、「個人の尊厳」などそれこそ赤子の手をひねるかのごとく簡単にねじ伏せられてしまいます。日本で「人権」や個人の「権利」がなかなか理解されにくいのも、このあたりにヒントがあるような気もします。
独立し尊厳を持つ「個人」を前提とする「社会」に対し、「世間」は個人をなかなか放っておいてはくれません。しがらみ、という言葉がよく似合うように、世間は個人よりも個人間・集団間の「関係」を重視します。互いに物を贈り合ったり(例:年賀状、お中元、お歳暮)、決まりきった言葉(例:いつも、先日は、今後とも)やふるまい(例:冠婚葬祭のしきたり)を通して儀式的なつきあいを強制することで、世間は個人を個人でいさせてはくれません。「関係を強制」し、人の人生にずんずん介入してくるおせっかいなものが世間のようです。
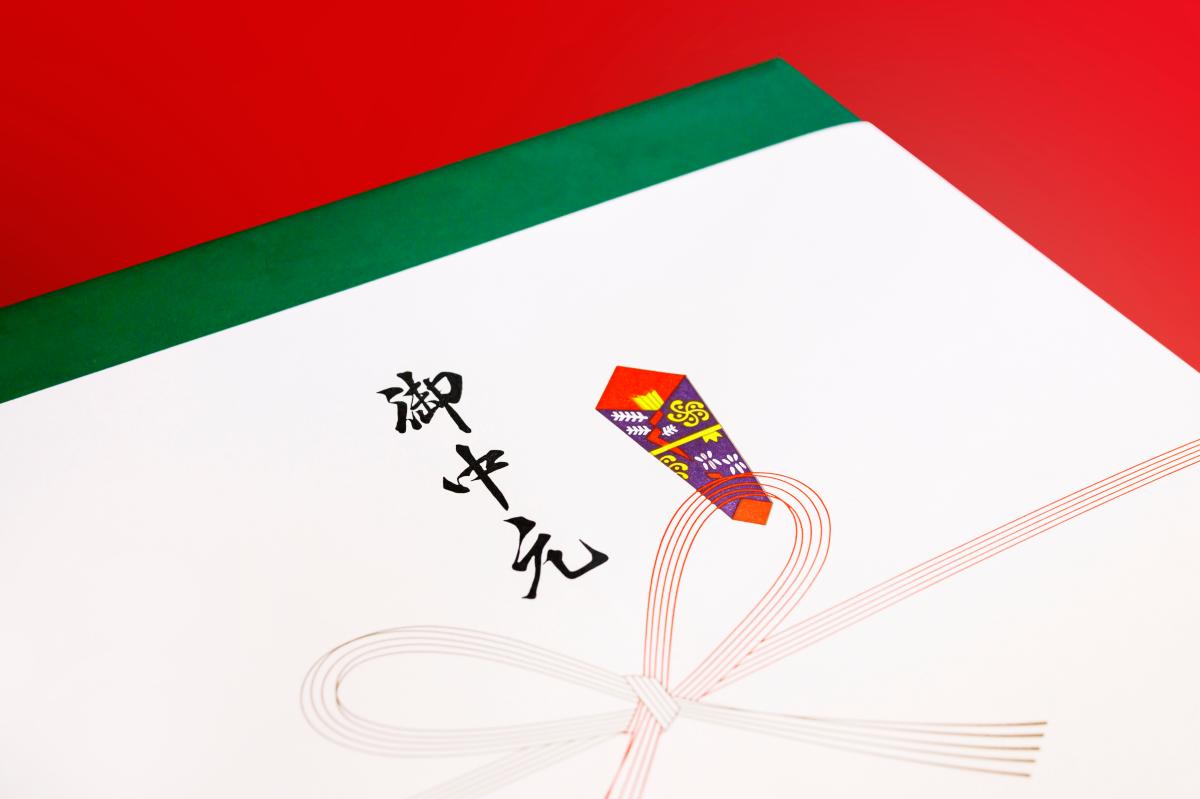
世間の要素——共通の時間へと誘う
西欧の「社会」と日本の「世間」を比較した歴史学者の阿部謹也さんは、世間を次のように説明しています。
「自分と利害関係のある人々と将来利害関係を持つであろう人々の全体の総称…基本的に同質的な人間からなる」「個人と個人を結ぶ関係の環」阿部謹也『「世間」への旅』pp.7-8および『「世間」とは何か』p.16
世間の特徴の一つに「共通の時間意識」があると言います(*2)。
阿部さんは「先日はありがとうございました」「今後ともよろしくお願いいたします」という欧米には存在しないあいさつに着目し、その前提となる時間意識の違いを指摘します。

欧米の個人——それぞれの自分の時間を生きており、相手と常に同じ時間の中で暮らしているとは思っていない。日本の個人——「世間」という共通の時間のなかですべての人が生きていると考える
阿部謹也『学問と「世間」』p.105
時代や人によっては必ずしもこう断言できはしないでしょうが、私たちが毎日のように使う「いつも…」「今後とも…」のことばはその名残ではないでしょうか。わたしがはじめて訪れた店のトイレで戦慄するのは、この「共通の時間意識」や「関係」の押し売りに対してです。その背後にあるのは、「私たちはかつて関係していましたよね?その関係はこれからも続きますよね?」というメッセージです。
魔物はどこに棲むのか?
と、このように世間をどこからか私たちを監視する恐ろしい魔物であるかのように言ってきましたが、肝心なのはその魔物が棲む場所です。世間のあれこれに苦しみもがいていた太宰治は、世間の正体を見抜いていました。
(それは世間が、ゆるさない)(世間じゃない。あなたが、ゆるさないのでしょう?)…(いまに世間から葬られる)(世間じゃない。葬るのは、あなたでしょう?)…(世間とは個人じゃないか)太宰治『人間失格』
「独立した自由な個人」をなかなか獲得できない私たちは、世間を憎みつつも、結局それをよりどころにして生きている部分もあるのです。世間を自分の気持ちの代弁者として利用したり、またはそれを主語にして自分に言い聞かせたりすることもあるでしょう。正体不明のXあるいは魔物としての世間は、どこか遠くから私たちを見つめているようで、実は、私たち個人の心の中にどっしり座っているのです。

「いつも」「今後とも」の世界へようこそ
存在しなかったはずの「いつも」の時間。逃れることのできない「今後」の時間。
なんだ、私たちの日常やビジネスは、ただのホラーの世界じゃないか。
キーボードの「い」や「こ」を押すだけで、私たちは相手を共通の時間へといざない、関係を強要することができます――あなたはわたしと関係していました・いますよね?
「いつも」と「今後」の呪いをかけあうことで、私たちは互いをがんじがらめにし、「よりよい空気」=ジョーシキを生み出して、それを維持するためにせっせと努力し、ホラーな世界を創り上げています。

かつて顔の見える範囲でとどまってくれていた世間は、今はインターネットを介して拡大してしまいました。広いんだか狭いんだかわからなくなった世界の中で、世間のために命を絶つ人が多くいることに、私たちはどう向き合えばよいでしょうか?
大学の授業で社会学は教えられていますが、世間という魔物がいまだに闊歩する現代日本にあって、日本の世間と近代社会との葛藤を学ぶ「ヨノナカ学」的なものが必要なように思います(*3)。抽象的な社会の理論ではなく、私たちがこの社会で生き残るための「実学」として。世界中の「世間話」を分析対象としている人類学にも、可能性があるかもしれませんね。私たちがその呪いを解きたいと切望しつつもかけ続けてしまう“世間モノ”は、またトピックスで取り上げたいと思います。
ということでみなさま、今後ともよろしくお願いいたします(心を込めての予測変換です)。
トピ画:Gettyimages/gan chaonanの写真
(*1) 西欧社会における「個人」や「自己」の成立は、都市化やキリスト教教会での告解の普及がその背景にあったと言われています(参考 フーコー1986)。
(*2) ほかの特徴として、贈与・互酬の関係、長幼の序などが挙げられています。
(*3) 関連して「世間学」という新しい学問の在り方も提唱され、多くの書籍も出版されています。
参考文献
阿部謹也(1995)『「世間」とは何か』講談社現代新書。
阿部謹也(2001)『学問と「世間」』岩波書店。
阿部謹也(2005)『「世間」への旅:西洋中世から日本社会へ』筑摩書房。
フーコー、M.(1986)『性の歴史1 知への意志』渡辺守章訳、新潮社。
更新の通知を受け取りましょう
























投稿したコメント