「事業計画はストーリーで語るべき」10X CFOがPEファンド時代に学んだ、 経営と現場のつなぎ方
本記事は、2023年9月29日にSPEEDAのオウンドメディア「&SPEEDA(アンドスピーダ)」に掲載した記事の再掲となります。
「事業計画はストーリーで作るべき」。そう主張するのは、小売チェーン向けECプラットフォーム「Stailer(ステイラー)」を提供している10XでCFOを務める山田 聡さん。
前職であるカーライル時代にさまざまな企業への投資を行うために事業計画を作り続けてきた山田さんはなぜ「ストーリー」に着目するようになったのでしょうか?
事業計画とはコミュニケーションツールである
──以前、山田さんは「事業計画はストーリーで作るべき」というnoteを書かれていました。まずはその真意から伺いたいです。
noteにも書いたのですが、僕が一番お伝えしたかったのは「事業計画とはコミュニケーションツールである」ということです。
前提として、事業計画を作る目的はさまざま。社員に対して事業の方向性を示してスピード感を上げるためだったり、投資家などのステークホルダーに自社のポテンシャルを伝えるために使われたり。さらにはM&Aで買い手と売り手双方で合意形成をするためだったりします。
数値を明示することも大事ですが、残念ながらそれだけでは一方通行なコミュニケーションになってしまいます。
深いコミュニケーションへ発展させるためにも、数値をもとに「事業を通じて何を実現し、それが財務数値にどう現れてくるか」を繋がりのあるストーリーで語る必要があるのです。
そう考えると、事業計画はシンプルでナラティブなほうが読みやすく、コミュニケーションツールとして機能しやすい。
逆に、例えばですが、(M&Aなどで精緻さが求められるモデルを作るケースを除き、)エクセルで200行以上あるような事業計画になると情報量が多すぎて「結局のところ、何を重視して取り組んでいきたいのか」が伝わりづらくなってしまいます。
なにより、ボリュームに圧倒されてしっかり見てくれる人も少ないし、作った本人もどこが重要なポイントなのかあまり理解できていないパターンも多い印象です。
スタートアップで言うところのエレベーターピッチのように、1〜2分程度で「つまりどういうことか」を話せるような内容にまとめることも大事なポイントです。
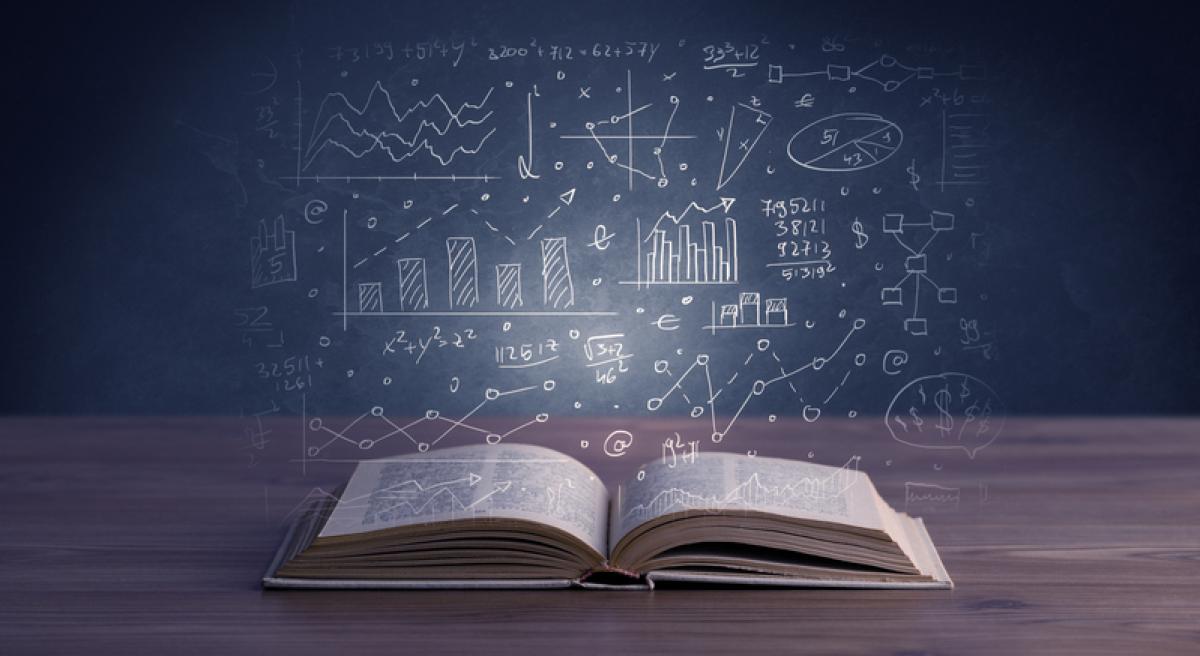
──山田さんは10Xへ入社する前はカーライルで働いていました。この気付きは、カーライル時代に得たものですか?
カーライルには「投資計画を作った人が最後まで責任を持ってその遂行までやり遂げるべき」という思想があります。
そのため外資系ファンドにしてはめずらしく、本来なら担当を分けて行われている投資フェーズとPMIフェーズ(Post Merger Integration、M&A成立後、企業統合による効果を最大化させるための一連のプロセス)を一人の担当・一つのチームが一気通貫で見る体制になっています。
あえて分けないことで、最初に想定していた事業計画に実行性があるのかどうかなどをリアルな経験から学んでいくことができます。とはいえ、4〜5年かけて計画から実行のギャップを理解するので壮大な学びになるわけですが(笑)。
おかげで、実体験をベースに「この事業計画にリアリティはあるのか?」を意識するようになりました。
事業計画でありがちなのは、経営層と現場それぞれが感じる課題が違うこと。誤解を恐れずに言うと、経営層の課題感だけであれば(ロジックだけで整理しやすく)数値に落とし込むのはわりと容易いのです。
しかし、事業計画をコミュニケーションツールとして活かすならば、それだけでは実際に実行を担う現場の方々の思いやモチベーションといった点を置いてけぼりにしてしまいます。
計画・戦略の実効性を高め、事業を強いものにするためにも、経営層と社員、スポンサーである株主が見ている方向性を一致させなければなりません。
実際、私も、PEファンド時代、投資先の企業で働く80名ほどの社員の方々と個別に面談をさせてもらったうえで現場が感じている課題感等も踏まえ、事業計画に修正を加えたりしていました。
さらに、そうして作った計画に対して現場が納得感を持って取り組んでもらうためにも、事業計画はストーリーで語れたほうがいいと、このとき学びました。

事業で重視すべき内容を落とし込む際、注目したいポイントは?
──事業計画をストーリーとして落とし込むとき、どういったステップで進めると良いのでしょうか?
事業計画を作るときは以下の流れで進めるといいと思います。
1️⃣ 事業構造を正しく理解する
2️⃣ そのなかで売上や利益へのインパクトが大きな指標を理解する
3️⃣ コントロールできるものにフォーカスする
まず「事業構造を正しく理解する」ために、売上やコストを分解していきます。ひとくちに「売上」と言っても、それが「顧客×単価」なのか、「新規顧客数×単価」なのか、もしくは「特定地域の顧客数×単価」なのか……いろいろあります。
これは事業構造やその特性によって切るべき形が変わってくるので、事業に対する深い理解や現場の声も踏まえて最適なものを考えていく必要があります。
次に、分解してみた結果から、インパクトの大きな指標を理解し、事業実態に合わせて計画を分解していくことが大事です。
そして最後の「コントロールできるものにフォーカスする」について。言い換えれば、事業計画の中にアンコントローラブルなものが混ざっていないかどうかをチェックするということでもあります。
どうしても事業計画にはコントロールできないものが混ざってきます。そのため、自分たちでコントロールできる・できないを見極め、それぞれの業績への影響を切り分けられるようにする視点も必要です。
そして、コントロールできないものに振り回されず、コントロールできることにフォーカスし、そこに対してのフィードバックサイクル(=振り返りのサイクル)を高められるようにしたほうがよいです。
その3つに加えてお伝えしたいのが「最初から精緻に作りすぎないこと」。なぜなら、事業計画作成後のフィードバックや実運用のプロセスで、ほぼスクラップアンドビルドすることになるからです。
事業計画を事業に即したものにするため、完成後は事業部側に見てもらいフィードバックを受けることになります。そうすると「これは重要じゃない」「こちらの優先度のほうが高い」といった声が寄せられ、計画の構造や変数の置き方を修正していく作業が発生します。
最初から精緻に作り込んでいると、修正作業も手間がかかります。シンプルにまとめておいたほうが、スクラップアンドビルドしやすいですよね。
──既存事業と新規事業では、事業計画の作り方はやはり変わりますよね?
既存事業と新規事業の違いをまとめると、次のようになります。
<既存事業>
・不確実性が低く、継続性が高い
・計画の参考にできる細かい数値や指標に関する過去実績がある
・成果拠出に必要な時間軸がはっきりしているので、5年など長めの計画を作っても問題ない
<新規事業>
・不確実性が高く、継続性が読めない
・アップサイドの大きさなどが精緻に読めず、詳細な数値前提も置きづらい
・成果拠出に必要な時間軸がはっきりしないため、2〜3年など短めに作る
既存事業は不確実性が低くて継続性が高いため、最初からカチッとした事業計画を作りやすい特徴があります。
先ほど事業計画は精緻にしすぎないほうがいいとお話しましたが、既存事業に関しては過去実績も十分ある場合も多く、前提として参考にできる数値・指標も多く、今後事業として取り組む時間軸もわかりやすいので、一定精緻に作り込んでも問題ないケースが多いです。
逆に、新規事業は不確実性が高く、アップサイドの大きさも想定しづらく、先を見通すのが難しい。例えるなら、新薬のR&D(Research and Development、研究開発)のようなもの。
「ガンの新たな特効薬の開発」を目指して開発を始めても最終的に完成するかどうかはわからず、完成しても薬として認証を取得し上市できるまでに時間がかかるなど時間軸の不確実性も極めて高いものです 。
つまり、数歩先で何が起こるかわからず、ゆえに研究の初期段階で販売数量などの計画を精緻に作るのではなく、あくまでR&Dの段階的な進捗(創薬、臨床試験、認可等)をトラッキングするマイルストーンアプローチを取ります。
新規事業の事業計画書を作るときに大事なのは、しっかりとマイルストーンを刻むこと。そして次のフェーズへ進むために何をするのか、何を重視するのか、どんなKPIがあれば判断できるのかをクリアにすること。
そうすると、自ずと情報もシンプルに整理できるはずです。そのためにも、新規事業の短期目標をブラッシュアップすることを意識したほうが良いですね。

10Xの事業計画を「あえて全社公開状態」にした理由
──10Xでも、お話しいただいた流れで事業計画を作ったのですか?
10Xの事業計画はわりとシンプルです。
我々は世の中にネットスーパーという買い物体験の選択肢を広げるための事業をしています。その背景には、日本の食品小売におけるEC化率がまだまだ低いことがあります。
食品小売業は国内だけでも20-30兆円規模の市場が存在していますが、小売事業者にとってリアル店舗(オフライン)での事業拡大は限界値に近づいている。
他方で、オンラインでの買い物のニーズは高まってきており、この小売事業のオンラインチャネルの提供を弊社が支援することで、小売事業者にとっても新たな事業成長の選択肢を提供することに繋がります。
そういった背景もあり、10Xはスーパーマーケットやドラッグストアなどの小売・流通事業者向けのECプラットフォーム「Stailer」を運営しています。
小売ECの事業成長に必要なことは多岐に渡るため、ユーザー向けアプリだけでなく、バックヤードでのピックアップや配送管理、受注・在庫管理などのシステムをフルセットにして提供しています。
そんな我々にとって大事なのは「ネットスーパーを普及させること(=ネットスーパーの流通総額)」と「サービス提供価値を上げること(=流通総額に対する10Xの売上比率)」です。この2つで我々の事業計画がほぼ決まります。
ちなみに、ネットスーパーの売上ボリュームと我々のサービス提供価値の掛け算で将来の事業計画・事業規模が算出できます。
──10Xで重視している指標は?
Stailerは、サービス提供先のネットスーパー売上の一定の比率をフィーとして頂くモデルになっています。そのため、ネットスーパーの流通総額とサービス提供価値の深さの2つを重視しているのです。
いくらネットスーパーが普及しても、サービスの提供価値が増えなければ売上連動費のパーセンテージを上げることも叶いません。なので、流通総額だけでなくサービスの付加価値も高めていくことも重視しています。
その2つの指標にfocusを当てた時に、そこで議論になりがちなのが「大手と組むのか、中小事業者と組むのか、もしくはその両方なのか」。
大手だと1社に対してのサービス提供の準備や提供後の運用負荷は重くなりがちで、中小事業者のほうが1社あたりの提供負荷は下げやすい。
逆に、大手はパイが大きいため流通総額へのインパクトを出しやすいが、中小事業者はパイが少なく、流通総額を積み上げるためには多くの社数を獲得する必要がある、などそれぞれにメリット・デメリットがあります。
しかもこの判断は事業環境により変化し得るものです。「どういった戦略的比重にすることが、が中長期的な売上・利益に寄与するのか」という考えをもとに、適切な判断をする。そのための主要な変数を、事業計画に織り込んでおき、判断の材料としています。
──10Xの中で初めて事業計画を公開したとき、事業部門からどんなフィードバックが寄せられましたか?
当初は店舗売上高合計1,000億円・50店舗のあるスーパーマーケットに10Xのサービス、Stailerを導入する場合、例えば最初の2年で店舗売上高合計の1%である10億円の売上を目指すという計画を作っていました。
しかし、小売事業者に近い事業部門の社員に話を聞くと、小売事業者は店舗ごとに年間の売上目標があり、それを各店長がKPIとして持っていることがわかりました。そして、日々の販促施策などの意思決定も店舗単位で行われていました。
ネットスーパーにどれくらい投資するのか、そのなかで各店舗がネットスーパーを1日何枠用意するのかも店舗ごとで決められていたのです。
僕が当初作ったものは、現場目線の意思決定の実態から少し離れていたため、ネットスーパーの計画についても、店舗ごとの目標値を設定できるかたちに変更しました。
こうした事業部からのフィードバックを受けやすくするためにも、僕がおすすめしたいのは事業計画をまとめた資料を「全社公開・編集可能状態」にしておくことです。
──つまり、社員であれば誰でもいつでも見られる状態にしておくということ?
そうです。繰り返しになりますが、事業計画はコミュニケーションツールです。社員の日々の行動に影響を与えるためにも、事業計画をもとにやりとりを発生させなければなりません。
10Xでは、事業計画書をまとめたスプレッドシートをあえて「全社公開・編集可能状態」にしています。誤った操作をされないようにロックすることも大事ですが、幸い、スプレッドシートの機能として「以前の状態」に戻せるので僕はしていません。
むしろ、「この数値が動くとどうなるのか」「ならばこれを加えるとどうなるのか」と、社員が自分ごととしてどんどん触ってもらえるほうが嬉しいんです。
コミュニケーションツールとして双方がやりとりしている状態が理想ですので、事業部との議論の中で自然と事業計画が使われ始めるとなおいいですね。

いいフィードバックを得るために必要なヒント
──先ほど、事業計画は経営陣だけでなく現場の声をしっかり反映することも大事だと話していました。しかし、いざヒアリングしようとしても事業部側の理解を得ることが難しいケースもあると思うのですが?
いきなり「事業計画を作るためにヒアリングさせてほしい」と言ってしまうと、事業部側は戸惑いますよね。そうではなく、「困っていることはないですか?」「KPIなどの可視化で手伝えることはありませんか?」というスタンスで始めたほうがいいです。
事業部のみなさんは常に忙しいし、ファイナンスに対して苦手意識を持っている人も少なくありません。ちょっとした手助けでも、すごく感謝されると思いますよ。
これは事業計画に限った話ではありませんが、「協力することに意味がある」と思ってもらえないと相手は動いてくれません。だからこそ、最初は寄り添う姿勢が大切です。
そしてKPIなどの数値の可視化をサポートし、ともに気づきを得る。そういうことをしていると、事業計画を作るこちら側も事業解像度が自然と上がってくるはずです。
また、事業部側から見ると「事業計画を見ているのはファイナンスや経営企画の人だけ」と思われがちですが、こうしたやりとりを増やすことで率直なフィードバックも得られるようになります。
最後になりますが、いいフィードバックをもらうために、事業計画を作る人がある程度のスタンスをとることも大事です。
──スタンス、ですか?
事業計画を通じて伝えたいのは「会社としてフォーカスすること」です。そうすると逆に「どの内容や投資を削るのか、どこに会社として注力しないか」を決めることにもなります。
その過程では、事業計画を作る人がある程度の取捨選択のスタンスをとることになる。スタンスを取れれば、そこに対して率直なフィードバックを得られるようになり、取捨選択の精度も上がります。
そもそも、玉虫色でスタンスをとらなければいいフィードバックはもらえませんしね。僕の場合、あえて変数を絞り、強いフィードバックをもらえるように意識しているところがあります。そうやって、事業計画の内容を磨き込んでいくのです。
──なるほど、まさにコミュニケーションツールとして活用されているのですね。本日はありがとうございました。
【まとめ】10X 山田さんが考える、事業計画書のポイント
・最初から精緻に作り込みすぎない
・「どの内容を残すか」を決め、ある程度のスタンスを取る
・事業部のKPI作成などに協力し、事業計画の解像度を上げる
・事業部との接点を増やして、率直なフィードバックをもらう
・完成した事業計画を全社員が閲覧できるようにする
(デザイン:古賀裕一郎 取材・執筆:福岡夏樹)
更新の通知を受け取りましょう

























投稿したコメント