なぜケアテック起業家の私が、クリエイティブを学び始めたのか。
この春から、私は株式会社GOが主催する、「THE CREATIVE ACADEMY」(以下TCAと表記)を受講し始めました。(私が受講しているのは「超実践コース」になります。)

このアカデミーではクリエイティブ・マーケティング・PRを中心とし、単なる広告行為に留まらない、事業成長を見据えた学びを受けることができます。
下記にTCA HP内にあるアカデミーの説明文を抜粋します。
THE CREATIVE ACADEMYは、これまでのべ1.8万人以上のビジネスパーソンが受講した、クリエイティブ能力向上を目的とした教育プログラムです。日本最高峰の現役のクリエイター、経営者、マーケッターの実際の企画や事業のプロセスを事例に、具体的な考え方や視点を実践的に学ぶことができます。受講後、ACCヤングコンペの受賞やGOをはじめとする広告業界への転職など具体的な成果への繋がった方を多く輩出しています。THE CREATIVE ACADEMY HPより抜粋(https://thecreativeacademy.com/)
なぜ起業家である私がクリエイティブ周りの学びを始めたのか、その中でどんな学びを得始めているのか。そしてそれは、ケアテックを生業とする者にとってどれだけ意義深いものであるかを、気持ちが新鮮なうちに書き留めておこうと思います。
目次
なぜ起業家である私が、クリエイティブを学ぶことにしたのか
「来るまで待つ」と「読んで打つ」の違い
ケアテック企業はクリエイティブを学ぶべき
なぜ起業家である私が、クリエイティブを学ぶことにしたのか
私は起業家であり経営者です。そのため製品を新しく世に出す際や、プレゼンテーションを作る際など、あらゆる場面で、クリエイターやデザイナー、プランナーやコピーライターの方々に助けてもらってきました。
私が代表を務める株式会社abaではこれまで、排泄センサー「ヘルプパッド」を発売しており、また昨年は介護の願いを叶える「ねかいごとプロジェクト」を発足させました。


その度にクリエイターの方々には、十分に言語化が済んでいない、私の考えやビジョンに寄り添っていただき、プロジェクトやプロダクトのコアアイディアを捻出することに尽力いただいてきました。
しかし近年、その活動の中で自分自身に苛立つことが増えていきました。
私の言語化がもっと進んでいれば、ビジョンを解像度高く伝えられれば、もっとクリエイターの方々に早く意図が伝わり、コアアイディアに辿り着くまでの時間を短くできた場面や、制作物を作っていただく時間を短縮せずに済んだ場面が目立つようになっていきました。
それでも納期内にコアアイディアを出し、クオリティを担保されるクリエイターの方には頭が上がらないのですが、一方で発注者としてもっとレベルを上げる責務を必然性を、日に日に感じていきました。
先日も勢い余ってXに受講における思いの丈を投稿しました。
起業家でクリエイティブを1から学ぶって、結構振り切った決断ではあったと思う。
— 宇井吉美 (@Wieee_aba) May 9, 2024
でも、発注しても発注しても、発注時の自分のオーダーがふわふわしすぎていて、上がってくるもののクオリティが満足しないことに、苛立ちが募ることが増えていた。
ならば発注者のレベルを上げるしかない!!!
会社もスタートアップの調達ラウンドでいう「Aラウンド」を超えており、事業成長もアウトプットのクオリティも一定レベル以上を求められる中で、いつまでもふわふわしたドリーミーな発言しかできない自分だけが、会社の成長スピードから取り残されていくような焦りさえ感じていました。
そんな中、TCAの広告をSNSで拝見し、受講内容を一通り見終わった瞬間、「これだ!」と思い、そのままエントリーボタンを押しました。(受講への意気込みを書く部分は、全て語尾を「!」にして暑苦しかった気がします‥笑)
起業家がクリエイティブについて本気で学ぶ。かなり振り切ったこの決断は、日々関わるクリエイターの方々への敬意と、反してプロジェクトのボトルネックになり続ける自分自身への苛立ちからでした。
「来るまで待つ」と「読んで打つ」の違い
現在、全12回中の3回の受講が終わり、課題提出を2回行いました。
ここまで受講して一つ気付いたのは、私たちケアテック企業が世の中に対して行なっていることは、「来るまで待つ」であることでした。
確かに介護現場でのテクノロジー導入は、ここ数年で加速度的に進んでいます。
介護ロボット補助金の拡充(今年度からは名称変更予定)、生産性向上委員会の設置が前進するなど、テクノロジーを活用し、持続可能な介護現場を国を挙げて推し進めています。そしてこれは、高齢者の増加や生産人口の減少を踏まえると、当然来る未来として誰しもがわかっていたことでもあります。
だからこそ、私たちケアテック企業に求められていたことは、その時が来るまで待つ忍耐力でした。コツコツと研究開発を続け、現場の声にひたすらに耳を傾け、それを一つ一つプロダクトに反映させていく。まさに素手で大岩を押すような戦いを5年10年とし続ける。この忍耐戦に打ち勝ったケアテック企業だけが、今も生き残っています(なのでケアテック関係の展示会に行くと、競合というよりも戦友という感じで双方にコミュニケーションを取るため、他業種から転職してきた当社のメンバーにはよく驚かれます)
一方、クリエイターやマーケッターの方がされているのは、「読んで打つ」だと実感しました。
波乗りで例えるならば、私たちケアテック企業は、波乗りに使う乗り物は変えません。それはずっとケアテックであり、例えばサーフボードなのかジェットスキーなのか、とにかく波に乗るその日まで、同じ乗り物で待ち続けます。だからこそ、その乗り物に一番適した波を、ひたすら待ち、タイミング良く打ち込んでいきます。
けれどクリエイターやマーケッターの方々は違うと思いました。
次にどんな波が来るのか、それは大波なのか小波なのか、右からなのか左からなのか、渦なのか真正面からかを瞬時に見極め、見極めた瞬間から、その波に適した乗り物を選定します。場合によっては乗り物から作り始めます。それがサーフボードになろうとジェットスキーになろうと、はたまた大型船になろうと関係ありません。あとは選んだ乗り物をいち早く誰よりも乗りこなし、誰よりもカッコよく波乗りを決めていきます。息つくまもないというのはこのことです。そしてここで求められるのは忍耐力ではなく、圧倒的な瞬発力であると思いました。

今こそケアテック企業はクリエイティブを学ぶべき
私たちケアテック企業に、このような瞬発力が求められる場面は、そこまで多くないでしょう。けれどもし、来るまで待つ忍耐力だけでなく、読んで打つ瞬発力も手に入れたなら、もっと私たちケアテック企業が届けられる範囲は広がっていくと思うのです。
例えば昨年から、経産省さんが「OPEN CARE PROJECT」というプロジェクトを立ち上げられました。経産省さんが介護関係のプロジェクトを発足されるなんて、数年前までは思いもよらなかったと思います。
けれど止まらない介護離職や、それに伴う経済損失を考えれば、予想できたこととも言えます。座して待つも良いけれど、もっと情勢を読んで打つ力を持てば、社会のうねりを大きく変えることも出来るはずだと、TCAでの学びから実感しています。
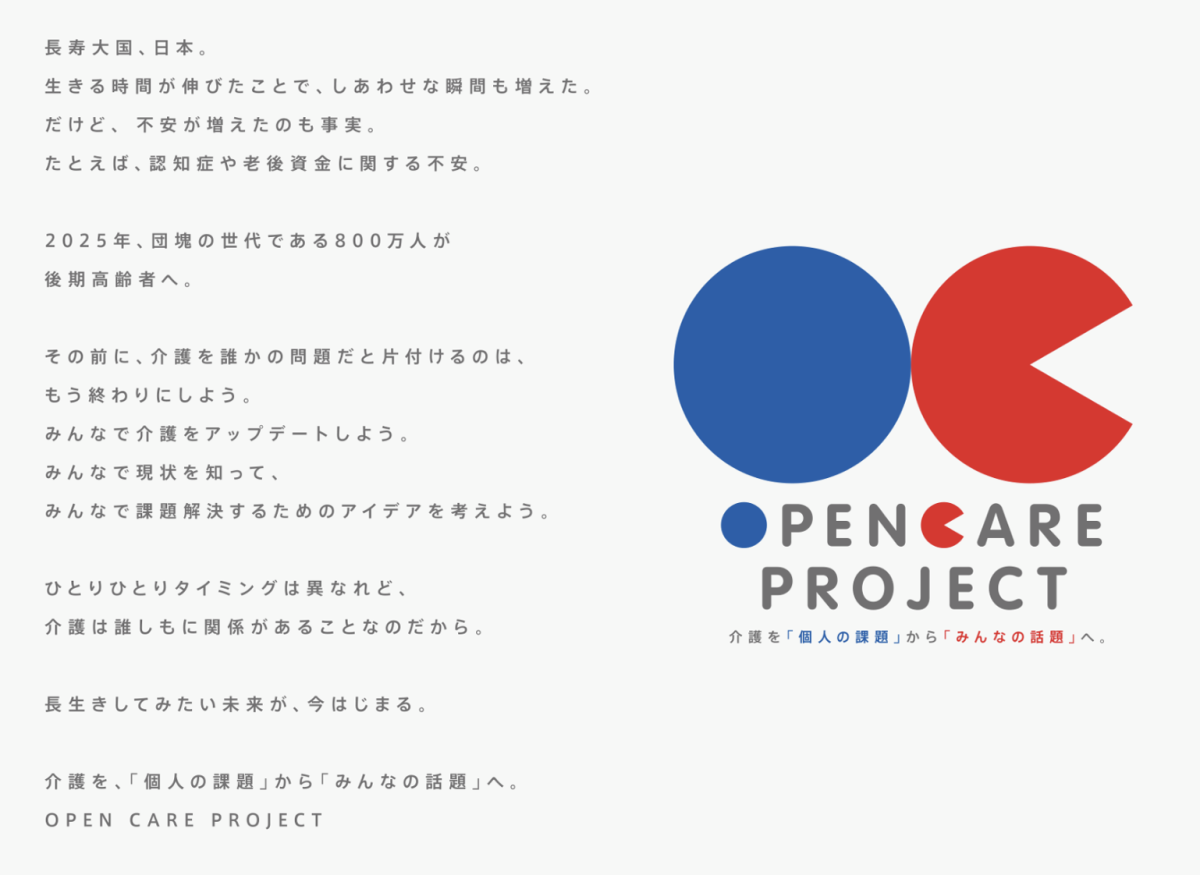
毎年10万人が自分の仕事を辞めて介護をしており、中学生の17人に1人が親兄弟の介護をしている日本社会において、介護がまったく関係のない人などいないはずです。
だからこそ一日でも早くケアテックを介護現場に届けるために、人の感情を揺さぶり届けることを専門とするクリエイティブを、今こそケアテック企業は学ぶべきだと確信しています。
今後もTCAでの学びをこちらの記事に展開していきたいと思います。引き続き頑張って受講していきます!

更新の通知を受け取りましょう
























投稿したコメント