「AI半導体時代」日本に勝ち筋はあるのか?
「マクロ経済教室」へようこそ。
11月21日、NewsPicksの番組『THE UPDATE』に出演。テーマは「AI半導体時代」日本に勝ち筋はあるのか?これからの10年で生成AIの市場規模は32倍に拡大する見通し。
自身は、アナリストとして半導体分野を1つの業界として追いかけてきた。しかし、株式市場の分析のなかで最難関の1つが「半導体分野」だろう。気づけば半導体を学び始めて8年経っていた。株価の分析をするにも、半導体をめぐるあらゆる仕組みや業界動向、専門用語など最低限の知識が必要だ。さらに、景気敏感株であるため、米国・日本の金融政策の影響を色濃く受けるため、分析が複雑すぎる業界でもある。今回の出演の役割として、金融業界から見える範囲で「半導体業界の動きをまとめつつ」「これからの期待できる勝ち筋」「機関投資家の動き」などについてお話させていただいた。
番組内では、一橋ビジネススクールの楠木 建特任教授から「競争戦略」の切り口で半導体について分析していただいた。企業の競争優位を構築する理論のご専門である楠教授が分析する「半導体の戦い方」は必見。日本がどういう視点をもち戦うことで、優位性を構築できるのか、未来に明るい光を照らしていただいた。
古坂 大魔王が「Mr.半導体!」とお呼びされた、東京大学の黒田 忠広教授の視点から半導体の「未来の姿」をお話。日本の半導体が世界No.1の頃から、長きに渡り日本の半導体業界を分析されている黒田教授。凋落の時期を経て、いま半導体戦略で立ち上がる日本に「必要なこと」。心がしびれるお言葉が炸裂。ぜひ動画で皆さんも「しびれて」みてください。
レゾナック・ホールディングス常務執行役員、CSO真岡 朋光氏からは、まさに現場で起きている半導体の現状とそこからの見えてくる「勝ち筋」について。半導体製造装置、半導体素材、検査装置、パワー半導体など半導体といっても多岐に渡るこの分野で真岡さんの言葉から「勝ち筋」が見えてきた。
今回のトピックスでは、番組内でも自身が解説した、「いま、半導体業界」で起きている現象「カエル飛び」と「モア・ザン・ムーア」について執筆する。
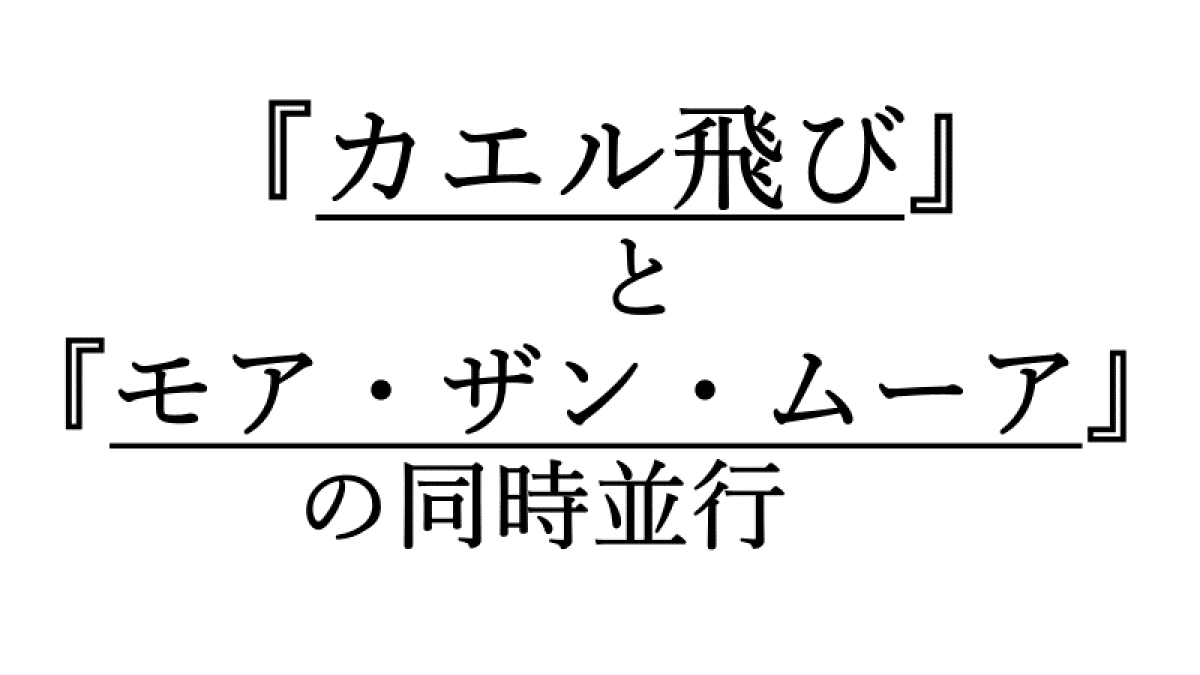
『カエル飛び』と『モア・ザン・ムーア』の同時並行
■「超 AI時代」 半導体産業で何が起きるか?
生成AIの登場によって、半導体業界の時計の針が、グッと早まった印象だ。「ロジック半導体=頭脳」はサービスを作り出す力がある。軍事技術、セキュリティ、様々な部分で演算力が必要に。演算力が国力に繋がるとも言えよう。つまり、ロジック半導体の確保は国力戦に突入している。国を挙げた戦いで強化しなければ、半導体の覇者に従うしかない。いま、半導体業界で起きている現象は。『カエル飛び』と『モア・ザン・ムーア』の同時並行だ。
■まず、『カエル飛び』
カエル飛び=リープフロッグとは、もともと途上国や新興国で新しいデジタル技術が一気に普及することを指す場合に使用されてきた概念だ。
しかし、日本の半導体分野にもそれが当てはまる可能性がある。
世界の半導体市況は、先端半導体の技術基盤を作り、微細化を突き詰める動きが加速している。その代表例がまさに、北海道に設立、稼働を目指す「ラピダス」。ラピダスはAIなどに使う次世代半導体を国内で量産するために、トヨタ自動車やNTT、ソニーグループなど日本企業8社が設立した会社だ。ラピダスは微細化の技術を突き詰め「2ナノ」の製造にチャレンジするわけだが、日本の先端半導体の開発が「40ナノ」で止まっている。
ちなみに、台湾のTSMCは2022年12月からアップルのiPhone向けの3ナノの量産開始。サムスンは22年6月に3ナノの生産を初めている。
「40ナノ」から「2ナノ」に飛躍。
まさに「カエル飛び」を狙っているわけだが、それができる理由が次のような内容だ。演算を行う核となる構造がこれまでの半導体と大きく異なるのであれば、積み上げ式の技術がなくても、全く新しく引き直されるスタートラインから勝負できるという考え方だ。
カエル飛びの動きは、なにも、日本のラピダスだけに限った話ではない。
GAFAM、そのほかのスタートアップ企業など元々半導体の技術など持たない企業が自前の先端半導体を作ってしまおうじゃないか。こうした動きが出てきている。
これは、積み上げ式でなくでもだれでも参入できる業界になりつつある兆候かもしれない。・・・民主化。つまり、番組内で、黒田教授が言及した「半導体の民主化」のキーワード。
これは、その先の半導体業界を見通す上で重要な視点になってくるでしょう。
詳細は番組内で確認してほしい。
■モア・ザン・ムーア「ムーアの法則を上回る」
半導体業界はムーアの法則でここまで拡大してきたが、限界を迎えている。
ムーアの法則の説明はNewsPicksジャーナリストの平岡乾ジャーナリストの以下の記事内での説明が最も変わりやすいため引用させていただく。
【決定版】10年後も役立つ半導体理解「5つのカギ」
ムーアの法則とはトランジスタの集積度が2年で2倍になる①半導体のパワー(データの処理能力や保存容量)が「2年で2倍」になる②半導体のスモール化(消費電力と価格の下落)が「2年で半分(2分の1)」で進む
平岡乾ジャーナリスト 【決定版】10年後も役立つ半導体理解「5つのカギ」
つまり、指数関数的に半導体のパワーはアップし、小さく(微細化)していく。
これがムーアの法則である。
しかしだ。「2ナノ」のフェーズにまで来ると。そろそろ微細化技術、ムーアの法則が限界に来ている。微細化だけに邁進していると足元を救われる。
そこで、半導体業界が次に追い求めているものが「機能追加」になる。ムーアの法則を超えた「モア・ザン・ムーア」の世界に突入し、その動きが加速している。
例えば、省エネができる半導体の開発、こうした開発は半導体の後工程がポイントになり、かつ「半導体の素材分野」が半導体の性能の能力を左右する。日本が強い、半導体製造装置、半導体素材が力を発揮するフェーズだと言えよう。
そのほか、生成AIの普及により、データセンターも規模が必要になる。
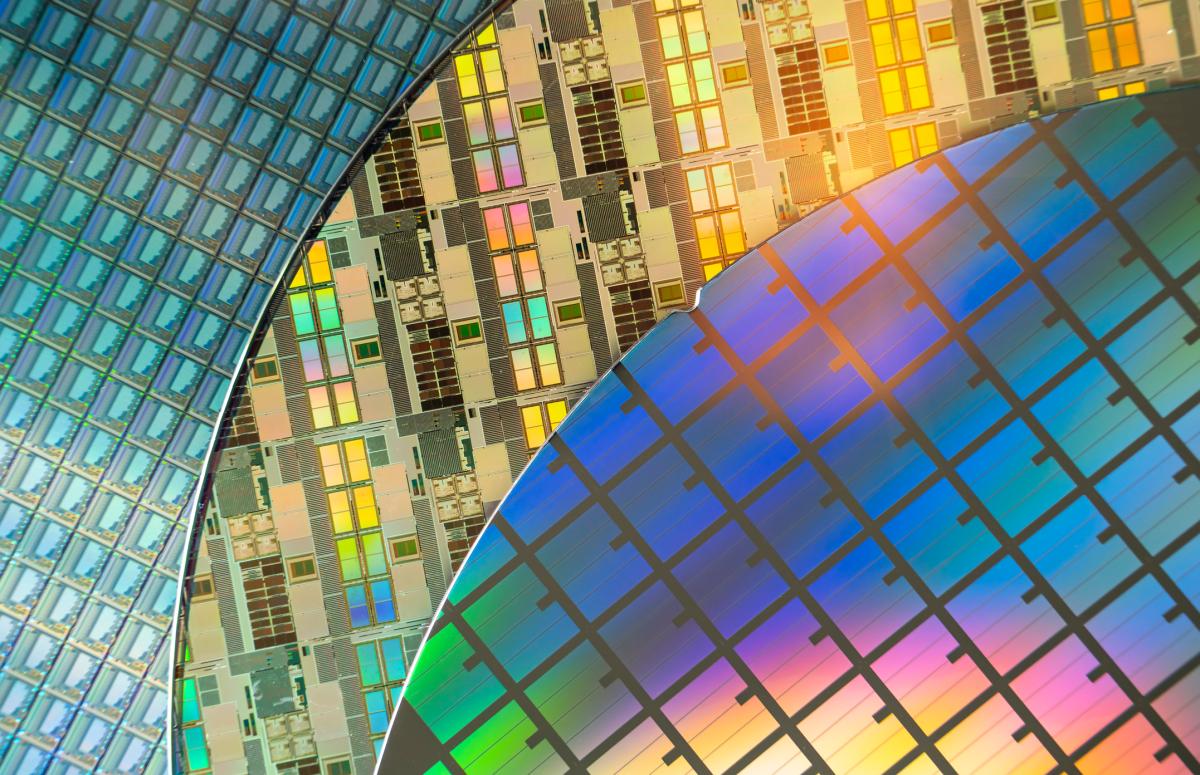
■NTTも商機?「光電融合技術」とは
そうした時に、NTTが考えているアイオン構想の「光電融合」の技術開発にも可能性が広がる。半導体の信号処理を電気だけでなく、光で行っていく技術と組み合わせていくなど既存領域とは異なるような、半導体が生まれくるかも・・・?と
NTTによれば、パソコンに複雑な処理をさせると、パソコン本体が熱くなる。パソコンが熱くなるということは、本来必要のない熱を発生させることにエネルギーが使われているということを意味する。さらに、発熱すると電気の通り道の抵抗が大きくなり計算速度の低下にもつながる。そこで、これまで電気で行なっていた計算を、光を用いた処理に置き換える研究が進められている。つまり、コンピューターの内部回路を、できるだけ電気を使わず光でつなぐことを目指し、省電力かつ低遅延を実現させる研究。光には電気に比べてエネルギー消費が小さく、遅延も起きにくいという大きなメリットがある。エネルギーの無駄遣いや処理の遅れを大幅に減らすことができる。※
こうした、光電融合技術が半導体で使われる研究も行われている。
■ラピダスに関する”課題” 主な意見
番組内で議論しきれなかった、ラピダスに関する意見。
ぜひ、専門家の皆様と前向きな議論をしたかったテーマの1つだ。技術の部分に関しては、金融業界のアナリストが出る幕ではなく、半導体の専門家に委ねたいが。
新しいスタートラインから勝負できるような分野であるならば、チャレンジの価値がある。ラピダスの「2ナノ」の製造に懐疑的な意見もあるが、5兆円の投資が必要だと言われているこの分野に、国は本腰を入れている。
▷半導体専門家の意見でラピダスに関する懸念点をまとめる
私の意見ではなく、アナリストとして(世の意見をまとめる役割)とさせていただく。
①そもそも「2ナノ」技術の飛躍は可能なのか?
②ラピダスの工場で製造する前の段階のプロセスの開発はLSTCが担う認識だが、 LSTC(技術研究組合最先端半導体技術センター)は研究機関であるため量産化に対応できるようなプロセス開発ができるのだろうかという問い。
③ラピダスは、前工程と後工程を同じ場所で行うわけだが、日本が昔、失敗した垂直統合とは異なるのか?今回は「オールジャパン」にこだわらず、様々な国と連携して進めている点が過去の垂直統合とは異なると言えるのか。
④そもそもラピダスの作った半導体を誰が買うのか「顧客視点」。今回のラピダス構想は「顧客視点」でありユーザーは米国IBMやスタートアップ企業だと言われているが、冒頭で述べた「カエル飛び」で自前の半導体を作ってしまう懸念はないのか。ユーザーを確保する戦略はあるのか。
こういったところが主な意見だろう。
もし、経済アナリストとしてラピダス社に取材させていただく機会をいただければ、こうした点を伺いたい。ひとつひとつ、疑問点を解消していく役割がアナリスト、取材者の役割だと思い活動している。半導体専門家だけでなく、国民への説明も嚙み砕いて届けることも必要だと思う。
黒田教授がおっしゃった「半導体の民主化」に向けて、志のある者たちがそれぞれの持ち場で力を合わせていけたらいいと思う。
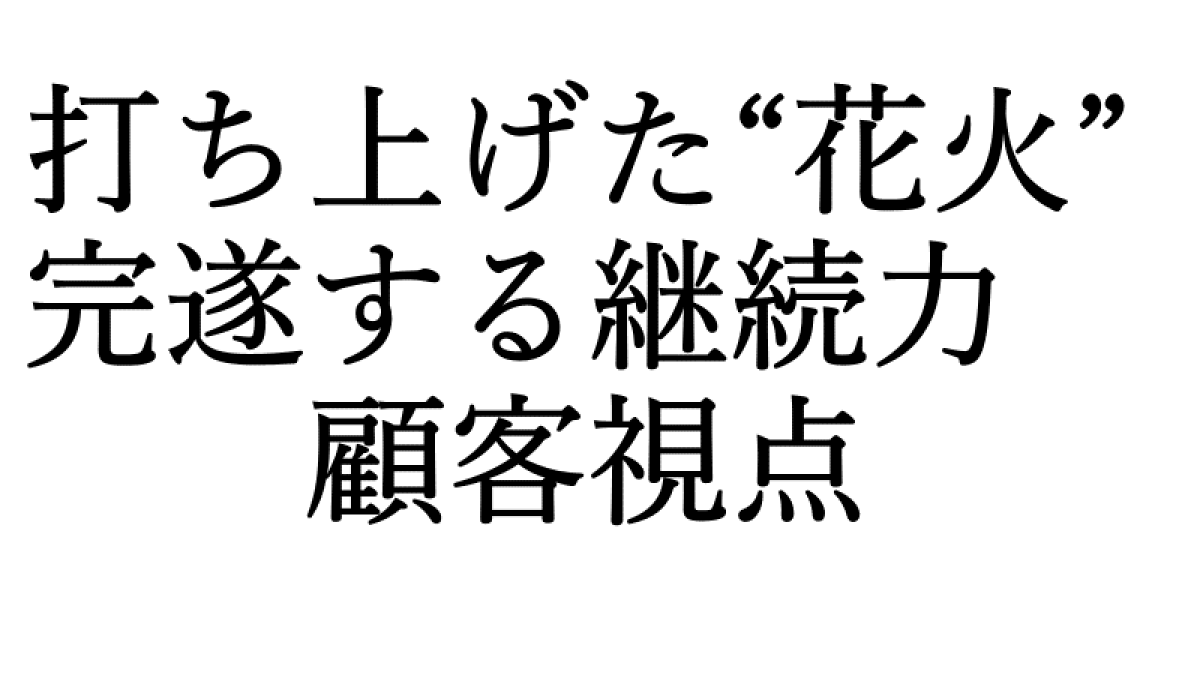
最後に、オランダの露光装置ASMLの戦い方を紹介する。勝ったものが、より勝つ。これが、いまの半導体の業界の構図になっている。
ASMLはEUV装置は1台200億円にも関わらず、生産台数が年間40台ほど。みな喉から手が出るほど欲しいがそもそも台数が限られている。専門特化できた企業は、こうした戦い方ができる。
日本にも、半導体素材、製造装置、検査装置、といった世界に誇る強い分野がある。さらに、様々な後工程の企業の技術を組み合わせることで付加価値も高められる。ASMLのような戦い方も夢ではない。
政府は「半導体戦略」という“花火” ーグランドデザインー を打ち上げた。
素晴らしい肝いりで、台湾のTSMCの誘致を驚くスピードで成功させている。11月21には第3工場の建設の報道もある。そのほか、半導体関連の企業の国内での投資、工場設立が加速していることも、「半導体戦略」がスタート地点となっている。
萩生田議員が言及されたが。
華々しく打ち上げられた花火を、最後までやり抜くところまで完遂してほしい。
継続力を、誰もが望んでいることだ。
詳細は2023年11月21日放送の『THE UPDATE』
課題に向き合いながら、前向きな未来が見える議論。日本の半導体の現状をスッと理解でき、未来にワクワク感が生まれます。業界を愛し、そして業界の中で戦っていらっしゃる皆さまのお言葉を受け取って欲しい。
ーーーーー
※参考
更新の通知を受け取りましょう


























投稿したコメント