テキスト(書かれた文字)の発明こそが「私」という自意識の根源である
映像メディアと活字メディアは、相異なるものとして比較されたり対照されたりすることも多いですが、目で「見る」メディアとしては同じものと言えます。言葉はもともと声でした。それが、やがて文字となって、石板や羊皮紙、紙の上に書かれるようになりました。人間がいつから言葉を話し出したのか、まだ定説はありませんが、古いところでは10万年くらい前だと言われています。一方、文字が生まれるのは6000年ほど前で、読書が声に出して読み上げる行為ではなく、沈黙のうちに目で「見る」行為へと変化したのは、今から800年ほど前に過ぎません。しかし文字を「見る」行為は、人間の意識に驚くほどの変化を生じさせました。
書物は音読して初めて理解できるものだった
哲学者のイヴァン・イリイチは『テクストのぶどう畑で』(岡部佳世訳、法政大学出版局、1995年)の中で、中世における修道士にとっての書物とはどんなものだったか、詳しく解説しています。当時は、黙読のできる人物は稀で、ほとんどの人にとって読書とは音読が普通の時代です。その頃の書物(印刷術の生まれる前なので、もちろん手書きの写本)は、今の書物とは見た目も全然違うものでした。まず、目次もなければ見出しもなく、そもそも語と語のあいだのスペースさえありませんでした。それはとてもとても読みにくい代物です。しかし忘れていけないのは、単語というものさえ、後世の発見だということです。人の話す言葉が、音節、単語、文に分割できるというのは後世の発見であり、書物が「読み上げる」ものではなく「見る」ものになったのは、つい最近のことでしかないのです。
したがって、かつての読書とは、洞窟を歩いてゆくような行為にほかなりません。語と語のあいだにスペースがないということは、ページの上へパッと目を走らせても、言葉の意味が頭に入ってこないということです。行から行へ、一歩一歩確実に、アルファベットを音に変換しながら声にして読み上げる以外、そこに書かれている意味を理解する手立てはないのです。アルファベットを音にして、自分の口から出た音を耳で聞いて、初めて意味がわかる。人間がレコードプレーヤーのような役割だったわけです。しかも、目で読める現代の書物ではないので、何が書いてあったかしっかり頭に記憶する必要があります。なぜなら、何がどこに書いてあったか、ふたたび見つけるのは非常に手間がかかるからです。確認するためには、また最初から音読する以外に手はありません。目で「見て」文字から意味を取れないとは、なんと不便なのでしょう。しかしかつてはそれが普通であり、だからこそ人々は偉大な記憶力を持っていたのでした。
「見る」書物の登場
しかし、中世も後期になると、だんだん書物は読み上げるものから目で見るものへと性質を変化させます。単語と単語のあいだにスペースが生まれると、パッと見ただけで意味がとれて、文章を視覚的に理解できるようになります。そのための工夫として、パラグラフ、句読点、見出し、目次、索引、ノンブルなどが生まれます。こうした工夫のおかげで、人は書物を素早く読むことが可能となり、必要な情報を素早く見つけ出せるようになったわけです。こうした書物のスタイルの変化は、読書の効率化を目指したものであり、タイパ重視の流れが引き起こしたものに他なりません。こう書くと、書物は明らかに進化したような印象を受けます。しかし、良い悪いは別にして、書物を「見る」ようになったとき、人間の意識にも劇的な変化が起きました。私たちのコミュニケーションが声から文字(テキスト)へ大転換すると、「私」という意識が生じたのです。あまりに突飛に聞こえるでしょうから、順を追って説明しましょう。

現代人の私たちは、言葉とはそもそも書かれた文字の姿がその本質的な姿であるように錯覚していますが、そうではありません。古代から中世半ばまで、人と人の会話は、記号としての言葉の交換ではありません。なぜなら、声でしかない言葉は、その言葉を発する人から独立した何かであるという発想が、そもそもないからです。現代人にはピンと来ませんが、かつて言葉は人の霊そのもので、人の存在と別個にある何かではなかったのです。文字が書かれ、写本が作られるようになっても、しばらくの間、言葉は声そのものであり、概念や意味の媒介物とは考えられていなかった。言葉は、現代人が思っているような、意味を伝える媒介物、記号ではなかったのです。それは人間そのものでした。
テキストが内面世界を生む
しかし、文字が書かれるようになると、特に活字が登場してくると、言葉は個々人のものというより、誰のものでもない、中性的で抽象的な記号のような気がしてくる。ウォルター・J・オングは『声の文化と文字の文化』(桜井直文他訳、藤原書店、1991年)で、「書かれたことばというのは残りかすである」(p.32)と言ってますが、イントネーションも調子も気分も奪われた言葉は、完全にその発声主の肉体を失っています。声によるコミュニケーションが当たり前の時代には、相手がいなければ人が言葉を発することはありません。しかし書かれた文字が当たり前の世界になり、私たちが書くことでコミュニケーションをとるようになると、途端に他者の姿は世界から消えてしまいます。話すとき、相手は肉体を備えた他者として目の前にいますが、書くとき、相手の姿はそこにありません。対話者は私の想像上の存在にすぎなくなってしまい、他者も私の想像が生み出したフィクションのようなものになってしまうのです。
読み書き能力を身につけると、私たちは文字を物質そのもの、人そのものとしてではなく、抽象的な概念として理解するようになります。そうして概念を、現実世界とは別に、私たちの想像の中だけでいじくり回せるようになると、私たちの知性は飛躍的に向上します。言葉は考えるための道具となったのです。しかし、何か複雑なことを考える手段として、書く言葉を用いるようになると(紙の上に字を書いて考えるようになると)、「私」が分裂してしまうことも確かです。他者がいないのに言葉を用いるということは、自分と対話するということです。つまり、書く「私」がいて、書かれたことを反省する「私」がいる。文字が使えるようになるということは、「私」が二人になることなのです。「私」がもう一人の「私」を相手にコミュニケーションするようになるということなのです。こうして、読み書き能力の習得は、自我を生み出すに至るわけです。
本来、言葉は他人と「私」をつなぐものでしたが、現代においては「私」を「私」の世界に閉じ込める傾向が非常に強い。それは、言葉が他者性を失ってしまったからです。テキスト(書き言葉)を綴るとき、そのテキストが他者に向かって書かれようと自分に向かって書かれようと、「私」は空想の対話者(つまりもう一人の「私」)を相手に話しているにすぎません。それはどこまで行っても孤独な行為です。声に出す言葉から、「見る」言葉への時代の変化には、私たちと他者(世界)の乖離が副産物としてあります。他方、読書は非常に効率化され、もはや紙の書物すら不要となり、スクリーン上の記号となった情報の集合体は、情報処理の効率化をこそ目指しています。中世から現代へ至る言葉の歴史の中で、我々人間が獲得したものも多い一方で、失ったものも多いと感じます。
トップ画像はUnsplashのWaldemarが撮影した写真
更新の通知を受け取りましょう



















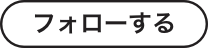


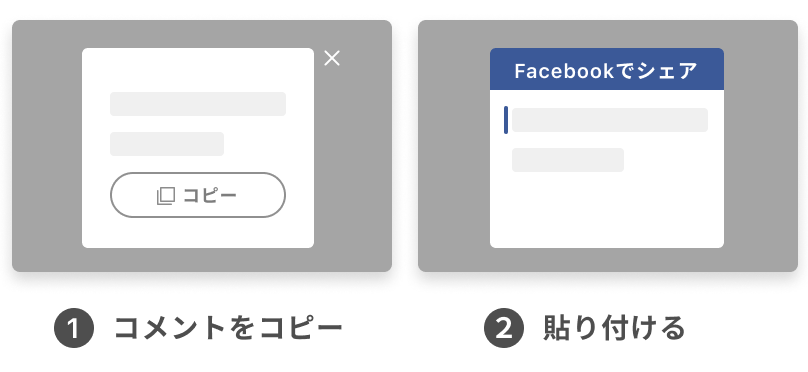

投稿したコメント