日本の貧困問題
*生活保護で痛感したシングルマザーの訴え
私が最初にドキュメンタリーの取材(本格的なニュース取材)を始めたのが、1987年のことです。当時、札幌の民放テレビ局にいたのですが、1月の寒い日、小学生2人と中学生の男子3人を育てるシングルマザーが餓死した姿で発見される事件が札幌・白石区で起きました。まだ時代はバブル経済の後期です。世の中はバブル景気が続いていて「世界第2位」の経済大国のはずなのになぜ餓死する人がいるのか? そのギャップは社会に大きな衝撃を与えました。餓死した母親は飲食店などでパートやバイトのかけ持ちで働いて体調を崩し、収入が途絶えがちになり、区役所の生活保護の窓口を訪問していたこともわかりました。聞き込み取材をするうちにこの女性が「生活保護の窓口で恐い目にあった。二度とあそこには行きたくない」と話していたという情報をつかみました。こうした情報を道内ローカルのニュース番組で放送し、生活保護について「体験談をお寄せください」と呼びかけたところ、北海道中から電話が殺到する事態になりました。多くが餓死した女性と同じ母子家庭の母親からでした。
「『女なんだから体を売ってでも食べていく方法はあるはず』と言われて生活保護の申請もできなかった」「『夫がいたのに離婚して母子家庭になったあなたの自業自得だ。別れた夫に土下座してでも復縁してもらえ』と言われた」「生活保護を受けることになったが、ケースワーカー(自治体の生活保護担当の職員)が体を求めてくる。拒めば『生活保護を打ち切られるのでは…』と恐くなり応じた」など。
涙ながらの訴えも多く、一度の電話で1時間2時間と話し続ける人たちがいました。「ずっと誰にも言えなかったことをテレビや新聞などのメディアで初めて聞いてくれた」。多くの女性たちがそういう感想を口にしていました。
こうした証言をしてくれた本人に実際に会いにいくと、実際に質素な暮らしをしていました。
生活に困った人が生活保護を受ける場合、まずは申請書に記入して申請という手続きを行うのが最初の一歩になります。ところが、電話をくれた多くの女性たちが話していたように生活保護の申請という手続きにいたる前に職員から数々の暴言を浴びせられたあげく「あなたは該当しない」と思わされ、申請をあきらめさせられていました。そうした実態が北海道中で蔓延していることがわかりました。背景には厚生省の指導方針などがありました。ドキュメンタリーを全国放送したところ、全国各地で行われている実態だと判明しました。
こうした運用は現在は「生活保護の『水際作戦』」と呼ばれていますが、当時こういう言葉はありません、生活保護は憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を送る権利、つまり生存権に裏打ちされた制度だと考えていた私はどうしてこうなっているのかと戸惑いながら取材しました。
市役所の生活保護の窓口の周辺で取材していると、生活保護制度についてきちんと説明されていないというシングルマザーにも会いました。そうした人と立ち話をしていると、男性職員が飛んできて「なぜ記者にそんな話をするのか」と女性を非難してきました。生活保護は様々な闇を抱えている…。そのことに気がつき、当時、メディアでこの問題を深く取材する人があまりいなかったこともあって、放送した1本のドキュメンタリー「母さんが死んだ〜生活保護の周辺〜」は全国的に評判を呼びました。放送後に自治体関係者の前で講演したり、出版社から依頼が来てノンフィクションの本も書くことになったりで、生活保護の専門記者のようになりました。
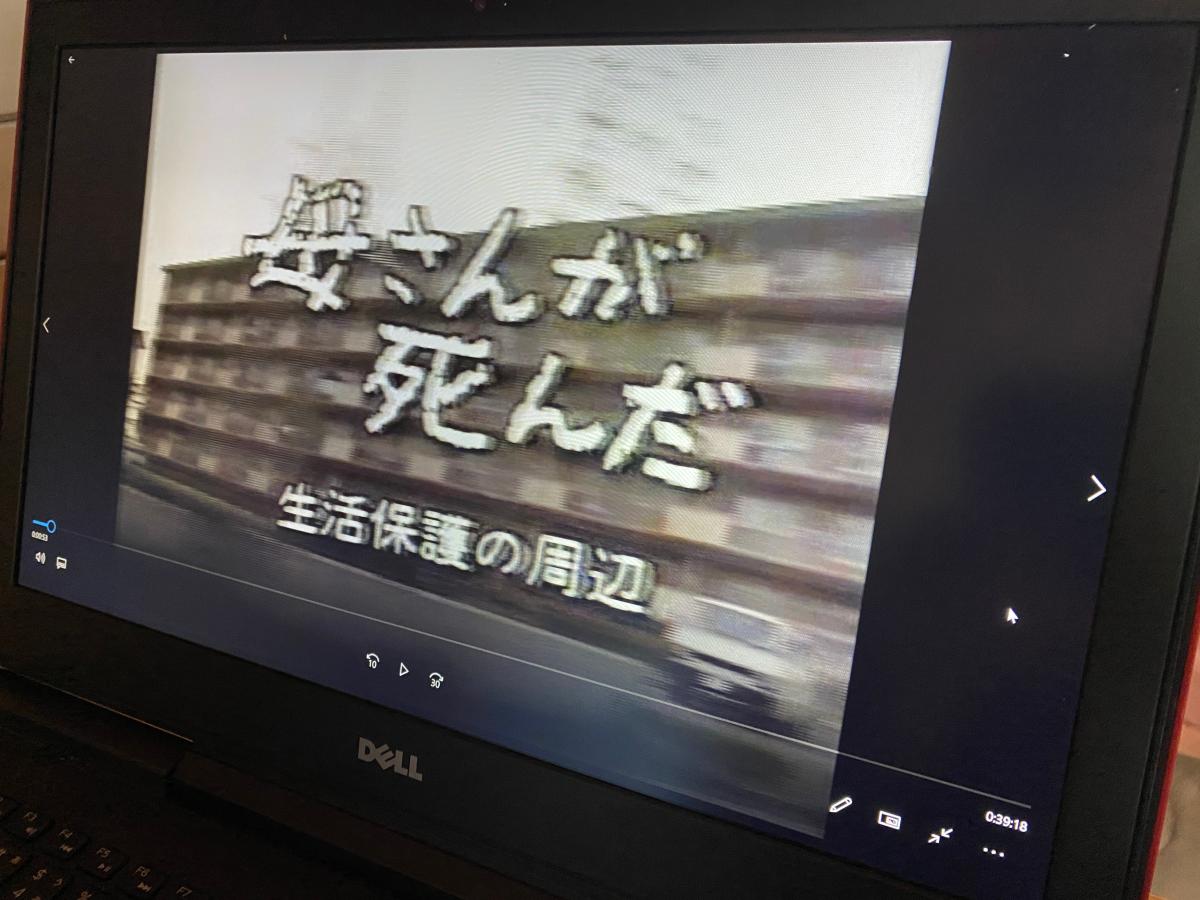
*英国での「貧困報道」と比べて希薄だった「貧困」の背景・構造への意識
この頃は自分が取り組んでいることはあくまで「生活保護」の問題であって、それを深掘りしているのだと考えていました。あまり社会の構造にまでは目が行き届いていなかったのです。
シングルマザーたち、女性たちは離婚したり夫と死別したりすると、たちまち生活に困窮してしまう。その構造に当時は気がついていませんでした。研究者によると日本社会は男性が圧倒的に優位な企業中心社会で、男性が社員として企業に勤めることで賃金を得ています。他方、女性は正社員になっても結婚するまでの期間限定の若い時期に企業でお茶くみなど補助的な仕事をするだけ。高度成長期からバブル期にかけての国や社会が想定してきたモデル的な家族のあり方は、わかりやすくまとめるならば、父親が大企業などで正社員として働き、妻は専業主婦。子どもは2人くらいというものでした。働く人間の賃金水準も、社会保障の制度もこうした家族像を念頭において設計されていました。
女性は結婚した後に働く場合もパートやバイトなどであくまで家計を副次的に支える程度だとされていました。賃金も安く、あくまで意思決定は男性の正社員に委ねられ、その補助的な仕事を想定されていました。このため、結婚している女性が夫のいない状態で一人で家計を支える立場になると、とたんにパートなど低収入で生活しなければならなくなって生活困窮に陥ってしまいます。
これがシングルマザーを取りまく「貧困」の背景です。日本のひとり親家庭の貧困率は先進国の中でもとりわけ高く、50%を超えるレベルです。
こうした「貧困」の構造に目を向けなければならないと気がついたのは、1987年〜1992年までの5年間、ロンドン特派員として駐在したイギリスでのことでした。イギリスではBBCなどの大手メディアに社会保障担当や貧困問題の記者や番組制作者がいて、大手メディアや生活困窮者への支援活動をするNPO、大学の研究者などが組織の枠を超えて毎年のように貧困問題のキャンペーン報道をしていました。これを目撃して自分も「貧困」問題の専門記者にならなければ…という意識を強く持ちました。
特派員として1989年の「ベルリンの壁」崩壊などを取材しましたが、旧東ドイツから旧西ドイツに初めてやってきた家族がマクドナルド・ハンバーガーが入っていた容器を大切そうに持ち帰る姿などを目撃しました。東欧での民主革命やソ連崩壊を取材し、「経済」や「格差」の問題が社会生活に大きな影響を与えるという認識を持ちました。
*准看護師の「お礼奉公」問題で知った女性差別の構造
1992年から1997年にかけてニュース取材を重ねてドキュメンタリーにしたのが准看護師の「お礼奉公」問題です。准看護師は中卒以上の学歴の人が医師会立などの准看学校に2年間通って資格を取る仕組みですが、多くの准看学校の生徒は医師会に所属する開業医の医院などで看護助手として勤務し、「働きながら学ぶ」というかたちになっていました。看護師や准看護師は当時、「看護婦」や「准看護婦」と呼ばれ、男女比では圧倒的多くは女性でした。「准」の一文字がつく「准看護婦」になるための准看学校の生徒は職場によっては過酷な夜勤をやらされたり、まだ資格がない看護助手なのに資格が必要な点滴や注射を「無資格で担当させられている」という内部告発が相次ぎました。生活保護の取材で力を発揮した、当事者から体験談を寄せてもらうスタイルの調査報道を進めたところ、卒業して准看護師の資格を得てからも数年間、同じ医療機関に働き続けなければならないという「お礼奉公」という習慣があちこちの医療機関で事実上のルールになっていることが判明しました。明らかに職業選択の自由を奪う理不尽が若い女性たちに強いられている現状がありました。そうした実態を「お礼奉公」問題としてテレビでキャンペーン報道しました。夜勤が続く過酷な勤務で無資格の医療行為をさせられて精神的な重圧から自殺に追い込まれたケースも取材で見つかりました。准看教育を行うという名目で最低賃金以下の扱いで下働きをさせる。職場を辞めたときには養成学校も退学させるケースもありました。医療の現場における女性への差別的な扱いが背景にありました。「准看護婦」だけでなく医師会が私的な資格制度として養成していた「副看護婦」という資格をもらったという女性も見つかりました。こうした知られざる事実を発掘していき、報道を重ねたことで1996年に厚生労働省の看護課長が「21世紀初頭に准看廃止する」と表明。これで一気に事態が動くかと思われました。ところがいったんは合意したかに見えた日本医師会が態度を翻したことで今も准看護師という制度はなくなっていません。日本の医療制度で絶大な権力を誇る日本医師会の実力を土壇場でまざまざと見せつけられました。これも日本の医療制度の根本的な構造を「事実」に裏切られたことで思い知ることになった経験でした。
テレビでの呼びかけで准看護師の当事者たちの内部告発を集めたことで他の報道機関ができなかった調査報道のドキュメンタリーを制作することができました。

*欧州や中東、アフリカで取材した難民キャンプ
その後、私は2度目の海外特派員として、ドイツのベルリンに5年間駐在することになります。1998年〜2003年のことです。そこではコソボ紛争など旧ユーゴスラビアの内戦、アフガニスタンでのタリバン政権の崩壊、イラク戦争などで難民キャンプの取材を数多くするようになります。以前もルワンダ内戦や湾岸戦争などで難民キャンプの取材はしていたのですが、「難民」という存在こそ、究極的な貧困の状態ではないかと個人的に関心を持ちました。
難民キャンプで暮らす難民たちは支援物資で食いつなぐことが大半なのであまり長期的なことは考えられません。その日暮らしです。基本的にその日何を食べるかという目先のことに追われています。将来の見通しがなく、刹那的にしか考えられない状態。それも貧困の状態に近いと感じながら取材していました。
2003年に東京に拠点を移して、報道ドキュメンタリーの担当者になります。
そこで「貧困」をテーマにしたドキュメンタリーを制作しようと考えて、生活困窮者の支援活動をする知り合いと雑談していた時に「今、貧困を取材するならネットカフェに行った方がいい」とアドバイスをもらいました。
ネットカフェという場所に行ったこともなかったのですが、2000円弱という格安料金で一晩を明かせるという東京・大田区蒲田のネットカフェで過ごしてみました。
実際にこの格安ネットカフェで夜を過ごしてみると、以前、海外で目撃したのと同じような光景が甦ってきました。
そこでどんよりした目をした人たちを目撃したのです。
*「ネットカフェ難民」という造語でドキュメンタリーを制作
それは海外の難民キャンプなどで目にしてきた難民にとても似た表情の人たちでした。
饐えたにおい。深夜の部屋で怒鳴り合うなど、殺気だった雰囲気。話しかけても余裕がなく人を拒絶する雰囲気。
食べることと寝ること。明日の仕事。宿泊者同士の会話を聞いていると、明日どこで仕事するか、どの職場がいくらになるか、キツいかなど目先のことばかりを話していました。
早朝4時すぎになるとネットカフェから出ていく人々の姿が目立ちます。
多くの人たちが日雇い派遣の現場に当時は携帯メールで「16532、これから出ます」などと日雇い派遣会社の事務所に自分の番号を打ち込んで行動を逐一連絡します。彼らは携帯メールで管理されていました。
ネットカフェに通うようになって次第に話をすることができる人が見つかって、その生活について教えてもらうことができるようになりました。パチンコ屋などでトイレを使い、1時間500円の個室ビデオでシャワーを浴びる…。
1日100円のコインロッカーを「タンス代わり」に使っていました。
日雇い派遣で働き、実家の親などに頼ることができずに、経済的な蓄積などの「タメ」がほとんどない状態の人たち。
「ネットカフェで夜を過ごしていても家がないという点では路上で眠る人たちと変わりない。事実上のホームレスなんです」
こう話してくれた20代後半の男性は、少しお金がある時にはネットカフェに泊まり、所持金がない時には公園や路上で寝ていると打ち明けてくれました。彼は無料の求人誌で様々な職場に派遣される日雇い派遣という不安定な働き方をしていました。倉庫での物品の仕分け作業や建設工事の運搬作業などで8000円程度の日払い収入を稼いでいました。労働の世界の規制緩和政策が生み出した究極の細切れ雇用でした。仕事がある時もない時もあり、当日朝になってドタキャンされて仕事がなくなるケースもあったといいます。
彼が以前住んでいたアパートは「貧困ビジネス」と呼ばれ、貧困層を食い物にしてさらに追い込むような不動産ビジネスが営むものでした。敷金なし・礼金なし・保証人なしで部屋を借りることができるかわりに家賃がかなり割高で、支払いが少しでも滞るとすぐに鍵を交換されて追い出されるという借地借家法に違反する違法な賃貸物件でした。驚いたことにこうした人の中には親にも頼ることはできない人が目立ったことです。そうなると、不動産を借りるにも就職するにも必要とされる「保証人」を得られない。そのため、そうした不利なビジネスを利用するしかありません。先に述べた20代後半の男性もそうでした。実の親に虐待を受けていてもし親に連絡したら実家に連れ戻されてひどい目に遭うというのです。なかには18歳の女性もいました。親や親類から性的虐待を受けて逃げるようにネットカフェを転々として生活していました。日々日雇い派遣の仕事を見つけて働いていました。手帳に自分を戒める言葉を書き綴っていました。この女性ヒトミさん(仮名・当時18歳)が手に持っていた手帳を見せてもらった時は本当に驚きました。
ボールペンで書き綴っていた言葉は「我慢する」「強くなる」「贅沢をしない」「夜ごはんを食べない」「ロッカーの管理」「お金の管理」…
なぜこういう言葉を書いたの…?と思わず尋ねた彼女が語ってくれたのは思わぬ言葉でした。
「これを書いて(気持ちを)上げるんです。これ以上、落ちないぞと自分に言い聞かせて…。落ちて、落ちてにならないように…」
思いがけずに遭遇した“ネットカフェ難民”として生きる少女の言葉。こんな言葉に出会えるとは想像もしていませんでした。ネットカフェでその日その日を生きる人の心情を象徴しているような言葉でした。私はヒトミさんのこの言葉をドキュメンタリーのラストに使いました。ヒトミさんのような人間が社会に増えている。そうした事実上のホームレスの人たちを象徴する言葉として放送したのです。
ドキュメンタリーというのは、そうした個々の小さなエピソードの積み重ねです。
そうした「事実の断片」のようなものに思いがけなく出会った時、取材者として「ドキュメンタリーの神様が味方している」と感じることがあります。ヒトミさんの手帳の言葉との出会いもその一つでした。
住居が定まらずに不安定な非正規労働者たち。彼らを「ネットカフェ難民」と名づけてドキュメンタリー番組のタイトルにしました。さらにニュースの特集でも使いました。放送でヒトミさんの肉声を使ったところ、大きな反響を呼びました。テレビ局にはヒトミさんに仕事や住居を提供したいという申し出が相次ぎました。
私が造語した「ネットカフェ難民」という言葉は他の局や新聞社なども次第に使うようになり、2007年のユーキャン新語・流行語大賞のトップ10にも選ばれることになりました。
私はこのドキュメンタリーを皮切りに「ネットカフェ難民」シリーズで5本放送しました。リーマンショックの直後の2008年末の年越し派遣村などで日本社会で貧困が広がっている現状を報道する一翼を担うことになりました。
一つの時代を記録することができたのではないかと思っています。
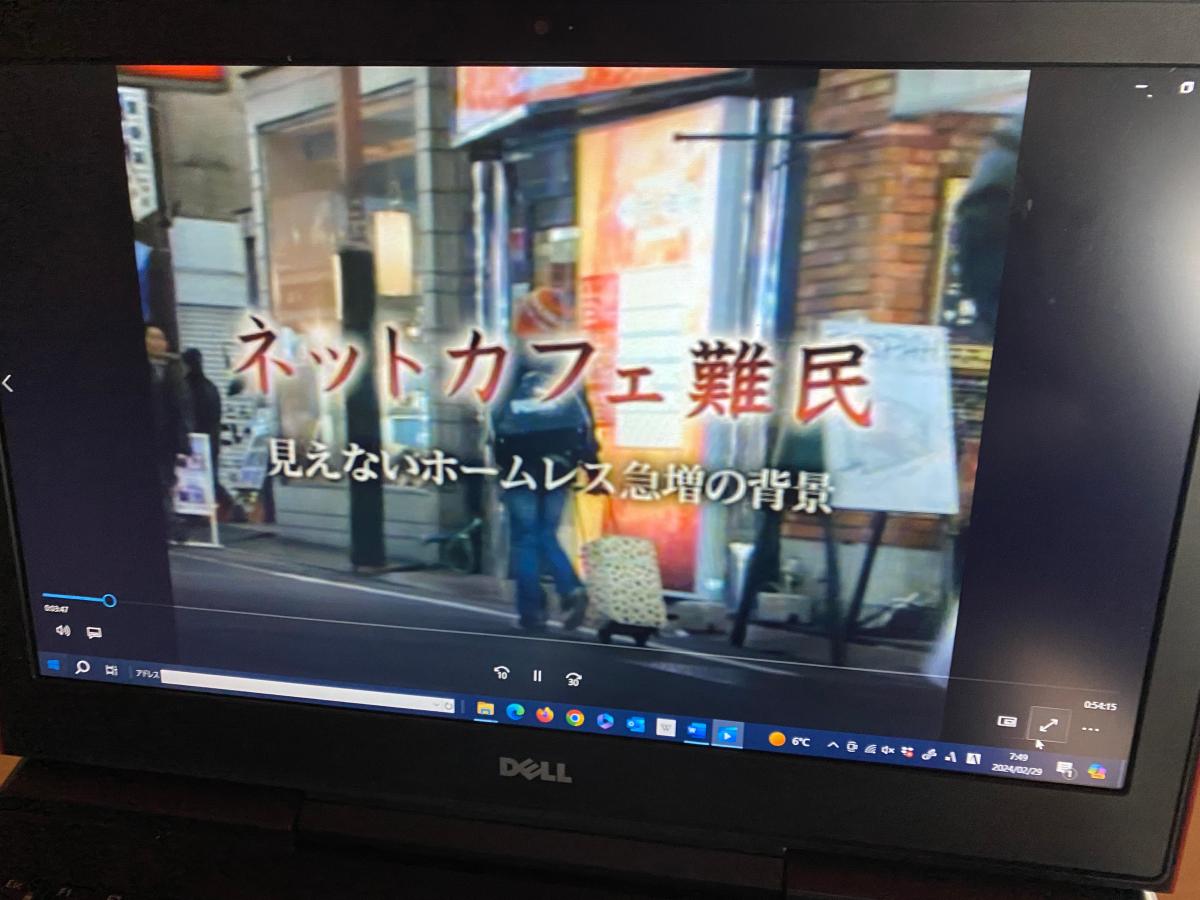
*「事実が『私』を鍛える」を座右の銘に
取材で遭遇する「事実」は奥深く、想定外で、時に不可解です。そうした事実の断片に出会った時、ジャーナリストとしての自分が試され、問われていると感じます。私が出会ったように若者たちにも事実の奥深さや不可解さに出会ってほしい。
今はそう考えて大学で「ドキュメンタリー」の取材・制作という実践教育に携わっています。30年近くテレビ報道の取材の現場に身を置いてきた私自身の経験から、取材などで日々直面する「事実」に鍛えられてきたという思いが根っこにあります。
それは自分が若い頃にジャーナリストを志すきっかけをつくってくれた1冊の本とも重なっています。
『事実が「私」を鍛える−いまジャーナリストであること−』という本です。1970年代から80年代にルポライターとして活躍した共同通信の編集委員、故・斎藤茂男さんが書いた名著です。高校生の頃にこの本に触発されて報道の世界を志したのですが、この世界に入ってみると著名な記者や制作者でもこの本の名をあげる人がけっこう多く、私以外にも「事実」に鍛えられたという実感をもつ人が意外に多いことに気がつきました。
取材する人間は相手がたぶんこんな話をしてくれるだろうとか、物事の展開はこうなっていくはずという「想定」をして取材を計画します。ところが実際には「事実」はかなり奥深いもので事前に頭の中で想定したような展開にはほとんどなりません。たいていの場合、想定は事実によって裏切られるのです。この「裏切られる」という経験こそがジャーナリストとしての成長の糧になっていきます。取材者は事実の奥深さを痛感させられます。ジャーナリストとしての物事の見方や知見が深まっていくのです。斎藤さんの名著はそれを体験的に書いたものでした。
自分自身の仕事を振り返ってみれば、他の人のようにあまり頭がよくなかったのか、予め「想定」をして取材計画をつくるということがすごく苦手でした。「当事者の体験」をテレビなどで募集して取材を進めていくという一種の“調査報道”を初期の段階から自分のスタイルにしていたので、事実に裏切られる、というよりも当事者たちに直接話を聞きに行って、彼らの話にじっくり耳を傾けることをくり返しているうちに、事実が持つ奥の深さ、面白さ、不可解さに魅了され続けてきた、というのが正直なところです。
最近は報道を志向する学生に女性も増えてきました。次第に改善されてきているとはいえ、今も女性に対する差別的な取り扱いは社会の隅々にまで残っています。単身の女性は非正規で働く人が男性よりも圧倒的に多くて未だ貧困の当事者になりやすかったり、最近も芸能界や芸術の世界などで女性に対する性暴力やセクハラなどが問題化するケースが後を絶たず、被害者になりやすい現状があります。そんな女性たちが報道の世界に進んでいくのはいい傾向だと考えています。教え子の女性たちも事実が持つ奥深さや面白さに魅了されて報道の世界に進もうとする人が少なくありません。大学で教えているドキュメンタリーの取材でも「事実があなたを鍛える」という考えが基本になっていますが、学生たちにも「事実」の奥深さを体験してもらいたい。そう願いながら彼女や彼の背中を押すのが自分の仕事だと考えています。(トップ画像はGetty Images、ラスト画像は学生が作成したゼミ紹介のパワーポイントから)

更新の通知を受け取りましょう



















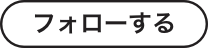


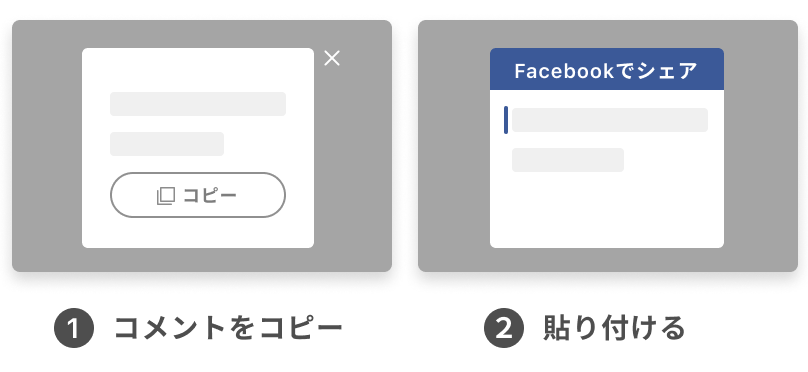

投稿したコメント