日本の刑事司法の問題点「人質司法」とは何か
刑事裁判で無実を主張しようとする場合ほど長期間身体拘束をされる日本の刑事司法実務の運用は、「人質司法」と呼ばれて国際的に強く批判されています。今回は、冤罪の原因にもなっているこの「人質司法」とは何なのかについて解説をしていきたいと思います。
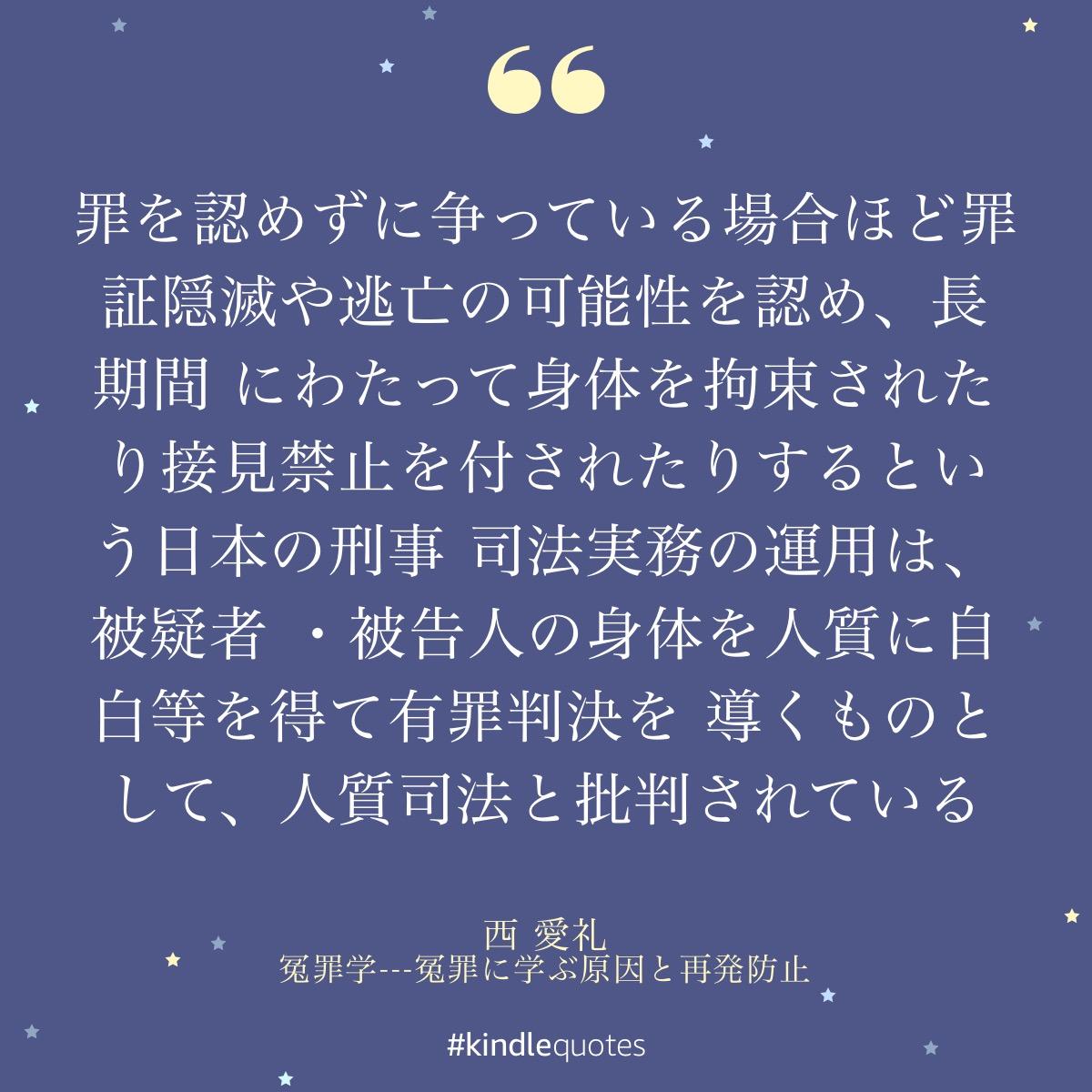
容疑者を身体拘束する理由
そもそも、どのような理由に基づいて容疑者を身体拘束しているのでしょうか。
よくある勘違いとして、逮捕された人は罪を犯したから刑事裁判までの期間も処罰として身体拘束がなされるという考えがあります。しかし、人は刑事裁判で有罪判決を受けるまで無罪であることが推定される「無罪推定原則」(憲法31条、自由権規約14条2項)があるため、刑事裁判までの期間についてその人が有罪であって処罰しなければならないことを理由とした身体拘束はすることができません。
また、取調べのために身体拘束をするという考えも間違いです。日本には「黙秘権」(憲法38条)があるため、取調べをする必要があったとしても、それは身体拘束をする理由になりません。
加えて、再犯を防止するという考えも日本では採用されていません。このような犯罪防止のための身体拘束は「予防拘禁」といって、犯罪などが存在しないにもかかわらず危険人物というだけで身体拘束をするという考えであり、日本では治安維持法の廃止などに伴って否定されています。
日本では、
刑事裁判への出頭を確保し、証拠隠滅を防止すること
有罪判決がなされた場合に刑の執行を確保すること
を目的として、身体拘束をすることになっています(この考え方自体は、刑事裁判実務において確立したものとなっています)。
そのため、①罪を犯したと疑うに足りる理由があり、②住居不定、並びに罪証隠滅又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき、③勾留の必要性、といった各要件が揃った場合にのみ、刑事裁判までの期間において「勾留」(身体拘束)することになっています(刑事訴訟法60条等)。
また、無罪推定原則がある以上、起訴された場合には「保釈」が権利として認められている(権利保釈)のですが、「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」には保釈は認められないことになっています。

無実を主張する人ほど身体拘束が長引く理由
統計上、2019年の通常第一審における保釈率は自白事件が33.1%、否認事件が28.2%であるところ、起訴後1カ月以内の保釈率は自白事件が23.3%、否認事件が9.4%と、否認事件の方が自白事件よりも保釈率が低く身体拘束が長期化する傾向があります。
つまり、罪を認めた人は早く身体拘束から解放され、無実を主張する人ほど身体拘束が長引くということです。
なぜこのようなことになってしまっているのでしょうか。
ポイントは勾留の要件である「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」です。
罪を認めて自白している人については、刑事裁判で有罪になることは確定していて後は量刑だけであり、証拠隠滅をする動機が低減されているため、証拠を隠滅する可能性が低く見られています。そのため、勾留が却下されたり、保釈が認められやすくなります。
一方で、罪を認めずに争っている人については、刑事裁判で有罪・無罪が争われることになりますから、情状事実だけでなく犯罪事実に関する証拠についても証拠を隠滅する余地が生まれます。更に、無罪を得ようと証拠を隠滅する動機があるとも考えられてしまいます。そのため、罪証を隠滅する理由があるとして勾留がされ、保釈が認められにくくなってしまうのです。その結果、法律上は保釈が原則であるはずなのに、無実を主張する場合は常に「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」があるとして、保釈が例外的に認められる実務運用になってしまっています。
特に、会社関係の事件については、関係者が多数存在するため口裏合わせの危険が高いとして保釈が認められにくいと言われています。そのため、これまでも厚労省元局長冤罪事件の村木厚子さん、プレサンス元社長冤罪事件の山岸忍さん、大川原化工機事件の大河原正明さん・相嶋静夫さんなどのホワイトカラーに関する冤罪事件で長期間の身体拘束があったことが問題視されています。つまり、一般の方々にとっても他人事ではないということです。

「人質司法」と呼ばれる理由
それでは、上記のような状況の下、無実を主張する人が身体拘束されるとどうなるのでしょうか。
そのような人としては、「どうすれば身体拘束から解放されるのか」を考えます。そして、罪を認めたり、裁判上の争点を減らすのが最も手っ取り早い手段になってしまいます。こうして、「虚偽自白」が生まれます。
また、刑事裁判では、捜査機関が事情聴取して集めた供述調書についても弁護人が同意しなければ採用されません。つまり、無実を証明するために、捜査機関にとって有利なことしか書かれていない供述調書には同意せず、法廷での証人尋問によって事実を明らかにするという手段があるのです。もっとも、供述調書に同意しない場合には、その供述者の証人尋問が行われることになるところ、証人も「罪証隠滅」の対象です。そのため、早く保釈されたい人としては、証人に対する「罪証隠滅」の可能性を下げるために、この供述調書への同意が誘発され、対等な立場で裁判を進めることができなくなってしまいます。
すなわち、身体を拘束されている人にとっては、あたかも自分の身体が人質として扱われ、身体拘束から解放されるために自白や供述調書への同意を差し出すことで、裁判が不利になるように導かれていくのです。
このような刑事司法実務の運用は「人質司法」(Hostage Justice)と言われて国際的に批判されています。

人質司法の実情とその批判
私が担当したプレサンス元社長冤罪事件において、元被告人の山岸忍氏はその回顧録『負けへんで』において、次のように語っています。
独房内は無機質なうえ、とにかく狭く、監禁されているということもあいまって、精神的な圧迫感が心をむしばんでいく。ひとりぼっちで話し相手のいないことで、気が変になりそうだった。年末になると刑務官の数すら少なくなってくる。案の定、精神的にまいってしまった。たったひとりで壁を見つめていると、グニャーっとゆがんで見えてくる。(アカン、幻覚が見えるようになってしもた。このままやったら廃人になってまう)おかしくなっていく自分のことが怖かった。山岸忍『負けへんで 東証一部上場企業社長vs地検特捜部』(文藝春秋、2023年)
拘置所の中で過ごしているこの1分1秒がすべてストレスなのである。わたしがなにか世間に顔向けできないことをしていて、その罰としてこういう目に遭っているというなら、納得がいくし、あきらめもつく。でも、わたしはなにもしてないのだ。それなのに、裁判所も検察官も「なにもしていないかどうかを決めるために、そのまましばらく我慢していろ」と言う。しかも、「しばらく」がいつ終わるのかもわからない。山岸忍『負けへんで 東証一部上場企業社長vs地検特捜部』(文藝春秋、2023年)
近年では、無実の罪で1年近く勾留された結果、身体拘束中に急激に体調が悪化し、保釈されるも間に合わず亡くなられてしまったという大川原化工機事件も発生しています。
2019年、日本の研究者や実務家の合計1010人が「『人質司法』からの脱却を求める法律家の声明」を法務省に提出しました。
2023年、国際的人権団体ヒューマン・ライツ・ウォッチは「日本の「人質司法」保釈の否定、自白の強要、不十分な弁護士アクセス」を公表して人質司法問題の解消を求め、冤罪救済団体イノセンス・プロジェクト・ジャパンとの共同プロジェクト「ひとごとじゃないよ!人質司法」が始動しています。
人質司法についてどう考えればよいのか
私は、刑事裁判において無罪を主張するほど身体拘束が長引くというのは裁判を受ける権利の侵害になることや、虚偽自白や供述調書への同意によって冤罪の原因になってしまうことから、この「人質司法」は1日も早く解消されるべき問題だと思っています。
元裁判官として、逃亡や証拠隠滅を防いで公正な刑事裁判をしたいという裁判官の気持ちや、実際に逃亡や証拠隠滅がされてしまっている事件を多数経験していることでその可能性を高く見積もってしまう感覚はよく理解できます。
しかし、裁判官が自白を強要する意図がなかったとしても、現在の実務運用のもとにおいては、保釈を得ようとするために虚偽自白等が生まれてしまう現実が存在します。裁判官が証拠隠滅のない公正な裁判をしたいと思う一方で、虚偽自白等が生まれてしまえば公正な裁判などできないわけですから、これでは本末転倒だと思います。
また、無実を訴える人にとって、最も裁判の準備が必要なはずな自分たちが身体拘束されて準備をすることができないというのでは、理不尽というほかありません。
法律に忠実に保釈を原則的なもの・身体拘束を例外的なものとして運用すること、そして公正な裁判のためには早期の身体拘束からの解放を実現しなければならないことが必要だと思います。
この「人質司法」の問題点を広めるため、Pickや拡散をよろしくお願いいたします。
プロフィール
西 愛礼(にし よしゆき)、弁護士・元裁判官
プレサンス元社長冤罪事件、スナック喧嘩犯人誤認事件などの冤罪事件の弁護を担当し、無罪判決を獲得。日本刑法学会、法と心理学会に所属し、刑事法学や心理学を踏まえた冤罪研究を行うとともに、冤罪救済団体イノセンス・プロジェクト・ジャパンの運営に従事。X(Twitter)等で刑事裁判や冤罪に関する情報を発信している(アカウントはこちら)。
今回の記事の参考文献
参考文献:西愛礼『冤罪学』(日本評論社、2023年)、山岸忍『負けへんで 東証一部上場企業社長vs地検特捜部』(文藝春秋、2023年)、高野隆『人質司法』(角川新書、2021年)、Human Right Watch「日本の『人質司法』保釈の否定、自白の強要、不十分な弁護士アクセス」(2023年)、日本弁護士連合会「『人質司法』の解消を求める意見書」、なお、記事タイトルの写真についてGetty ImagesのMarvin Samuel Tolentino Pineda の写真。
更新の通知を受け取りましょう
























投稿したコメント