ノーベル賞授賞式で感じた「科学との付き合い方」
12月10日、スウェーデンの首都ストックホルムで、ノーベル自然科学3賞と文学賞、経済学賞の授賞式が開かれた。コロナの影響で、本来なら現地に集うはずだった受賞者たちは、すでに居住国でメダルや賞状を受け取っている。当日はノーベル財団の関係者らが受賞者の業績を称えたという。
メダルを受け取った物理学賞の真鍋淑郎さんの写真の表情は、とても晴れやかだった。けれど、真鍋さんがストックホルムでの「ノーベルウイーク」を経験できないことについては、いささか残念に思わずにはいられなかった。
私は前職の新聞記者時代、ノーベル賞の取材でストックホルムを2回訪れたことがある。
1回目は、鈴木章、根岸英一両氏が化学賞に選ばれた2010年。両氏は二つの異なる有機化合物をつなげる「クロスカップリング反応」を開発した。
2回目は2012年で、この年はiPS細胞を開発した山中伸弥氏が医学生理学賞に選ばれた。iPS細胞のマウスでの開発が発表されたのは2006年。最初の記者会見からずっとこの技術の動向を追いかけてきた身としては、感慨深い受賞だった。
授賞式までの約1週間はノーベルウイークと呼ばれ、受賞者の記念講演や記者会見をはじめ、連日、関連イベントがある。受賞者は家族や友人と滞在し、他の受賞者とも交流を深めながら、温かいもてなしを受ける。クライマックスの12月10日は、コンサートホールでの授賞式に引き続き、市庁舎の「青の広間」で晩餐会も催される。
雪の積もった極寒の街をブーツで歩き回り、受賞者の動向やイベントの様子をレポートする日々は、体力的にはハードだったが思い出深い。

受賞者やご家族の人柄に触れる機会も多かった。妻が授賞式の日に着る着物にまつわる夫婦の思い出を、しみじみと嬉しそうに語ってくれた鈴木さん、親族や友人とのプライベートな夕食会で、くつろいだ笑顔を見せた根岸さんの姿は、今もはっきり覚えている。
2012年には晩餐会の模様も取材することができた。晩餐会には、男性は燕尾服、女性は足首が隠れる長さのドレス、または民族衣装の正装というドレスコードがあり、記者にも適用される。参加できると決まったのが出発直前だったため、ドレスを買いにいく余裕はなく、先輩から急遽借りたロングドレスを着て臨んだ。
大広間を正装の男女が埋め尽くす様子は壮観だった。食事中は光の演出を駆使した歌や踊りのショーがあり、食後には上階のホールでダンスタイムも。それまで体験したことのない、華やかな夜だった。

一連の行事を通じて強く感じたのは、科学を「文化」として慈しみ、楽しむ雰囲気だ。
ノーベル財団のスタッフから、晩餐会の食事を作るシェフ、受賞者や家族の世話を焼くノーベルウイーク専用の付き人(アタッシェと呼ばれる)に至るまで、関わる人々が皆、誇らしげで、「受賞者の人生にとって最良の時間を提供する」という喜びと気概に溢れているのも印象的だった。
考えてみればそうした雰囲気は、日本で科学を取材しているときにはほとんど感じたことのない種類のものだった。
それは、日本の科学技術政策が、科学技術をイノベーションや新たな産業につなげることを至上命題としてきたことと、決して無関係ではないように思う。政治家の中には、将来的に経済に資することのない研究は無駄だ、という趣旨の発言をする人もいる。
でも、そういう科学の捉え方、科学との付き合い方って、なんだか寂しくないだろうか。科学は、人類の知見を少しずつ積み重ね、広げていく営みだ。一見、「役に立たない」成果に見えたとしても、その営み自体に価値を見出し、科学者と発見の喜びを分かち合えるのが、本当の豊かさではないだろうか。
もちろん、スウェーデンにも科学技術を産業の発展に役立てる発想はあり、そのための施策もある。けれど、何よりもまず、科学を文化として楽しむ、という土壌があり、それが受賞者をもてなすノーベルウイークでのホスピタリティを支えている。
いつか、そんな雰囲気が日本にも醸成されることを願っている。それこそが、科学を社会に根付かせる、本当の意味での「科学技術振興」になると思うからだ。
更新の通知を受け取りましょう



















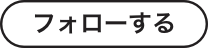


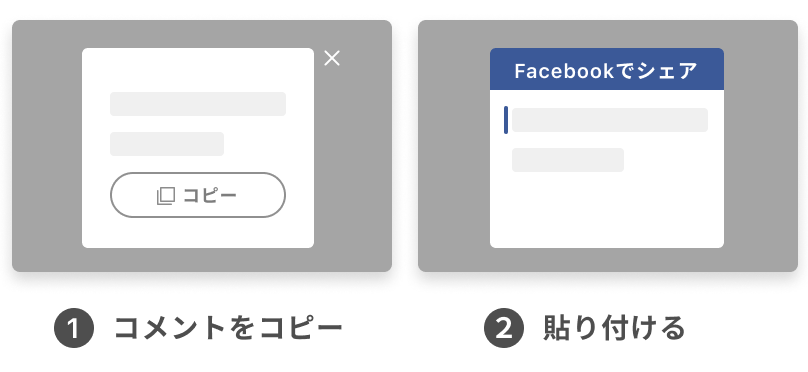

投稿したコメント