合成生物学の社会理解と人材育成
12月25日は、アイザック・ニュートンの誕生日です。今回は、日本科学振興協会(JAAS)の「教育対話促進プロジェクト」アドベントカレンダーに登録するために筆者が書いた科学教育関係の記事を紹介したいと思います。
合成生物学の社会での理解や研究開発人材育成にもつながるBioBusとiGEMの紹介をすることで、日本の科学教育のあり方についての提言となっています。
以下、内容の簡単なまとめです。リンク等、もっと詳しい内容に興味のある方は上のnoteの記事をご覧いただければと思います。
🚌Science for allの試み:バイオバス
バイオバスは、ニューヨーク市を中心に活動する非営利団体「BioBus」が運営する移動式の科学研究室です。幼稚園児から高校生、大学生までを対象に、実験や研究のスキルを学ぶ機会を提供しています。
バイオバスの特徴としては、科学コミュニティから排除されている生徒にも焦点を当てていること。学校や地域団体など、さまざまな場所に出向いて活動していること。博士などの専門家も指導を担当していることが挙げられます。
日本では、科学館や博物館などの施設へのアクセスが都市部と地方で大きく異なるなど、科学へのアクセスの格差が課題となっています。また、科学に興味・関心を持つ人は、都市部に住む高学歴の子どもに偏る傾向があります。バイオバスは、こうした課題を解決する上で有効な手段となる可能性があります。バイオバスは、学校や地域団体など、子どもたちが身近に感じられる場所に出向いて活動しています。また、博士などの専門家が指導を担当することで、子どもたちに本格的な科学教育を提供することができます。
日本の科学教育においては、科学館のように待っているのではなく直接アプローチするバイオバスのような取り組みが広がることで、科学へのアクセスの格差が解消され、科学に興味・関心を持つ人が増えることが期待されます。
📌Science for excellence:iGEM
日本の科学教育は、大学受験に代表されるように、個人の学力を科目別の試験で計測し、その数値を上げるということを、過剰に重視する傾向があります。 一方、iGEMは、学生が自らテーマを考え、研究を行い、研究成果を社会に実装するというプロセスを最初から最後まで体験するコンテストです。iGEMは、科学知識や研究だけでなく、社会への影響も考慮しつつ、サイエンスコミュニケーション、教育、イノベーション、アントレプレナーシップといった要素も競います。
「Science for excellence」の新しい形として、このような総合的な科学力の教育が、現在の日本の教育現場に求められていると私は考えます。iGEMでは、優秀な科学論文を書いたり、ノーベル賞のような偉業を成し遂げたりすることを目指しているのではありません。
iGEMのような総合的な科学力を育成する事業を通じて、科学技術を社会に役立てる力を育むことが、日本の科学技術のさらなる発展につながるものと考えます。iGEMのような教育は、日本の現在の教育制度や社会の理解との間に、いくつかの隔絶があると感じます。
🍎アドベントカレンダー
ユール、ハヌカー、クワンザ、年末年始の季節ですが、12月25日は、偉大な科学者の一人であるアイザック・ニュートンの誕生日です。ニュートンは、ヨーロッパでアリストテレス以来の自然観から脱却できずにいた自然科学分野において、人類史における科学の革命を成し遂げました。
科学教育についての多様な考え方についてのコラムを紹介している日本科学振興協会(JAAS)の「教育対話促進プロジェクト」アドベントカレンダーをのぞいてみてください。
【Twitter】 https://twitter.com/yamagatm3
更新の通知を受け取りましょう







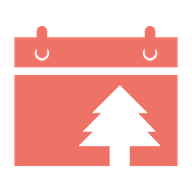



















投稿したコメント