【インタビュー】パナソニック 採用部長に訊く:キャリアのチャンスをどのように呼び込むか?
成功しているビジネスパーソンの多くは、キャリアのスタート時には自分では想像もしていなかった道を歩んでいます。彼らは思いがけない偶然のなかでチャンスを得て、そのチャンスをつかむことを繰り返しています。これを「計画的偶発性(Planned Happenstance理論)」といい、キャリア形成においてもっとも基礎になる考え方です。
以前、この「計画的偶発性」について解説しましたが、この理論では、成功する人は偶然やってきたチャンスをつかみ取っていくとされています。これを聞いて、「チャンスはどうやって呼び込めばいいのか?」と思った人もいるのではないでしょうか。
実は、チャンスを呼び込む人は普段からチャンスが来やすいような準備をしています。
今回は、大企業の中で偶然のチャンスを得てキャリアを大きく変えながら、人事部門のリーダーとして活躍するパナソニックの坂本 崇さんとのインタビューを紹介します。

自分が思うキャリアを歩むには、起業したり、スタートアップに入ったりするべきではないかと考える人も多いと思います。
たしかに大企業では人事異動やキャリアチェンジが自由にしにくいという側面がありますが、一方で自分の意思次第では、強みを獲得するのにこれほど恵まれた環境はありません。
坂本さんのキャリアはまさに「計画的偶発性」の実践そのもの。読者の皆さんにとっても参考になると思います。ぜひ最後までお読みください!
◇目次
・全く迷いがなかった大企業への就職
・自分の学びにつながる機会を逃さない
・キャリアの意思を周囲に伝える大切さ
・キャリアを変えたいなら「ボスマネジメント」が超重要
・強みを広げることが結果的にキャリアにつながる
◇全く迷いがなかった大企業への就職
南 坂本さんと初めてお会いしたのは、私がSAP時代のときでしたね。パナソニックさんの人事部門の若手育成プログラムを担当させていただいたときの受講生としてお会いしました。
そのころはすでに人事部門で採用を担当されていましたが、人事部門に長くいた方と比べると、ビジネスへの理解が深いことを感じる発言が多く、キャリア採用で違う会社からパナソニックに入ってこられたのかなとずっと勘違いをしていたほどでした。
「大企業に新卒入社すると、一度配属された部門や事業からなかなか抜けられない」という印象を持つ人も多いと思います。坂本さんは工場のエンジニア職からキャリアが始まったと伺っておりますが、キャリアのスタートを決めるのに迷いはなかったのでしょうか。
坂本 高専を卒業後、エンジニア職として当時の松下電器AVCネットワークス社の仙台工場に入社しました。高専在学中に工場でインターンを経験させてもらっていたので、仕事の内容や工場の雰囲気もよくわかっていたこともあり、「このままこの会社に就職する」という確信に近い思いを持っていて、就職活動でいろいろな会社を探すことはせずに入社しました。
今思うと、少しはほかの会社と比べてみてもよかったのかなと思いますが、会社のブランド力も高かったですし、全く迷いはありませんでした。
入社してからは技術習得の毎日で、日々できることが増えていくなかで成長を実感できました。途中で山形工場に移りましたが、約10年間にわたって、エンジニアとして技術を磨きました。
南 キャリアのスタートは、学生時代からの強みを活かして、エンジニアとしてできることを増やしていったわけですね。そのなかで、どのようにキャリアチェンジしていったのでしょうか?
◇自分の学びにつながる機会を逃さない
坂本 エンジニアとしてある程度仕事ができるようになったときのこと。周囲を観察していると、所属している事業部の事業企画担当者が「次にどのような製品を作ろう」といった話をしに、工場に時々来ていることに気がつきました。
それまでは、エンジニアとして「高品質・高精度なものづくりをいかに実現するか」ということに集中していたのですが、事業企画の人たちから「この製品がどんな意図で作られて、最終的に顧客にどのように使われるのか、どんな役割を社会で果たしているのか」といった話を聞くうちに、自分も視野をもっと広げたいと思うになりました。
そこで上司にかけあって、事業企画の人たちとの会議に自分も出席させてもらうようにお願いし、受け入れてもらいました。最初は会議で使われる用語もあまりわかりませんでしたが、ビジネスのフレームワークや言葉の意味を自分なりに必死に勉強していくうちに会議の内容を少しずつ把握できるように。エンジニアの目から見た製品の改善点や、現場から見える意見を積極的に発言しました。
事業企画チームとの会議はとても楽しく、いつの間にか「この製品が世の中でもっと使われるようにするにはどうすべきか?」という視点で考える習慣が身についているのを感じました。そのタイミングで、事業企画で人を探しているという話を耳にして、迷わず異動の希望を伝えました。
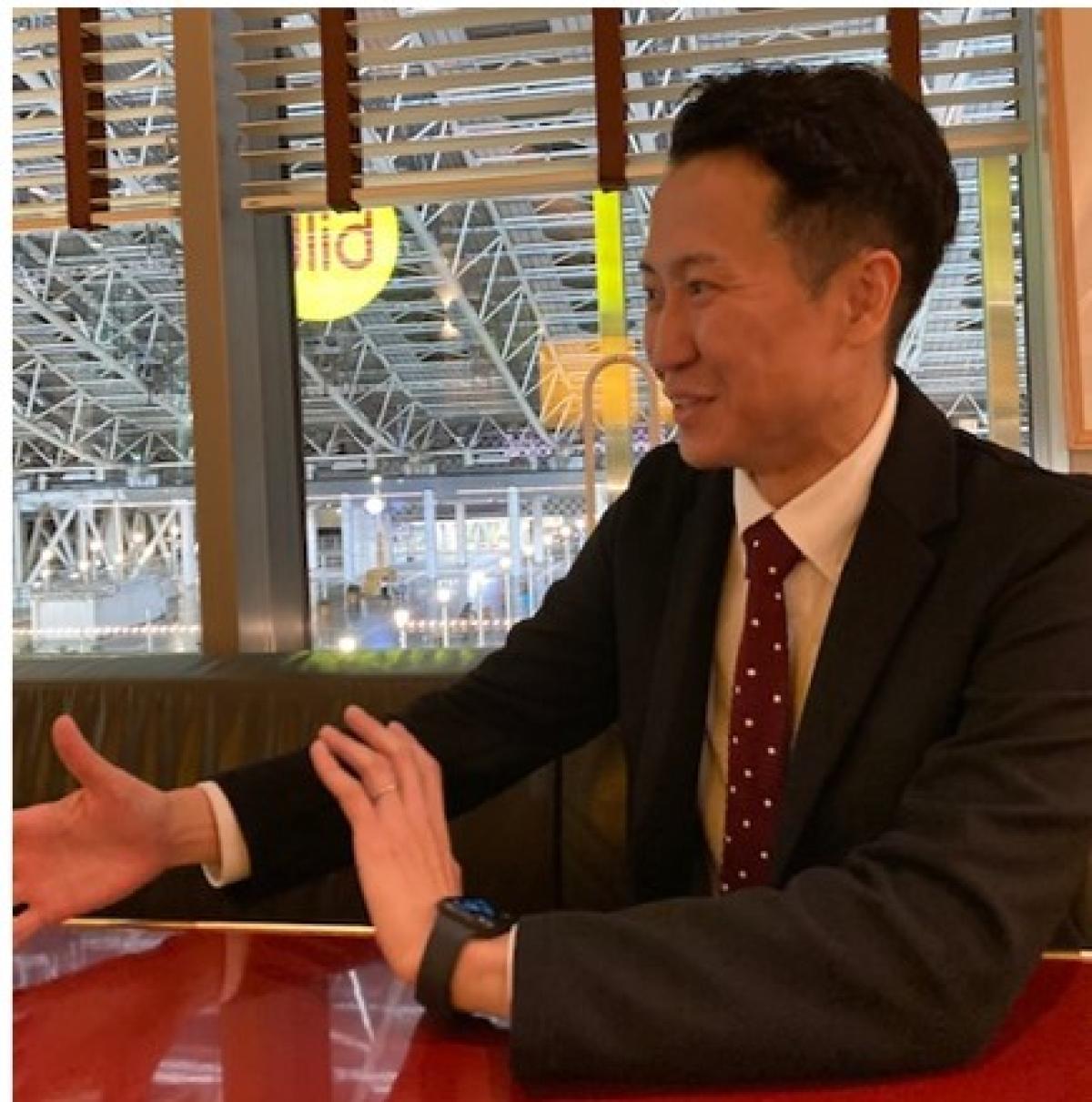
◇キャリアの意思を周囲に伝える大切さ
南 「やってきたチャンスをつかもう」と手を挙げたわけですね。エンジニアとしても10年選手でちょうど中堅になって周囲の期待もあったと思いますが、スムーズに異動できましたか?
坂本 それが、そのタイミングではうまく話がまとまりませんでした。
でも、自分の思いやキャリアに対する希望を周囲に伝えたことや、普段の事業企画のチームとのミーティングで、私が積極的に発言をしている様子を当時の上司や、事業企画部門のマネージャーが見ていて、「技術に精通している人間が事業企画にいるほうがいいだろう」ということになったのだと思います。それからしばらくして、事業企画に異動できることになりました。
そのとき痛感したのは、自分の意思や強みは、頭の中で思っているだけではダメで、周囲にわかりやすい形で積極的に伝える勇気を持たないと伝わらないということ。
私の場合、事業企画の人たちとの会議や、事業の勉強をしていることは周囲も何となくわかっていたはずです。しかし、「それはあくまでエンジニアとして成長するためにやっていることだろう」と考えている人も少なからずいたと思います。
自分の考えは、口に出して伝えなければ結果として考えていないのと同じです。私を事業企画部門に配置してみようと思ってもらえる姿勢を普段から見せていたことが異動につながったと感じています。
南 自分の強みを周囲に伝えることで、新たなチャンスが向こうからやってくるという、まさに「計画的偶発性」そのものですね。
◇キャリアを変えたいなら「ボスマネジメント」が超重要
南 とはいえ、特に上司に対しては、なかなか異動の希望など言いにくい人も多いと思います。坂本さんは何か心がけていることはありますか?
坂本 いわゆる「ボスマネジメント」はとても意識しています。自分のことを理解してもらうためには、まずは上司との信頼関係をうまくつくっていくことが大切です。
私が心がけていることは、次の3つです。
①上司が目指す世界や実現したいことを把握し、自分がそれを理解していることを折にふれて上司に伝えて想いを共有する
②上司の強みを理解し、自分の強みも上司に理解してもらえるように心がける。
③仕事以外の話題でのコミュニケーションを欠かさない。
普段からこれらを積み重ねることで、上司ともキャリアについて相談しやすい関係ができていくと思います。
南 上司に対して、言いにくいことを避けるのではなく、言いやすくなるように部下のほうから関係構築をしていくわけですね。ボスマネジメントは、これからキャリアを考えていく人たちにとって大事なポイントになりそうです。
そこから今度は人事部門にキャリアチェンジですが、これもご自身で希望されたのですか?

坂本 そうですね。事業企画として多くの部門と関わるようになって、「社内にはたくさんの素晴らしい人材がいる」と初めて知りました。大企業に入社して1つの部門に長くいると、どうしても視野も人間関係も狭くなって、大企業にいることすらわからなくなってしまうということを感じましたね。
そのころ、どういうわけか、一緒に働いている社員からキャリアの相談を受けるようになっていました。おそらく、私のキャリアが社内でも珍しかったので、「少し違う視点の意見がもらえる」という期待があったのではないかと。
話を聞いていると、優秀で可能性にあふれているのに自分の強みがわかっていない、あるいは今の仕事や立場を失うことを心配するあまり、自分を意思や考えを表に出せていない人が非常に多いことに気がつきました。
「これがいわゆる大企業病なのか」と実感しました。私自身は、目の前の仕事に集中することで強みをつくることができましたが、みんながそうできているわけではない。自分の強みが何かもわからないまま時間だけが過ぎている人がとても多い。これは全社的に変えていかなければならないのではと思っていたところで、たまたま人事の採用部門で公募があったので応募しました。
◇強みを広げることが結果的にキャリアにつながる
南 ここでもチャンスに飛び込んだわけですね。エンジニア職、事業企画と、強みを活かしてキャリアを重ねてきたところで、年齢的にも30代中盤となってまさにこれからというところですが、いきなり人事部門となると、また一から経験を積み重ねるということですよね。迷いはありませんでしたか?
坂本 たしかに、事業企画部門で管理職になるキャリアが具体的に見えている時期でもありました。ただ、全社的な変化を起こせる仕事に就けるチャンスはそれほどないですし、募集されていたポジションが、採用した社員に対して、入社後早期に活躍できるよう支援するという内容であったので、ぜひチャレンジしたいと考えました。
また、同僚や後輩からたくさんの相談を受けたことで、「人の力を発揮させる」ことの面白さと、「これが実は自分の強みなのではないか」と感じたこともあり、人事を経験することのほうが自分の強みが広がっていくと考えました。まさに偶然が重なって新たな道が見えたという感じですね。
南 結果として、坂本さんは人事として責任のある立場となって強みをさらに広げているわけですが、大企業には自分の強みに気がつかないまま、キャリアに悩んでいる人も多いと思います。坂本さんは大企業のなかでキャリアを形成するメリットをどのように感じていますか?
坂本 大企業は組織ごとの役割分担がはっきりと決まっていることが多いので、いつの間にか視野が狭くなってしまうこともあると思います。
一方で、「キャリアは自分の強み次第で変わる」ということさえわかっていれば、大企業はさまざまな経験を得られる非常に良い舞台でもあります。
だいたいのことは社内の誰かが知っていますし、会社の名前によって、自分の立場に関係なく若いときから社外からの情報も収集しやすいことも大きなメリットです。私がキャリアを大きく変えながらも新たな仕事を早く覚えていけたのは、まさに大企業にいたからだと確信しています。
◇対談を終えて:大企業こそのメリット。強みを早くつくるには最適な場所
「巨大な船に乗っていると、そこが船であることを忘れる。そして沈没しかかったときに泳ぎ方も忘れてしまっていることに気づく」
よく、大きな組織に慣れてしまうリスクをこのように表現します。
大企業に入ると、いつの間にか「会社は当たり前のように存続し、自分の雇用は当たり前のように継続する」という考えが定着してしまいます。そして、できるだけ長くその場に残ることだけを考えるようになり、会社の指示どおりに働き続けた結果、ある日、外に出なくてはならなくなったときに、外の世界で通用する強みをまったく身につけていない――そんな人がたくさんいます。
しかし、新卒で大企業に入社していく人たちは、もともと非常に優秀な人材であったはず。なぜそんな人が強みを発展できていないかというと、キャリアに関してある誤解をしているからです。
それは、「会社が自分のキャリアをつくってくれる」と信じてしまっていること。
日本おいては、ある程度雇用は守られています。ただしキャリアを作るということとは異なります。
坂本さんは、仕事を通じてさまざまな人から学び、刺激を受けるなかで自ら強みをつくり、周囲に伝えることでキャリアを形成してきました。ただ、これは大企業だけでできることではなく、現代社会においてはオンラインも含めて、より簡単に多くの人と関わることが可能になっています。
もし自分のキャリアがわからなくなってしまったら、自分だけで考えるよりも、社内外の人たちと話をしてみるのも大切です。自分の強みは、社外の人のほうがよく見えることも多々あります。
坂本さんも、人事としてこれからたくさんの社員の可能性を伸ばしていかれると思います。ありがとうございました!

更新の通知を受け取りましょう
























投稿したコメント