任天堂の稼ぐ力を分析 新ハードは今期中に発表へ
家庭用ゲーム大手の任天堂は、5月7日の取引時間後に2024年3月期(2023年度)本決算を発表しました。同社の古川俊太郎社長がXにてNintendo Switchの後継機に言及したことが話題になりましたね。ただ、決算発表翌日の株価は地合いの悪さもあり5%超の下落。決算のどの辺りに株価下落の要因があるのか、全体を俯瞰しながら要点を解説していきます。

24年3月期の売上高は前期比4.4%増の1兆6718億円、営業利益は同4.9%増の5289億円、親会社株主に帰属する当期純利益(以下、純利益)は同13.4%増の4906億円となりました。25年3月期の見通しは、売上高が前期比19.3%減の1兆3500億円、純利益は同38.9%減の3000億円です。純利益3872億円を見込んでいた市場予想に届かず、年間配当は前期実績の1株211円から今期予想は1株129円へと大幅減配になったことなどが嫌気され、翌日の株価は大きく下落しました。以下では決算の詳細を見ていきます。
24年3月期の経営成績について、2023年5月9日に同社が当初予想していた24年3月期の売上高は1兆4500億円、純利益は3400億円でしたので、かなり上振れしたことが分かります。もともと同社は業績予想を保守的に見積もる傾向があるほか、販売単価の高いNintendo Switch(有機ELモデル)の販売比率が高くなったことや追加コンテンツが好調だったこと、為替が想定以上に円安だったことなどが24年3月期の業績上振れに繋がった形です(売上高における為替の影響額は前期比944億円のプラス)。為替差益に注目すると24年3月期は615億円の増益となっており、23年3月期の397億円から大きく増加。任天堂の海外売上高比率は78.3%に上り、為替の影響を比較的受けやすいという同社の特徴は以前から変わりません。
売上総利益率は57.1%と前の期の55.3%から1.8ポイント改善。一方、売上総利益に対する販管費比率は44.6%と前の期の43.0%から1.6%上昇(利益的には悪化)。同社は2023年2月7日に同年4月から全社員の基本給を10%引き上げる方針を明らかにしていたほか、従業員数の増加も重なったことが販管費比率上昇の要因と見られます。
原価率の改善と販管費比率の上昇がそれぞれ打ち消し合い、売上高営業利益率は31.6%と前の期の31.5%からほぼ横ばいになりました。コロナ禍の巣ごもり期に記録した36%前後の水準からは低下していますが、依然として高水準をキープしています。
ただ、利益が積み上がる中で株主資本は2兆4011億円と前の期の2兆1467億円から11.8%増加したものの、営業利益は微増。これらの関係から、企業の稼ぐ力を表す投下資本利益率(Return on Invested Capital、ROIC。税引後営業利益を有利子負債と少数株主持ち分及びその他の包括利益累計額を含む株主資本の合計値で割った値のこと)は下図に示すように21年3月期をピークに低下傾向にあります。

数年毎に新ハードを開発・発売するという事業サイクル的に致し方ない部分もありますので、Nintendo Switchが販売8年目に入ってもある程度のROIC水準を維持しているとポジティブに見ることも出来ますが、投下資本に対して稼ぐ力が低下しているのは明らかです。
会社の今期業績予想とこれまでの実績を基に私が25年3月期のROICを試算したところ、24年3月期から更に低下すると予想されます(10%を下回る水準になりそう)。それでも資本コストを上回ると見られるものの、ROICスプレッド(ROICから加重平均資本コストを引いた数値のこと)の縮小は避けらず、Switch頼りの価値創造拡大は相当に難しい状況と言えるでしょう。現預金と短期保有有価証券の合計額から有利子負債を引いたネットキャッシュは2兆円を超えており、潤沢すぎるほどの手元資金を如何に継続的な価値創造に結びつけられるかが課題です。
任天堂は収益機会の拡大を狙い、2014年から自社IP(知的財産)の積極的な活用を掲げています。2021年にはユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて「スーパー・ニンテンドー・ワールド」がオープンし、2023年には「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」が世界的に評価されたことは記憶に新しいでしょう。映画の次回作は2026年4月にも米国で公開される予定です。いずれもゲーム以外における収益の獲得及びブランド力・認知度の向上に寄与していますが、主力事業は家庭用ゲーム機であることに変わりはありません。そこで期待されているのが新しいハードウェアです。
Nintendo Switchの「次」がゲームユーザーや投資家から注目される中、今年2月には一部メディアで「25年3月にも後継機を発売」との記事が出されました。当時、任天堂は「当社が公式に発表したものではない情報に関しては、お客様や投資家の皆様を惑わせることにもなりかねません」と苦言を呈していましたが、今回の本決算発表にあわせて同社の古川社長が、Xの任天堂公式アカウントにて「2015年3月にNintendo Switchの存在を公表して以来9年ぶりにSwitchの後継機種に関するアナウンスを今期中に行います」と明言。今回、オンラインで行われた決算説明会で古川社長は「現段階でこれ以上お話できることはありません。本日の発表に際しては、『Nintendo Switchの後継機種』という表現を用いることが最適だと判断し、このような表現にしました」として多くを語りませんでしたが、その「Switchの後継機種」という表現からは、Wii UからSwitchへの移行で見られたような大きな変化を伴うものではなく、WiiからWii Uに移行した時のような、あくまでSwitchの延長線上にあるものではないかとゲームユーザーの間などでは推測されています。
新ハードの開発については同社の売上高研究開発費比率の推移が参考になります。同社は新ハードの発表前数年間において売上高研究開発費比率が高い水準になる傾向があり、下図に示すようにここ数年の同比率も上昇傾向です(14年3月期よりも前は概ね2〜8%での推移)。

今期の売上高研究開発費比率は約10%と前期の約8%から上昇を見込んでおり、研究開発のアクセルを強めている様子が分かります。ただ、Switchが発売された2017年3月の直前数期は同比率が12〜14%と高い水準で推移していました。それだけSwitchを含む研究開発費が嵩んでいたということが示唆されますが、その当時と比べると最近の売上高研究開発費比率の水準及びその伸び率は緩やかです。この緩やかな伸びが、新ハードがSwitchの延長線上になるということを示唆するものなのか、あるいは26年3月期以降も研究開発費が積み増しされるのかが注目されます。
昨年には、任天堂がハードウェアに関する新たなの特許を申請していたことが明らかになり、ゲーム界隈で話題になりました。特許を申請しても、それが製品として実現しないケースは多々あるため確実なことは言えませんが、新ハードへの期待は膨らむばかりです。新ハードがSwitchの後継機であるならば、ユーザーが期待する要素のひとつは「後方互換性」であり、Proコントローラーなど周辺機器を含めてそのまま使えるかどうか?ということも注目ポイントになるでしょう。
今後も引き続き、新ハードの情報ならびに同社の業績に影響を与える為替動向に関心が寄せられます。
出典)古川社長のコメントは任天堂の「2024年3月期決算説明会(オンライン)質疑応答(要旨)」より引用
この記事で取り上げたような決算や日々の経済・金融ニュースの解説などをnoteのメンバーシップ(月500円〜)で行っています。是非、こちらも併せてご覧ください👇
更新の通知を受け取りましょう






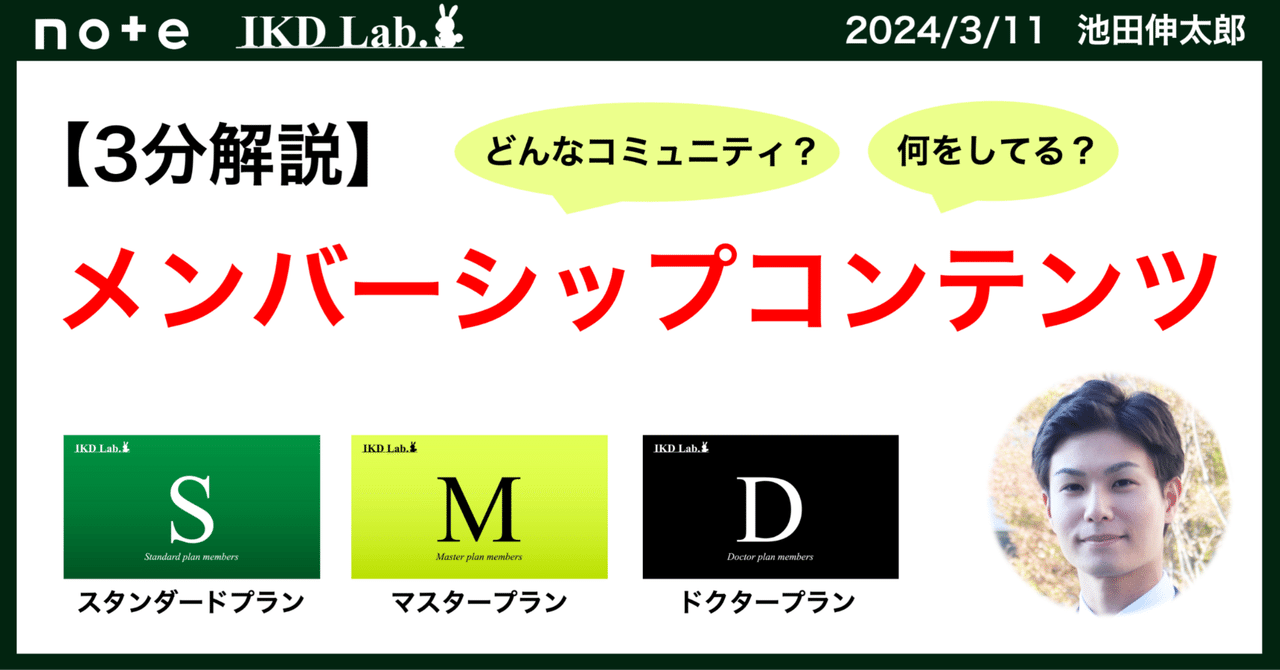


















投稿したコメント