剣と魔法と暗黒——『クロノ・トリガー』にみる西洋の歴史
『クロノ・トリガー』——1995年に発売されたスーパーファミコン用ソフトで、当時それはそれは大きな話題を集めました。『ドラクエ』のエニックスと『FF』のスクウェアというRPGの二大巨頭がタッグを組んだ、まさに夢のような作品でした(両者は2003年に合併、現「スクウェア・エニックス」)。さらにはキャラクターデザインに漫画家鳥山明氏を招聘。夢そのままに世間では「ドリーム・プロジェクト」と呼ばれました。そんな本作は後に続編の発表や数々のリメイク、リバイバルを経て、多くの人々に今なお愛される不朽の名作として知られています。
この電撃のコラボに心躍らないゲームファンはいたのでしょうか。『ドラクエ』や『FF』が好きだった私は真っ先に地元にある唯一の「ファミコンショップ・アラジン」で予約したのを覚えています(田舎部では発売日に手に入る可能性は低く、もどかしかったのですが)。ひとたびゲームを始めるとその壮大な世界に引き込まれ、学校の友達と進行度合いをシェアするのが日課となりました。冒険の先を越されるのが悔しく、なるべく時間をかけて翌日の登校に備える——「RPGマウント」の取り合いとでもいうべき健気な戦いがそこにはありました。
『クロノ・トリガー』のはじまりは何気ない日常の一ページ。
「いつまでねているの?いいかげん起きなさい!」——そう言って母親がカーテンを開けると、主人公クロノの部屋いっぱいに朝日が差し込みます。舞台は〈現代〉のガルディア王国、建国千年を祝うお祭りの日。クロノと幼なじみで機械少女のルッカは「テレポッド」と呼ばれる転送装置を発明し、街の広場ではそのデモンストレーションが行われようとしています。クロノは偶然出会った少女マールとともに見物へと向かいますが、このテレポッドの誤作動がきっかけで、マールは忽然と姿を消してしまいます。
マールを追って、クロノとルッカは「中世」にタイムスリップ——そこは西暦600年のガルディア王国で、魔物が全土を攻め立てる争乱の世でした。そんな中、人々は消息不明だったリーネ王妃が戻ってきたと安堵しています。実はマールはガルディア王家の子孫で、祖先にあたるリーネ王妃と間違われ城に迎え入れられていたのです。そして事態は魔王軍にさらわれた本物の妃を救出すべく進むことに。「現代」から「中世」へのタイムトラベルを皮切りに、物語は「原始」「古代」「未来」を駆け巡る大冒険へと発展していきます。
ところで、本作の前年の1994年に発売された『ライブ・ア・ライブ』(スクウェア、2022年にリメイク発売)も、「原始編」「幕末編」「西部編」「SF編」など、七つの異なる時代を巡るオムニバスRPGでした。全てクリアすると八つ目のステージとして「中世編」が登場し、姫を追い魔王を打倒する勇者の物語が始まります。数ある時代の中で「中世編」をクライマックスにもってくるあたり、「中世」にこそRPGの王道があるという意思を感じます(とはいえ「魔王」の定義を巡って一種の仕掛けがある)。対して、『クロノ・トリガー』の「中世」は冒頭に現れ、以後も各時代と関わり合いながら展開していきます。また、オフィシャルサイトに「剣と魔法の世界」と表現されているように、深い森、修道院、廃墟、竜の聖域といったファンタジー的様相を帯び、『ライブ・ア・ライブ』の「中世編」をさらに掘り下げた内容になっています。
『クロノ・トリガー』の中世はとりわけ印象に残っています。何より、フィールドに流れる物悲しいサウンド〈風の憧憬〉——2019年、ゲーム総合誌「週刊ファミ通」で組まれた特集「すばらしきゲーム音楽の世界」で五位にランクインした珠玉のナンバーです。切ない旋律とともに、中世のフィールドにはこの時代特有の演出が施されています。それがまるで霧がかかったように薄暗い大地です。この薄暗さはゲーム冒頭の明るさとはあまりに対照的です。クロノの部屋に差し込む光、その晴れやかな現代の日常から一転、中世の暗さは物語に立ち込める暗雲と王国の不穏な情勢を占うかのようです。

そもそも「中世」はどうして暗いのでしょう。電気照明が発明される以前の風景を忠実に再現しているのでしょうか。どの時代も太陽は平等にこの世を照らしたはずです。この薄暗さの正体は「中世」という時代のもつ特異なイメージと関係しているように思います。
中世とは西洋の歴史区分の一つで、およそ五世紀頃から十五世紀頃までの長い期間を指します。476年の西ローマ帝国の崩壊から1453年のビザンツ帝国の終焉、あるいは大航海時代や宗教改革の始まりなどが分岐点に挙げられます。英語では “The Middle Ages”——「古代」と「近代」の〈中間〉にある時代、これが「中世」の由来です。
ただ、中世とは単に歴史の一期間を指すだけでありません。手元の辞書で、「中世の」を意味する英語の形容詞 “medieval” を調べてみると、時代区分の次に「古臭い」「旧式の」といった後ろ向きの意味が出てきます。より専門的な辞書をみてみると「無知」「残酷」「野蛮」といったネガティブな語義が並びます。“get medieval” というフレーズにおいては「中世風になる」ではなく「暴力的になる」ことを意味します。このあからさまな意味の凋落には当然疑問を覚えることでしょう。「クラシック」や「モダン」 といった語から連想するイメージを考慮すればなおさらです。
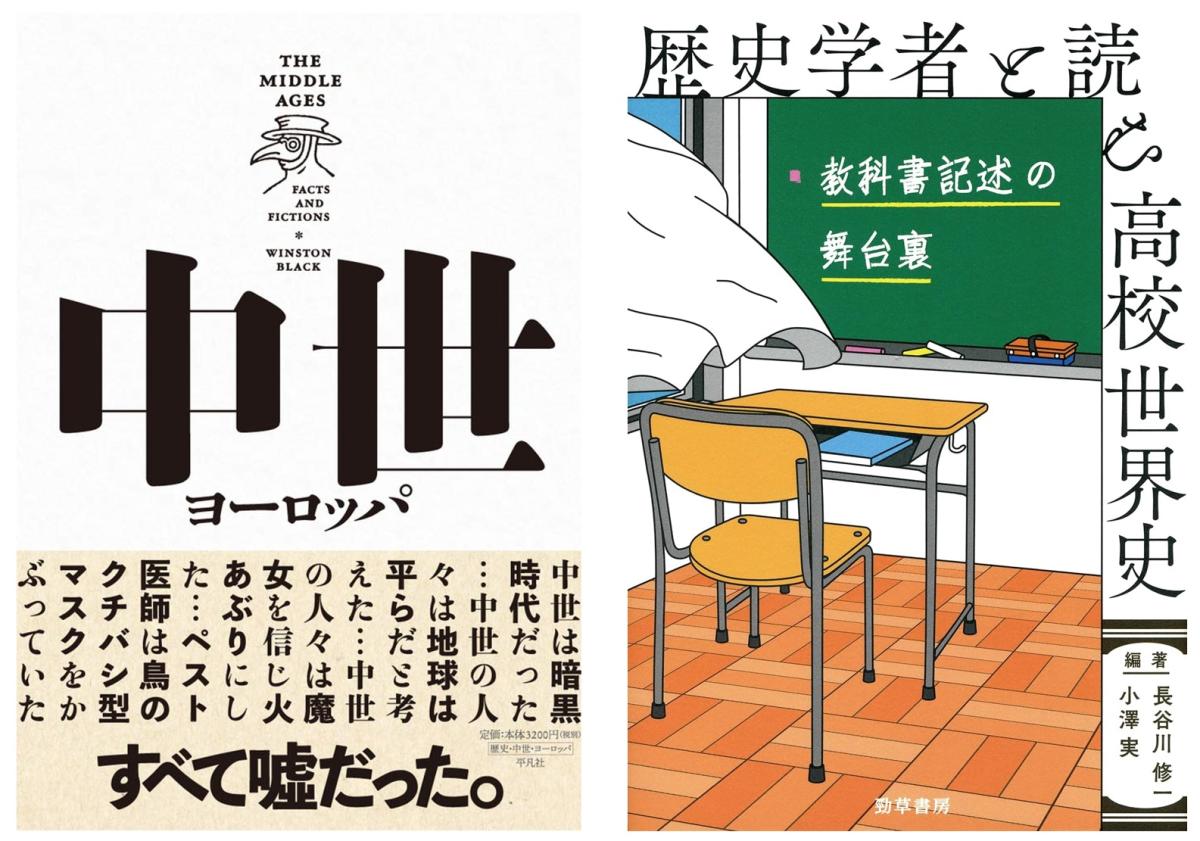
何やら穏やかならざる中世——歴史区分は人間が創り出した便宜上・認識上の区切りですから、必然「中世」は「中世」以後に生まれた概念ということになります。中世の負の連想には後世の人々の捉え方が大きく関係しています。14世紀のイタリアから広がったルネサンスは「古代」の文芸を尊び、その再生に努めた文化運動でした。この古代賛美の陰で直前の「中世」は貶められ、野蛮な風習や無知のはびこる「暗い時代」(いわゆる「暗黒の中世」)とされていきました。それは〈いにしえの栄光〉と〈近代の出発〉を引き立てるシャドー。約千年に渡る期間は一緒くたに語られ、時代錯誤やフィクションを含むいわくつきの中世像が生まれていったのです。
「この世 暗黒に染まりしとき 四人の光の戦士 現れん・・・」
——初代『ファイナル・ファンタジー』はこの一節(予言)で幕を開けます。〈光〉と〈闇〉あるいは〈善〉と〈悪〉の対立は、とりわけ初期の「剣と魔法」の世界には不可欠で不可避なモチーフとなりました。ファンタジーRPGは「暗黒の世界」という根深いステレオタイプをある種巧妙に使ってきたかのように思われます。
『クロノ・トリガー』の中世フィールドもこうした文脈と無関係ではないでしょう。中世の薄暗さの正体とは単に物理的な暗さだけでなく、中世に対するイメージが作り上げた心理的情景とでもいえそうです。つまり、本作も歴史上構築された中世像を継承しているということができます。
ただ、中世の暗さは〈光〉と〈闇〉の対立を助長するだけのものでしょうか。中世は「ラスボス」が潜む最終ステージではないし、一見そのように佇む「魔王」は後に半生が深堀されるほどの存在で、物語後半にはパーティの主軸を担うほどの変わり様をみせます。同様に、冒険の起点となる中世は、前後の時代と関連する中で変化し、また後の変化のきっかけをも作り出すのです。
霧がかかった中世——フィールド冒険を進めるプレイヤーは、まるで霧が晴れてゆくかのように、その先に広がりうる多彩な世界に出会い、現代そして未来へとつながる重要な「ルーツ」であることを再認識するのではないでしょうか。ともあれ、スーパーファミコンRPGの円熟期に誕生した『クロノ・トリガー』は、ポップカルチャーに浸透した西洋中世像を考える上でも意義深い作品に違いありません。
更新の通知を受け取りましょう



















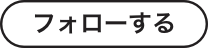


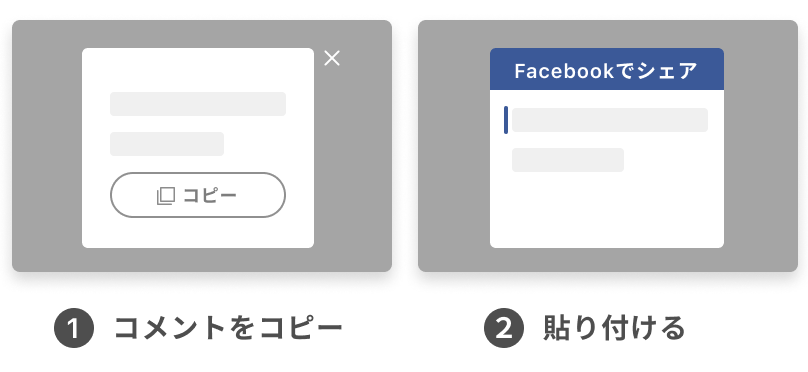

投稿したコメント