「異文化間感受性」で異文化交流が楽しくなる!発達段階の違いと、学習方法②
世界中にある多様な文化と触れる。体験する。楽しむ。
これは、個人の人生を豊かにするためにも、社会の中で人が円滑にコミュニケーションをするためにも、とても重要なことです。
でも、当然、一つの国の中にも多様性と多文化は溢れています。
日本の中に住む外国人や、外国に(も)ルーツのある人、日本の都心部と農村部、家に仏壇がある人とモスクに通ってお祈りをする人、昭和の時代を知っている人と令和生まれの人、肉食の人とビーガンの人、障害と向き合っている人とそうではない人、異性愛者と同性愛者、、、このように、「マジョリティとマイノリティ」だけでは片付けられないほどの多様性が溢れています。
このような違いがあるとき、多くの場合、それぞれのコミュニティが生まれてきます。
ハーフの人たちのつながり、キリスト教徒同士のつながり、大阪に住む人のつながり、身体障害がある人のつながり、、このようなつながりには、そのコミュニティ(集合体)としての「文化」が生まれてきます。
もしかしたら、それは「日本とアメリカの文化差」のようにイメージしやすいものではないかもしれません。でも、価値観や共通認識、言語など、いろんな文化が作られ、共有されていくのです。
「多様な文化の違いを理解し、感謝し、 受け入れようとする意欲や積極性 」
異文化間感受性は、このように、さまざまな文化を受け入れ、楽しみ、うまく交流することができるようになる態度に影響します。日本の中にあるさまざまな文化も含めて、これができるようになると、国内や地域における多様性の共生や、社内における相互理解の促進につながるのだと思います。
前半の記事では、この「異文化間感受性とは何か」について解説しました。後半は、その学習方法について触れていきたいと思います。

「異文化間感受性」はどのように発達する?
交流に関する感受性を高めるには、交流をすることが最も望ましいと言われています。しかし、同時に、「安易な接触は偏見を強める」とも指摘がされており、すべての接触が好意的なコミュニケーションに繋がるとは限りません。
海外旅行に行った先で、現地の人にとてもよくしてもらい、仲良くなった経験から「〇〇人はみんな優しくて最高だった」と感じる人もいます。
一方で、スリにあった上に、漢字の悪い人に出会う経験があったならば、「〇〇の国は最悪だし、もうその国の人は関わりたくない」と思う人が出てくる人もいます。
もちろん、後者よりは前者の方が望ましいですが、いずれも国という枠組みで全てを評価してしまうステレオタイプや偏見がある状況は変わらないのです。
ここで、望ましい交流のあり方を実現するために提案されてきたのが、Allport(1954)の提唱する「接触仮説」(intergroup contact theory)です。
これは、偏見の低減をするための交流の方法に、条件を提示したものから始まりました。そして、この交流方法は、偏見を減らすだけでなく、異文化間感受性を高めて、相互の感情を好意的なものにすることにも有効であることがわかっています。
この条件には、次のものが含まれます。
(1)協働を伴う活動に参加すること
異なる属性の2名(または集団)が、協力をしないと達成できない課題に取り組むということです。例えば、それぞれの経験を語り合うことや、それぞれの専門的な知識を持ち寄ることなど、協働が必然であるタスクが設けられていることが必要です。
(2)双方の立場が平等であること
上司と部下、先輩と後輩、先生と生徒、などの立場に関係なく、この活動に参加している間は、立場が平等であることが求められます。
(3)共通のゴールがあること
共通のゴール、つまりお互いが目指しているものがある、ということです。例えば、共に一つの作品を作る、あるプロジェクトを達成させる、物語を作る、などのゴール設定で達成しやすくなります。いい関係性を維持しながら、同時に達成感を味わえるような共通のゴールを、全員が認識できるような支援が求められます。
(4)ファシリテーターの元で社会的に認められた接触であること
接触はあらゆる日常的な場面で起こりうるものかもしれませんが、このプログラム自体が、ファシリテーターの元で行われているものであるという認識も必要です。
この4つの条件については、過去の記事でも触れているので、詳しくご覧になりたい方はぜひご覧ください。
接触仮説を取り入れたプログラムのサンプルは下記の記事に載せています。
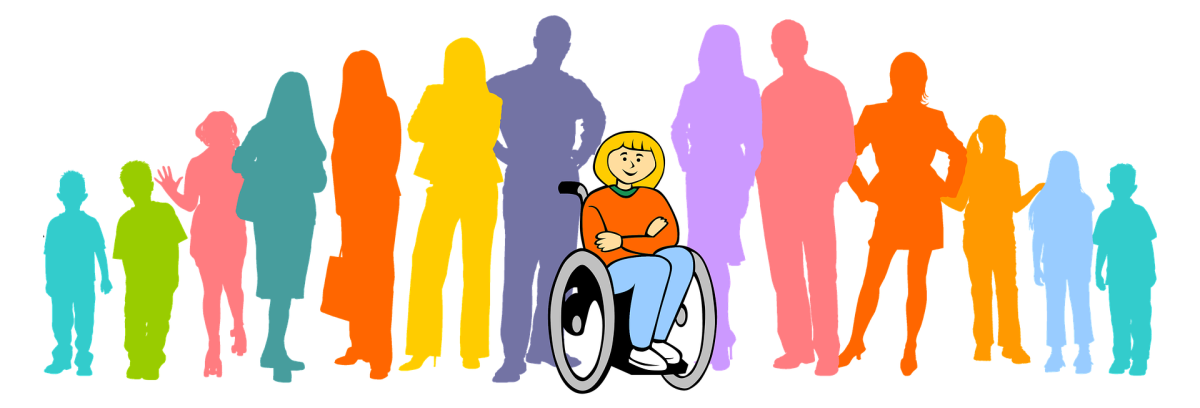
「接触仮説」をより強力なものにするコツ
さて、接触仮説の条件を揃えることが異文化間感受性の発達につながることについて言及しました。ここからは日本のコミュニケーションの特性や、文化的背景を踏まえて、どのように効果をさらに高められるのか、ご紹介したいと思います。
特に外国人や海外にルーツを持つ人との身近な接触において言えることですが、日本では特性として「傍観者的態度」を持つ人が多いと言われています。これは、 傍観者的態度とは、異文化受容態度のあり方の一つであり、異文化を認めるものの相手と関係性 を構築することに踏み込まない態度です。
街中で困ってそうな人を見ても、「迷惑になるかもしれないし、面倒なトラブルになるから話しかけないでおこう」という心理が態度に現れたものです。日本語がわからなくて迷っている人、車椅子でエレベーターに乗り込めずにいる人、高齢者で大きな荷物を下ろすのに苦労している人ーー街中でさまざまな人を見かけることがあっても、「関わることに価値を見出さない」「トラブルに巻きこまれたくない」という理由から、「わざわざ接触しなくていい」という判断をしてしまうことがあります。
このような判断は、プログラム中にも発揮されることがあります。特に、「どう話しかけたらいいかわからない」「話題がないから距離を置く」などの消極的態度につながりがちです。
そこで、交流する前に、相手のことを想像しながら、自分との共通点を探る質問づくりをすることが望ましいこと明らかになっています。(私の修士論文と博士論文では、この事前学習のプログラムを開発しています)
事前情報だけで相手のイメージを固めてしまわず、「聞いてみないとわからないことがたくさんある」ことを前提に、自分の趣味や興味、好きなものに関連しそうな質問を準備しておきます。
この質問をアイスブレイクでうまく活用するだけで、大きく接触仮説を取り入れた交流のあり方が変わってきます。
もしかすると、実践する対象によって、事前学習は変わってくるかもしれません。
ぜひ、それぞれの現場での工夫を試みてもらえればと思います。

更新の通知を受け取りましょう
























投稿したコメント