農家と消防団
消防出初式が昨日私の地元、国立市でも開催されました。
出初式とは新春の消防仕事始めの行事で、ニュースなどでもハシゴのぼりなど見たことある人も多いでしょう。国立市では消防団全6分団と各町内会の自主防災グループ、総勢300名ほどが参加し、恒例の一斉放水などを行いました。
新年からの痛ましい震災で地域防災にも関心が集まっているかと思いますが
地域防災の要といえる「消防団」と「農家」はかなり深いつながりがあるので、それについて紹介したいと思います。私もいまは引退しましたが消防団員として8年務めました。
消防団員は市民有志による「非常勤の公務員」
消防団は法律で定められて各区市町村に設置されている公的な組織です。常勤公務員である消防署員とは違って、基本は市民によるボランティア組織でありますが、分団小屋と呼ばれる屯所や消防車、耐火服など設備費も多くかかりますし、団員には報酬も支払われます。非常勤の行政職員ということになります。
国立市は人口7万5千人ほどの街ですが、本団のほか6個分団があり各19名の団員、130名ほどの消防団員がいます。市内で火災の連絡が消防本部にはいると各団員のLINEやメールに通知が届き、出動できる団員で消防車を現場に走らせます。
日々のそうした取り組みもあり、国立市では10年以上火災による死者は一人も出ていません。
港区のような都心部にも消防団はあり、消防車などはさすがにありませんが、救命講習や放水訓練、防災のPRなどにあたっています。日本全国ということになると80万人を超える現役消防団員がおります。

消防団の歴史は「大岡越前」がつくった1700年代初頭の「町火消」までさかのぼります。明治維新も太平洋戦争敗戦の歴史もこえて「地域防災の要」でありつづけています。これは賛否あるところですが未だに江戸時代から続く農村文化と明治以降の洋式軍隊型規律がミックスされた「村社会的雰囲気」が色濃く残っています。
村の若者たちを教育して、上下関係にもとづく村の一体感を醸成する役割をずっと担ってきた側面も大きいのです。
13年前に国立市に引っ越してきて農業を始めた私が、今も残る東京の「農村」に帰属する道として消防団入団は必要な選択だったと思っています。
また、いざという時に地域で避難所を設置する、何かの伝達をする、一緒に作業をするなど組織力を発揮しなければならないときに、こうしたある種の技術と規律をもった市民集団が必要となるのは想像に難くないでしょう。
日本全国80万人、地域の有力者の多くが「消防団OB」
現在も避難所では消防団やそのOB(町内会などの自主防災組織の一員となっている場合も多い)が活躍されていると思います。とても大事な仕組みであると思う一方で、団員の確保は容易ではありません。火災出動だけではなく年間の訓練や市内巡回、火を取り扱うイベント等への出動を換算すると年間の出動日数は50日以上となる団員も少なくありません。毎週のように消防団に関する集まりが何かしらあるわけで、家族からはヒンシュクですし、そもそも普段は自分の仕事があるわけなので、仕事を終えて20時ぐらいから訓練に出かけるなども、言ってしまえば「かったるい」職務でもあります。任期は一応2年となっていますが、基本的には最低4年、班長、部長、副分団長、分団長などと昇進していくと長い団員では20年以上続くのです。

一昔は、あるいは今も、地域の農家や商店主など古参の地主の家からは長男が団員となるのはほぼ義務のようなところもありました。よく消防団では「市民の生命と財産を守る」という言い方をするのですが、失う財産が多い家の若者が防災組織の一員となり、やがて地域コミュニティを支えるというのも自然な流れといえるでしょう。
結果として、日本全国どこへ行っても地域の有力者は「消防団員」を経験していることが多いのです。消防団の話をすればほぼ確実に共通の話題が見つかり、ちょっとした武勇伝や失敗談、愚痴などいくらでも出てきます。
言ってしまえばいまだに「兵役」的な要素が大きいため、徴兵、訓練、従軍にまつわる上下関係やすったもんだ、酒と色がらみのいろいろが混然一体となって各自のなかに刻まれているのです。日本のホモソーシャル極まれりというところでしょう。
しかし、連帯感や信頼というのはキレイごとではないところから生まれやすいですし、初めて会う農家などと踏み込んだ話をするときにこれほど便利な話題はないといえます。
「村」への入り口として、農村文化の担い手として
地域の古参と「仲間」になる道筋として消防団は誰に対しても門戸は開かれていますし、担い手が少ないこともあって、ある程度参加して役を担えば確実に感謝と信頼を獲得出来ます。しかし一方で、部活の上下関係のようなホモソーシャルが苦手な人にとっては苦痛かもしれないですし、最近のジェンダー的なコンプライアンスからみたらだいぶギャップを感じることも多いでしょう。

しかし、コンプラ的な正しさでこれからの超少子高齢、人口減社会において「共助」の精神を守れるかというとそうはいかないでしょう。共助は個々の利害がぶつかるところをコミュニティの差配で調整する役割を持ちます。なにかあったらすぐ市役所や警察に電話して問題解決を迫るようなことではとても社会が持ちません。 暗黙の上下関係がなければ対立する個人同士の調整などつけようもありません。地域のことは地域で解決する社会であるためには「表面的な正しさ」を超える「仲間」と「上下関係」は確実に必要です。
年末年始は歳末警戒から出初式、私の地域では「どんど焼き」での防災活動など消防団は大忙しです。地域住民としては日々の尽力に感謝しつつ、彼らの自主的な活動をサポートして、いざという時は彼らの判断を尊重するというような作法がこれからも続いてほしいと思います。それが失われるときは日本型のコミュニティの核となってきた農村文化や祭りも失われるときだろうと思うのです。
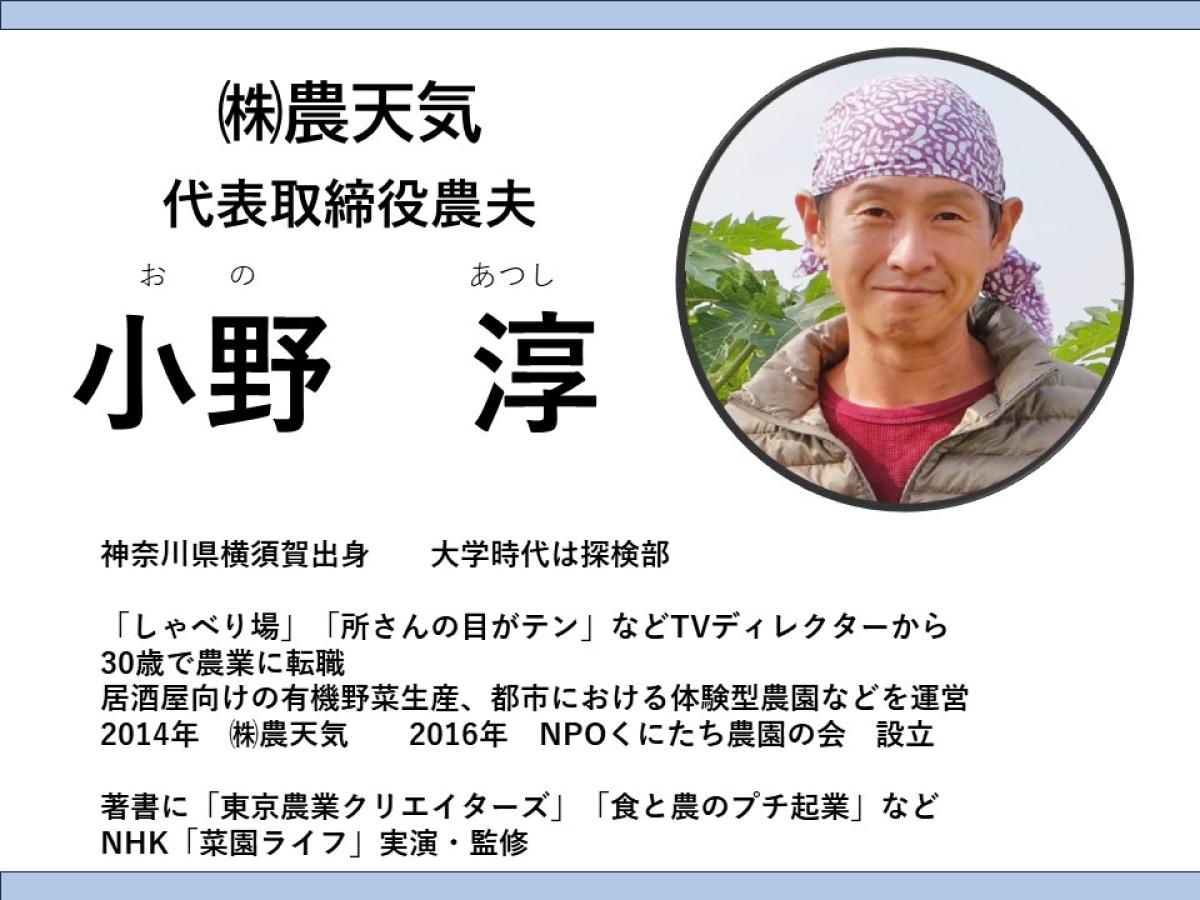
更新の通知を受け取りましょう
























投稿したコメント