7割以上が「後継者がいない」農業界のモヤモヤ② 安易な「福祉との連携」の落とし穴を超えて
農福連携という言葉あります。農林水産省も力を入れているジャンルで、公式ページによると「障害者等が農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現していく取組です。」とのこと。担い手不足の農業界、働きたいとおもう障がい者、そのマッチングを促進することで双方の課題を解決しようというのが国の方針なのです。
このジャンルの先進事例として高名な農業法人があります。静岡県浜松市で「京丸姫」などミニ野菜の水耕栽培を手掛ける「京丸園」です。年商5億、約100名の従業員のうち20名以上が障がい者手帳を持っています。勤続20年以上の社員もおり、農業経営としても大変優れています。
先週、実際に尋ねて鈴木厚志社長とお話しする機会をいただいたのですが「農福連携という言葉はありますけど、本質的な意味ではありえないと思っています。」とまさかの発言。
現場も拝見しながら実際に話を聞いてみるとまさしく、この言葉に農業界の問題が凝縮されていると感じました。

京丸園の右肩上がりの成長を支えた「障がい者雇用」
農林水産省による農福連携に優れた事例を表彰する「ノウフク・アワード」において京丸園は2021年グランプリを受賞しました。つまり日本における農福連携のお手本というお墨付きが付いたと言えるでしょう。もちろん、農福連携という言葉が生まれる前から京丸園は障がい者雇用を実践してきています。

最初は、事業拡大に伴う人手不足の解消が目的で試しに採用してみたところ案の定様々な課題が生まれたそうです。しかし、その課題を経営者として「個人の努力や成長」に依存するのではなく、作業指示や職場環境の改善によって解決していったところ、全体の生産性が向上、以後毎年一人づつ様々な障がいを持つひとたちを雇用して、その都度改善を重ねていったところ「誰もが働きやすく結果をだせる農業」になっていったというのです。
例えば、個人の技量によって善し悪しの差が出やすい苗の植え替えという作業があります。これを誰が作業しても同じ深さに植わるように植穴となっている発泡スチロールを特注で改善するなど、一つ一つの作業精度のばらつきをなくしていったということ。工業の現場では珍しくないようなことですが、そこまで投資して作業標準化を図る現場は農業界では稀有です。

そうした改善のヒントをくれたのが「できることとできないこと」の凸凹が大きい障がい者であったという実感を鈴木社長は持っており、誰もがやりがいをもって働ける職場づくりは結果的に農業の生産性も上げ、個人農家だった京丸園は法人化してさらなる成長を遂げました。こうした改善の詳細は、書籍「ユニバーサル農業~京丸園の農業/福祉/経営~」(鈴木厚志著 創森社より2023年刊)に詳しく紹介されています。
農福連携が見落としがちなこと
私のところにもときどき農福連携に関する相談が来ることがあります。常時雇用100名以上の企業であれば法定雇用率が定められており、従業員数の2.3%は障がい者雇用をする義務が課せられています。未達の場合には社名が公表され、不足人員一人当たり月額5万円の「障害者雇用納付金」を支払わなければなりません。つまり大きな会社であればあるほど障がい者が勤務できる職場を創らなければなりません。そこで農業部門を社内につくってなんとか解決できないかと考える企業がしばしばあります。
しかし、ことは簡単ではありません。その会社は農業をやりたいわけでも福祉をやりたいわけでもなく「なんとなくイメージがよさそうな農福連携」に手を出そうとしていることも往々にしてあるからです。結果として多額の投資をしたものの結果が出ないということになりかねません。
鈴木社長が本質的に農福連携などない、と言ったのはそういうことです。農業をやるならまずはどんな農業経営でどのような結果を出すのか明確にすべきだし、経験のない組織であればそれは新規事業を立ち上げるために必死で取り組むべき。逆に農業生産ではなく福祉に力を入れたいのであればどのような福祉事業にするのか考えるべき。なんとなく農福連携ではどっちつかずで、経営がうまくいくわけがない。ということなのです。
90歳まで働ける農業を
京丸園では障がい者だけではなく高齢者にとっても働きやすい現場を目指しています。出荷する野菜の調整(萎れた葉などを取り除いて袋詰めするまで整える作業)を見える化して個々人の生産性を把握、それによって必要な出荷数を確実に確保できるようにするとともに、個人の能力に応じた支払いが可能となっています。

表題の通り、日本の農業後継に関する展望はかなりネガティブです。しかし、実は働き手がいないわけではない。いままでほとんど個人のマルチタスク化によって生産性を保ってきた農業現場を改善することで、誰もが生産に関われるようにしなければ、農業の未来は厳しいと鈴木さんは気付いているのです。実際に京丸園では87歳で働いている方もいるということ。それを実践して農業経営としての結果も出しているので説得力があります。
それぞれの作業現場にはオリジナル開発の機械も数多くあります。一般的には人手不足を補うスマート農業は「人がいなくてもできる農業」をイメージすることが多いでしょう。私自身もそうでした。しかし、京丸園では「誰もが働けるようになるスマート化」を目指しており、人員削減のための機械導入はしていません。
多くの人が関わることで会社としても社会のなかでより必要とされ価値を生み出せるという信念が伝わってきました。
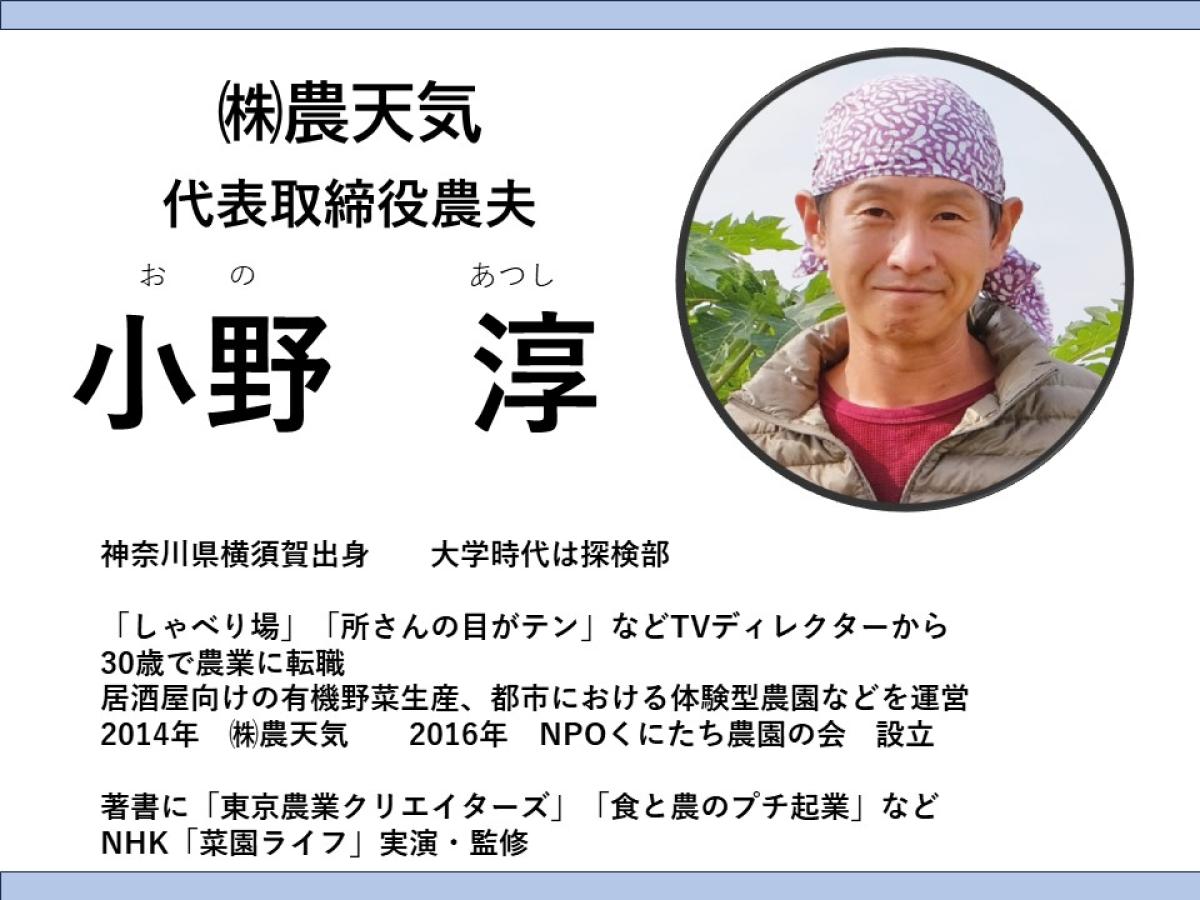
更新の通知を受け取りましょう
























投稿したコメント