Vol.69 「尊敬」は批判の後に現れる/『本を読む本』
所詮は人間である
本を読む時に、気をつけていることがあります。
それは、どれだけ著名であろうと、書いている相手は人間であることを忘れないこと。
どれだけ名前が売れて、どれだけ深いことが書かれていて、どれだけカリスマとしての評価を受けていようとも。所詮は人間なのです。
人間だから、感情に左右されて物事の一面しか見ることができない時もあるし、大間違いもする。
その本の内容が、そのタイミングとその近辺では正しかったとしても、時代や土地を超えて、その内容が全て正しいということはないのです。
そりゃそうだろうと思うかもしれません。
ではなぜ、こんな当たり前のことを言うのか。
それは、僕の中に「誰か、信頼できる人の思想に寄りかかりたい」という欲求が明確にあるからです。だから、ちょっとでもすごい人がいれば、自分の中でその人を神格化し、「その人が言っているから」として、考え方を安易に飲み込んでしまう。
めっちゃ楽なことです。
楽をしたい怠惰な僕は、いつも心の中で、神格化できる存在をどこか心待ちにしている。
でも、残念ながら、そんな存在はいません。
それを確認したければ、哲学史をちょっとでも見ればよくわかります。
プラトン、アリストテレス、デカルト、スピノザ、カント、、、、今まで数えきれないくらいの天才的哲学者が出現してきました。
しかし、彼らの思想は、当時から今まで、たくさんの批判を受け続けています。そして、またその批判から新たな思想が立ち上がり、そしてまた批判を受ける。こうして思想は発展(あるいは循環)してきました。
結局、神格化できる存在や非の打ちどころのない思想など、今まで出てきたためしがありません。
真の理解・尊敬とは何か
だとするならば、とある人の考えを本当に理解するというのは、その誤りや限界を指摘できてこそ。理解するということは、無条件に信じるのではなく、その効用範囲を知っている、ということと同義なのです。
これは、他者に対する「尊敬」という感情も同じことだと思います。
もし、誰かを全人格的に尊敬していると言い切れるならば、それは単にその人に対する理解が表面的なだけです。人間だからこそ、醜い部分もあれば、賛同できないところもある。
その人の限界を理解する。
その上で初めて「尊敬」という言葉を口にできるのではないでしょうか。
カントには、三大批判書というものがあります。著名な『純粋理性批判』、『実践理性批判』、『判断力批判』の三作品です。
この「批判」という言葉の意味は何か。それは、ネガティブな意味での「批判」ではなく、概念の限界を指し示し、明確な線を引くことで縁取りをしていこうということです。そうすることによって、初めて僕たちは、たとえば「純粋な(経験によらない)理性」というものがどういうものなのかを理解することができる。理解するとは、批判(縁取り)をした後で初めて現れてくるものなのです。
読書本のロングセラーである『本を読む本』では、このようなくだりがあります。
たしかに、読者に何かを教えるという意味で、読者よりもすぐれている本を批評するには、まず、その内容を理解することが前提である。
そこではじめて、読者は著者と肩を並べたことになる。対等者としての特権を行使するのは、それからである。
ここで存分に批評の手腕を振るわない読者は、著者を不当に扱ったことになる。
著者は、読者を自分の水準まで引き上げることに努めたのだから、当然、読者にも、対話の相手として、対等に語り返すことを要求できるのである。本を正しく批評する P.147
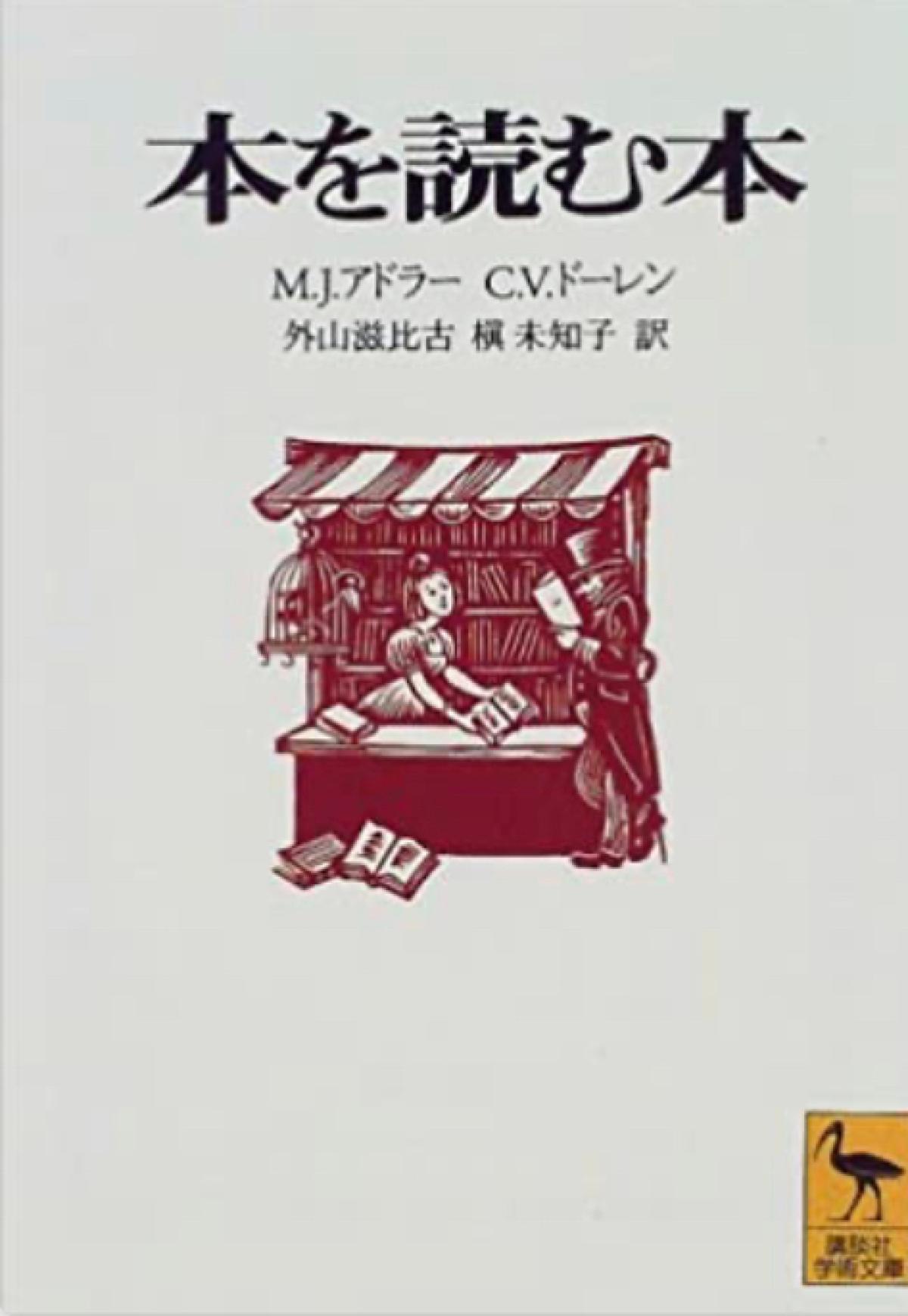
「ここで存分に批評の手腕を振るわない読者は、著者を不当に扱ったことになる」
という表現はとても秀逸だと思います。
もし、その著者を、もしくは著書をリスペクトするのであれば、その考えを存分に批評してから、ということなのです。
もし本気で好きになれる本があれば、その本の批判、つまり効用の限界を指摘してみましょう。
そして、リスペクトできそうな人がいれば、その人の欠点を深く理解してみるのです。
その批判的精神を発揮した後に、僕たちは本当の「尊敬」という地平に辿り着けるのではないでしょうか。

更新の通知を受け取りましょう
























投稿したコメント