韓国映画『毒親<ドクチン>』。新鋭キム・スイン監督ロングインタビュー。過ぎた母の愛と、それを受けた娘の選択。印象的なラストシーンに秘められたもの。
優等生の高校生ユリ、誰よりもユリを愛する母親ヘヨン。周りからは、理想の母娘とみられる2人だったが、実はユリは母へヨンの度を過ぎた教育と執着に悩まされていた。そんなある日、集団自殺をした若者の中で、ユリの遺体が発見される。なぜ、彼女は死を選択したのか。刑事が事件を探る中で明らかになる歪んだ母親の愛とは。
第27回富川ファンタスティック映画祭、第28回あいち国際女性映画祭と映画祭で注目を集めた『毒親<ドクチン>』。監督は、この作品が長編デビュー作となる、キム・スイン。4月6日(土)日本公開にあわせて、来日されたキム監督とイ・ウンギョン(プロデューサー)に、作品を製作するきっかけや監督として演出することになったいきさつ、テーマへの想いなど、ロングインタビューをしました。

キム・スイン(映画監督)
1992年11月5日生まれ。2019年 長編映画『ウォルチェ』で韓国映画シナリオ公募展優秀賞を受賞。2023年4月に公開され大ヒットした『オクス駅お化け』では脚色で参加。韓国の男性アイドルグループ「神話(SHINWA)」のキム・ドンワンが主演を務めた犯罪スリラー『覗き屋』は脚本を担当。様々な長編映画の製作に参加しつつ活動の領域を広げてきた。そして、2023年11月に満を持しての長編デビュー作『毒親』が韓国で公開。本作も自ら脚本を務めているが、監督としても新人とは思えないスキルと演出力が高く評価されており、韓国で期待の若手監督のひとりである。
ロングプロットから脚本、演出へ
ーーまずは、この作品を製作するきっかけを教えてください。最初に脚本の製作を依頼され、そのあと、監督へ抜擢された、というお話ですが、経過を含めて、お聞かせください。
イ・ウンギョン:当初、キム監督は、弊社で半年間、インターンをされていたことがあります。その際に、私から、この作品のテーマを伝え、ロングプロットの製作を依頼したのです。そして、その1年後、その時書かれたもの(最終稿とは異なる)を、国の韓国コンテンツ振興院に提出したところ、補助金(1500万)※1が採択されたので、弊社から追加出資をして、この作品を製作することにしました。
※1 参考:2022年版 韓国コンテンツ産業支援政策調査報告書(引用:(特非)映像産業振興機構(VIPO)より)
キム監督は、初稿を書いていただいた縁もあり、また、母親世代ではなく、子の世代に近い監督との方が、良い作品になるのではないか、と考えて、監督(演出)も依頼したところ、快諾いただきました。

ーー依頼されたテーマから、この作品の形になるまで、監督ご自身の創作性は、どのように反映されたのでしょうか。子供の自殺、親子関係、警察の捜査から明らかになる展開など、初稿からどのような変更が加えられたのでしょうか。
イ・ウンギョン:日本の小説『モンスターマザー』(福田ますみ著)の映画化の動きがあるという噂を聞いたのですが、マザーの前に「モンスター」をつけることに違和感がありました。母親は、子供のために、犠牲をはらい、献身しているのに、「モンスター」という表現を使いたくなかった。そんな時、友人の高校教師から、米国・スーザン・フォワードの著作『毒になる親 一生苦しむ子供』を紹介され、その中で「毒親」という言葉があると。
また、監督には、母娘関係に加えて、教師や同級生との関係性なども加えてはどうかと提案させていただきました。
一方で、この作品の中で描かれる刑事による捜査劇や、同級生イェナの人物像、担任の教師の背景など、登場自分の関係性は、すべて映画化に向けて、監督が創作されたもの。また、初稿では、母親の異常性が誇張されていましたが、本作品のような形へと母親像を変化させていただきました。そういう意味では、この作品の脚本は、ロングプロットからゼロベースに戻した上で、再構築いただいています。

ーー韓国映画は、実話を元にした作品が多く製作されている印象があります。この作品も、主人公が集団自殺するシチュエーションや、母親の過干渉な姿は、とてもリアリティがあるように感じますが、この作品は、実際に起きた事件などが元になっているのでしょうか。
キム・スイン:韓国で集団自殺というニュースが報道されることもありますが、そこまで多いわけではありません。ただ、起きていないわけでもありません。この作品の脚本を製作するにあたり、集団自殺の募集サイトのようなものを発見し、参考にしたり、しました。
また、私の好きな小説家に、パク・ミンギュという作家がいるのですが、彼の『朝の門』(パク・ミンギュ著(短編集『カステラ』に収録されている)いう小説があるんです。この作品で、いろんな分野の、繋がりも何もない、知らない人たちが集まって、集団自殺をする設定が登場し、印象に残っていたので、自分ならではの演出で表現できないか、というのを考えて、オープニングのアウトドアのシーンを用意しました。
ですから、実話を元にした、というわけではありません。

母親が変わる必要があるのか、ということは重要ではない
ーーラストシーンが、特に印象的だと感じたのですが、なぜ、あのラストシーンを、あのユリの印象的なセリフを設定したのでしょうか。その意図や監督の想いをお聞かせください。
キム・スイン:撮影に至るまでに、何度も推敲を重ねていますが、あのラストシーンは、初期のシナリオには、なかった設定です。もう少しドライなラストを用意していました。また、私は、あのセリフを用意しつつも、ユリの自殺は、母親への復讐が目的というわけではなく、基本的には、何か社会的な、さまざまな要因が原因になってると考えています。ただ、脚本を読んだ方から、もう少しユリの気持ちを観客に伝える必要があるのではないか、という意見を多くいただき、ラストシーンを現在の形へ改稿しました。なので、あのシーンに強い意図があるというわけではなく、ただ自然にあのエンディングにたどりつきました。

ーーそのラストシーンの前に、母・ヘヨンとユリの弟のシーンも印象的です。このシーンでは、ヘヨンは、結局、子供の愛し方がわからないまま、救われることがない、というか、あのままでは、ヘヨンと弟は、同じ悲劇を繰り返してしまうのでは、と心配になりました。また、このシーンをラストシーンに置くという選択肢もあったのではないでしょうか。その場合、作品を観終わった時の印象が変わったのではないか、とも感じましたが、監督は、どのように考えたのでしょうか。
キム・スイン:私は、最初から、この作品のエンディングは、ユリがいちごケーキを食べるシーンで終わらせようと、決めていました。なので、エンディングについて、迷いはありませんでした。あのラストが、オープニングのアウトドアのシーンと対になっています。
また、実は、ヘヨンに関して、彼女がどういう風に変わっていくのか、変わる必要があるのか、という点は、自分としてはあんまり重要じゃなかったんですよ。
あのヘヨンの姿をみている、私たちの考えが大切だと思ったので。
この映画を観た観客の方々が、「これは変えなければならない現状だ」と感じていただけると、「信頼」というか信じていました。つまり、「変えなければ」とみなさんが感じることが大切なのであって、ヘヨンが変わるかどうかは重要ではありません。もちろん、変わってほしいんですけど。そういう意味では、観客のみなさんが、「大変だ」「何か変えないといけない」という風に思って思ってもらえるのか、というのが自分の意図という意味では、意図だと思うんですね。

ーーこの作品の時代設定について、お聞きします。先に日本で上映された「あいち国際女性映画祭」のQ&Aでは、ヘヨンは、監督ご自身のお母さんの世代を少し意識して、ユリは、監督に近い世代を意識されたとお話されていました。一方で、作品中の防犯カメラ映像の日時表示は「2024年6月」と、今よりも少し先の時代の設定がされていましたが。
キム・スイン:この作品は、2022年の7月に撮影しました。 そして、公開は、1年後ぐらいになるのではないか、と考えていました。そして、私は、作品を観た方には、ちょうど1年後の物語を見てほしいと考えています。
これから1年後の世界でも、こういう問題は続くのではないか。これからこういうことが起こりうるかもしれないので、皆さん気をつけましょう、みたいなメッセージを入れたいっていうことで、ちょうど1年後っていう設定なんです。

ーー最近、特に韓国映画では、若手の女性監督の活躍が印象的だと感じているのですが、、監督ご自身は、どのように感じておられますか。
キム・スイン:私は、そこまで特別に女性監督が増えたって感じは、していません。最近日本で公開した作品、映画祭などで紹介された作品が、たまたま女性監督が多かっただけで、そう言われればそうなのかなっていうぐらい。
ただ、現在、大学の映画学科の学生は、確かに女性が増えています。講義に訪れたりすることもあるのですが、彼らが卒業して、今後、4、5年後は、本当にもっと増えてるかもしれないとは、感じています。
ーー韓国の映画事情について、お聞きします。韓国では、とても若い層の方が映画館に、多く行かれるというニュースをよく目にするんですけど、実際のところの印象はいかがですか。
キム・スイン:(私は、リサーチする立場でははく、脚本や演出する側の人間なので、文化的な脈略から考えると、もうちょっと深い話が出てくるかもしれないですが)まず、韓国には、ほとんどミニシアターがありません。基本的にシネコンです。そして、シネコンの多くは、大型ショッピングモールの中に入ってるんですよ。そこ行けば、別に映画だけではなくて、食事もできるし、買い物もできる。だから、ちょっとデートコースのひとつなんですね、映画を観るというのが。だから、若者が集まりやすい。週末に、そこにいけば、映画だけではなくて、いろんなことができる。デートの一環として映画を見るっていうのが、結構、長い間、定着してるような気がします。
(大型商業施設側も)プロモーションみたいな感じで、若者に来てもらえるような、色んな取り組みをするので、その影響じゃないのかなっていう風に感じています。
イ・ウンギョン:ただ、コロナ以降の変化はあります。特に配信サービスの普及。韓国は、新しいものを買いたいという国民性があり、急速に家に大型モニターテレビが普及しました。大きなモニターが自宅にあるものだから、例えば、アクション映画であっても、映画館の大きなスクリーンで必ず観なければならない、という感覚が薄れつつあります。
コロナ前は、やっぱり「映画は映画館」という意識があったのですが、コロナ後は、それが薄れてしまい、2023年は、1000万人を動員した作品は、2本だけ。コロナ後の動員は、全然回復されておらず、6割ぐらいと言われている。全盛期は、1人が年6回観る国民だったのですが。

ーー今後、監督は、演出または脚本で、チャレンジしたテーマやジャンル、興味を持っているテーマはありますか。
イ・ウンギョン:実は、キム監督は、2本目の作品の撮影も終わり、2024年中の公開を控えているんです。
キム・スイン:私は、人と人の関係にとても興味があるんです。それぞれの関係の中に、社会的な何か要素があれば、それを取り入れて描きます。ただ、やはり、注目するのは関係性なんですね。
そして、それはシンプルな関係じゃなくて、多層的な関係性の中で物語を展開させるのが好き。また、例えば、「誰かの死」が物語の中心にあったとしても、その死に興味があるわけではなく、 その周りの「残された人々」を観察したり、彼らの生活に何の変化が起こるのか、それをちょっと考えたりとかするのに、興味があります。
ジャンルとは関係なく、そういう「関係性」を中心にした物語を、これからも作り続けるんじゃないのかなっていう気がしています。

--<INFORMATION>--
『毒親<ドクチン>』
監督:キム・スイン
出演:チャン・ソヒ、カン・アンナ、チェ・ソユン
2022年/韓国/104分
2024年4月6日(土)ポレポレ東中野ほかロードショー!

【執筆者:藤井幹也】
映画情報「Life with movies」 の運営を担当。 年間400本以上の作品を映画館で鑑賞しつつ、国内で開催される映画祭(東京国際映画祭、大阪アジアン映画祭、SKIPシティ国際Dシネマ映画祭、フランス映画祭、イタリア映画祭等)へ参加している。作品配給側の視点ではなく、作品鑑賞側・観客側の視点を持ちつつ、客観性と多様性を持つ映画情報を届けるべく、と日々活動中。活動エリアは、京都を中心に、関西地域ですが、映画祭へ参加のため全国各地を飛び回る日々。
X:旧Twitter
https://twitter.com/with_movies
Threads
https://www.threads.net/@lifewithmovies_jp
Filmarks
https://filmarks.com/users/Lifewithmovies
ソーシャル経済メディア「NewsPicks」
https://newspicks.com/topics/life-with-movies
更新の通知を受け取りましょう




















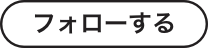


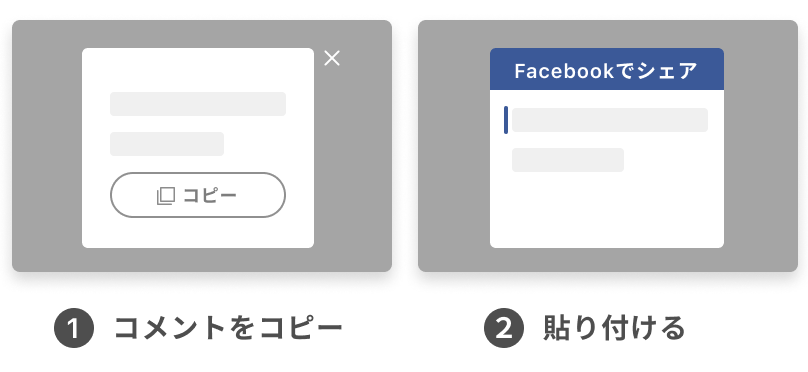

投稿したコメント