キャリアを見つめ直したい時に読みたくなる本、超個人的三選
お盆休み中の方々も多いかと思いますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。私は先週お休みをいただき、妻の実家のある京都方面に1週間ほど滞在していました。コロナもあって数年単位で帰れていなかったので、3歳の娘を初めて妻の親族にオフラインで会わせられたり義母のお墓参りができたりと、ずっと心のどこかで引っかかっていたイベントをこなすことができ、久しぶりにリフレッシュができました。
さて、少しまとまった休みが取れると落ち着いて考える余裕もでき、ご自身のキャリアについて考える方も多いんじゃないでしょうか。今回は普段と趣向を変えて、夏休みの読書(には少し遅いですが…)に良さそうな、私なりにキャリアを考える分岐点になった本を3つほどご紹介してみたいと思います。
もし起業を考えるなら: 『レイジング・ザ・バー〜妥協しない物つくりの成功物語(ゲーリー・エリクソン著)』
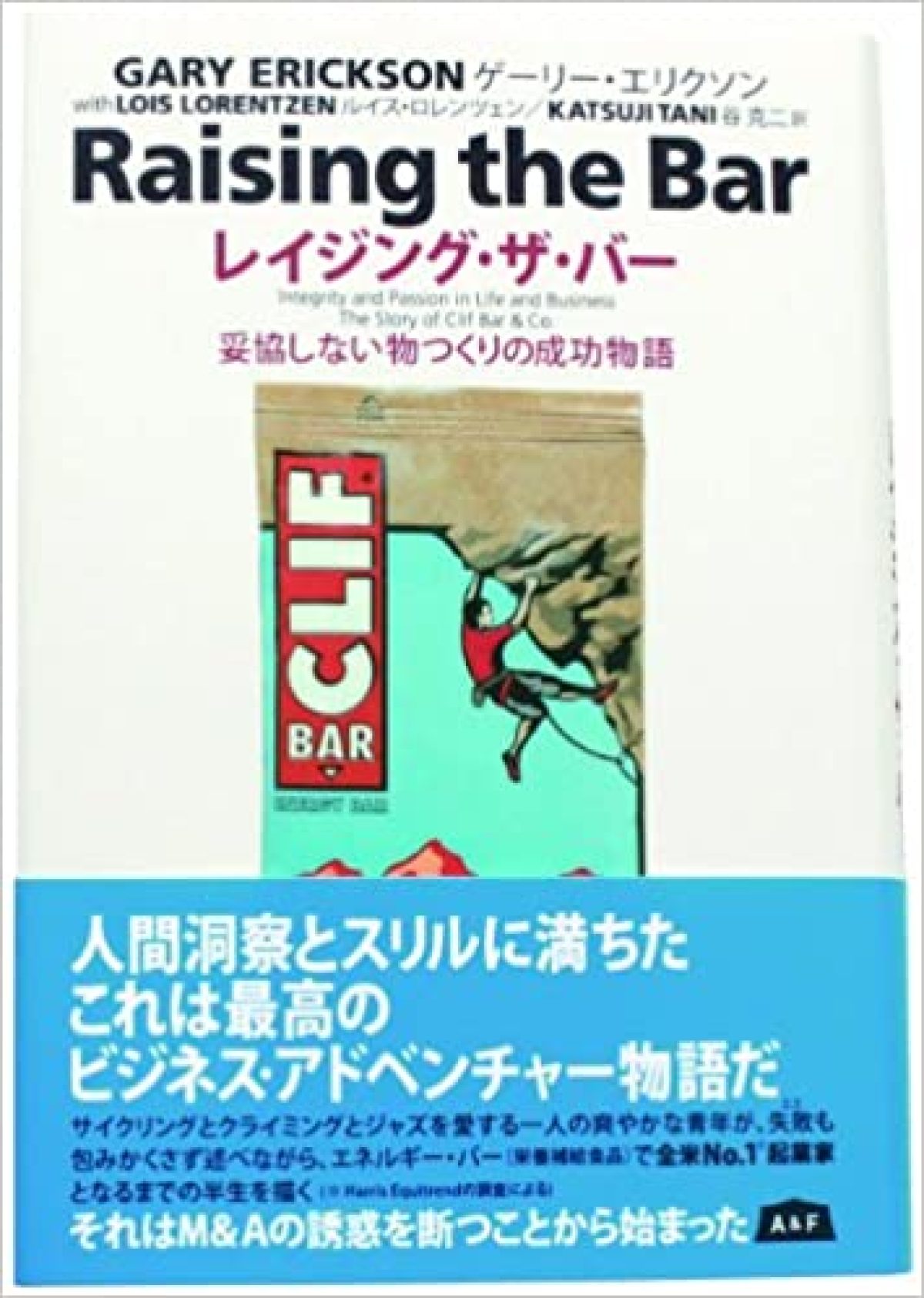
https://www.amazon.co.jp/dp/499070651X/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_W3JWAVB1TKV9X5DCE6AA
クリフバーというオーガニックなエネルギーバー(栄養補助食品)を作っているクリフ社のCEO、ゲーリー・エリクソンの著書です。今の会社BONXを創業する時にこの本を読んだことが一つのきっかけになったので今でも非常に印象深い本となっています。
もともとサイクリングやクライミングが非常に好きでクライミングガイドなどをやっていたゲーリー氏、サイクリング中の自分の体験がきっかけで母親のキッチンで作り始めたエネルギーバーが非常に好評を博し、加速的にビジネスが拡大。ついには年商4,000万ドルという巨大ビジネスになる中で、会社を売却するかどうか非常に大きな決断を迫られます。
本書は悩みに悩んだあげく巨額のM&Aオファーを「直感で」蹴ったゲーリー氏が、もう一度クリフ社の創業時のストーリーや自分の半生を振り返りながら、ビジネスとしてクリフ社の舵を切り直す一部始終が記されています。特徴的なのはゲーリー氏のバックグラウンドであるクライミングなどの用語をつかって様々なシーンが表現されていることで、エンターテイメントとしても非常に面白いにも関わらず、M&A交渉の舞台裏などビジネスで使える知識もちゃんと織り込まれていることです。
ポップでサブカルの匂いのするビジネス書という意味ではクラフトビールBrewDogs社について書かれた『ビジネスフォーパンクス』に近いものがあり、ビジネスの裏側まで手に汗握るトーンで書かれているという意味だと名著『HARD THINGS』にも通じるところがあります。残念ながらKindle版はないようですがとても読みやすいのでおすすめです(何よりも小難しいテクノロジースタートアップの話ではないところがいいですね!)
さて、この本からは様々な示唆が得られますが「会社のストーリーやビジョンに真摯に向き合いつづけることが如何に難しく、そして如何に大切なのか」というポイントを教えてくれるように思います。クリフ社は従業員も含めた人々の健康や自然環境との共生、サステイナビリティについて非常に注力しており、早期からNPOや自然保護コミュニティへの還元を実施しています。言い換えると創業前からゲーリー氏が大切に思っていたストーリーが今でも非常に大切にされていて、それが会社や商品そのもののブランディングにつながっているのです。
最近では"パーパス経営"という言葉が非常に重要性を増してきていますが、ある意味で2000年代からずっとパーパス経営を続けているのがクリフ社に他なりません。下記企業サイトの沿革ページを見れば大まかにわかるかと思いますが、こんなに面白い沿革ページを公開してる企業もあまりないように思います。
https://www.clifbar.com/who-we-are/our-journey
もし読者のどなたかでいつか(もしくは今すぐ)起業しようと思っているのであれば、どんな課題を解決したいのか/どんなプロダクトを作りたいのかというビジネス観点の内容とは別に、その会社を通じてどんなビジョン・価値観を生み出したいのかを考える一つのきっかけをくれるのがこの本ではないでしょうか。
最後にクリフ社のサイトにも記載されているゲーリー氏の言葉をご紹介します。起業に限らず、あえて前例のない困難な旅路にチャレンジする勇気を与えてくれる本の一つという意味でも非常におすすめです。
"The red road is predictable, a known entity, safe, and conservative... The white road is just the opposite. It is the road less traveled. It is an unknown entity, unpredictable, and there may be danger and hardship along the way... But along with this hardship or danger, there is often reward. The reward is a sense of accomplishment—the joy and beauty of the journey along the road less traveled."Gary Erickson
小さな組織を立ち上げてみたいなら:『燃えよ剣(司馬遼太郎著)』
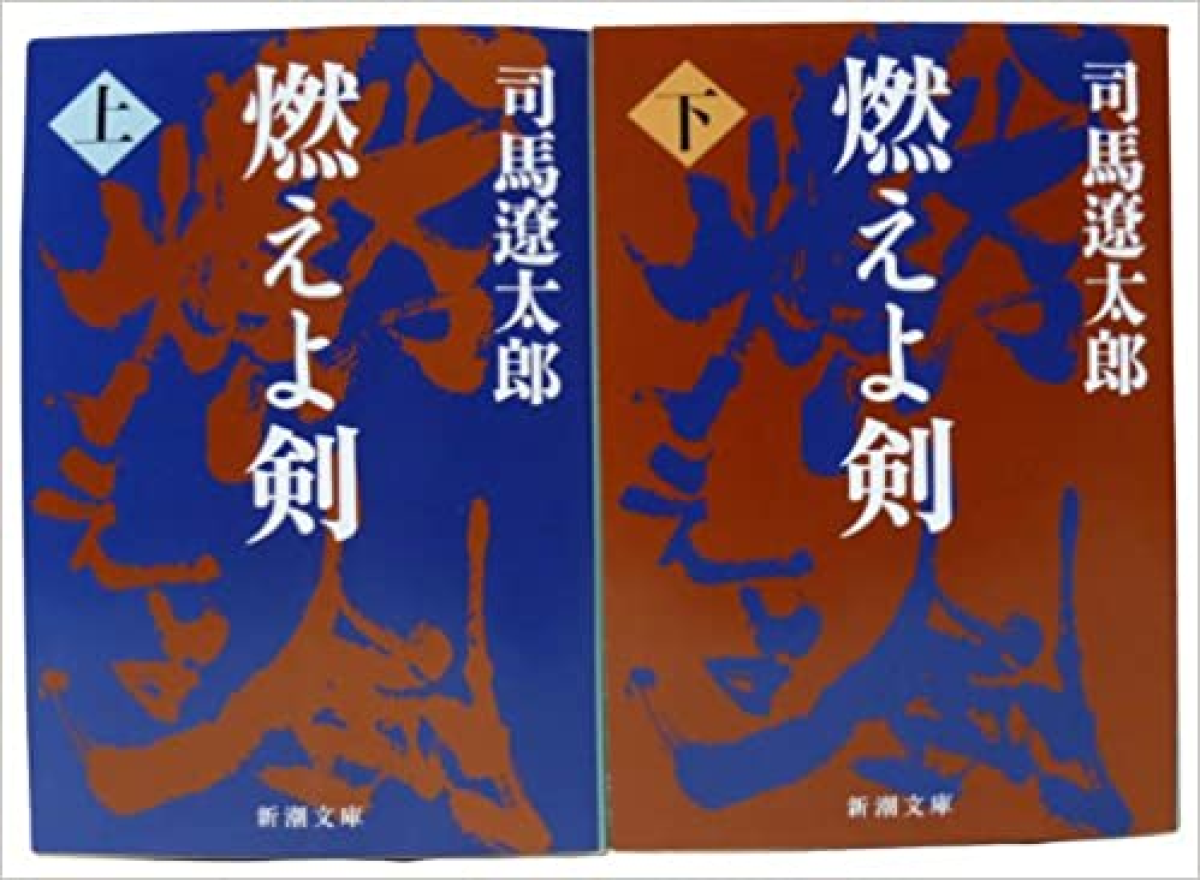
土方歳三と新撰組の歴史を描いた司馬遼太郎の『燃えよ剣』、去年あたり映画でもやっていたので皆さんご存知かもしれません。私は時代小説が小学生くらいから非常に好きなんですが、大人になって改めて読みなおしてもめちゃくちゃ面白いです。
幕末の動乱期に関する歴史エンタメ的な要素も勿論面白いんですが、新撰組という組織をどうやって盛り立てていくのか・リーダーである近藤勇をどう担いでいくかなど、No.2的なポジションである土方なりの組織づくりの観点として読み直してみると色々と学びがあるように思います。
どこまで史実から離れた脚色なのかは勿論わからないのですが、こういう書き方をするとめちゃめちゃスタートアップ感あるように思いませんか?笑
本当の意味で命懸けであるという違いはありますが、典型的な組織の栄枯盛衰が全て詰まっているように思います。
・田舎(多摩)から都会(京都)に意気揚々と出てきて創業
・最初のスポンサー(会津藩)をどうにか見つけてきて投資させる
・創業メンバー(芹沢一派)との政治的対立と排斥(というか暗殺)
・最初の大舞台(池田屋事件)で大きな結果を残し組織拡大。
・組織拡大に伴って規律を大幅強化(というか切腹・粛清の嵐)
・規律強化に伴う組織の変質についていけず初期メンバー離脱(山南敬助切腹)
・大スポンサーから大型資金調達(正式に幕府直下の幕臣として取り立て)
・異なるカルチャーの受け入れに失敗し、社内政治が活発となった結果として組織が瓦解(伊藤甲子太郎入隊〜油小路事件らへん)
・最終的に結果が伴わなくなり、創業者(近藤勇)一人が追い出される
(戊辰戦争〜甲陽鎮撫隊らへん)
・残ったメンバーをNo.2(土方)が取りまとめ、別組織へ転籍しクロージング(五稜郭)
※実はこれらの大イベント、たった6年ちょっとの期間で全て起きたって知ってました?
そういう意味で、成長期にある小さな組織に飛び込んで自分の力で盛り立て大きくしていこうと思う人にはものすごくおすすめの本ではないかと思います。この本を読みながら、組織の急拡大とそれによる弊害、あるいは”組織と政治"の問題が追体験できるように思うからです。
『ネットフリックス 最強の人事戦略』にもありましたが、組織拡大に伴う一つの大きな問題は初期メンバーによる懐古主義とのせめぎ合いに他なりません。試衛館派と呼ばれる昔馴染みの近藤・土方一派だけだった初期フェーズは良かったものが、組織拡大にあわせて土方が取り入れた隊律や指揮権によって組織のあり方は大きく変わっていきます。山南が懐古主義だったかはともかくとして、組織の拡大の中で居場所を失ってしまうことが脱退を決意させた一つのきっかけになってるように思いますし、そういうメンバーが出ても組織のあり方を優先し温情措置を取らなかった土方の冷徹さも目を見張るものがあります(小説の中では元々二人は馬が合わなかったような表現になっていますが)
加えて組織が拡大する中でどうしても権力闘争や社内政治が始まってしまい、それを抑えられなかったトップの末路についても学ぶところがあるように思います。新撰組の創業トップである近藤勇も政治的な活動が多くなってしまい、学のある伊藤甲子太郎を重用し土方を冷遇し始めたことによって組織として分裂(のちに伊藤一派は"油小路事件"で粛清)。政治活動を優先するようになった近藤に人もついていかなくなってしまい、戊辰戦争の途中で旗揚げ組の永倉・原田も離脱。最後は土方とも袂を分かつこととなります。
時代が大きく変質する中でも自分を"バラガキ(=喧嘩屋)"と規定し続けた土方は非常に魅力的なキャラクターとして描かれていますが、一方で周囲の期待に応える政治的なリーダーシップを取ることは最後までありませんでした。環境に流されることなく自分の立ち位置をちゃんと見極めること、あるいは周囲の期待値とのバランスの取り方の難しさが土方の生涯を通じて学べるのではないでしょうか。
今の組織で得たチャンスを生かしたいなら:『影武者徳川家康(隆慶一郎著)』
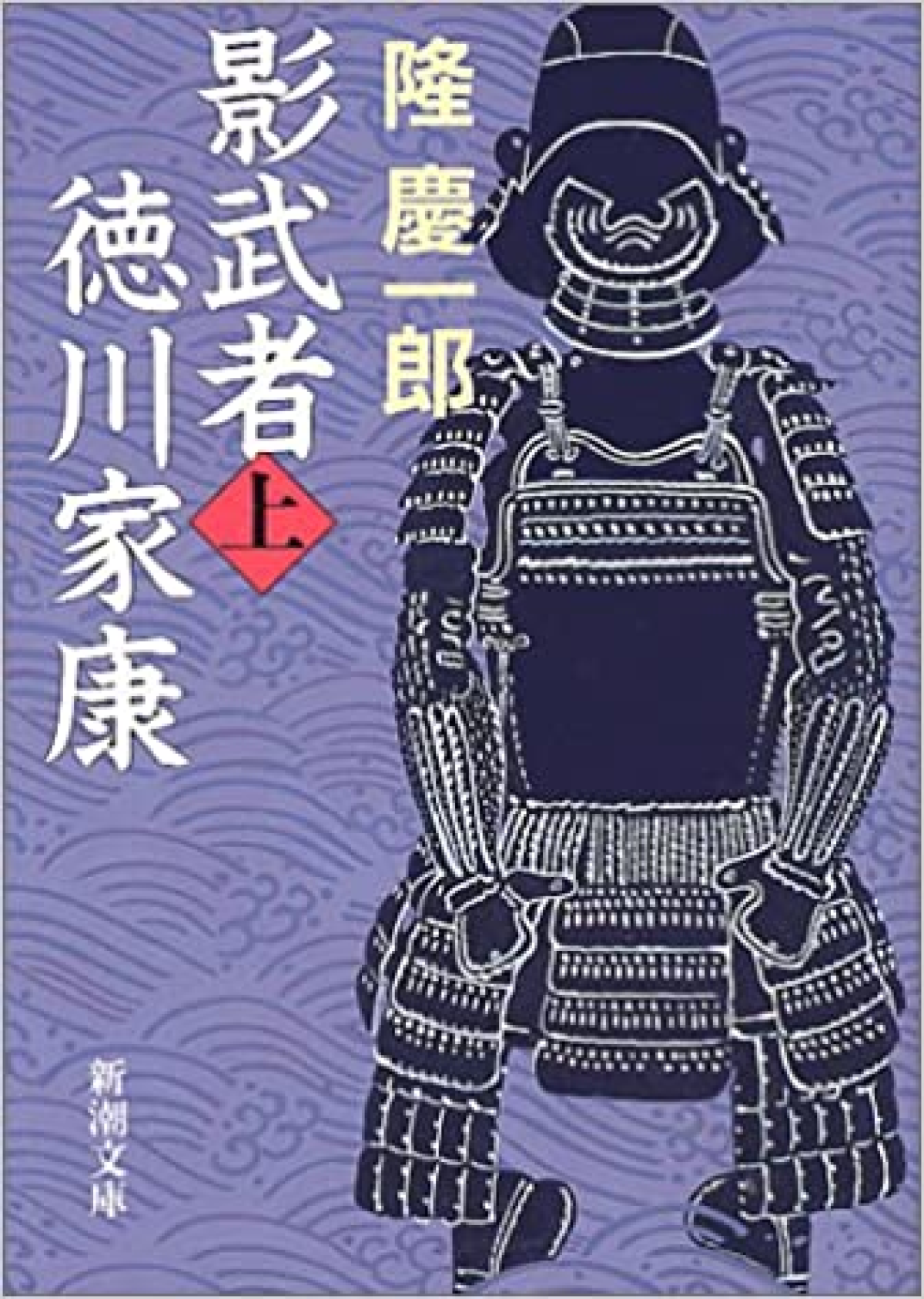
https://www.amazon.co.jp/dp/4101174156/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_DZA2SHNB0BZ4HJFFGZVC
「花の慶次」の原作など、数々の時代小説で有名な隆慶一郎先生の名著。幕末からさらに時代を遡り、舞台は関ヶ原の戦いから始まります。実は関ヶ原の戦いで徳川家康が暗殺されていて、その影武者だった人物(世良田二郎三郎)と入れ替わっていた!という奇想天外なところから始まる歴史IFものの小説です。花の慶次同様、原哲夫氏によって漫画化されているのでそちらでご存じの方もいるかもしれませんね。
お梶の方とのラブロマンスあり、風魔忍者が出てきたりと伝奇小説的な側面があったり、あるいは一向一揆や駿府城築城などなどいろいろな史実と紐づけた歴史エンターテイメントとしても非常に面白いのですが、突如降って沸いた”徳川家康"としての立場を生かして自分なりのビジョンを持って世の中を良くしていこうと奮闘する二郎三郎の生き様には本当に魅せられるものがあります。
当然ですが単なる影武者でしかない二郎三郎には、誰一人として味方はいません(あえて言えば家康の死を知っている本田忠勝ただ一人)。滞りなく関ヶ原を乗り越えたあと、可能な限り早く徳川秀忠に家督を譲ることのみを求められます。自分が影武者に過ぎないことも不用意に明かせないなか、自分の才覚のみで少しずつ味方になる陣営を増やしつつ(なんと家康暗殺をした忍者を説得して腹心に!)自分が生き残るメリットをアピールするなかで、もともとの思想であった「自由な世の中の実現」というミッションに目覚め、自分中心の強権政治に突き進もうとする秀忠陣営と暗闘を繰り広げていく・・・というのが作品の大まかなプロットです。
これも『燃えよ剣』と同様、単なるエンタメではなく組織運営的な考え方で読んでみると色々な気づきが得られる作品だと思います。大きな違いは、新撰組における土方は創成期から自分で組織を立ち上げていったのに対して、二郎三郎は完全に出来上がった組織(徳川家)を急遽アクシデント的に引き継ぐ形になったという点。
気のおける部下も誰一人としていない中で少しずつビジョンを共有できるメンバーを集めながら、反体制側だった自分だからこそできる世の中の実現をトップとして目指していくというサクセスストーリーは、現代の企業組織に置き換えてみると大企業の中にいるからこそ得られたチャンスを最大限生かしていくという読み方ができるのではないでしょうか。
スタートアップにいる自分がいうのもあれですが、小さな組織を自分で育てる楽しさはもちろんありつつも豊富なリソースと組織力を活用できるなら、それに勝るものはありません。大企業にいると気づかないかもしれませんが、外に出てみるとそれを得ることがどれだけ難しいかが身にしみてわかることです。
もちろん目の前で上司が暗殺されるようなケースはほとんどないでしょうが笑、組織に所属しているからこそ急遽ポストが巡ってくるなどの新しいチャンスはあるはずです。組織に不満を持って外に飛び出るだけがキャリアではないですし、そういったチャンスを見逃さずしっかりと組織の中で仲間づくりをすることで実現に導く、そういったキャリア志向も一つの考え方として尊重されるべきなのではないかと思い、今回選んでみました。
みなさんの推しも教えてください!
というわけで、3つ選んでるうちにやたらと時代小説に寄ってしまったので、超個人的三選と銘打って書いてみました。完全に個人的な趣味に走り恥ずかしい限りですが、冗談抜きで多分10回ずつくらい読んでる本なのでぜひ何かの機会に読んでみていただければと思います。普通にエンターテイメントとしても秀逸なものばかりなので。
私個人はいわゆるビジネス書を読むことは実はあまりなく(スキルを手っ取り早く吸収したい時が中心です)どちらかというと歴史物などを読む中で自分なりに考えて示唆を得たいタイプなのですが、みなさんは自分のキャリアの節目になった本はありませんか?
もしあればぜひコメント欄でご紹介ください!ビジネス本でも小説でも、とにかく活字好きなので私もぜひみなさんの"推し"から視座をひろげたいと思います。
更新の通知を受け取りましょう
























投稿したコメント