"これでいい"がこれがいいになる、満ち足りた今に必要な「引き算のデザイン」
使わない機能がたくさんあるスマホを利用している。読まない情報が商品にたくさん表示されている。作り手も使い手もそういうものとしてその状況を無意識に受け容れているが、そろそろ引き算の思考に頭を切り替えても良いのではないか。
引き算と言っても、無駄を極力省く禁欲的なものではない。ましてやミニマリズムやわびさびのわびのような不足の美学でもない。「それで十分」の十分な状態にすることである。最近は、環境意識の高まりも味方に付け、むしろ「これがいい」と思える「これでいい」表現が、現れてきている。
様々な可能性を秘めた、これでいいの「で」のデザイン
フランスの高級ファッションブランド「メゾン・マルジェラ」が、だまし絵デザインのトートバッグを発売した。同ブランドのアイコンバッグ”5AC”をリネン製の本体に印刷し、取っ手のみ本物と同じ革製にして、写真とつながっているように見せた遊び心のあるデザインのバッグである。

左のだまし絵バッグは218,900円、モチーフになっている右の5ACバッグは488,400円なので、価格は半分以下だ。それでも泣く子も黙るプライスだが、それはさておき商品として見て「これでいい!」と思ってしまった。
エルメスのようなオーセンティックなブランドではそういうわけには行かないだろう。だが、マルジェラのようなアバンギャルドなブランドのバッグなら、品質だけではなく「独創性」が大きな価値となるので全く問題なさそうだ。革製の本物を買えないからではなく、自分の意思でこれを選んでいるという説得力もあるので、これでよいのではないかと思った。
良品計画は、2002年に公表したブランドのヴィジョン「無印良品の未来」で、「これがいい」ではなく「これでいい」というメッセージを発信している。

無印良品はブランドではありません。無印良品は個性や流行を商品にはせず、商標の人気を価格に反映させません。無印良品は地球規模の消費の未来を見とおす視点から商品を生み出してきました。それは「これがいい」「これでなくてはいけない」というような強い嗜好性を誘う商品づくりではありません。無印良品が目指しているのは「これがいい」ではなく「これでいい」という理性的な満足感をお客さまに持っていただくこと。つまり「が」ではなく「で」なのです。
しかしながら「で」にもレベルがあります。無印良品はこの「で」のレベルをできるだけ高い水準に掲げることを目指します。「が」には微かなエゴイズムや不協和が含まれますが「で」には抑制や譲歩を含んだ理性が働いています。一方で「で」の中には、あきらめや小さな不満足が含まれるかもしれません。従って「で」のレベルを上げるということは、このあきらめや小さな不満足を払拭していくことなのです。そういう「で」の次元を創造し、明晰で自信に満ちた「これでいい」を実現すること。それが無印良品のヴィジョンです。
勝手な解釈だが、「良い意味での中庸」の追求でないかと感じた。
「理性的な満足感」というのも重要なポイントだ。無印良品はそれを指針とすることで、多様なライフスタイルに寄り添える「普遍性」を手に入れたと考える。
冒頭で触れたマルジェラのだまし絵バッグも抑制や譲歩を手法としている点で、無印良品と同じだが、そのある種の諦めをジョークとして見せ「感性的な満足感」につなげているところが異なる。いや、無印良品にしても敢えて「無印」にする点が既にアーティスティックだし、細部にまで気を配ったデザインの美しさも購入動機になっていることから、ユーザーの満足感が100%理性的というわけではないだろう。
見出しに書いた「で」のデザインは、無印良品の言葉の引用だが、この「で」というのは意外と奥深い。それに着目した同ブランドの視点も鋭いなと感心する。

筆者が「これがいい!」と思う無印良品の「これでいい」の商品(シリコーンキッチンツール)。最近は、料理番組でも使われている。
近年の「これでいいデザイン」をこれがいいと思える要因には、環境意識によってものの見え方が変わったこともある。最近では、高級ブランドもショッピングバッグの素材を再生紙に切り替えたりしていることもあり、かつて見劣りしていたものもお洒落に映るようになった。

2019年に日本国内の美容院で初めてBIO HOTEL JAPAN認証を取得した千葉県柏市のヘアサロン「THE ORIENTAL JOURNEY」では、古い新聞紙を使った手作りのショッピングバッグで商品を提供している。
今回は、その「これでいい」の「で」が、どのように説得力のある魅力的なものになっているかに着目する。デザインの創造力で、それがどのように表現されているのかを、以下の視点で考察する。
①【空間】
期間限定という制約下、これでいいを美しく表現した「仮設のデザイン」
②【パッケージ】
「情報過多、過剰包装へのアンチテーゼ」としてのこれでいい商品パッケージのデザイン
③【プロダクト】
「要らない機能やスペース」を省き、これでいいをポジティブな選択肢にした工業製品
①【空間】期間限定という制約下、これでいいを美しく表現した「仮設のデザイン」

東急文化村の複合施設Bunkamuraの再開発完了時までの5年間限定で開設した映画館「ル・シネマBunkamura渋谷宮下」の内装デザインが良いと思った。取り壊しを前提とした「仮設」のため、施工費を抑える、解体時の廃棄物を少なくする、原状復帰を容易にすることを念頭に置いたデザインで、それらの厳しい条件が設計者の感性によって見事にクリアされている。制約をバネに生み出されたデザインと言った方が良いのかもしれない。
映画=光の芸術を際立たせる「影」をテーマに、廉価素材と簡素な造りで雰囲気が出るよう様々な工夫がされている。什器には、舞台装置に使われる産廃リユース材が使われているそう*¹。光を吸収する質感のカーペットも廉価品で、コーン型のランプシェードもこれで作られている。
「これでいい!」と思った。と同時に「これはいい!」とも思った。

設計は、中山英之建築設計事務所。

2016年のグッドデザイン賞の展示会場の什器も「これはいい!」と、わたしが思わず感心した”これでいい”デザインである。無塗装のベニア合板にスリットで十字に組む相欠きで接合し、事務用のクリップで固定したディスプレイ棚など、簡素さに意思が感じられて魅力的だ。使用後にまた元の状態に戻すことができるのも良い。こういうのは簡単そうに見えるが、そう簡単に思い付くものでもない。これでいいの「で」のデザインには、センスも必要だ。

設計は、スキーマ建築計画。
ナショナル・ジオグラフィックの2017年の調査によると、世界の30%の温室効果ガス排出は、都市での建設から発生しているそうだ*²。
筆者が昔、百貨店の中のブティックの内装設計の仕事をしていた頃、解体工事の現場を見ると心が傷んだ。その当時はまだ、今のように環境意識が高い世の中ではなかったが、それでも罪悪感を感じた。今よりも店舗の配置換えの頻度が高く、素材も重厚感のあるものが使われていたため、廃棄物の量や環境へのインパクトは相当だったと思う。
ここに挙げた事例は、仮設風ではなく本当に期間限定の仮設なので、耐久性や安全性を考えると全てがこれでいい訳ではない。だが、売上に応じて入れ替わりの激しい店舗などは特に、このように「簡素さ」を魅力に置き換える設計を心掛けても良いのかもしれない。幸いなことに近年は、工夫された簡潔さが好まれる傾向にあるので、空間の見栄えの点でも歓迎されるのではないだろうか。
②【パッケージ】「情報過多、過剰包装へのアンチテーゼ」としてのこれでいい商品パッケージのデザイン

現在、開催中のUEFAチャンピオンズリーグのサッカーの試合中継を観ていて、CMで流れるオフィシャルスポンサーのLay's(ペプシコ)のポテトチップスのパッケージデザインが目に止まった。CMの中で、ソファで観戦しながらメッシが食べているあのLay'sの袋だ。文字情報はほぼロゴのみで、色数やグラフィックの要素も少なく、物足りなくもある。だが、普段から文字量の多いパッケージを見慣れている筆者の目にはそれが良い意味で新鮮に映った。これでいい!と思った。

2007年までのデザイン(右)と、それまでのデザイン(左)。見出し下の画像にあるのが、2019年に刷新された最新のパッケージ。一貫して余分な情報のないシンプルなデザインである。
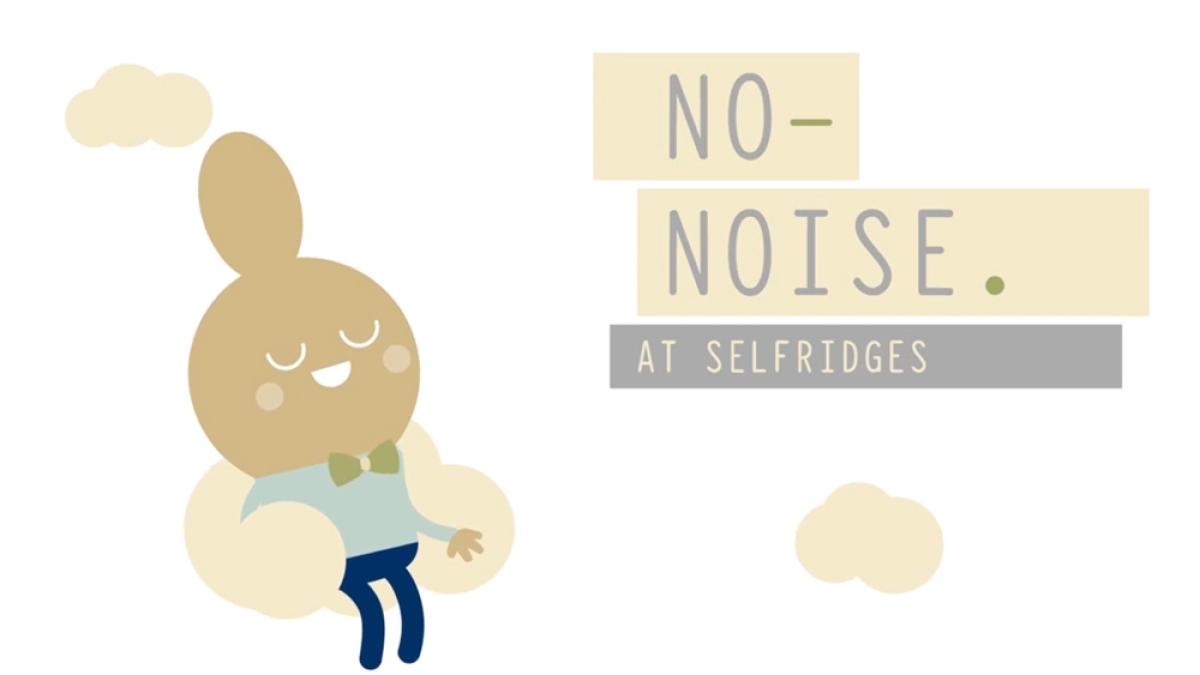
英国の高級百貨店セルフリッジズは、今から10年前の2013年に「No Noise」と称したキャンペーンを行った。情報デトックスを呼び掛ける企画で、瞑想ルームの設置の他に、見慣れた商品のラベルからブランドロゴと商品名を排除するという実験的な試みも行っていた。

この「のっぺらぼうラベル」の商品は、実際に販売され、当時、筆者がオンラインショップを見た時には既に売り切れていた。セルフリッジズは時々、こうした問いを投げ掛ける企画を展開する。この大胆な試みも面白いと思った。Lay’sのシンプルなパッケージを見て、ふとこの企画のことを思い出した。サントリー伊右衛門が、2020年の角型容器へのリニューアル時にラベル付きとラベルレスを並行販売する施策を採ったが、あれも近いものがある。日本では、定番商品であってもパッケージデザインの変更を頻繁に行うので難しいのかもしれないが、これを参考に簡素化を図っても良い商品はありそうだ。
ギフト用の「過剰包装」も見直されつつある。2020年に誕生した資生堂の化粧品ブランド「BAUM」では、ギフトラッピングを排除し、リボン掛けのみで対応している。

外箱が美しくデザインされているので、これでいい。
③【プロダクト】「要らない機能やスペース」を省き、これでいいをポジティブな選択肢にした工業製品
プロダクト、とりわけスマホやカメラなどの精密機器は、機能や性能を向上させて新規性を打ち出すのが常態化しているが、既にオーバースペックになっている印象がある。その進化に完全について行けるユーザーも恐らく一握りだろう。
自動車もそうだ。自動車の場合は、多機能だけではなく、空間を持て余すケースもあるだろう。空気を運んでいると揶揄されるようにオーバーサイズ気味の状況もある。小型車がファーストカー的な位置づけにされているため、それで間に合う人も敬遠してしまうのだろう。

イタリアの自動車メーカーFIATが今年発表した”超小型”電気自動車「トポリーノ」は、航続距離75kmのシティコミューターだ。2人乗りで全長わずか2.53m。内装も簡潔で、ステアリング周りもすっきりしていて清々しい。普段遣いの車なら、これでいいと思った。

特別仕様のDolce Vitaモデルの方は、昇降部にドアがなく太い綱を張っただけだ。これは駐車時の日除けなのか、ダッシュボードに置かれたストライプのシェードのようなものも素敵にデザインされている。FIAT 500のデザインを踏襲したエクステリア同様に、インテリアもクラシックモダンで統一されているところもデザインの質を高めている。

FIAT 500の "Topolino"(イタリア語でちっちゃなネズミ)の相性の由来である、「500 Topolino」の内装。最新EVは、これをアップデートしたような印象。

小さくで簡素でも、今どき必要な「スマホホルダー」はちゃんと装備されている。

世界中の幅広い世代の人たちが、スマホを使いこなすようになる中、NOKIAは新しいフィーチャーフォンを発売している。30万画素のカメラというのは今さら感があるが、デザインが良いので気になった。また個人的な話で恐縮だが、うちの母用にこれが欲しいと思った。現在、折りたたみ式の簡単ケータイを充てがっているが、放置されている。UIが複雑で、使い方がわからないからだ。バータイプの簡単ケータイは、子機の要領で扱えるので家電(いえでん)代わりに使っていた。
今、日本で販売されている折りたたみ式の簡単ケータイは、わたしでも操作に手間取る。「本当に簡単な」ケータイであって欲しいというのもあるが、スマホが使えない高齢者向けのステレオタイプなデザインにしていることも不思議に思う。例えば、電話番号を使い分けるためにスマホを2台持ちしている人など、「これでいい」と思う人はいるのではないか。このNOKIAの携帯電話や、スイス発のPunkt.のMP02のような普遍的なデザインにした方が、市場性の面でも良いと感じる。
前向きな引き算のデザインが、ものづくりの新たな指標に
最後は愚痴のようになってしまったが、こうして見ると、最近の「これでいいデザイン」は、なかなか乙である。ないものはないほどに物が溢れ、技術が向上しできることが増えたことで、機能過多、情報過多に陥る中、このように「前向きな引き算のデザイン」が、ものづくりの新たな指標の一つになるのではないか。
筆者は、炊飯器を買い替えてからご飯が美味しく炊けるようになり、それ以来、おにぎりは塩を付けずに握っている。「これでいい」が「これがいい」になっているからだ。
無印良品が提唱した「で」のデザイン。この「で」は、無限の可能性を秘めていそうだ。ものづくりに携わっている人たちは一度、機能を盛る手を休め、「で」のあり方について考えてみてはどうか。今までにはないユーザー価値が導き出せるかもしれない。
************************************
最後までお読みいただき、ありがとうございました。(o^∇^)ノ
(トップ画像は、「てがきですのβ」のイラストに筆者が描いたギフトとバカボンのパパの絵を組み合わせて作成いたしました)
《脚注》
*¹ 出典:CINRA「『Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下』が6月16日にオープン。『影』がコンセプトの内部をレポート」2023.6.15
*² 出典:IDEAS FOR GOOD 「サーキュラー建築で廃棄物を最小限に。デンマークの『分解可能な』複合施設」2021.3.3
トリニティ株式会社は今年、25周年を迎えました!(^ω^)☆
更新の通知を受け取りましょう






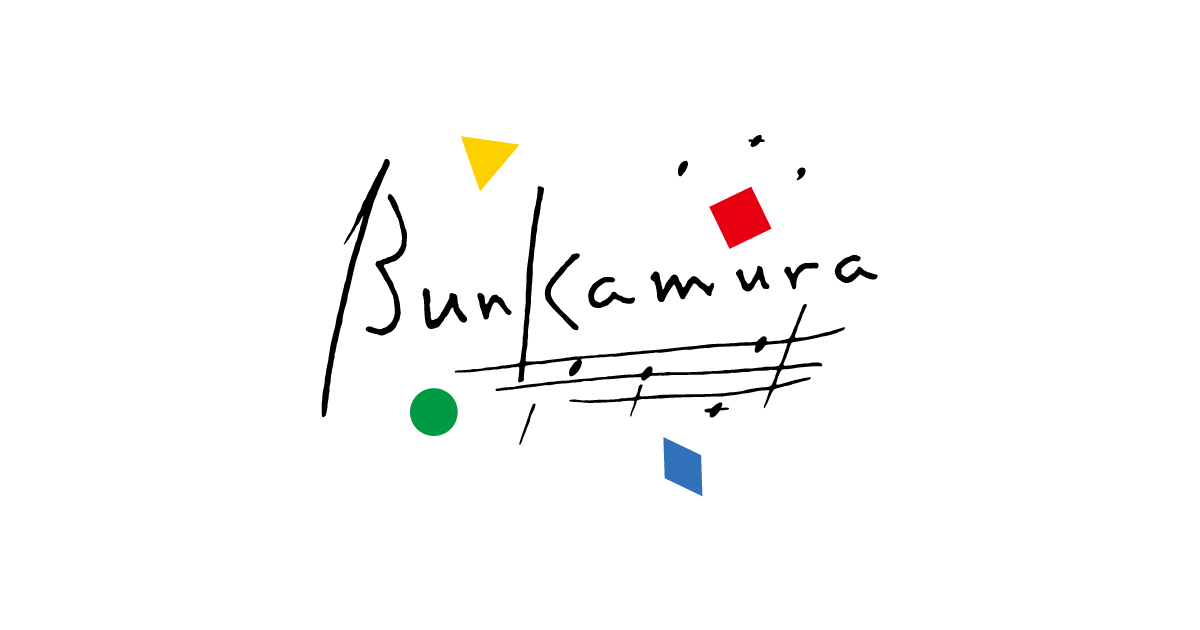





















投稿したコメント