英議会報告書が問いかける「目先の利益に目を奪われるな」
「何年も前から中国の脅威について指摘されていたにもかかわらず、英国政府の動きがあまりに遅いことに驚きをおぼえる」。
「米国政府は保護すべき先端技術20分野を指定して、中国に対して先端技術で優位性を保つことを国家安全保障に位置付けているが、英国政府にはそのような動きは見られない。深刻な失態だと言わざるを得ない」
これは英国議会のインテリジェンス・安全保障委員会が7月13日に公表した中国の脅威に関する報告書(The Rt Hon. Sir Julian Lewis MP, Intelligence and Security Committee of Parliament, Presented to Parliament pursuant to sections 2 and 3 of the Justice and Security Act 2013 Ordered by the House of Commons to be printed on 13 July 2023)にある一文だ。
舌鋒鋭く政府を非難する率直かつ直截な表現は政府を追及するマスコミの論調のようだが、れっきとした英国議会が出した公的文書だから驚かされる。
この報告書の趣旨は、中国がその経済力や企業買収、学会や産業セクターとの交流を通じて英国に影響を及ぼしており、それに対抗する政府の取り組みは不十分だと批判している点にある。
経済安保の本質をえぐる英議会報告書
この報告書は経済安全保障が持つ本質的な課題を浮き彫りにしている点で格好の題材だ。
シンプルに言ってしまえば、経済安全保障とは経済合理性と安全保障を両立させることだ。企業やビジネスパーソンは、いち企業だけの経済合理性(利益の最大化)だけでなく、国や国際関係の視点や安全保障というレンズも使って経営判断をすることを求められている。
もちろん言うは易し、行なうは・・だ。
そもそも経済安全保障は、軍事でもビジネスでも優位をもたらす先端技術をめぐる米中の競争と対立から生まれている。米国も中国も将来の覇権を左右する先端技術の開発や獲得にしのぎを削る一方、制裁や輸出規制を使って相手陣営に重要技術がいかないようにしている。
その競争においては企業合併、直接投資、合弁事業といった合法的手段から、サイバー攻撃による技術情報の窃取、スパイなどの諜報活動などの非合法、不法的手段まで駆使されている。
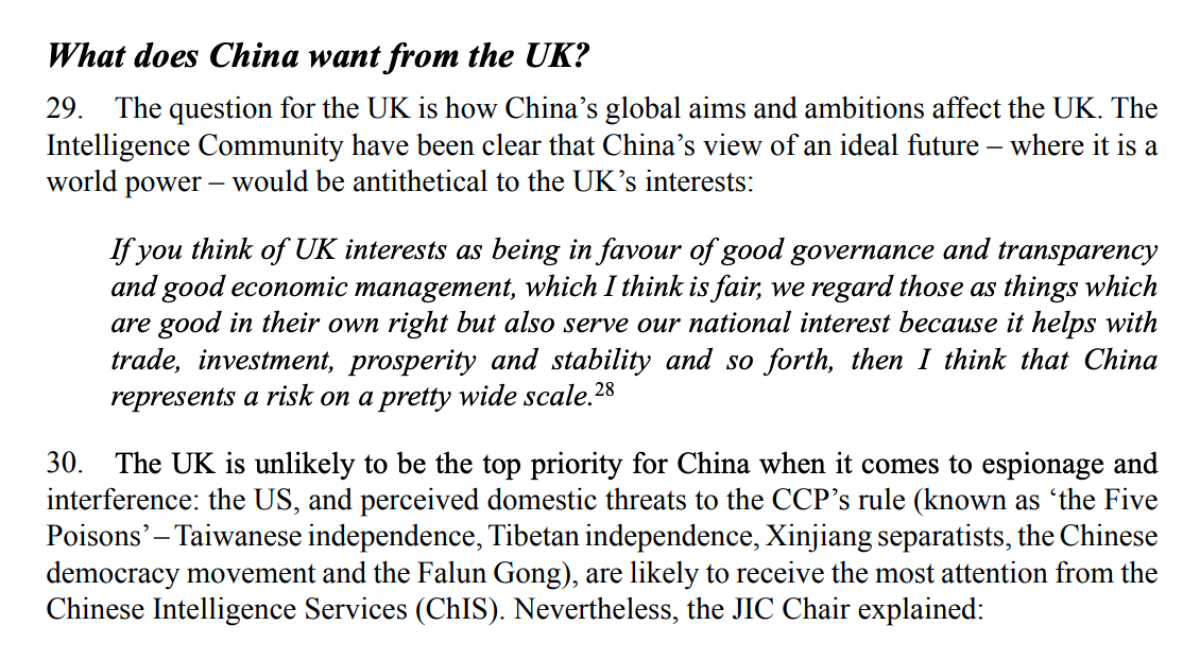
企業に経済安保センスが求められている理由
こうした合法、非合法の手段を織り交ぜた、先端技術の獲得の動きは、中国政府や情報機関だけによるものではなく、あらゆる中国企業、大学、研究機関、文化交流機関、そして一般の国民個人までもが参画する「国全体を挙げたアプローチWhole-of-State Approach」によるものだと、議会報告書は指摘する(この点は米国政府の見解とも一致している)。
相手が企業や大学、国民までも動員して技術を取りに来ているからこそ、安全保障の世界とは無縁だった企業にも安全保障上の影響を理解しながらビジネスをおこなってほしいー。これが経済安保が急浮上してきた理由だ。
ここで問題なのは先端技術、つまりAI、半導体、クリーンエネルギー、バイオテクノロジー、量子技術、ナノテクノロジー、通信機器、原子力技術などを保有しているのは企業であり、政府ではない点だ。
その企業は経済合理性に従って、売上を拡大しようとする。高い値段で買ってくれる買い手や、共同開発をしたい、投資をしたい、投資を受け入れたいと思う魅力的な相手とビジネスをする。
そんな企業にとって中国市場の潜在的な成長力やマーケット規模、購買力は非常に魅力的だ。経済合理性でいえば、ここを攻めない理由はない。安全保障上の配慮から事業機会を見逃す、諦める、ということは容易なことではないし、安保か経済かのオールオアナッシングにならないようにするには、知恵と決意(見切り)を要する。
こうした事情は報告書を出した英国議会の委員会も理解している。
「安全保障と経済的繁栄のバランスには器用さが必要となるし、どちらかを優先すれば、他方が犠牲になるトレードオフが発生する難しさもある」と、経済安保が持つ難しさを率直に認める。
そのうえで「この点は英国政府が中国戦略を立案する際に、配慮すべき重要要素だ」として
安全保障の論理だけを振りかざすのではなく、経済上の利益とバランスをとることを求めている。
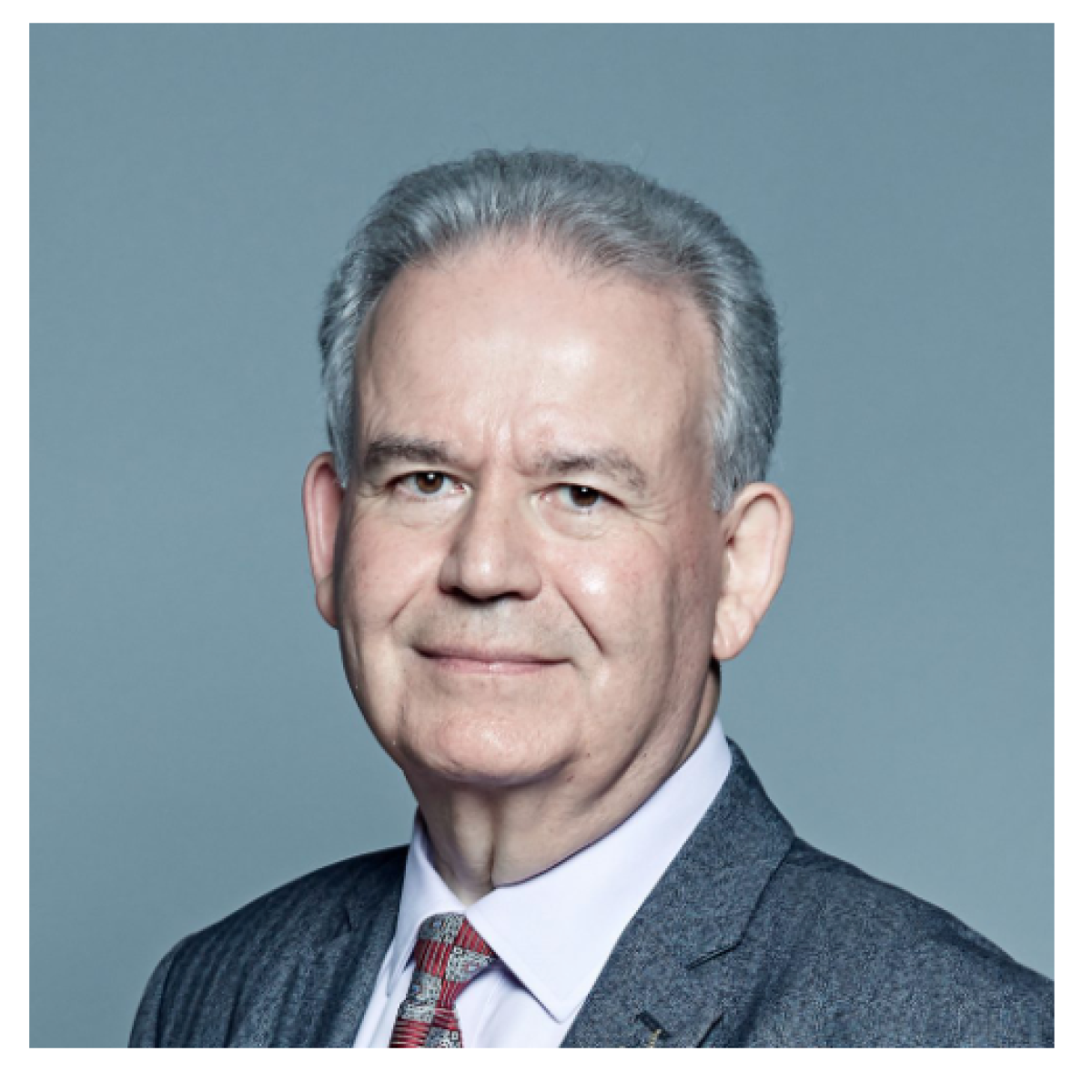
KPIを抱えるビジネスパーソンたちをどう説得するか
企業の現場にいる者として気になるのは、こうした経済安保の本質を日々の業務でどう具現化させるか、だ。
中国製の製品やサービスを調達するほうが欧米製よりも3割、へたをしたら4割安い。将来の市潜在的成長率を考えれば中国市場で合弁事業を立ち上げて進出したい。
そんな中、4半期毎に達成すべきKPIを背負っている現場のビジネスパーソンたちに、安全保障の観点から「もしかしたら起きるかもしれない。でも起きるかどうかはわからない」安全保障上のリスクを優先して、計画の見直しあるいは撤回を場合によっては求めることになるのが経済安保の現実だ。率直に言って、これを事業会社で実行するには、空気を読まない、相当な胆力と鈍感力が必要となるだろう。
安全保障にも配慮しながら経済合理性も企業として追求しなければならない。その一致点、均衡点はどこにあって、どういう基準で見出すべきなのか。
残念ながら、報告書は考え方の大枠を示すだけで、この問いへの答えとなる具体例や基準には触れていない。英国自身もまた確たる答えを持ち合わせず、安全保障とビジネスの均衡点を見出そうと悩んでいるのかもしれない。
その一方でこの報告書の末尾には、ビジネスパーソンがこの課題に取り組む際に参考になる視点になることが書かれている。
目先のメリットに目を奪われるな
「中国は長期的視点に立って動いている。中国の脅威が明らかになった今でさえも英国政府は目の前の脅威や短期的視点にばかり目が向いている。中国の野望に対抗し、英国の将来の安全保障のためには、より長期的な視点を取り入れなければならない」。
目の前の短期的な利益に目を奪われていると、長期的に、より大きな損失を被ることもあることに気がつくべきー。
目先、コストの安さに目を奪われて飛びつくと、データを取られたり技術が漏洩したりして、長期的には痛い目に遭うことになるぞ。多少コストが高くても安全や信頼のあるプロダクトを使う発想に切り替えなさい。
筆者はこう読み取ったが、読者の皆さんはどうだろうか。
経済安保を考える重要な基準とは安全保障か、ビジネスか、だけではなく、短期的視点か、長期的視点か、ということでもあるのかもしれない。
更新の通知を受け取りましょう
























投稿したコメント