「褒め」の悪徳:赤ちゃんをディスる文化に学ぶ
親のいる前で、公然と赤ちゃんをディスる〔=否定する、侮辱する〕…これは私たちの社会ではかなりヤバいことですよね。
「かわいい!」「癒される!」「元気そう!」
たとえ全くかわいいと思えなくとも(そんな人はいないはず、ですって?その発想は「呪い」です!)、赤ちゃんを褒めることは、私たちが共有する一つのコード=倫理規範となっています。
新入社員をどう褒めるか、ということがよく話題になっています。「褒め」について検索してみると、「新入社員 褒め方」に加え、「上司 褒め方」「女性部下 褒め言葉」なども候補で出てきます。みなさん「褒め」に相当苦労されているようです。

みなさんは人前で褒められたいですか?今回は、誰しもが求めがちな「褒め」が、一体何をもたらすものとみなされてきたのかについて考えたいと思います。
赤ちゃんはディスらなければならない?
わたしが調査をしているアフリカ・南スーダンのヌエル社会では、赤ちゃんを公然とディスることが一種のモラル、「お約束」になっています。誤解のないように言っておきますが、これは彼らが虐待気質だとか、悪習蛮習を持っているとか、そういう話では全くありません。むしろ逆です。
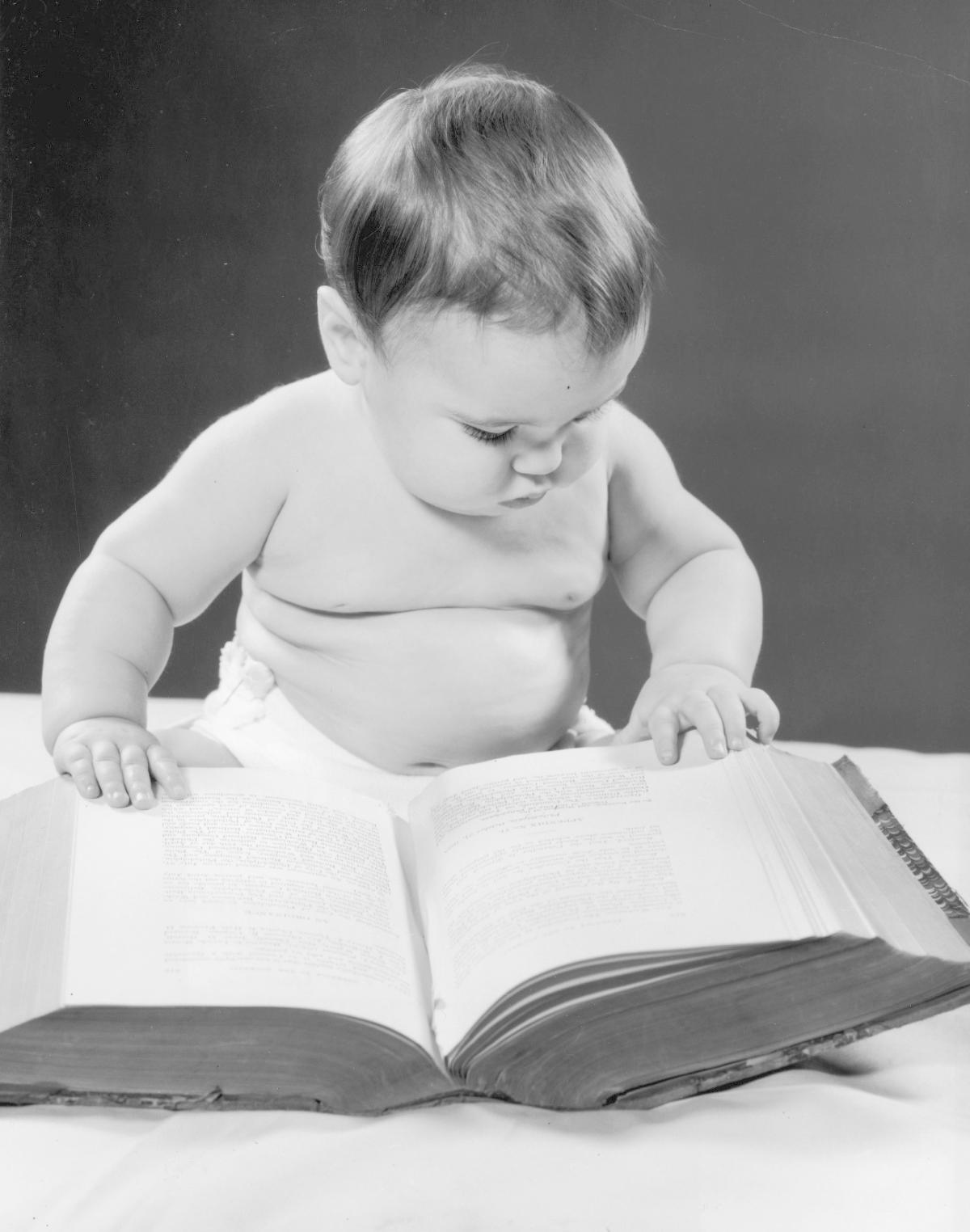
赤ちゃんはディスらなければならない。これははっきりとヌエルの民族誌(*1)にも記述されています。この記述をすっかり忘れていたわたしは、つい日本のコードに沿って、赤ちゃんに「かわいい!」的な褒めをやらかしてしまいました。当然、「こんなモノに対して何でそんなことを言うんだ!」と怒られました。「こんなモノ」って…。わたしは何と言ったらよかったのでしょうか?
「このわるいやつが!」「わいせつなサルめ!」
・・・これが礼儀正しい赤ちゃんとの接し方です。初対面の赤ちゃんにこんなことを言うのは、なかなかハードルが高いですよね。赤ちゃんの親族、なかでも女性たちによるディスりは激しく、時として卑猥な言葉すら投げつけたりします。
「褒め」が危険な理由
では、どうして赤ちゃんを褒めてはいけないのでしょうか?
人間が「良い」と考えている事柄や、弱い存在には、「悪いもの」(=ひとまず悪霊とします)が寄ってくると考えられています。特にアフリカのような地域では、赤ちゃんはちょっとしたことで死にやすい、きわめて脆弱な存在です。だから周りの人間は、「これはそんなに良くないものですよ!」というアピールをして、必死に悪霊の気をそらし、ターゲットから外そうとするのです。

赤ちゃんを悪霊的なものから守るための文化実践は世界中にあります。赤ちゃんにあえて悪い・汚い名前を付ける慣習はいろんな地域にあります。アフリカだと:
何人も子供が早死にした後で生まれた子に、生死をつかさどる精霊へのメッセージとして、わざと卑しめる名前(〈奴隷〉〈明日死ぬだろう〉〈墓〉)をつけることもよく行われる。『アフリカを知る事典』 より(*2)
悪魔に扮する男が赤ちゃんをジャンプするスペインの「エル・コラチョ」や、泣き声で邪気を払ったり個人や地域の健康と安寧を祈ったりする日本の「泣き相撲」も有名ですね。何も知らない人たちがこれを見た場合、ただの虐待と思うかもしれません。“ディス(にみえるもの)=愛情”という、ややこしい関係がこの背景にありそうです。では、“ディス”の反対の「褒め」はいったい何をもたらすのでしょうか?

「褒め」は悪霊を呼ぶ失礼な作法
そもそもヌエル社会では一般に、人のことを褒めるのは良くないことというよりも、無作法を超えた大変失礼な行為です。牛の頭数を褒める、子どもの数を褒める、十分な食事をとったことを褒める・・・これらはいずれも、悪霊を呼び寄せかねない、不吉な予言、つまり呪いと考えられます。
・「君は太っているね」(補足:ヌエル社会では「太っている」は褒め言葉)と言われた人が、病気になった・痩せた・牛を褒められたら牛が乳を出さなくなった
『ヌアー族の宗教』より(*3)
このように、褒められたことによって悪いことが生じたという例は枚挙にいとまがありません。
世界の呪いの多くが、幸運な人に対する嫉妬や羨望の感情から来ています。ゆえに、呪いがさかんな社会では、嫉妬されないように、人は自分が幸運であることを隠したり、ごまかしたりするのは当たり前のふるまいです。

これって、じつは私たちも「謙虚」や「謙遜」という名の下でやっていることですよね。「私はそんなに幸せじゃないですよ」アピールは、悪霊はびこる世界におけるリスクヘッジのために重要です。私たちは悪霊を、超自然的な存在、くだらない迷信として笑って切り捨てることはできません。というのも、悪霊を呼び寄せるのは、これまた姿かたちを持たない、人間の悪意、あるいは悪意になる一歩手前の嫉妬や羨望の感情だからです。私たちがキラキラしたSNS報告を目の当たりにしてモヤモヤする、そのモヤモヤそれ自体が“悪霊”であるともいえます。それによって、実際に炎上したり人生が狂ったりする人たちもいるわけですから。
幸福になると不安になる?
前記事で「幸せ」について書きましたが、ヌエルの人たちは、人の噂になるほどの幸運に恵まれると、ひどく不安になると言います。どこから“悪霊”が飛んでくるかわからないからですね。

最近の大学生は、人前で褒められることが大変苦手だという指摘があります。わたしの周りの学生は「褒めが足りない」などと苦情を言ってきたりするので(!)、必ずしもみんながみんなそうではないはずですが、一部の人には共感を得られる現象のようにも思います。
これについては色々な説明が出てくると思います。和を重んずる日本だから、謙遜の文化があるから、SNSの炎上文化の中に育っているから、などなど。今ある自分の人物評価の変化や、「できるやつ」になってしまって人間関係が変わってしまうことを恐れるという指摘もあります(*4)。
が、いずれの場合にしても、私たちが人前での過剰な「褒め」を警戒するのは、自分という存在と社会とのバランスを乱す“悪霊”を恐れているからではないでしょうか?

褒められたいけど褒められたくない
さて、それでもみなさんは褒められたいですか?
褒められたい、という感情は多くの人に共有されているかと思います。が、どうも人前で褒めすぎると「あまり褒めないでください!」となるようです。「褒められたいけど褒められたくない」のは、最近の若者の特徴でも、日本人独自の性格でもなく、多くの人類の傾向としてもあるようです。なんと面倒くさい動物!
しかし私たちはただの駄々っ子ではありません。「褒め」は身の危険、さまざまな“悪霊”とセットになっているので、それを回避しようとするのは理にかなっているようでもあります。
・・・逆に、誰かに“悪霊”を呼び寄せたいときには、人前で「褒め殺し」をすればよいのかも。あなたは「褒め」から身を守れますか?どうか、お気をつけて!
トピ画:Getty Images
(*1) 民族誌(エスノグラフィーともいう)は、フィールドワークの成果をまとめた著作のこと。ヌエルについてはエヴァンズ=プリチャード著『ヌアー(ヌエル)族』『ヌアー族の親族と結婚』『ヌアー族の宗教』が有名。
(*2) 川田順造(2010)「命名」、小田英郎・川田順造・伊谷純一郎・田中二郎・米山俊直(監修)『新版 アフリカを知る事典』 平凡社、p.373。
(*3) エヴァンズ=プリチャード、E.E.(1982)『ヌアー族の宗教』向井元子訳、岩波書店、pp.23-24。
(*4) 金間大介(2022)『先生、どうか皆の前でほめないで下さい―いい子症候群の若者たち』東洋経済新報社。
更新の通知を受け取りましょう
























投稿したコメント