【対談】詩の読み方、書き方、作り方(前編)
更新に間があいてしまいましたが、前回のつづきです。
松下育男さんと2023年4月15日に池袋コミュニティ・カレッジで対談した内容を掲載します。松下さんとは継続的に対話を続けてきましたが、文字にするのは、今回が初めてです。何回かに分けて掲載します。7月20日からは、隣町珈琲で連続講座・松下育男「現代詩の入り口」もスタートします。お楽しみに。
https://peatix.com/event/4011300?lang=ja
***
藤井 今日は、まず、松下さんに最初にお話いただいて、あとから二人で話すという形にしたいと思います。よろしくお願いいたします。
松下 今日は8つ、最近考えていることをお話したいと思っています。
詩は、心細い文学
1つめ、「詩は心細い文学だ」ということ。
詩には、ほかの短詩型、俳句、短歌、川柳のようなきまった形がない。形という、つかまるところがない。バスの中で、バスと一緒に揺れているのと同じです。身を寄せるところがない。
詩を書こうとする人の前には、何もない。最初、自分に何かが書けるなんてとても思えない。不安で仕方がない。形がないだけではなく内容もない。全部作者が決めるしかない。詩は、何もないところから自分の力で一から作り上げるものです。
これが詩、これが詩ではないというマルバツ式の項目リストはない。“こういう条件を満たせばこれが詩ですよ”という条件リストがない。いろいろ言うことはできますが、人それぞれ、これが詩だと決めているだけです。
詩の定義は曖昧です。その曖昧さ、心細さこそが、詩が詩である理由であり、ぼくが詩を好きな理由です。詩は、心細いものだということ。心細いって素敵なこと。詩の定義は、自分で作る。それって奇跡のように素敵なこと。これが一つめ。
すべての詩をわからなくていい
2つめ、「詩には、わからない作品がたくさんある」ということ。
詩を書き始めるときに、商業誌や同人誌を手にとって、その雑誌に書いてある詩が全部わかるという人は、まずいないはず。ぼくも長く詩を読み、書いてきましたが、わからない詩がたくさんあります。すべての詩がわかるということはない。
わからない詩がたくさんあると、詩の評価そのものを疑いたくなりますよね。それでも、自分の好みだけではない、詩の良し悪しってある。自分の感じ方が狭くてわからないだけで、いい詩というのがあるんです。自分がわからない詩があるからといって、全否定するのは違う。かと言って、わからない詩の前で、自分がダメだと思ってしまうのも違う。
わからない詩がたくさんあっても、そのままにしておく。詩を書いたり詩を読んだりするうちに、だんだん自分の感じ方の間口がひろがって、以前はわからなかった詩でも理解が広がっていきます。わからない詩は、そのままそっと放っておく。これが二つめ。
他人の評価にこだわらない
3つめ、「評価されなくても書きつづけていい」ということ。
詩の世界には、投稿という仕組みがあります。「現代詩手帖」や「ユリイカ」「詩と思想」といった雑誌には、文芸誌同様、投稿欄というのが設けられています。詩を書き始めた人たちは、最初はどうしていいかわからない。そのうち投稿という方法があると知って、そこで選ばれることを目標にするようになります。
でも、一篇の詩が書かれる意味って、他人の評価がすべてではない。もちろん評価されるとうれしいけど、それだけではない。というのも、自分が詩を書いているとき、少なくともその詩は、書いている本人の胸を打っているはずなんです。自分を感動させるほどには、他の人の胸を打つことがないかもしれないけど、自分だけは、その詩に感動しているはず。少なくとも、その詩には、書いた人の情熱が込められている。
そういう詩があっていいと思うんです。誰にもほめられないけど、詩を書きつづけることは、その人にとってかけがえのない意味がある。作ること自体の喜びや幸せを詩作から受け取っている。そういう詩との付き合い方もあると思います。
憧れに近づきたい
4つめ、書いているだけで幸せで、その詩があればいい、誰かに認められなくてもいいはずなのに、もっといい詩、人に伝わる詩を書きたいと思う心ってある。書いているだけで楽しいのに、認められたいと思ってしまうのはなぜでしょう。
ぼくは、それって自分が初めて詩を書きはじめたときに関係しているのではないかと考えました。誰でも他の人の詩を読んで、感動した経験があるはずです。これはすごい、自分もこんな詩を書いてみたい、こんなのが書けたらどんなに素敵だろうと思う。それが生きがいになります。そう思って詩を書きはじめた人も多いと思います。ぼくもそうでした。萩原朔太郎を読んで、こんな詩をいつか書いてみたいと思いました。それが詩を書くきっかけになりました。
詩を書き始めるきっかけは、特別に感動する、特別な詩に出会ったことだった。それは、自分の生存を新しくさせてくれるような詩との出会いだった。世の中には、そういうふうに人を揺り動かす詩が間違いなくある。読んだ人の生涯にわたってそばにいてくれるような詩。
そんな詩に心を打たれて、自分も詩を書いてみたいと思ったとしたら、今自分が書いている詩も、かつて自分が憧れたその詩に近づきたいと思うのは当たり前です。詩を書いているだけでも嬉しいし、幸せだけど、それだけではなくて、さらにいい詩、よりよい詩を書きたいと願う。それは普通の感じ方だと思う。憧れに近づきたい。それが4つめ。
詩は、詩の世界から自由であっていい
5つめ、詩を書くときには「誰にも遠慮する必要はない」ということ。
当たり前のことですが、案外、遠慮しているんですよね。この「誰にも遠慮する必要はない」の「誰にも」は、人だけじゃなくて、そのときそのときの詩の状況であったり、これがいいとされている目につきやすい詩の書き方とか、そういうものにも遠慮する必要はないということです。
自分の書いているものは詩なんだろうかって思っているくらいがちょうどいい。自分が胸を打たれている、憧れている詩に向かってまっしぐらに進んでいっていいんです。著名な詩人が書いている詩に気を使う必要なんてない。自分の詩なんだから、好きに自由に書いていい。それが次の時代の現代詩になる。詩は詩の世界からもっと自由であっていい、ぼくはそう思います。それが5つめ。
遠くを見て書く
6つめ、「遠くを見て詩を書こう」ということ。
毎年たくさんの優れた詩集が出ます。どの詩集が賞をとるかとか、評価が高いとか、SNSで反応がいいとか、そういう話題で盛り上がる。そういうのを見たり読んだりすると、自分の詩はこれでいいんだろうかと焦りますね。
でも、自分の詩を書いていくペースは、他の人と違っていていいんです。去年はこの詩人、今年はこの詩人と、あわただしく追いかけてなくていい。じっくり自分の詩と付き合って末永く書いていく。そのうち自分の詩の一番いいところが見つかるだろう、それまでは、自分のペースで書いていこう。自分が憧れるような詩人にいつかはなりたいと、遠い未来の自分の姿を思い描いて書いていこう、今年や来年のことではなくて、もっとずっと先。遠くを見て書く、これが6つめ。
詩の技術は書きながら身につける
7つめ、「詩の技術は書きながら身につける」ということ。
ぼくも『これから詩を読み、書くひとのための詩の教室』(思潮社)という、詩の書き方の本を出していて、そこには少しは技術論も入っているけど、詩の技法って、じつは自分の詩を一生懸命書いていれば自分の詩の中から自然と見つけ出せるものなんです。
自分の書きたいことを書くために、どうしたらより効果的に読む人に伝えられるかをいろいろ試してみる。どのように書けば、より人とつながることができるかを真剣に考える。そのことを見つめてやっていると、自分の詩から自分なりの技法ができあがっていく。
自分の書いている詩が、詩の技法、技術を教えてくれる。自分に合った技法や技術は、自分にしかわからない。暗喩を使おうとか、擬人法を使おうとか、言葉を飛躍させてみようとか、技法が先ではない。まず自分が書きたいことがあって、自分にとっての詩の技法を自分の詩の中から見つけ出すという順番がいいと思います。
作品と自分だけで正面から向き合う
最後、8つめ。「詩を読むときは無防備に読む」ということ。
とにかく目の前にあるテキスト、詩を、そのときの自分の理解力、感じ方で、前知識なく読む。未熟でも、そのときの自分の力で読み通すことが詩を読むということです。有名な詩人だからとか、どんな背景を持った詩人であるかということは関係ない。書かれているものを自分の不完全な知識や感性、貧しい読解力で、自分なりの感動を受け止める。
まったく面白くないなら、そう感じてしまっていいんです。みんながほめる詩でも、自分が面白くないと思えば、そのときの自分にとっては面白くない詩なんです。わかったふりをしない。人の読みに迎合しない。本当はわからないのにみんながいいと言っているからと言ってわかったふりをしていると、自分の読みが成長していかない。
作品と自分だけで正面から向き合う。詩には、わかりづらいものがたくさんあって、全部わからなくても構わない。さっきも言ったけど、それをそのままにしておく。素手で立ち向かって、その上で感動する詩、胸を打つ詩をしっかり受け止めていけばいい。詩に気を使うことはない。詩は、自由に読んでいい。これが、8つめです。
***
自由詩の不自由
藤井 ありがとうございます。素晴らしすぎて、もう言うことない(笑)。
松下 言いたいことも言ってしまったし、もう帰りましょうか(笑)。
藤井 何も言うことがないけど、違うところがあるんですよね。最初から違うところがある。この、詩という形式が自由で、評価が曖昧というところ。本来は、というか、建前はそうだけど、実際は、不自由だし、いろんな制約があります。そこがわかってもらいにくいところ。
松下 詩そのものは、形式もないし、詩とは何かという定義は曖昧だと言ったけど、藤井さんが言うように、いい詩、悪い詩はあるよね。
藤井 最近、詩人さんたちが教えているカルチャーセンターや大学の授業がたくさんあって、よみうりカルチャー荻窪の池井昌樹さんの教室とか、池袋コミュニティカレッジの川口晴美さんの教室とか、隣町珈琲の伊藤比呂美さんの教室もありました。教室に行くと、詩人のかたが言うことに最大公約数があることに気がつくんです。
このなさそうである詩の読み方、書き方の最大公約数、自由と言いながら、実際はそうでもない、目に見えないルールのたくさんあるこの「現代詩/自由詩」の、この「外側」を説明することが批評なのではないかというのが、わたしが最近よく考えていることで、その話をできるだけ言葉にしてみようというのが今回の企画のスタートでした。
松下さんも、『これから詩を読み、書くひとのための詩の教室』の中で、そのことについて書いている。それは、私の言っていることと重なっているのですが、重ならないところもあって、それは、松下さんが作品としての評価をどこかで手放しているから。そこが少し他の詩人と違うところかなと思います。
松下 評価を手放すことには二つの意味があって、詩を書くこと自体に意味がある、上手い下手にあまり重きを置かない、という意味ですよね。うまいにこしたことはないというのは、ぼくも言っていて、評価をすべて手放しているわけではない。
うまいにこしたことはないけど、どちらが大事かというと、自分のうちにある喜びだよということ。ぼくにとって、ダイニングテーブルの隅でひとりで楽しく書いて終わるのが詩なんです。詩は、やっぱり手元の文学だと思う。それが雑誌に載ったり、詩集になって評価を受けるということは、大きな問題じゃない。自分が書く喜びが生きる喜び、生きていく励みになることなんですね。
藤井 一方で私も、詩が生まれる場所が大好きなんです。他人の評価にさらされる前の、まだ詩が詩人さんたちの手元にあって、それだけの状態をとても尊いと感じる。一番いい時期、時間じゃないですか。
松下 それを編集の人が思ってくれるっていうのは、すごく嬉しいですね。
藤井 そこは松下さんと同じですが、私は編集者だから、最終的には、いい作品が欲しいわけです。それがどうしてもある。詩人のみなさんの詩が手元にある時間を大事にしてほしいと思う気持ちと同時に、仕事としては、いい詩が欲しいと思っているということ。
詩は自由、自由に書きなさいといいながら、じつはそうではない、この建前と本音、詩の良し悪しの評価というものを少しでも言語化してみたいというのが、私の希望です。「条件リストがない」と松下さんはおっしゃるけど、じつはある。
松下 誰かかわりに作ってくれないかな(笑)。
藤井 講義録には、少し書いてありますよね。
松下 ぼくは、なくてもいいと思う。それは自分が決めればいい。さっきも言ったけど、自分の詩の技術は、自分の詩の内実が要請してくることだから。詩ってすべてが字余り、すべてが字足らずというか、形のない定型詩みたいな感じ。
「現代詩」という言い方がありますよね。不思議な言葉だけど、「現代詩」ってこういうもの、という共通理解がある。投稿欄などを見れば、これが現代詩かと思うわけです。ぼくも若い頃には、そう思っていました。でも、だんだんそれだけじゃないことがわかってくる。繰り返しになるけど、自分のペースで、自分の読み方で自分にとっての詩を見つけていけばいい。よしあしはあるけど、基本的には、平場だと思う。
藤井 松下さんがSNSでアップされている言葉と、詩として発表される作品には少し違いがあるけど、松下さんの意識の中では一緒なんですよね。松下さんがここまで書いてこられて、たどりついた境地。
松下 たどり着いたのか、元に戻ったのかよくわからないけど、一緒ですね。
藤井 松下さんのように小学生の頃から詩を書いていて、その積み重ねの末に技術的なことを問わないということと、詩を書き始めたばかりの人が技術を習得しなくていい、勉強しなくていいということは、まったく違うことかもしれませんけれども。
夜の招待 石原吉郎
窓のそとで ぴすとるが鳴って
かあてんへいっぺんに
火がつけられて
まちかまえた時間が やってくる
夜だ 連隊のように
せろふあんでふち取って――
ふらんすは
すぺいんと和ぼくせよ
獅子はおのおの尻尾(しりお)をなめよ
私は にわかに寛大になり
もはやだれでもなくなった人と
手をとりあって
おうようなおとなの時間を
その手のあいだに かこみとる
(…)
もはやどれだけの時が
よみがえらずに
のこっていよう
夜はまきかえされ
椅子がゆさぶられ
かあどの旗がひきおろされ
手のなかでくれよんが溶けて
朝が 約束をしにやってくる
石原吉郎『サンチョ・パンサの帰郷』思潮社、1963年
解釈の向こう側
藤井 今日は、それぞれ作品を選んできました。
石原吉郎「夜の招待」「馬と暴動」
松下育男「タクシーで」「火山1」「顔」
佐々木安美「キューピー」
岩田宏「いやな唄」
富岡多惠子「between――」「女友達」
松下さんは、いつも石原吉郎さんの詩を挙げられますね。松下さんは、石原さんが「現代詩手帖」の投稿欄の選者だったときに選ばれたことがある。
松下 そう、他でも書いたり言ったりしているけど、1973、74年だったかな、大学出るか出ないかの頃に「現代詩手帖」に投稿したら、選ばれたんですね。びっくりしました。ぼくの詩って、なんてことのない詩なんです(笑)。その頃から「現代詩手帖」の投稿欄には格調の高い詩が載っていたから、まず載らないだろうと思っていた。ある日、うちの郵便受けに「現代詩手帖」が届いて開けてみたら、後ろのほうに小さい字で載っていたんです。
その号では「現代詩手帖」の投稿欄は2ページしかなくて、ぼくと阿部恭久、宮園マキ、もうひとり相沢英子さんという人の4人の詩が載っていて、選者が石原吉郎さんだった。そのときぼくは、石原吉郎という詩人を知りませんでした。萩原朔太郎とか室生犀星とか、伊東静雄、北原白秋みたいな、いわゆる近代詩人ばかり読んでいたから、現代の詩をあまり読んでいなかった。
それで大学の図書室に行って、初めて石原さんの詩集を読んだんですね。読んだとき、日本語にこんなことができるんだ、こんなすごい詩、詩人がいるんだと全身を打たれたように感じました。図書室のガラス窓から夕暮れの日差しが入ってきて、石原吉郎に接した、生涯忘れられない経験です。
好きな詩はたくさんありますが、とくに「夜の招待」、これは本当に名作です。石原さんは、シベリアの抑留から帰ってきて、わりと歳をとってから詩を書き始めた。これは、「現代詩手帖」の前身だった「文章倶楽部」に石原さんが投稿して特選になった詩です。そのときの選者が鮎川信夫さんと谷川俊太郎さんで、鮎川さんもほめているけど、谷川さんがとくに激賞しているんです。さっきも言った、ぼくにとっての特別な詩、特別に感動する詩が、この「夜の招待」です。
そういう意味で、この詩はぼくにとって、一生忘れられない詩だけど、じゃあ、この詩をわかっているのかどうかというと、そうとも言い切れない。不思議なことだけど、わからないところがあるわけです。
もちろん解釈してみることはできる。じゃあ、その解釈が、ぼくの胸を打ったのかというと、そうじゃない。この言葉の前に立ったときにすでに感動しているんです。意味が頭を通過する前に感動している。言葉ひとつひとつの立ち姿がぼくの胸を打つ。言葉の立ち姿ってなんだって言われると、すごく曖昧ですが。
命令形や断定形の使い方もうまくて、そういう技法的な部分もいい。でも、そういう技術的に高度な詩は、他の詩人の作品にも、いくらでもある。たとえば「せろふあん」のように、わざわざカタカナをひらがなで書いたりする書き方だっていくらでもある。戦争を書いた詩も、たくさんある。
それでも、この詩は特別なんです。どうして特別なのかわからない。意味を通過しないで、すべての言葉がダイレクトにぼくのところへ届く。まさに言葉のひとつひとつの立ち姿なんですね。
藤井 私があげた岩田宏さんの「いやな唄」も同じです。あるとき、雷に打たれたように読んで、意味を理解して感動したのとは少し違う。あとからなにか言うことはできても、あの打たれるっていう感覚に対して意味や解釈は関係ないですよね。
松下 意味じゃないよね。
藤井 私は、石原さんの詩の中だったら「位置」を選びます。「しずかな肩には/声だけがならぶのでない/声よりも近く/敵がならぶのだ」。石原さんの代表作です。
けして難しい言葉は並んでいないけど、難しくないとも言い切れない。そういう場合は、手がかりを探しますよね。石原さんの場合は、戦争です。「夜の招待」も「位置」も戦争のメタファー(比喩)を手がかりとして読むというのがこれまでの石原さんの従来の読み方です。
今は少しその読み方が変わってきていて、そういうふうに喩として読まずに、言葉そのものの面白さを受け取る読み方をする人も増えていて、石原さんの読者は今でもたくさんいます。
松下 間違っているかもしれないけど、解釈はできます。ぼくは、この詩は時間のことを書いていると思うんです。「まちかまえた時間」「おうようなおとなの時間」「来るよりほかに仕方のない時間」「もはやどれだけの時」、それから「夜」とか「朝」も、時間のことですよね。たくさん「時」とか「時間」という言葉が出てくる。つまり、我々が生きている時間、死んでしまった時間、それが戦争やラーゲリ体験に繋がっています。
今だったら、ロシアのウクライナ侵攻と繋げて読むこともできる。過ぎさった時、これからくる死の時間、精神についての詩だと感じる。最初に読んだとき、我々の生き死にについての詩だと感じました。
途中で「もはやだれでもなくなった人と/手をとりあって」とあって、これがキーワードだと思う。ぼくが最初に感じたのはやっぱり亡くなった人なんですね。これは戦争によって理不尽にも暴力的になくなってしまった、「だれでもなくなった人」、死について、そういう人と「手をとりあって」と書いている。
これは、ぼくの解釈です。石原吉郎論は、たくさん出ていますから、そちらを参照してもらえればと思いますが、例えば最後の「かあどの旗がひきおろされ/手のなかでくれよんが溶けて」とあって、「かあどの旗」とか「クレヨンが溶ける」もメタファーだと思うけど、正確にはわからない。
さっき言ったように、ぼくが前情報なしに無防備に読んだ立場から言うと、「かあどの旗」とか「クレヨン」とかいう言葉は、やっぱり時と関係しているのかなと思う。夜が明けて空の色が変わっていく、死んでいた時がだんだん優しく蘇って色づいていくというのを書いているのかなと読みました。
詩の豊かさ
松下 繰り返しますが、自分の解釈が当たっているかどうかは、どうでもいい。ぼくがこの詩が好きなのは、その解釈の先なので。ぼくはこう読んで、感動した、ということが一番大事なことです。
藤井 ありがたいことですね。自分がこう読んだよということをみんながちゃんと言っていけば、詩はもっと豊かになるのではないかと思っています。
松下 意外とみんなやらないよね。
藤井 やらないですね。一篇の詩を語って、みんな全然違うふうに読んでいる。同じじゃなくて、みんなそれぞれこう読んだ、私はこう読んだ、というのがあって、私にはこうとしか読めないというのもあるはずで、それがたくさんあることが詩の豊かさですよね。
石原吉郎さんの『望郷と海』というエッセイ集があります。20年以上前に荒川洋治さんの詩の教室に、詩ってなんだろうと思って参加したときに、荒川さんが紹介されていました。何度も参照される名著です。
「位置」がどういう成り立ちで書かれているのか、どうしても背景を読んでしまうところがあって、この本にはそのヒントになることが書かれています。ただ、そういう情報なしに素手で読んでもこの詩はすごいというのが今の松下さんの話だし、実際、詩はそのように読んでみるのがいいですね。
松下 そう思いますね。
解釈の先と言いつつ解釈してしまうと、われわれの個々のいのち、何十億何百億あるいのち、親父だったりおふくろだったりお姉さんだったり、個々のいのちの持つ固有の寂しさ、それが時とともに衰えて失われてしまう、当たり前の寂しさとか悲しさを書いている詩なのかな。ぼくは、その何者でもない、人が死んでいくことの厳かさを、言葉の立ち姿から受け止めたから、こんなに惹きつけられるのかなと思う。
藤井 石原さんは、同時に戦後詩の代表的な存在で、鮎川さんがいて、谷川さんがいて、石原さんがいてという歴史の系譜に位置づけられていますが、松下さんは対個人で石原さんに出会って、それがたまたま戦後詩代表の詩人でもあったわけです。
私がこの松下さんの話から受け取ることは、石原さんが戦後詩の代表かどうかということよりも、自分の信じる「神様」に忠実かどうか、ということなんですよね。みんなが自分が本当にいいと思っているものを信じる、自分が信じているものをいいと言いつづけることが大切なことだと思っています。
目の前の流行とかシーンがあって、圧倒的に流行っている書き方があると、これに準じなければいけないような、自分の詩は詩じゃないんだっていう気持ちになることもあるかもしれないけど、本当に自分が感動して、自分が詩と出会ったときの感動で読んで書いていくしかない。松下さんはそのことをずっとおっしゃっていて、それをみんながそれぞれの持ち場所で言いつづけることが、詩の世界の豊かさにつながるはずです。
(中編につづく)

photo by Gettyimages
更新の通知を受け取りましょう



















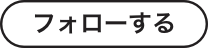


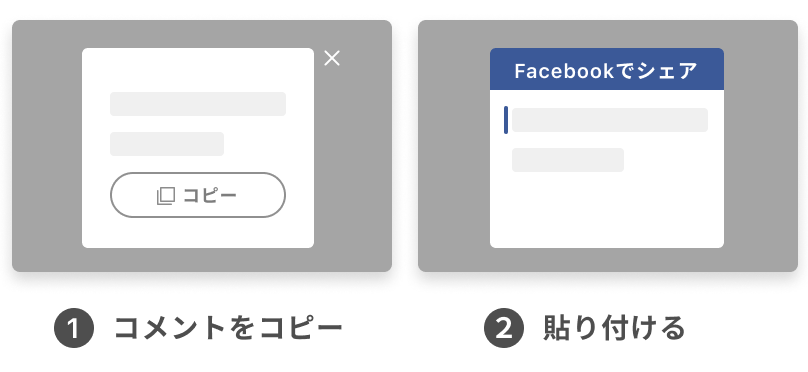

投稿したコメント