「AI時代は身体性・五感が人間の強みである」と言えるのか?
<目次>
1. AI時代の「身体性と五感」の価値
2. AI × スタントマン(身体性)の事例
3. AI × モデル(身体性)の事例
4. AI × 味覚(五感)の事例
5. AI × 聴覚(五感)の事例
6. Epilogue
7.フォロワー特典やお知らせ
1. AI時代の「身体性と五感」の価値
「AI時代は、身体性や五感がますます人間の強みになっていく」という言葉を時々耳にする。
身体性で言えば、身体能力を活かしたテーマパークでのスタントマンや容姿を活かしたモデル。
五感で言えば、飲料メーカーで味覚を駆使した新製品開発や自動車の製造ラインで高級車のドアが閉まる際、聴覚を活かして音から異常を発見する官能検査が思い当たる。
今回は、次週から4週に渡り連載する「AI時代のコンサル」の解説に関わる前段として身体性と五感が人間の強みと言えるのかどうかを解説していく。
2. AI × スタントマン(身体性)の事例
そもそも、スタントマンとは?
スタントマンは、映画やテレビドラマなどのエンターテインメント作品で、俳優や女優の代わりに危険な場面やアクションシーンを演じる専門家のことを指す。彼らは特定の技能や訓練を持ち、シーンのリスクを最小限に抑えながらも、リアルで迫力のあるパフォーマンスを提供する職業。
このスタント、人間の身体性が発揮される領域に見えるが、実は、アメリカのマーベルスタジオのテーマパークでは、スパイダーマンのスタントを姿勢制御AIの入ったロボットが代行している。
外装は3Dプリンターで作られており、万一着地に失敗した時、外装が壊れてモーターやバッテリーといった重要なパーツは壊れないように設計されている。
3Dプリンターで外装をプリントして装着すれば、すぐに再開できる。
これはビジネス的に見ると、事業の継続性が担保された状態と言える。
ただし、今の時点では同じ動きを繰り返す部分に使われているため、複雑な動きを要するスタントにはまだ使われていないので、すぐにスタントの仕事がなくなることはない。
今後、ボストンダイナミクスのような忍者のようなロボットが、スリム化され、人間のような体格にまでサイズが小さくなると、複雑な動きのスタントの領域に進出してくる可能性もあるので、スタントの方は注視が必要だ。
3. AI × モデル(身体性)の事例
そもそも、モデルとは?
ファッションモデルとは、衣服、アクセサリー、化粧品などのアイテムを宣伝や広告、ランウェイショーなどの場で披露するための人々を指す。モデルの主な役割は、デザイナーやブランドのビジョンを視覚的に表現すること。モデルは身体的な特徴やポーズ、表現力などが求められ、多くの場合、特定の美的基準や市場の需要に合わせて選ばれる。
容姿を活かしたモデルも人間ならではの価値をもっていそうだが、実は生成系AIの普及により、AIのモデルを提供する会社が出てきている。
また、モデルとは少し異なるがグラビアに関しても集英社がAIグラビアを発売している(その後、理由を明示せず即販売終了)。
今後、モデルの分野でも、急速にAIが進出してくるだろう。
ただし、いくら美しく・カッコいいAIのモデルが生成できても、一つ欠けているものがある。
それは人が持つストーリーだ。
InstagramやX(Twitter)で、フォロワーが何十万人もいるモデルも珍しくない。
ファンは、モデルの表面的な美しさやカッコ良さだけでなく、ライフスタイルやこだわって選ぶ品々、自分と同じように日々の家事・育児といった様子を見て、共感や憧れを持つ。
そして、自分と同じように歳を取り、美しく、カッコ良く歳を重ねていく様に感化されて、自分の生活も変わっていく。
そういったストーリー性・感化させる力はAIで生成されたモデルでは、不可能ではないが、価値を波及しづらい。
これからのモデルで重要なことは、共感を生むタッチポイントを、どんなポイントで、どこの媒体で作るかが重要になってくるだろう。
・身体性のまとめ
スタントマンやモデルは身体性(身体能力や容姿の良さ)を活かした職業だが、姿勢制御AI搭載のロボと画像生成系AIという全く異なる分野のAIによって、攻め込まれ始めている。
攻め込まれる側の職業の人は、こういった流れをなるべくリアルタイムでキャッチしながら、下記のトピックス『スティーブ・ジョブズの逸話から考えるAIの価値と、生成系AIの実演から見る「プロ」の危機』で紹介しているように、下記の戦略を選び、実践する必要がある。
① 退避戦略:AIの進出が難しい別分野のピボット先を考える。
②防御戦略:+αの付加価値を別分野から持ってきて、自社のモノ・コトに加える。
③波乗り戦略:攻め込まれている自分の専門領域で、逆にAIを使ったサービス作りに乗り出す。
では、五感の を見てみよう領域はどうなのか、見てみよう。
4. AI × 味覚(五感)の事例
味覚も人間の強みが活きる領域と見られることが多いが、キリン生茶の「味のリニューアル」で、味覚AIが使われた。
今までは鋭敏な味覚を持つ専門集団が、既存の商品と競合商品を分析し、目指す方向性を決め、試作品を作り、最終的に商品を作ってきた訳だが、AIが定量的に味を表現し活用されている。
こういったAIが誕生することで、人によって感じ方が微妙に異なる感覚の領域が定量化され、誰でもAIを使えばこのケースで言うと味の分析や比較ができるようになるため、この点は、経営的な観点で見るとメリットがあるだろう。
5. AI × 聴覚(五感)の事例
トヨタのレクサスの製造ラインではドアの開け閉めした時の音を聞き分けて異常を検知する「官能検査」が行われている。
官能検査とは、人間の五感(目・耳・鼻・舌・皮膚)を使って品質を判定する方法であり、メッキや塗装の光沢、色つや、表面傷、表面の粗さ、音質などの品質特性を、感覚で判定基準と対比して合否を判定する検査方法。
人間の聴覚を活かしたいかにも人間の強みが活きる仕事だが、実は、この仕事にもスマホのアプリに異音検知AIが搭載され AIが使われるようになった。
これが可能になると、今まで試験を担当していたコストが嵩むためレクサスのような高級セグメントの製造ラインでしか行なっていなかった官能試験を、大衆セグメントの製品ラインにもスケールすることができる。
そうすることで製造ライン全体の品質向上や、試験を行なってわかる製造工程での改善ポイント(例 思いの外、後部座席左側の異音発生率が高かったなど)が見えてくることもあるかもしれない。
・五感のまとめ
五感を使った仕事もAIの進出が急拡大していくことが予想される。
五感を使った仕事をしている方は、例えば、波乗り戦略を使い、むしろこのようなAIを作っている会社に転職して五感AI PFの改良に力を貸したり、それを活かした製品作りに積極的になることで、さらなる活躍が期待できる。
退避戦略・防御戦略を取るせよ、外部環境の理解と、自分が好きなこと・できることを踏まえ、将来ビジョンを早めに考え、行動に移すことが重要だ。
6. Epilogue
今回はモデルやスタントマン、飲料の商品開発や車の製造といった領域で広く浅く、AIの事例を取り上げたが、次週からの4週間は「コンサル」という職業に絞り、最新事例から近未来予測まで、丁寧に解説していきます。
是非、コンサルの方は、自分の得意/不得意とAIが進出してくる分野を見定め、自分が伸ばすべきストロングポイントはどこにあり、新しくキャッチアップすべきことは何かのヒントを得て頂ければ嬉しいです
また、就職先を選ぶ大学生や、これからコンサルに転身しようとしている社会人にも有用な記事になる想定なので、そういう方々も是非参考にして頂ければと思います。
7.お知らせ
①NewsPicksのTHE UPDATEに出演しました!
IBMさんSponsoredで、THE UPDATEの生成AIのテーマの回に出演させて頂きました!生成AIがビジネスに与える影響に関心のある方は是非ご覧ください!
②『AI時代のキャリア生存戦略』が好評販売中です!
NewsPicksのNewSchool「次世代ビジネス書著者発掘プロジェクト」で最優秀賞を頂いた書籍が好評発売中ですので、AI時代を生き残る3種類の戦略について解説していますので、是非参考にしてみてください!
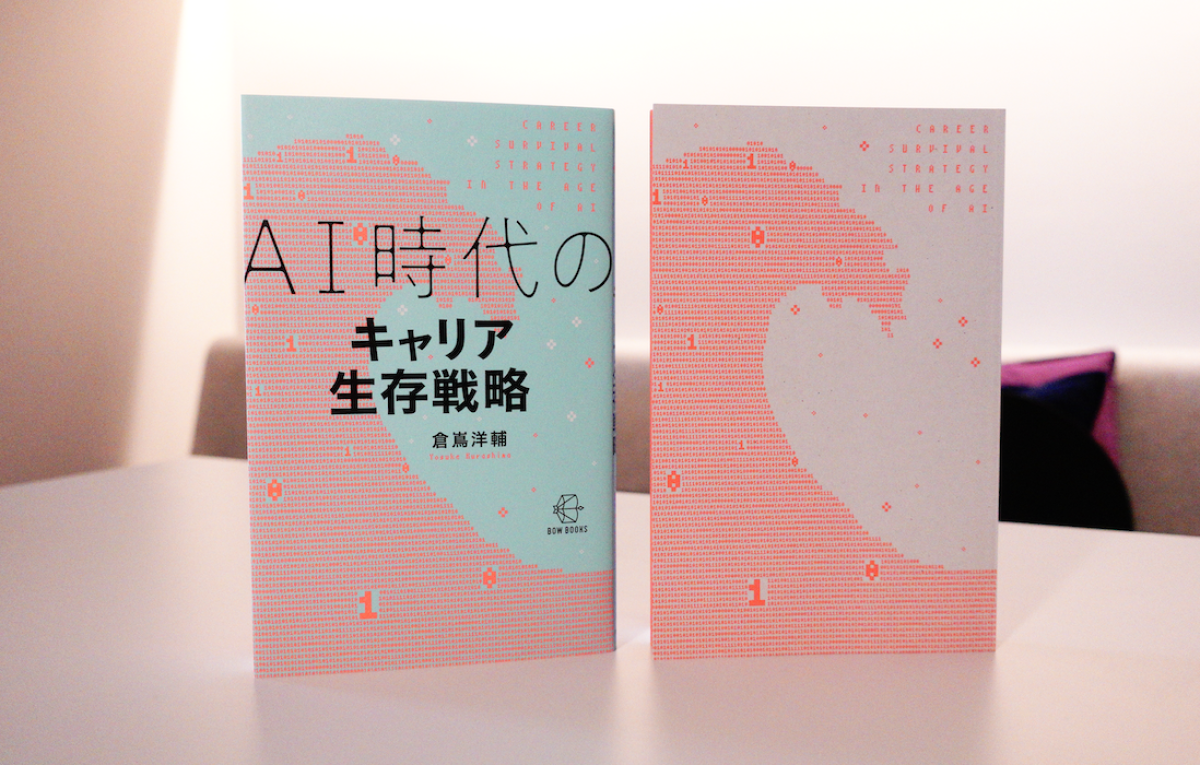
③「ChatGPT」と「LifeVision」の作り方の2つのUdemy動画コースをリリースしました!
Udemy主催のトピックチャレンジという動画講座の企画コンテストで2案採択頂き、今月公開されました!
トピックの購読特典として、ChatGPTの速習コースやLifeVisionの作り方、広告無しで市場を切り開いたTeslaの戦略など、今月末まで引き換え可能なクーポンを発行しましたので、気になる方は下記のリンクより入り、是非ご活用ください!
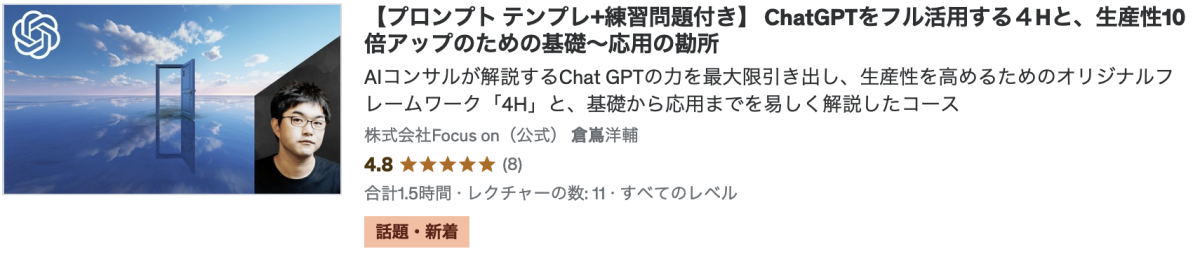
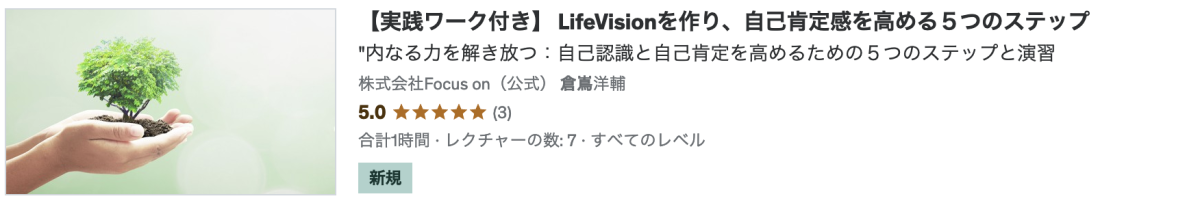
トップ画像:にじジャーニーで筆者が生成
更新の通知を受け取りましょう






























投稿したコメント