【しゃもじ論争1/2】ウクライナの「必勝」を願うのは良くないことか?
みなさま、お久しぶりです。
最後の更新から間が空いてしまいました。改めまして、いつもこの部屋を覗いてくださりありがとうございます。
今回は、久しぶりにウクライナのことを書いてみようと思っています。
突然ですが、皆さんは「平和」と「自由」のどちらをより重要だと思いますか。「両方」という人が10割だと思いますが、もしも両方は手に入らなかった場合に…。
そんなことを念頭に置きつつ、お目通しいただけたらと思います。
岸田さんの「電撃」ウクライナ訪問
さて、岸田首相は3月22日にウクライナを訪問しました。
メディアはこれを電撃訪問と報じ、中継地のポーランドで姿を捉えたTV局は速報を打ちました。ちょうど真裏ではWBC準決勝で村上選手がサヨナラ打を打っていたくらいの時間でした。
G7やEU各国の首脳は2023年になってから当たり前のようにキーウに入っているので、遅すぎたと感じる人もいたようです。
ただ、日本では基本的に要人の警護は警察によるもので、自衛隊による活動が非常に難しい。こうした中での訪問の難易度は、他国とは単純比較できません。
G7の首脳としては最後のキーウ入りとなりましたが、訪問が実現したことは素晴らしいのではないかと考えています。

虐殺が行われたキーウ近郊のブチャに入り、自分の目で惨状を目撃した岸田首相は「残虐な行為に憤りを感じる」と述べています。
この訪問は、日本の外交にとって非常に大きな意味があります。
というのも、今年は日本はG7の議長国。各国の議論をリードする立場にあります。
ウクライナが重要なトピックになる中で、岸田さんだけが現地の様子を自分の目で見ていないとなると、なかなかリードしていくのは難しいということになるでしょう。
「結束してウクライナを支援しよう!」
「…。(いや、あんたウクライナの現状知らないでしょ)」
と、なりかねなかった訳です。少なくとも外形的には。
そうした点は、以前に取材した駐日ウクライナ大使のコルスンスキー氏も仰っていました。
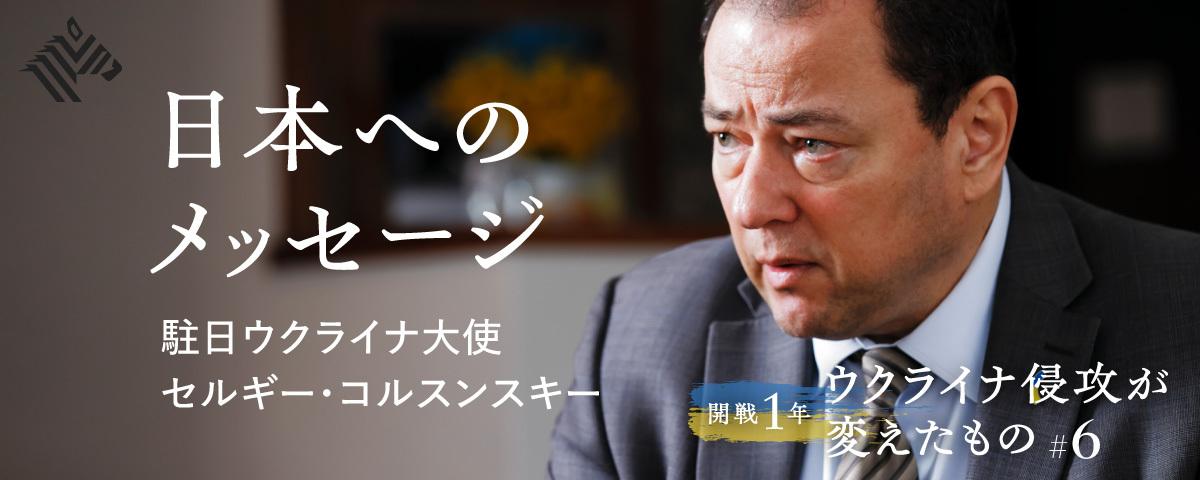
岸田首相は現地でウクライナのエネルギー分野に約600億円の無償支援を行うことなどを表明しており、もちろんウクライナとしても心強かったことでしょう。
思いもよらぬ「必勝しゃもじ」論争
今回の訪ウは、国民からの受け止めも良かったようです。例えば日経新聞の世論調査では内閣支持率が上がり、7ヶ月ぶりに不支持を上回ったとのことです。
訪問を「評価する」という回答は71%だったそうです。
一方で、岸田首相へは批判も向けられました。お土産に持っていった「しゃもじ」についてです。
岸田首相は地元広島の名産品でもあるしゃもじに「必勝」と書いてゼレンスキー大統領にプレゼントしたそうです。
これに対して、Twitterなどの一部では「ウクライナの勝利を願うのではなく、和平を願うべきだ」という批判が出ました。
これは、ちゃんと考えておかなければいけない問題です。
一刻も早く戦闘をやめて和平を結ぶことと戦場でロシア軍を駆逐して勝利することには、それぞれどんな意味が含まれるのか、これまでもNewsPicksの記事などで何回か書いてきました。
重要な議論なので今一度、整理してみたいと思います。
それでも、「和平」を求めるか
まず、今戦争を止めることがウクライナにとって何を意味するのかを考えてみたいと思います。
ポイントは①国土、②国民、③意図です。
まず、①国土。
現状、ウクライナの領土は約20%がロシアの支配下にあります。
そもそもロシアは2014年にウクライナの領土であるクリミア半島を一方的に併合してロシア領土にしました。
加えて、2022年2月24日からの全面侵攻で、10%ほど追加で占領地を増やした形です。
国土の20%というと、日本にとっては九州と四国を足したよりも多い面積です。

ウクライナにロシアと停戦せよと求めることは、すなわちウクライナが国土の20%を諦めることを意味します。北方領土を見れば分かるように、一度ロシアに取られた領土は、還ってくることはありません。
中高で習う「国家の3要素」というものがあります。それは領域(領土・領海・領空)、国民、主権の3つです。
停戦を結べというのは、このうち1つ目の要素である「領域」を諦めろ、というメッセージになります。
日本に置き換えてみて、この決断ができるでしょうか。
あるいは、岸田首相にそう判断してほしいと思うでしょうか?これが一つ目の論点です。
土地と人の命は「セット」
↑の決断が「できる」というロジックもありえると思っています。つまり、国土を諦めて停戦するという判断です。
というのも、国土を取り戻す戦いはものすごい犠牲を払うからです。国家の3大要素のひとつの国民、つまり②人命を大量に失うことになります。
全面侵攻が始まって一年あまり、報道では「ロシア軍は弱い」「ウクライナが押し戻している」という論調が目立ちました。
しかし、実際にはウクライナ側の損耗もとんでもなく、数万人は死亡し、数万人が負傷しています。
国土を優先するあまり、国民を大量に失ってしまうのもまた大きな問題になるのです。
では、②人命を優先して①領土をロシアに譲り渡すか──。
残念ながら、その決断は今のウクライナにとっては、ありえないのです。というのも、今回の場合、①領土と②人命が「セット」になっているからです。
どういうことか。
ロシア軍が一度占領し、その後撤退した地域というのがいくつかあります。つまり、ウクライナが力で領土を取り戻したパターンです。
そこで何が起きていたか。多くの街では民間人が拷問を受け、暴行され、虐殺された跡が見つかっています。衛星画像からロシア軍の行為だということもわかっています。
■ブチャ(キーウ近郊)
【検証】 ウクライナ・ブチャの住民虐殺 衛星画像がロシアの主張を否定
■イジューム(ハルキウ州)
“第二のブチャ”か イジュームで起きた悲劇【ボロディミル・マツォーキン副市長】
■ヘルソン州、ハルキウ州など
ロシア撤退の4州に民間人991人の遺体、オンブズマン「これまでの州と比較にならない」
ロシア軍に国土を支配させるということは、人命を奪われ、拷問され、暴行され、拉致されることとイコールになっているのです。
ウクライナへ今停戦せよ、という言うことは「あなたの国は国土を削り取られ、人命も失われているけれど、戦争が終わるならあきらめよう」ということとほとんど同じ意味になります。
ゼレンスキーも、譲ろうとしていた
それでも、ロシアの支配下で生きる道を選ぶという選択肢がいいという人はいるでしょう。それはそれで一つの考え方であって、排除されるべきではありません。
ですが、ウクライナに停戦を迫るということの意味が領土と国民を失うことである、というのは理解した上での議論であるべきなのです。
実はゼレンスキー政権としても①領土だけで済むならロシアと交渉しようという時期がありました。
全面侵攻が始まった22年2月から4月頃にかけてです。
なぜ和平交渉が終わったかと言うと、上記のブチャの虐殺が明らかになったからです。ロシアに国土を奪われるということは、そこに住む人たちの権利や命も奪われるということが明らかになったのです。
###
平和を願うのは何よりも重要なことだと思います。しかし、平和を願うことと、いまウクライナに和平を迫ることは、全く違う意味を持つということなのだと思います。
さて、3つのポイントといいながら、2つ目の時点で2000文字を超えてしまいました。
残りの一つは「ロシアの意図」ですが、これが多少ヘビーなので別途、次回の記事で書いてみます。最後までお付き合いいただいた皆様、ありがとうございます。
更新の通知を受け取りましょう
























投稿したコメント