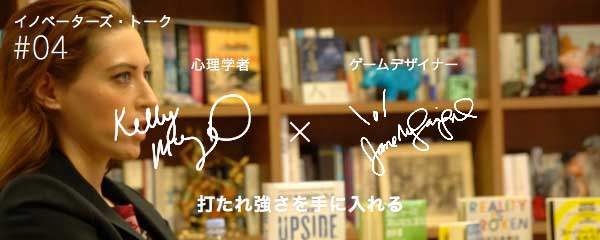
イノベーターズ・トーク Part 4
【マクゴニガル姉妹(4)】「みんなが勝者教育」は大間違いだ
2015/12/3
11月、アメリカから著名な研究者、マクゴニガル姉妹が来日した。
姉のケリーは著名な心理学者。妹のジェインはゲームデザイナー。一卵性双生児の姉妹は、職業は異なるが、「ストレス」「レジリエンス(打たれ強さ)」「心理学」を専門的に研究することで共通する。
姉のケリーは、近年まで「ストレスは健康に悪い」と講義してきた。だが今では、「それは間違いだった」と語る。妹のジェインも、ある程度のストレスは人間のメンタルを鍛えるうえで能力向上のために必要だと同意する。
本対談では、ストレス社会にさらされる現代人が「折れない心」を身につけるためのセオリーやノウハウについて対話する。

ケリー・マクゴニガル
1977年生まれ、ジェイン・マクゴニガルを双子の妹に持つ。スタンフォード大学でヒューマニスティック医学を研究し、博士号を習得。心理学者、スタンフォード大学「思いやりと利他心の研究、教育センター」講師。新刊のテーマ『ストレスと友達になる』を取り上げたTEDトーク動画は、全世界で900万回以上視聴されている。主な著書に『スタンフォードの自分を変える教室』『スタンフォードのストレスを力に変える教科書』(ともに大和書房)がある
弱くなったスタンフォード生
──幼児教育や初等教育の現場では今、IQとは関係ない意欲や忍耐力、社会性といった「非認知能力」やリーダーシップ、チーム育成スキルを教えることなどが重視されています。こうした生徒をみんな平等に、なおかつみんなが勝者になることを目指す教育についてお2人はどうお考えですか。
また、失敗することの大切さを教えるべきだという声もありますが、それを教えることが子どものストレスと付き合う能力やレジリエンスにどう影響するでしょうか。
ケリー:子を持つ親としてジェインは話したいことがたくさんあると思いますが、まずは私から。アメリカでは今、「みんなが勝者」教育法への反発が起きています。
私は10年ほど前に大学生を対象にした調査を始めたのですが、この世代の変化に衝撃を受けました。彼らはとても精神的に弱かったのです。試験の成績がよくないけれど、どうしていいかわからない。
課題のやり方がわからず、どうにもならない。それ以前のスタンフォードの学生たちには見られなかった弱さがありました。
非認知能力を教える大切さについて、アメリカではさまざまな意見がありますが、教えるべきは自尊心ではなく、共感や勇気、失敗から学ぶ力といったものです。それに、自身を成長に導く考え方も教えるべきでしょう。
今の学生たちにレジリエンスが欠けているのは、甘やかされることに慣れているからではないかと思います。
つまり、失敗から学ぶ経験をしてきていません。リスクは冒していいものであり、失敗しても誰もあなたを嫌わないということをわかっていません。失敗し、そこから学んで進歩することを教えられていないのです。
最も興味深いのは、子どもにとって非常に大切な「人に愛されている」という感覚が、テストで評価されるものと、ごっちゃになっていることです。
子どもたちは大きな達成感を得なくても、自分がナンバーワンだと感じることがなくてもいいんだと教えられ、でも実際には、目標を達成しないと愛情を受けられないという不安に駆られている。
私は親や教育に携わる人たちの考え方を変えたいと思っています。子どもにとっての「安全」とは、失敗をしないことでも、100%成功することでもありません。「大人に愛されている」と感じることなんです。大人は自分を裏切らない、どんな自分でも受け入れてくれる、と。

ジェイン・マクゴニガル
1977年、ペンシルバニア州フィラデルフィア生まれ。カリフォルニア大学バークレー校で博士号を取得。ゲームデザイナーであり代替現実ゲーム(Alternate reality game、ARG)研究者。2010年、『ビジネスウィーク』誌による「注目すべきトップ10・イノベーター」に選出。主な著書に『幸せな未来は「ゲーム」が創る』『スーパーベターになろう!』(ともに早川書房)がある
“受け放題”試験を導入する学校
ジェイン:失敗について言えば、独自のカリキュラムを実践するアメリカのチャータースクールでは、新しい取り組みをたくさんしています。ゲームを通して、失敗はしてもいいし、失敗がプラスにもなるということを教えているんです。
評価やランキングがつくテストを頻繁に受けている子どもは、失敗を恐れます。なぜなら、失敗すると実際に問題が起きるからです。テストに失敗したらそれまで。やり直しはききません。それが成績に反映されたり、入れる大学にも影響します。
でも現実社会では、大人になって自分の力を発揮するチャンスがたった1回だけなんていうことはほぼありません。最初に挑戦してうまくいかなくても、挑戦し続けようとやる気が湧いたり、挑戦したこと自体に喜びを感じたりします。
多くのチャータースクールでは、テストの方法が見直されています。ゲームの場合、あるレベルをプレイしたらスコアを獲得します。そのスコアに満足できなければ、もう一度挑戦する。もっとハイスコアを狙ったり、パーフェクトを目指したり、3つのスターのうち2つをゲットしたりしたいのかもしれない。
ここで重要なのは、ゲームではどれくらいのスコアなら合格点かを自分で決めることができ、次のレベルに進めるという自信がつくまで好きなだけ同じレベルでプレイできるということです。
自信がついたら、次のレベルに進む。チャータースクールでは、子どもたちが好きなだけ何度もテストを受けることができるようにしています。「やった! B評価だ! 次に進もう」とするか「A+を取るまでこのテストを受けよう」とするかは、子どもたち次第です。
「試験を受ける」学習効果
この方法が素晴らしい理由はいくつかあります。
1つは、結果に対する恐れを取り払うことです。“チャンスは1回”というプレッシャーがないんですから、実生活でもいいですよね。
2つ目は、習得することを重視していることです。ある調査によれば、「試験のために勉強する」よりも「試験を受ける」ことのほうが学習効果が高いことがわかりました。試験のために勉強しているときは、すでに学んだことを勉強する傾向があるんです。脳は過去に得た知識すべてを復習したり練習したりはしないことと関係しています。
試験を受けると、自分の知識や能力の足りないところがあぶり出されて、否が応でも自分の知らないことがわかります。たった1回の試験のために勉強させるのではなく、何度でも好きなだけ試験を受けさせるほうが、学習法として効果が高いのです。
このゲーム・デザインの原理は、あらゆる分野で取り入れることができます。学校でも、職場でも。テストの方法を変えて、ゲームをするときのように自分にとっての成功は自分で決め、挑戦し続けられるようにするのは、とても素晴らしい方法です。
ネガティブなストレスと不安、失敗に対する恐れをなくすことで、学習することへの意欲も湧きます。失敗のリスクを避けるのではなくてね。
(翻訳:前田雅子、撮影:佐藤英和)
*明日掲載の「SNSはメンタルにいい。その理由とは」に続きます。
*特集の目次
第1回:仕事量を減らしてもストレスは減らない
第2回:自己成長の「見える化」が人を伸ばす
第3回:米通信大手ベライゾンの営業成績が急伸した理由
第4回:「みんなが勝者教育」は大間違いだ
第5回:SNSはメンタルにいい。その理由とは
