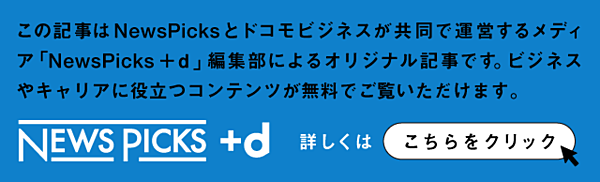2023/6/10
ファミリービジネスの呪縛解き...瀬戸内文化を和菓子で発信
広島県福山市にある老舗和菓子店「虎屋本舗」400年続くのれんをついで会社の経営責任者となって3年目となった30代の若い17当主は、仕事をしながら、常に「伝統」と「革新」について考えをめぐらせてきました。10年、50年、そしてその先の未来を見据えて、やろうとしていることとはいったいどんなことなんでしょうか。(最終回/全4回)
INDEX
- 「ファミリービジネスの呪縛」
- 伝統と革新を調和させた経営を模索
- 「瀬戸内エリア」を強みに文化を発信
公私を分けにくい。家庭内の不和が、そのまま仕事に影響して会社の空気が重たくなる……。家族経営の企業ではよくあることなのかもしれません。
広島県東部、福山市で400年以上にわたって和菓子を作り続けてきた「虎屋本舗」も、2年前に16代当主の高田信吾さん(60)から息子の海道さん(36)に社長が交代し、時折衝突も重ねてきました。
海道 「やっぱり本来、上司である父に対して、吐くべきでない言葉を浴びせてしまったこともあるし、専務である母に対してもそうです。ファミリービジネスの事業承継での正の側面は、親子でもあり、経営者同士でもあり、っていう二つの視点があること。でも負の側面としては、感情が先行するのでこじれる。あまりそれが過ぎると、社員さんにとって良くない」
「ファミリービジネスの呪縛」
同じように家業を継いだ人たちと情報交換する中で、どこにもあることなんだと悟ったそうです。ある時、広島の著名企業の経営者の方がこう言ったそうです。

高田海道社長(左)と父の信吾会長
海道 「父や母が嫌いかもしれないけども、そんなことやっている間にも大手は、そんなどうでもいい話を抜きにして、マーケティングに全て注力している。家族一つ御せないで、そういう会社を相手に勝てるのか」
海道さんは、最も尊敬する経営者として、父の名を挙げます。父が尊敬する、虎屋の商人道十訓のベースとなる教えをまとめた石田梅岩(いしだばいがん:「道徳と経済の両立」の理念を江戸時代中期、日本で初めて全国に広めた思想家)も。
そしてもう一人、尊敬する人がいるそうです。それは、あの芸術家・岡本太郎。

海道さんは岡本太郎著『日本の伝統』が経営バイブルだという
海道 「革新的な芸術家と思われていますが実は岡本太郎って、伝統と革新でいったら伝統だと思うんです」
海道さんが好きで何度も読んできた本が、岡本太郎の『日本の伝統』。伝統とは何か、そして革新とは何かを考える上で学びが多いそうです。
「岡本太郎さん的には伝統とは創造であらねばならぬとか、何か現代に生きるエネルギーでなければならないっていう。一番読んでて納得したのが、日本の古来の伝統文化を中軸に据えた上での創造とかエネルギーなんですよね」
家業を継ぐべく、東京から福山に戻った海道さん。
一言でいえば、コンビニでもインターネットでも、どこでもおいしい和菓子や洋菓子が手に入る時代、この先どうしたら生き残っていけるのだろうか……。そんなことを考えながら、最初に自分の発案で始めたのが、熟練の和菓子職人とタッグを組んで出かけていく和菓子づくり教室でした。
公民館や老人ホームなどに求められたら出かけていき、練り切りなどを作る、ということを重ねていくうちに、だんだんと広がっていきました。

虎屋神辺店での和菓子教室で手ほどきをする海道さん=提供
ある日、福山市の隣、岡山県南西部笠岡市沖にある白石島の小学校の先生から、電話を受けました。島の子どもたちに和菓子教室を開いてほしい、という内容でした。
全校児童わずか6人の小学校で手ほどきをすると、苦戦する子どもたちに、島の大人たちが助け舟を出す光景に海道さんは目を細めました。その後、別の島でも廃校が決まった小学校の児童たちと和菓子づくりをしました。
校長先生から、こんなことを言われ、胸が熱くなったそうです。
「小学校がなくなって、子どもたちが別の場所に行ってしまう前に、島の文化を伝えられて良かった」

高田海道(たかた・かいどう) 1987年、広島県生まれ。早稲田大学政治経済学部を2009年に卒業後、東京での不動産会社勤務、議員秘書を経て、2013年に株式会社虎屋本舗へ入社。2021年、17代当主・社長に就任。2018年、第2回ジャパンSDGsアワード「SDGsパートナーシップ賞」受賞。2018年にグロービス経営大学院修了。
地元福山も含めた瀬戸内の文化を、次世代につないでいくことが、この地で400年商売をしてきた自分たちがすることではないだろうかーー。
そう考えるようになりました。
和菓子を売る。それだけではなく、和菓子を通じて、文化を商いにする、それがあるべき姿ではないだろうか、と。
「せとうち和菓子キャラバン」と銘打ったその取り組みは、年間2000人以上の方が受講するまでに成長。そして、2018年12月、外務省主催の第2回「ジャパンSDGsアワード」で、「SDGsパートナーシップ賞」を受賞しました。JICA(国際協力機構)を通じて、海外へオンライン教室もするそうです。

SDGsアワードで講演する海道さん=提供
伝統と革新を調和させた経営を模索
こうした営みも含めて、海道さんがいつも模索してきたのは、伝統と革新の調和でした。それらをどうしたら調和できるのだろうか。そしてそこからどうやって、サステイナブルな商いを生み出せるのだろうか、と。
海道「虎屋の伝統でいうならたぶん、代々守ってきた商人道十訓のエッセンスや、地域のお客様、伝統的な菓子である和菓子が中軸にあるべきです。それら中軸から、今の時代に合った新しい商売の価値を見いだすのがビジネス、今の中小企業に求められることだと思うんです」
自社製品だけでなく、瀬戸内の産品を並べた「とらまるしぇ」や、地域の人たちが集って思い思いのクリエーティブ活動を展開するコミュニティースペース「とらきっちん」。それらを取り入れた神辺店のリニューアルも、まさにそんな考えに基づいたものでした。

瀬戸内エリアの産品が並ぶ神辺店の一角の「とらまるしぇ」に置かれた他社商品
海道 「石田梅岩は商人道という理念を打ち出し、商人の身分を上げたいわゆる革新者。それが、企業が何百年も続くと美しいとされる、日本人の美的感覚になるけど、時代が変われば逆転する可能性もある。岡本太郎のアート作品だけを見れば革新的だって思うけど、むしろ革新を連続させることが日本人の伝統的なビジネスの考え方だとすれば、伝統と革新って別に二項対立の関係である必要ないなと思うんです」
そう考えたとき、和菓子という菓子が秘めた可能性を感じるそうです。
「子どもたちとのお菓子づくりとかで、アニメーションや漫画のキャラクターの上生菓子とかを作るんです。そうするとすごい喜んでくれるし、お寿司そっくりなお菓子を外国人の前で作ったりすると、驚き、喜んでくれる。それって、伝統的なものに対してそれを裏切る余白があるってことなので。洋菓子との違いって、和菓子は基本的にこの余白を楽しむものだと思うんです」

「瀬戸内エリア」を強みに文化を発信
そして、瀬戸内エリアという「場」にこそある力。
海道 「瀬戸内のいいところは多島美。多くの島々が一つの海に美しく内包されている。そこに文化の多面性がある。それこそが瀬戸内というエリア。だから、それを感じ取ってもらえるような店づくりをしたいし、それぞれがつながりあって、また新たなものを生んでいけたらと思います」
海があって、山があって、風があって。そこにおいしい食べ物やお酒があり、素敵な人々との出会いがある。
「そんな強烈な原体験の中にうちのお菓子があるならば、菓子屋冥利に尽きるし、そういう原体験になれるようなシーンを作りあげていきたいんです」
そして、伝統と革新の調和は、まさに、先代の信吾さんも同じように模索してきたものでした。爆発的ヒットとなった「たこ焼きにしか見えないシュークリーム」をはじめとする「そっくりスイーツ」シリーズもまさに、伝統と革新の調和の模索から生まれたものだったのです。

お好み焼きそっくりなマロンケーキ
「のれんに傷がつく」「和菓子屋がやることではない」と散々批判される中で、信吾さんが押し通した商品でしたが、今となってはそれが、社内でも、そしてお客さんにも、受け入れられるだけの理由はあったのです。
信吾 「あのときは必死だったし、嗅覚みたいなものだけで動いたけれど、のちのちわかったことがあってね。そっくりスイーツって、お花とかそういったものをそっくりに作る、工芸菓子の文化が下敷きになっている。目の前のものをそっくりに作るっていうのは、ものづくりの原点みたいなもんです」
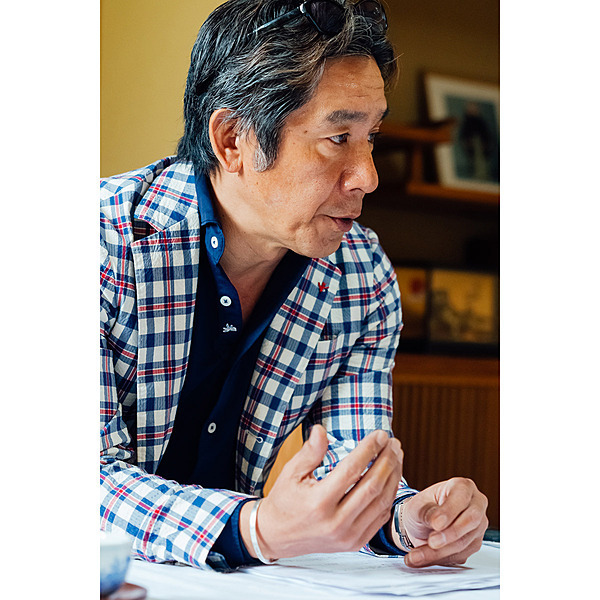
高田信吾(たかた・しんご) 1963年、広島県生まれ。虎屋本舗16代当主。国学院大学経済学部卒業後、大阪のアパレルメーカーに勤務し、先代の危篤をきっかけに福山へ戻り、1990年に株式会社虎屋本舗に入社。4年後に社長に就任。2003年、大ヒット商品の「たこ焼きにしか見えないシュークリーム」を考案した。2021年から会長。
子どもたちの前での講演で自らの仕事を語るとき、その話をするそうです。
信吾 「和菓子っていう伝統的な文化がベースにあって、それが形を変え、その作業を現代に受け継いでるっていう話かなって」
コロナ禍で地方移住が進むなど、地方や地域のポテンシャルに光が当たった時期があったが、コロナ禍が収束に向かう中、東京一極集中という長い流れが復活したような気配もある。広島県は、人口流出が全国一。商圏も先細る一方なのでは……。
若き17代はキッパリ言います。
海道 「確かに地方のマーケット縮小はよく言われるし、このままじゃいけないっていう危機感もある。だけど、一方で都市圏のほうが商圏が大きいとかチャンスが多いっていう評価は違うと思うんです」

虎屋の実店舗は、広島から岡山にかけての瀬戸内エリアのみ。しかし、インターネットなどに下支えされた、販路の多様化や物流の発展などがある。虎屋の商品が、様々な形で、遠くに旅をすることができる時代。「商圏という考え方が、もうなくなってきていると思う」と海道さんは言います。
海道「やっぱりその、お店の後ろに見える風景っていうかストーリー性だと思うんですよね。それに関して言えば、この福山という瀬戸内の一つのまちで商いをしている私たちは、なんら都市圏のお菓子屋さんに負けてないんです」
瀬戸内という確固たる立脚点から、和菓子を通じて文化を発信する。若き17代のまなざしに、きらりと覚悟が光りました。
(完)
取材・文:宮崎園子
撮影:浅野堅一
デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)
編集:野上英文
撮影:浅野堅一
デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)
編集:野上英文
「ファミリービジネス」は呪縛か、革新か?
和菓子400年 商人道の親子バトン