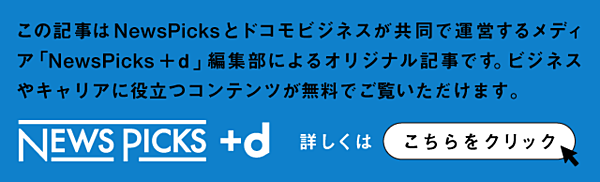2023/5/20
1万円羊羹を生んだ「高い=売れない」からの逆転の発想
桐箱に入ったその羊羹の値段は、1本1万円。製造・販売しているお店は、有名和菓子店が店舗を構える東京や京都ではなく、茨城県日立市にありました。
「御菓子司 風月堂」3代目の藤田浩一さんは、和菓子業界に根強くある「値段が高い=売れない」という常識を変えようとしています。素材と製法にこだわった高級羊羹は、発売から10カ月で800本の売り上げを記録。現在は海外からも注目を集めています。和菓子の世界を変える挑戦を追いました。(全3回)
- 1つのイガに実が1つの最高級品
- 12日で目標額の4倍以上
- 味をなじませる「真空パック」
- 台湾のクラファンで調達成功

藤田浩一(ふじた・こういち) 1983年、茨城県生まれ。東京製菓学校和菓子学科を卒業後、神奈川県で5年間修業し、2009年から茨城県日立市にある「御菓子司 風月堂」に事業承継を目的にUターン。3代目として菓子づくりを担当する。2020年に株式会社常陸風月堂を立ち上げ、代表取締役に就任。
1つのイガに実が1つの最高級品
北海道産の小豆で作られた上品な味わいの羊羹に、見たこともないような直径4センチの大きな栗がゴロリ。一口ではとても食べきれないほどの大きさですが、ひとたび口に入れると蒸した栗の風味がしっかりとありながら、羊羹の甘さと絶妙に溶けあった味と食感が絶品です。
商品名は「万羊羹」。値段は、なんと1本1万円です。
和菓子の世界で常識外れのこの価格設定も、原材料の品質にこだわった結果です。使用されている栗は、茨城県の最高級栗「飯沼栗」。栗を扱う業者では知らない人はいない国内最高級品なのです。藤田さんは、こう話します。
「一般的な栗は、1つの毬(イガ)に3個の果実が入りますが、飯沼栗は1個だけ。農家さんの長年の研究によって生まれた門外不出の特殊な栽培技術によって、『一毬一果(いっきゅういっか)』を実現させました。栽培できる農家は10軒程度で、希少価値が高い栗なんです」
甘さの引き出し方にも、こだわっています。一般的に、栗は収穫するとすぐ出荷しますが、飯沼栗の場合、2週間は低温熟成させます。それによってでんぷん質を糖分に変え、甘さを引き出すそうです。

(提供:常陸風月堂)
手間がかかるだけに、値段は一般的な栗の約3倍。万羊羹では、その飯沼栗を1本あたり11個使用しました。「1カ月で1本でも売れたらいいかなと思っていた」という藤田さんですが、2021年12月に販売を始めると想像を超える売れ行きで、ふたを開けてみれば、10カ月で800本を売り上げました。
「売れるのは、お中元とお歳暮の贈答品のシーズンかなと思っていました。ただ、昨年夏のころは万羊羹の認知度が高くなく、売れ行きはそれほど伸びませんでした。それが、1本1万円の羊羹としてニュースになると一気に売り上げが伸びて、月に100本以上の注文が入ることもありました。発送作業に追われて、本当に大変でした(笑)」
いまでこそ藤田さんは笑ってこう話しますが、ここに至るまでの道のりは平たんではありませんでした。
12日で目標額の4倍以上
和菓子業界を取り巻く環境は厳しいものがあります。国内の和菓子の生産数量をみても、2003年に32万7000トンあったのが、2022年には28万9700トンまで減少しています。コロナ禍では有名和菓子店の倒産も相次ぎました。
その要因のひとつとして藤田さんは、「和菓子業界では高価な商品は売れないという思い込みが強い」と話します。1本1万円の羊羹なんて、誰も思いつかないアイデアでした。
藤田さんが万羊羹の構想を考え始めたのは、2020年の秋が終わりかけたころ。知人から「飯沼栗というおいしい栗がある」と言われたのがきっかけでした。
藤田さんが飯沼栗のサンプルを食べてみたところ、「それまで食べたことのある栗の味との違いに驚いた」と言います。そしてすぐに、この飯沼栗をふんだんに使った羊羹の開発を決意しました。
「茨城県は栗の生産量と栽培面積が日本一で、それまでも茨城県産の栗を使用した羊羹を商品化したことはありました。でも、栗農家さんと会って話をすると『暮らしていくのはできるけど、孫の教育資金がないんだよね』と言うんです。飯沼栗のような素晴らしい栗を作っていても、後継者は育たず、いなくなってしまう。それなら、私が飯沼栗を使った和菓子を商品化すれば、栗の宣伝になって次の世代につながるかもしれないと思ったんです」
ただ、羊羹の試作を始めてみたものの、これまでの価格設定ではコストが合わず、商品化までは至らず……“突破口”のないまま、時が経っていきました。
そんなとき、運命の出会いが訪れます。2021年夏、名古屋で展示会に出展するための準備をしていた際に、隣のブースにいたデザイナーと、何げなく飯沼栗を使用した羊羹についての話をしたところ、「面白いですね!」と言われて意気投合。一緒に商品開発をすることになったのです。
「1本1万円」という値段も、デザイナーチームとの議論のなかで生まれました。
「最初は、7000〜8000円ぐらいの単価での販売を考えていました。ただ、原価を計算すると、どうしても1万円以上にしないと合わない。そういった話をしていたら、『むしろ1本1万円だとインパクトがあっていいと思いますよ』と言われたんです。その言葉に背中を押され、品質に妥協しない栗蒸し羊羹を作ることになりました」
品質の高さを表現するために、パッケージに桐箱を使用。桐箱の注文は、1ロットで1000個。味には自信を持っていた藤田さんでしたが、「いざとなれば、赤字覚悟で値下げして売るしかない」という気持ちでした。

(提供:常陸風月堂)
デザイナーチームと知り合ってからわずか4カ月、2021年11月末に資金集めとPRを兼ねたクラウドファンディングを開始します。すると、ここで奇跡が起きました。目標額30万円に対して、わずか12日間で141万円の寄付が集まったのです。こうして万羊羹は、12月15日に販売開始となりました。
「当時、通っていたビジネススクールで、商品開発はスピードが大切だと言われていて、とにかく早く商品化することを目指しました」
味をなじませる「真空パック」
飯沼栗のおいしさを引き出すために、さらにもうひとつ、和菓子業界の常識をくつがえす挑戦をしました。羊羹を真空パックで包んだことです。
「飯沼栗は1つが大きいので、あんと味をなじませるために3回蒸しています。さらに、作ってから時間を置いたほうが栗とあんの水分がお互いに通い合って味がまとまっていく。だから、真空パックにしたら味が良くなるんです。さらに、通常の羊羹の賞味期限は1週間程度ですが、それを1カ月まで伸ばすことができて、贈答用として使いやすくなりました」
いまでは、地元銀行の重役が得意先への手土産に持って行く、というような用途も増え、阪急百貨店が選んだプレミアムギフトのひとつにも選ばれました。
値段を高くしたことで、店舗全体の売り上げは1.5倍になり、利益率も5%上昇。飯沼栗の発注は年間1トンになり、しかも栗農家が“持続可能”なように正規の値段で買い続けています。
「じつは洋菓子の世界では2008年ごろから価格を押し上げていき、この15年ほどで商品単価が倍以上に上がっています。それによって、従業員の給与や待遇も改善されました。一方で和菓子業界では、自分たちが作った羊羹でも『有名な和菓子店が販売している価格より高く値段設定をしてはいけない』という思い込みがあるんです。その“価格の壁”への挑戦を、自分がやってみたいという思いがありました」
台湾のクラファンで調達成功
今後は、海外への販売拡大も視野に入れています。海外進出の第一歩として始めた台湾でのクラウドファンディングでは、59万7600ニュー台湾ドル(約263万円)の調達に成功しました。
「外国では、栗を食べる国は多いのですが、栗蒸し羊羹は食べたことがない人がほとんどです。輸出で経費などがかかっても、そういった国では1本2万円、3万円といった価格で売れる可能性もあります。最近は海外でも人気になりつつある和菓子ですが、高級和菓子販売は誰も挑戦したことのないことで、競争相手がいません。とくに台湾は、高品質な栗を使った栗蒸し羊羹を販売しているお店がなく、ブルー・オーシャンだと現地の方に教えてもらいました」

(提供:常陸風月堂)
「万羊羹」という商品名の由来は、日本最古の歌集である万葉集からきています。茨城県で詠まれた歌に、次のようなものがあります。
「三栗の 那賀に向へる 曝井(さらしい)の 絶えず通はむ そこに妻もが」
栗が実る那賀(現在の茨城県)に流れ込む湧き水のように絶えず通い続けたい、そこに愛する妻がいるなら――。枕詞の「三栗」から、当時からこの地が栗の名産地であったことがわかります。いまでは栗の実は3つではなく、飯沼栗という1つしか実をつけない栗が生まれました。
1000年の歴史を変えた奇跡の栗から生まれた常識破りの最高級羊羹はいま、世界に飛び立とうとしています。
取材・文:西岡千史
撮影:越智貴雄
編集:鈴木毅(POWER NEWS)
デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)
タイトルバナー:越智貴雄