
2023/3/2
【選書】どん底を味わった編集長が選ぶ「弱さ」の10冊
NewsPicks トピックス「弱さ考」で自身の双極性障害を明かし、弱くなった経験を通じて得た考察を公開しているNewsPicksパブリッシングの井上慎平編集長。
かつては「強く優秀なリーダー」であろうとしていたが、今の目標は「弱くてごきげん」と言う井上さんが、「強さ」を求められる能力主義の世の中で「弱さ」を否定せず生きるために読んできた本を紹介します。
かつては「強く優秀なリーダー」であろうとしていたが、今の目標は「弱くてごきげん」と言う井上さんが、「強さ」を求められる能力主義の世の中で「弱さ」を否定せず生きるために読んできた本を紹介します。
井上慎平
NewsPicksパブリッシング編集長。
レーベルコンセプト「経済と文化の両利き」へ。経済だけではつまらない。文化だけでは形にならない。
2021年に双極性障害を発症、今も共存中。復職後、トピックス『弱さ考』を開始し思考を綴るほか、ユーザベース全体のD&Iにも関わる。強さより弱さ、答えよりも問いの人。
みなさんこんにちは。「弱さ考」トピックスオーナーの井上です。NewsPicksパブリッシングという書籍レーベルの編集長をしています。
「より強く、より速く、より大きな結果を出せる自分であれ」
そんな強迫観念にとらわれていたこともあってか、2021年に双極性障害(昔で言う躁鬱病)を発症。それ以来、僕は格段に弱くなりました。
しかし今振り返ってみても「優秀たれ」と自らを駆り立てる強迫観念は、僕個人のみの課題ではなく、能力主義で回る経済社会が必然的に生み出す社会的な課題だったと思います。
今、僕たちは、「強くなろうとせずにいること」がとても難しい時代を生きているのです。
(このあたりの問題意識は初回記事で書きました)
人はずっと強くはいられません。けれども、ずっと弱いまま安心して生きるのもまた難しい。そんな強さと弱さの狭間を、ゆらゆらと歩くあなたの「杖」になるような10冊を選びました(マンガもあるよ)。
INDEX
- ⚫︎強さを解体する3冊
- 鈴木宏昭『私たちはどう学んでいるのか』
- 鷲田清一『だれのための仕事』
- 立岩真也『人間の条件 そんなものはない』
- ⚫︎弱さを発見する3冊
- 松岡正剛『フラジャイル』
- 浦河べてるの家『べてるの家の「当事者研究」』
- 鷲田清一『老いの空白』
- ⚫︎弱さに傷つき、それでも生きていく4冊
- 宮野真生子、磯野真穂『急に具合が悪くなる』
- 田島列島『水は海に向かって流れる』
- 若松英輔『悲しみの秘義』
- 近内悠太『世界は贈与でできている』
⚫︎強さを解体する3冊
僕は鬱のどん底期、自らがまったくの「無能」になったことをきっかけに能力主義(=成果を出す人は出さない人より偉い)そのものを疑う視点を手に入れました。
また、能力主義の中で生じる「成長」のナラティブ(=物語)についても、絶対的なものではないと気付きました。
(成長については弱さ考でも触れています)
大事なのは、能力も成長のナラティブも「自分自身ではない」と気づくこと。それらは「鎧」のようなもので、いつだって脱ぐことが可能なのです。
もし「能力主義」の社会に戻るなら、また着ることもあるでしょう。しかし、それは「鎧」であって自分ではないのだと知れば(つまり、能力主義が大人に課せられた「演技」なのだと知れば)、とたんに人生は軽くなります。そんなことに気づく3冊です。
鈴木宏昭『私たちはどう学んでいるのか』

2022年のマイベスト本。
認知科学者の鈴木は、「能力なんて言葉は使わないほうがいい」と断言します。
井上慎平という人間の中に「編集力」「ロジカルシンキング力」なんてモノのがあるわけではない(=「モノ的」な能力観)。
実際には、自分の内部にあるリソース(過去の経験・記憶)が外部にあるリソース(環境)と反応を起こすことで、創発的に「能力」が生まれます(=「コト的」な能力観)。つまり、能力は人の内部ではなく、外部との関係性の中にある。それなのに「力」というメタファーは、それを筋肉のように体「内」にあると錯覚させる点で、ミスリーディングなのだと。
わたしたちが日々高めようとする「能力」を、わたしは所有できない。びっくり仰天、しませんか。
鷲田清一『だれのための仕事』

競争はいいものだ。より良いものが、より安く手に入るのだから。だからこそ、私は日々成長を目指している。競争に負けないために。私が、自らの意思で。いや、本当に?
最後の「本当に?」は「私が、自らの意思で」という心の声に対する疑問です。
「誰に命令されたのでもなく、私が自分の意思でそう思っている」。その自律性こそを、鷲田は批判します。
自由であることの根拠であった「自律性」が、実は、自分で自分を「監視し、検閲し、制御し管理」するための考え方なのではないか。そして、「学校や学寮、兵営、工場、病院といった施設」はその訓練の場だったのではないか(ここはフーコーという哲学者の引用です)。
あるいは、いかに「生産性」の論理が、個人のアイデンティティを形づくる重要な要素になっていったのか。
なんだか小難しそうですが、心配いりません。鷲田のエッセイのような語り口が、心強い杖になります。お忙しい方は1,2章の「問題提起」だけでも。
立岩真也『人間の条件 そんなものはない』

立岩真也は不思議な学者です。
ゼロから、本当に自分が納得できる言葉だけを道具として、思考を積み上げていく。その営為がまるで子どものように純粋で、作為がないのです。自分を賢く立派に見せようという力みがまったくない。その思考の足跡を追うだけでも、「ものごとってこうやって考えるのか」という考え方の考え方について多くを学べます。
- 無能な人は無垢な人として描かれるのはどうしてか。
- 人間が知性を持ち優れた存在だ、地球を支配するに値する、そう思う人はたくさんいるが、それは、なぜか。
- できないことはないにこしたことはないのか、できることはあるに越したことは無いのか。それはなぜか。
- なぜ努力した人はそれを受け取るに値するのか。
- 自分の身体は、親からもらったものにすぎないのになぜか自分の所有物だとみなされている。それはなぜか。
まさに「問い」の人。問うて問うて空高く舞い上がり、帰ってこなくなるのでは、と心配させられる。そんな、子どものような知性を持った大人です。
⚫︎弱さを発見する3冊
松岡正剛『フラジャイル』

現代の知の巨人、松岡正剛。彼は、今から四半世紀以上も前に、弱さの中に「何かが過剰に相互反応する劇的な可能性」を見出しました。彼のセンスを伝えるには、その美しい日本語を引用するだけで十分でしょう。
「弱さ」は「強さ」の欠如ではない。
「弱さ」というそれ自体の特徴をもった劇的でピアニッシモな現象なのである。それは、些細で壊れやすく、はかなくて脆弱で、あとずさりするような異質を秘め、大半の論理から逸脱するような未知の振動体でしかないようなのに、ときに深すぎるほど大胆で、とびきり過敏な超越をあらわすものなのだ。部分でしかなく、引きちぎれた断片でしかないようなのに、ときに全体をおびやかし、総体に抵抗する透明な微細力をもっているのである。その不可解な名状し難い奇妙な消息を求めるうちに、私の内側でしだいにひとつの感覚的な言葉が、すなわち「フラジャイル」とか「フラジリティ」(fragility)とよばれるべき微妙な概念が注目されてきたのだった。
浦河べてるの家『べてるの家の「当事者研究」』
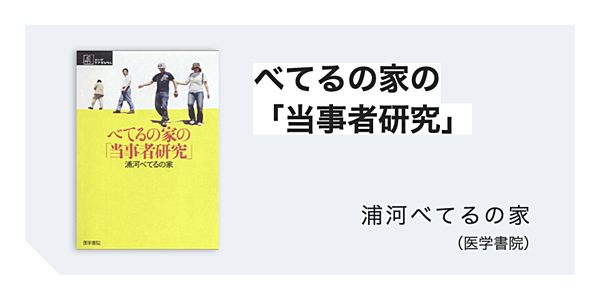
べてるの家は北海道浦河町にある精神障害等をかかえた当事者の活動拠点です。ここでは社会から「弱者」として排除された人が、日々ドタバタ劇を繰り広げながらも、文字どおり“生き生き”と生々しく生きている。彼らが編み出した、自分で自分の病気を研究するという「当事者研究」の手法は、いまや医学・看護界に大きな影響を与えるまでになりました。
「弱さを絆に」
「苦しみの主人公になる」
「順調に問題だらけ」
「安心してサボれる会社づくり」
「病気になってよかった。治りませんように」
これらの言葉に「おっ」と思ったなら、あなたはべてるに呼ばれています。弱さのイメージが倒錯し、世界観が愉快に混乱する、奇妙奇天烈「べてるワールド」へようこそ。
鷲田清一『老いの空白』

僕は鬱のとき、擬似的に「老い」ました。当然のようにできたことが一気にできなくなった。この能力の喪失ーーつまり老いーーは誰にも等しく訪れます。
今、多くの人は、知らず知らずに「生産する能力」をアイデンティティの拠り所としているでしょう。しかし、それはいつか必ず失われます。ノーベル賞を受賞するような天才も、排泄ひとつ自力でできない日がやってくる。そのとき、何が自分を支えるのか。
哲学者はこの問題に関わるのを避けてきた、とフランスの哲学者ボーヴォワールは喝破します。「老いは文明のスキャンダル」なのだと。僕が探したかぎり、この「老いの空白」というスキャンダルに真摯に向き合った哲学者は、鷲田清一ただ一人でした。
老いる親を見守るあなたへ。そして、いつか必ず老いるあなたへ。
⚫︎弱さに傷つき、それでも生きていく4冊
宮野真生子、磯野真穂『急に具合が悪くなる』

鬱からの回復期、最も生きる力をくれたのはこの本でした。偶然性をテーマに研究する哲学者で、まさに偶然にも癌を発症した若き宮野と、その友人であり人類学者の磯野との往復書簡による一冊。
人生における偶然とは何か。そしてその偶然性をいかに引き受けて生きるか。この本から得た問いへの僕の答えは「弱さ考」の鬱地獄生還記で語り尽くしました。
ひとつ付け加えるとすれば、最後の1ページで著者から引き受けた言葉の余韻を、どうか忘れることなくあなたの中に留めておいてください。
夏が来るたび、私たちは驚けるでしょうか。いま自分が生きていることは、なんという偶然なのかと。
田島列島『水は海に向かって流れる』

唯一のマンガです。弱っていて活字を読むのが辛い人にはまずこれをオススメします(3巻完結なのですぐ読めます)。
本書は、「傷」を負って生きる者の物語です。僕は鬱地獄生還記の最後に、「傷」について語りました。偶然性を引き受けて生きるとは、傷つく可能性を抱いたままに他者と言葉を交わすことであり、そして、そこで生じた傷こそが(能力ではなく)人のアイデンティティになりうると。
では、生まれた傷はどのように癒えるのか。この物語では時間、そして「巻き込み」と「巻き込まれ」が鍵となっています。
自分一人では、一歩を踏み出す勇気はなかなか出ない。そこに他人が強引に介入してくる。その先に何が待ち受けるかはわかりません。さらなる傷を呼ぶこともあるでしょう。でも、この物語のように、傷を傷のまま、癒しが訪れることもないままに、前に進む可能性がひらけるかもしれない。結局、どこまでいっても世界は自分を傷つけてくる可能性に満ちています。でも、その残酷さを知った上で世界に飛び込む。その先にしかありえない、なんとも言えない、いい「顔付き」があるのです。きっと。
若松英輔『悲しみの秘義』

僕の大切な知人は、「病気になって初めて見えるようになった『弱い光』がある」と教えてくれました。そして自分はもっともっと(ふだんは「強い光」によって消されてしまう)「弱い光」が見えるようになりたい、そのためなら、さらに深く病むことすら厭わないのだと言いました。
たしかに、苦しみや悲しみをくぐりぬけることでしか気づけないものがあります。病から回復した時、そこに存在するのは「健康」ではありません。「病の不在」なのです。「『負』の不在」が見えてくると、世界はまったく様相を変えます。
しかし、病と違い、他者を喪うとき、それが「回復」することはありません。
本書のテーマである他者の喪失。永遠の不在。それは、その人が「在」だった過去と生きることなのでしょうか。僕にはまだ知らない「弱い光」の物語。その光を亡き人からの「贈与」として生きていく人の言葉が、この本には散りばめられています。
悲しいとき、苦しいとき、何かを喪失したときにこそ開いてみてください。きっとあなたの欠損こそがこの本と共鳴するはずだから。
近内悠太『世界は贈与でできている』

『悲しみの秘義』は喪失の一冊でした。僕もまた、鬱のさなかほぼすべての能力を「喪失」し、絶望の中でもがきました。
「自分には、何もない。何も持っていないし、何もすることができない」
そんな圧倒的な無力感に打ちひしがれたとき、ぜひこの本を手にとってください。以下、引用します。
「私は何も与えることができない」「贈与のバトンをつなぐことができない」というのは、本人がそう思っているだけではないでしょうか。
宛先がなければ、手紙を書くことはできません。
そして僕らは手紙を書かずには生きていけません。
「宛先としてただそこに存在する」という贈与の次元があるのです。
僕らは、ただ存在するだけで他者に贈与することができる。
受け取っているということを自覚していなくても、その存在自体がそこを宛先とする差出人の存在を、強力に、全面的に肯定する。
人は弱い。人は傷つく。傷つける。その地平から、生きることを考えるのが「弱さ考」です。お付き合いいただける方は、フォローをどうぞ。
執筆:井上慎平
編集:豊岡愛美
デザイン:九喜洋介
編集:豊岡愛美
デザイン:九喜洋介

