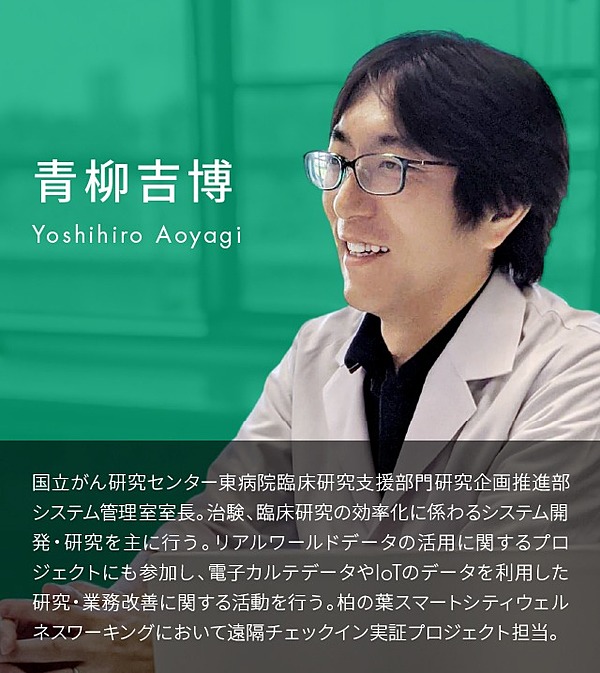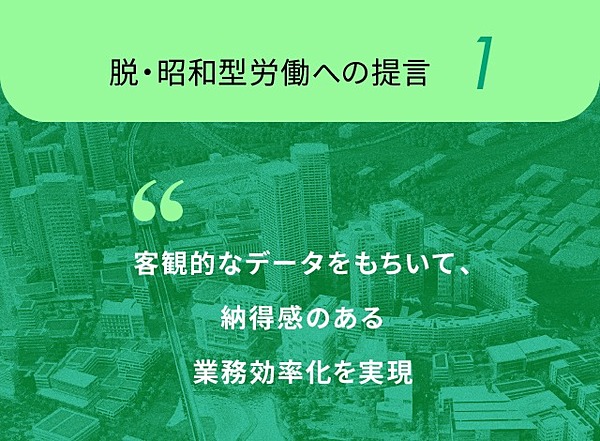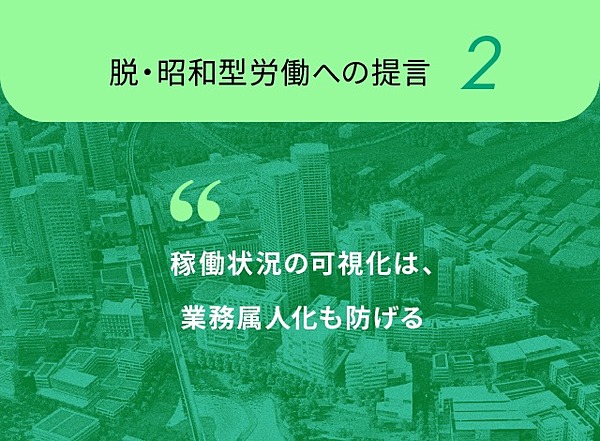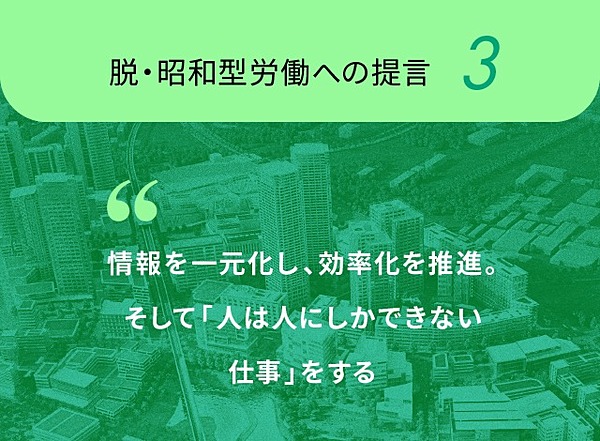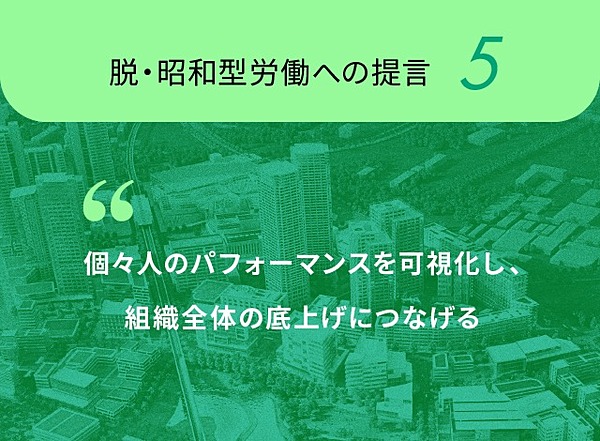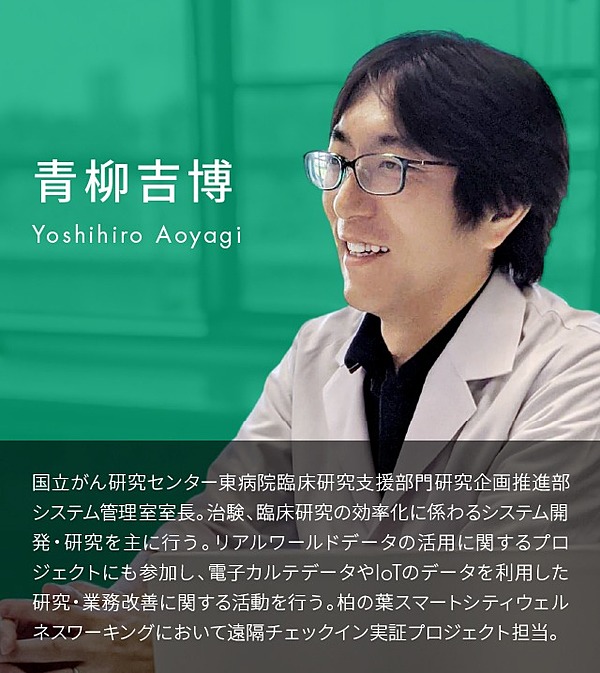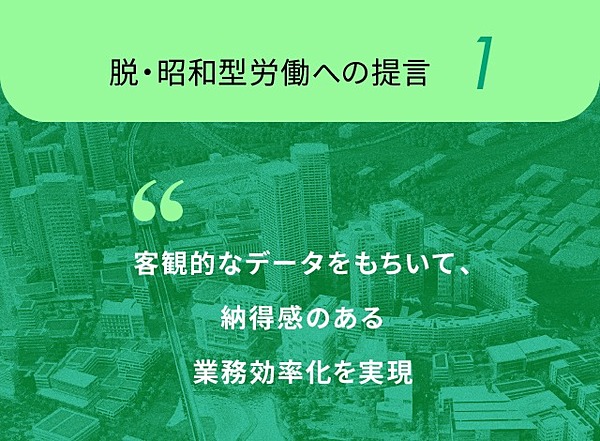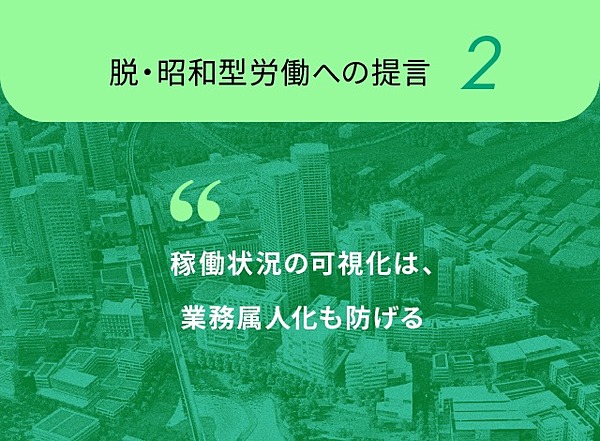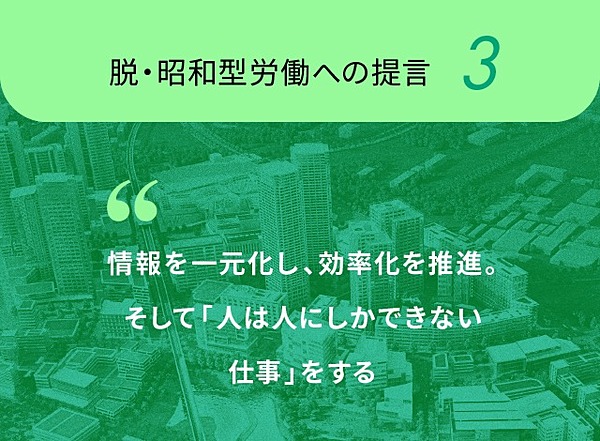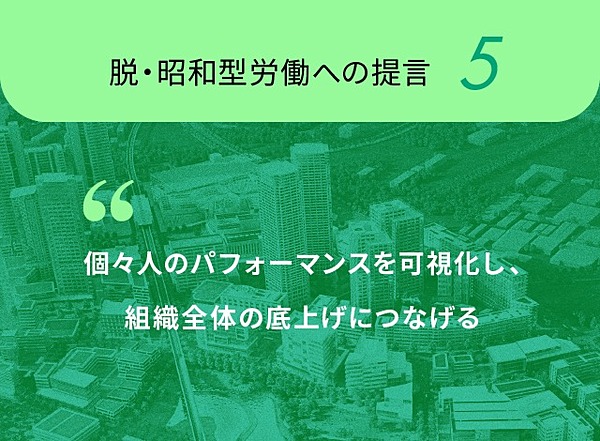「IoT×街」に見る、with コロナ時代のニューノーマルな働き方
2020/9/1
3密回避のカギとなるものは?
国の経済成長に伴い都市に雇用が生まれ、教育や娯楽、医療、情報が集中し、多くの人々が農村部から都市部に移動した。2018年には、世界人口の約55%が都市部で生活をしており、2050年には約68%まで増加すると予想されている。
日本では、特に東京への「一極集中」が問題視されていたが、新型コロナウイルスによって状況は一変。3密を避け、ソーシャルディスタンスを保つ生活が今後数年は続くともいわれるなか、オフィスや飲食店、商業施設、製造現場などは、そのあり方を見直さざるを得なくなっている。
これらの課題を解決するためにも、今まで以上にIoTやDX化などによる業務改善・効率化の必要性が叫ばれている。その最たる例として、スマートシティの取り組みが参考になるだろう。
スマートシティとは、IoTなどの先端技術を用いて、環境に配慮しながら生活の質を高め、継続的な経済発展を目的とした新しい街のこと。
都市部への人口集中によって引き起こされていた大気汚染などの環境問題や、少子高齢化における労働人口減少問題などを、IoTを活用しながら解決する取り組みとして、未来に向けた期待が寄せられている。
今回は、課題解決型都市のロールモデルである千葉県柏市の「柏の葉スマートシティ」を取材。街だけでなく、施設や労働現場をIoT化する意義について解説する。
「公・民・学」連携でつくる柏の葉スマートシティ
柏市は、南部に位置するJR常磐線柏駅が200万人以上の商圏人口を抱える拠点駅として栄えており、柏の葉スマートシティがある北西部は、もともと広大なゴルフ場が広がる場所だった。
1990年代から2000年代にかけて、ゴルフ場の周辺にあった国有地に、国立がん研究センター東病院や政府の研究所、東京大学と千葉大学のキャンパスが作られ、2005年には秋葉原まで約30分で行けるつくばエクスプレスの「柏の葉キャンパス駅」が開業。
2006年には、まちづくりの拠点となる「柏の葉アーバンデザインセンター(UDCK)」が設立、2008年には柏市と千葉県、東京大学、千葉大学により「柏の葉国際キャンパスタウン構想」が策定され、その後三井不動産なども加わる中で「公・民・学」連携の大規模な都市開発が始まった。

2004年頃の柏の葉キャンパス駅周辺。空き地が目立つ。

2015年頃の柏の葉キャンパス駅周辺。タワーマンションなど多くのビルが立ち並ぶ。
そして、社会課題解決モデルの次世代都市になるべく、「環境共生都市」「健康長寿都市」「新産業創造都市」の3つの軸を設定。
国内で初めて、太陽光発電や蓄電池などの分散電源エネルギーを地域内で相互に融通する「スマートグリッド」の運用を始め、地域で約26%の電力ピークカットを達成するなど、省エネルギー・CO2削減を実現させている。
また、新産業創造の取り組みとして、企業規模や業種にかかわらず「AI・IoT」もしくは「ライフサイエンス・メディカル」の2分野での実証プロジェクトを受け入れ、新たな製品・サービスを企業と共に生み出す実証プラットフォーム「イノベーションフィールド柏の葉」を開設した。
地域機関や企業は、そこで具体的にどのような実証実験を行っているのか。国立がん研究センターと柏魚市場の事例を見てみよう。
IoTで業務効率化を実現
国立がん研究センター東病院では、IoTの導入によって院内の看護助手の動線を把握し、業務効率化を実現している。そもそもなぜこの取り組みを検討したのか。背景にあった課題について、同院のシステム開発を担当する青柳吉博氏はこう語る。
「看護師をサポートする看護助手の仕事は、多種多様であるがゆえに、病棟ごとに仕事の仕方が違ったり、属人的で業務タスクがわかりにくかったりする点が課題でした。
看護師や各病棟からの依頼方法もまちまちで、電話や立ち話での依頼ですと履歴が残らないため、把握が難しい。そこで、看護助手の動線を把握して業務改善につなげられないかという話になりました」(青柳氏)
具体的には、看護助手にBLEタグを携帯してもらい、病院内で彼らが移動する場所にルーターを設置。さらに、「いつ・どこで・どの部署から依頼を受けたのか」も並行して調査し、その結果とIoTソリューションのセンシングデータを解析した。
すると、ガバナンスが取れている病棟と取れていない病棟があり、依頼する時間が決まっている病棟もあれば、散発的に依頼をしている病棟もあることなどが可視化された。
「他にも薬剤師の動きを調査した結果、調剤した薬をいつ、どのように受け取りに行くのかも病棟によって違うことがわかりました。
特に、3階の病棟から1階の薬剤部まではかなり移動距離があるため、依頼の仕方によってはどうしても非効率な動き方になってしまいます。でも、業務全体を客観的に可視化できたので、依頼の仕方やタイミングを統一した運用ルールを決めて、効率化を図ることができました」(青柳氏)
データのような根拠がない状態で、一方的に仕事のやり方を変更しても、なかなかうまくいかない。IoTソリューションで業務を可視化し、その客観的なデータを看護助手や依頼する看護師と共有することで、皆で協力しながら業務改善が実現できたという。
「看護助手の業務が効率化されたので、今まで依頼できなかった新たな仕事もできるようになったと聞いています。
看護助手の結果を受けて、今度は看護師の行動を可視化しようという動きがあります。業務を効率化してそれぞれが本来やるべき仕事に集中できるようになれば、病院全体の効率化が実現するはずです」(青柳氏)
後期高齢者が増加し、若年人口と労働力人口が減少する日本は、この先、医療従事者不足の問題に直面する日がやってくる。
そうした課題に対しても、IoTソリューションによる業務実態の把握は有用だろう。医療従事者たちの時間の使い方や業務配分の最適化につなげ、負担が軽減できるからだ。
それが結果的に、患者のケアに充てる時間として還元されれば、患者にも医療従事者にもメリットがある環境づくりにつながる。
「稼働状況を可視化すると、プロセスの見直しだけでなく、業務の属人化などもフラットに解決できると思われます。
医療関係だけでなくあらゆる業種で応用されるのではないでしょうか」(青柳氏)
魚市場はバーチャルでやり取りする「スマート魚市場」へ?
病院と同じく、ITとはほど遠い存在の印象が強い、魚市場。柏の葉スマートシティではこうしたアナログな業界からもAI・IoTによる業務改革を望む声が上がっている。
まちづくりの拠点となる柏の葉アーバンデザインセンターの後藤良子氏は、柏魚市場の社長から相談を受けた日をこう振り返る。
「魚市場の現場は、病院以上にアナログに運営されています。
たとえば、『●●漁港から水揚げされた●●マグロ』という情報は、小さな紙の伝票に手書きで記載されます。そのままマグロを入れた箱に貼り付けられ、セリで卸問屋に買われた後は、手書きの荷渡し伝票をマグロに貼り付ける、という流れで情報管理されます。
そんな柏魚市場の社長から、“漁港から食卓までの魚の情報をどう扱うかが魚市場の未来を左右するかもしれない。IoT化などにも挑戦し、自分たちの道を探りたい”と、魚市場の未来を見据えた相談を受けました」(後藤氏)
魚市場の情報管理業務は大部分がアナログなため、まずは2021年6月から完全制度化される「HACCP(ハサップ)」による食品衛生管理に対応すべく、IoTを使った魚市場内の温度・湿度管理から始めた。
それにより現在は魚市場内の温度・湿度管理を実証できたタイミングだが、これから徐々に漁港から魚市場、魚市場から卸問屋、卸問屋から飲食店へと、さまざまな情報をつなげていく計画だという。
「温度や湿度だけでなく、魚の情報を一元管理できるプラットフォームができたら、将来的に魚市場はバーチャルで完結する“スマート魚市場”になるかもしれません。
さらに、極限まで情報が可視化されるようになれば、たとえば漁師さんが海で魚を釣り上げた瞬間からセリを始めることも可能なはず。
それを適切な管理のもと、効率的なルートで運べるようになれば、魚市場で働く人たちの提供価値はもっと洗練されて、“その人たちにしかできない目利きの仕事”に凝縮されていくと思っています」(後藤氏)
また、人力での仕事がほとんどの魚市場では、競り落とした後の、魚の箱の積み間違いといった人為的ミスも少なからずあるという。しかし、それらの仕事は必ずしも人の手でやる必要はない。
人間だからこそ起こってしまう間違いも、IoTをはじめとしたテクノロジーの力を駆使すれば解決できる。
「こうした、必ずしも人がやる必要のない仕事における人為的ミスの問題は、前述の医療機関や魚市場だけでなく、各種製造業の現場でも数多くあると思います。
技能を必要としないのに、ダブルチェックなどが必要なルーティーンの単純作業は、IoTに差し替えていくべき。そして、人は人じゃないとできない仕事に特化していければ、人材不足の中でもその業界における新たな価値創出につなげられるのではないでしょうか」(後藤氏)
DX化やIoT化がもたらすのは、人が人らしく生きる社会
これからも柏の葉スマートシティでは、テクノロジーを駆使したプロジェクトを進めていくという。目指しているのは、柏の葉スマートシティのエコシステムを、社会普及できるモデルにまで磨き上げること。そのためにも、国立がん研究センター東病院や柏魚市場での課題をしっかりと解決し、他業種や他地域にもノウハウを広めていきたいと、後藤氏は語ってくれた。
また後藤氏は、「現場で働く人が非効率だと思っていても、個人の発言や意見だけでは変えられない習慣や業務フローは、どの業界の企業にも多々あるはず」だと言う。
まさに国立がん研究センター東病院の事例は、一人の意見では変えにくくても、実態を可視化して客観的なデータを全従業員にまで共有することで、組織全体の変革ができると証明したものだ。
「実態を可視化すると、パフォーマンスが高い人がわかります。すると、なぜパフォーマンスが高いのかを分析して、ナレッジ共有できるようになり、全体最適化につながります。
ベテランの知恵をどうやってトランスファーするかは重要な課題なので、その解決にもIoTは役立つと思っています」(青柳氏)
また、不確実性の高いwithコロナ社会においては、働く現場のIoT化を進めることは、以前からの課題である少子高齢化や労働力人口減少だけでなく、3密回避の観点からみても避けられない。
そのなかでも、こうした医療現場や魚市場での例などは、仕組みや考え方はそのままに、視点を変えれば製造や物流など他の環境でも応用できる。
「コロナ禍で、IoT化やDX化は当然進むと思います。人手不足に直面している地域や業界などは、これを機に踏み切るきっかけを得たのではないでしょうか。
IoTの力で、煩わしいと思う業務や、精密さを求められるストレスのある業務から人びとが解き放たれます。そして自由度が増すと、新しいことや創造性の高いことにチャレンジできる時間も増える。
その時間で付加価値を創造できるようになれば、GDPも維持、もしくは向上ができるはず。今後の人口減少社会で、人が人らしく生きていくためには、IoT化やDX化は欠かせないと思っています」(後藤氏)
IoTやDXの力は、企業の未知の課題発見やその解決につながり、ニューノーマルな働き方を生み出すきっかけにもなるだろう。
(構成:田村朋美 取材・編集:川口あい デザイン:板庇浩治)