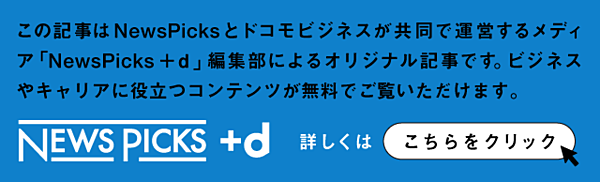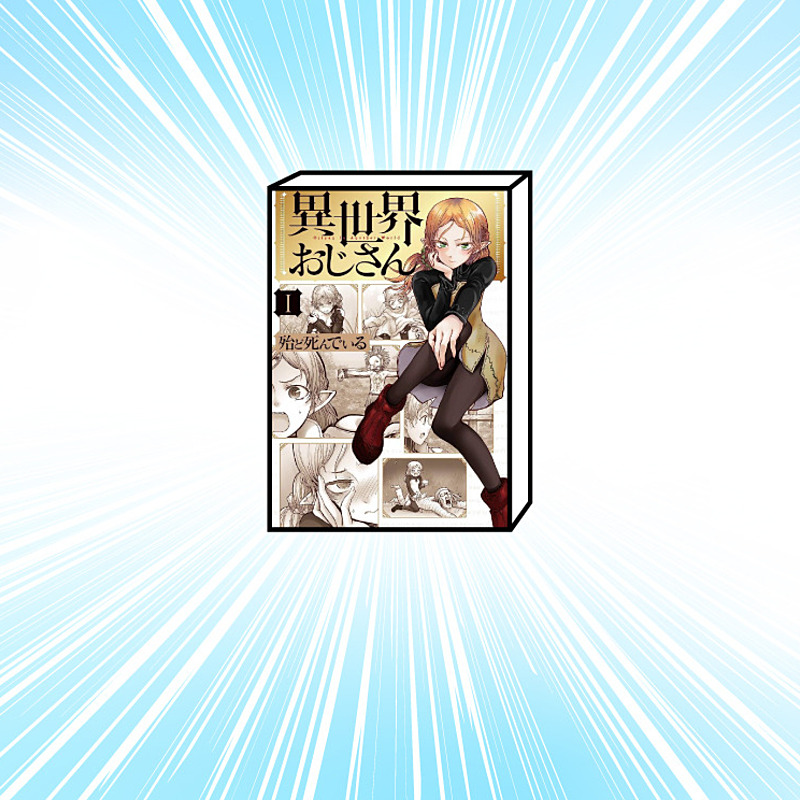
2023/9/23
環境変化に適応できる人、できない人はどこが違うのか
仕事やビジネスを題材にした作品ではないけれど、なぜかその作品には仕事の悩みを解決するヒントや知見があった。人に相談しづらいことでも、共感できるマンガに出合ったことでいつのまにか心が軽くなっていた──。そんな魅力が人気マンガにはあります。
マンガ編集者の経験を持ち、作家業の傍らマンガ原作も手掛ける堀田純司氏がさまざまな仕事の悩みを軽くするヒットマンガを紹介する連載がスタート。
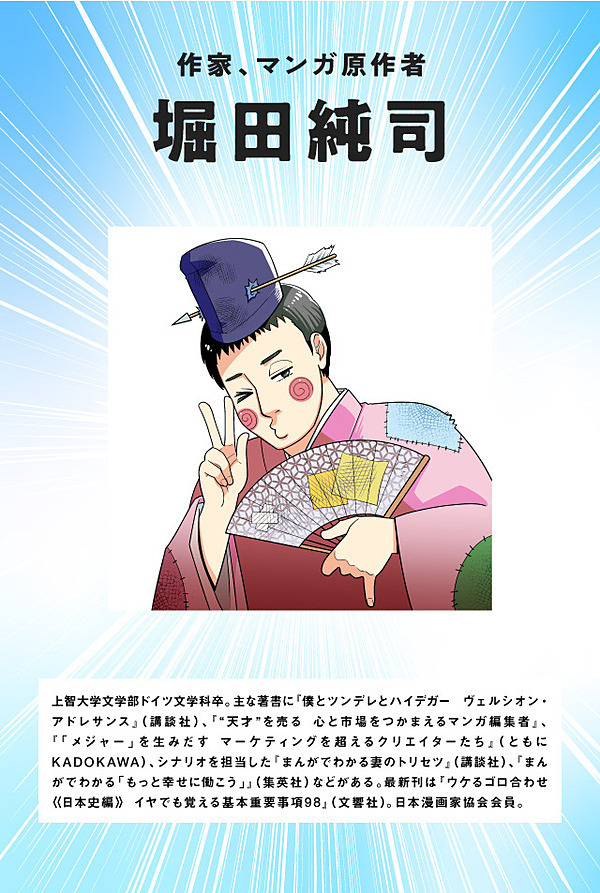
ビジネスパーソンが直面しがちな悩みをテーマとし、堀田氏ならではの視点で多角的に分析します。きっと悩みを解きほぐし、ブレークスルーをもたらしてくれるはず。
INDEX
- 異動や転籍、転職や独立より激しい変化。「異世界転生」
- 中心教義はチート能力を手に入れて“無双”
- 異世界でうまくいかなかったのはなぜか
- マイノリティーの弱さが強さになることもある
- 異世界に期待する人は現世に絶望しているのか?
異動や転籍、転職や独立より激しい変化。「異世界転生」
ビジネスパーソンにとって、働く環境の変化は避けて通ることのできない道。異動や転籍、さらには転職や独立。自分自身の選択の結果であったり、あるいは会社からの要請であったりと、その理由はさまざまですが、変化はつきものです。
同じ業種でも企業が違うと文化の違いは大きいし、そもそも同じ会社の中でさえも、部署が違うと風土が違っていたりする。当初は戸惑うこともあるでしょう。
こうした「環境の変化」の中でも、もっとも劇的な変化が「異世界への転生」であることを、疑う人は少ないのではないでしょうか?

FangXiaNuo / iStock
「異世界転生」とは、文字通り、私たちが暮らすこの世界から異なる世界へと生まれ変わること。
ただ外国に移住するのではなく、根本から異なる摂理の世界、たとえば「剣と魔法のファンタジーワールド」のような、人の想像力が生み出した世界の住民となることです。
そうした異世界に「生まれ変わって活躍する」という物語が、現在の日本のキャラクタービジネスでは花盛り。
それが決して一過性のブームではなく、もはや長らく支持される定番、Standard productとなっている状況は、おそらくみなさまも耳にして、あるいは目にしていらっしゃることでしょう。
こうした物語がもはやひとつの定番ジャンルとなり、長く支持されている。そうした状況の背景には、日本社会の現実のなにかが反映されている。
それだけに「異世界転生もの」の中には、ただ娯楽であるだけではなく「環境変化に適応できる人、できない人はどこが違うのか」という知見を、切実に伝えてくれる作品もあります。
たとえば「殆ど死んでいる」氏作の『異世界おじさん』というマンガもそのひとつ。この作品は2018年からマンガ配信サイト「ComicWalker」で連載が開始。その後、単行本9巻の時点で330万部を突破し、アニメ化もされるヒット作になっています。
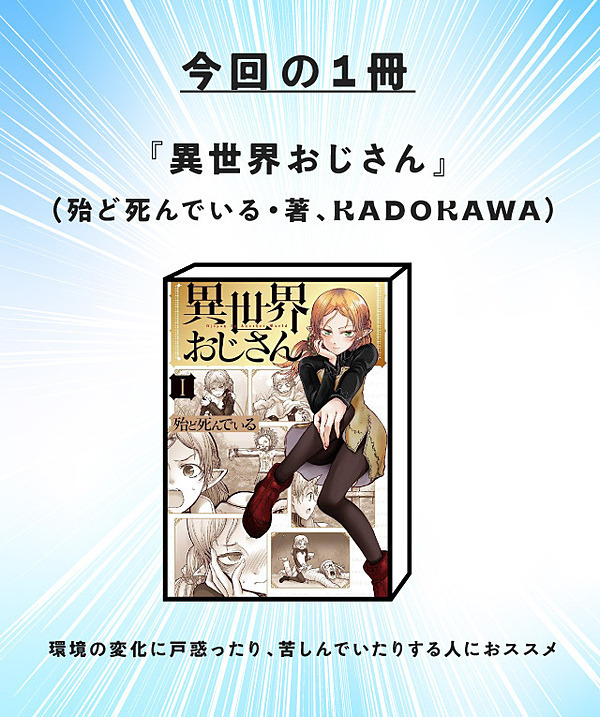
中心教義はチート能力を手に入れて“無双”
「現世を離れて、ファンタジーの世界で英雄になってみたい」。こうした願望は決して日本固有のものではなく、世界的に見られます。たとえばアメリカの作家、エドガー・ライス・バローズ(あの「ターザン」の作者です)の「火星シリーズ」。
この作品では元南軍の軍人、ジョン・カーターがある日とつぜん火星へと転移してしまう。火星は地球よりも重力が小さい。
そのためカーターは、現地で超人的な身体能力を手に入れることになり、本来は戦争の終結とともに失職してしまった彼が、お姫さまと結ばれ、家族を持ち、ついには火星の頂点に立つ偉大な存在にまで上りつめていく。
彼が火星で手に入れたようなパワーは、日本の「異世界転生もの」においても非常に重要で、一般に「チート能力」と呼ばれます。
チートとはもともとだます、ごまかすといった意味の英語。ゲームの世界では「システムの裏をかく」といったニュアンスで使われてきました。
そのチート能力は、カーターのような身体能力、あるいは魔法などダイレクトに戦闘に役立つ力の場合もありますが、現代社会で身につけた政治経済のタクティクス、価値観、ビジネススキルなどが、いまだ古い社会構造にある異世界を改革する、大きな武器になることもあります。
「チート能力」とは
作品内のキャラクターが備える、現実にはありえないズバ抜けた能力や特別な技のことを指す。向かうところ敵なしの主人公が活躍していくストーリーに必須。
作品内のキャラクターが備える、現実にはありえないズバ抜けた能力や特別な技のことを指す。向かうところ敵なしの主人公が活躍していくストーリーに必須。
たとえばカルロ・ゼン氏作『幼女戦記』では冷徹な合理主義者のエリートサラリーマンが、同僚に恨みを買って事故に遭う。
そして20世紀初頭の欧州に似た戦場に「少女」として転生してしまいますが、その世界で「彼女」が頭角を現す理由は、前世の記憶。サラリーマン時代のビジネス思考が戦局の予想に役立ち、戦略にも生きることになる。
もっともこうしたキャラクターはどちらかと言えば例外で、主流はやはり平凡な主人公。中には「理不尽な孫の手」氏作『無職転生』のように「34歳まで無職だった」という転生者もいます。
特に並外れた資質があるわけではない。そんな平凡な人物が、転生することで世界をひっくり返す「チート能力」を手に入れる。そして非凡な大活躍を見せて(これもゲーム由来のスラングで「無双する」と呼ばれます)、勇者として尊敬されることになる。
これが「異世界転生もの」の中心教義。
こういうと「男性オタク向けか」と思われるかもしれませんが、実は「異世界転生もの」は女性にも大人気で、あちらはあちらでごくふつうの女性が転生して、異世界でイケメン魔族たちに愛されたりしています。
(こうした状況について、筆者の友人の女性向けマンガ誌編集者は「男性は異世界で暴れまくり、女性は異世界でモテまくり」と表現していました)
異世界でうまくいかなかったのはなぜか
かくも百花繚乱の「異世界転生もの」ですが、その中でも『異世界おじさん』は異色の作品です。
この作品の主人公は、17歳、高校生のときに事故に遭遇し、以来17年間昏睡状態にあった「おじさん」と、その甥のたかふみ。
事故は2000年1月。2017年の秋に目覚めたおじさんは、正気を失っているように見えた。
昏睡状態にあった期間、自分は剣と魔法の異世界「グランバハマルにいた」と、たかふみに語る。
暗い表情になるたかふみだが、おじさんは彼の目の前で実際に魔法を使って見せる。マジかよ!?
たかふみはおじさんと同居し、とりあえずYouTuberとして生計を立てていくことにした。と、ここまではよかったのですが、問題はおじさんの「異世界生活」でした。
たかふみもやはり現代の若者。彼自身、異世界ファンタジーの大ファンで、おじさんの冒険を胸をときめかせながら見せてもらうのですが(魔法を使って映像的に見せてくれます)、その内容は悲惨。
異世界の住民はみな容姿が整っている。
そうした中、ごくふつうのオタク少年だったおじさんの容貌はよほど醜く見えるらしく、オークと間違えて狩られてしまうのはお約束。
よかれと思って村のために水を生成するインフラを整えてあげても、宗教的タブーにふれてしまったらしく、やっぱり狩られてしまう。
一方、おじさんのほうにも問題がありました。現在、家庭用ゲーム機のシェアは任天堂とソニーの寡占状態にありますが、かつては他にも競合するメーカーがありました。
おじさんは(今となっては)そのマイナーメーカーのゲーム機のファンで、人生経験はほぼゲーム。初恋の人もゲームキャラ。学んだ人生の知恵もぜんぶゲーム。しかもそれは現実の歴史の中で過去のものとして忘れ去られる、“古い"ゲームの知識でした。

Roman Prysiazhniuk / iStock
要するにおじさんは、異世界生活に適応するための、柔軟性に欠けていた。深刻なカルチャーギャップと、ジェネレーションギャップというふたつの課題を解決するだけの柔軟性に欠けていたのです。
そのため、せっかく自分を助けてくれるエルフの好意に気がつかなかったり、竜を倒すための秘剣を手に入れることをせず、ダイレクトに直接倒してしまったりする。
うまく他者と協調することができず、自分から苦労している面がありました。
マイノリティーの弱さが強さになることもある
そもそも、転生するにあたって、せっかく全能に近い魔法の力を獲得しておきながら、自分を変えようとはしなかった。容姿を変えることもしませんでした。
「もっといろんな経験を積んで糧としておかないと、環境の変化に対応することはできない」
それがおじさんが伝える最初の知恵です。
ただ、人間の弱点と長所は裏腹で、弱さが強みになることもある、という真理も彼の異世界生活は教えてくれます。
もともと子どもの世界の流行に多様性は希薄。勝ち組が一気にシェアを占有してしまうゼロサムゲームになってしまうことは有名です。
これが大人になるにつれて「いや、俺が乗るのはあくまでカワサキのバイクだから」みたいな人が現れて「第三勢力」もある程度、シェアを確保できるようになるものですが、自我が未分化な子どもの世界では寡占化が進む。
しかしおじさんは、もともとマイナーゲームのファン。孤立を恐れない、個人行動の人でした。
過酷な異世界生活を生き抜くことができたのは、こうしたメンタリティーがあってのこと(つらい記憶は魔法を使ってすぐ消去していた、という面も大きいのですが)。
もしおじさんがスクールカースト上位の陽キャであれば、すぐに心が折れていたかもしれません。
しかし、もともとマイノリティーの彼は環境の変化を耐え抜くことができました。
いざ激変が起こったときに、マジョリティーは同じ原因で全滅してしまう。しかしマイノリティーは生き延びることもある。
柔軟性も大事だが、自分だけのポリシーも大事。
弱点と長所は同じコインの表と裏。
おじさんの冒険は、こうした知恵を示唆してくれます。
もしあなたが環境の変化に戸惑ったり、苦しんでいたりしたら──。読んでみるのもおすすめです。
異世界に期待する人は現世に絶望しているのか?
しかし、今の「異世界転生もの」の隆盛を見ていると、複雑な思いを抱くところもあります。みんなそれほど異世界に憧れているのか?
つまり逆にいうと、それほどみんな現世に絶望している。「現世ではどんなに努力しても報われることはないと感じているのか?」と。
もしそうだとしても無理はないです。現実世界は混沌としており、未来は見えない。世界は複雑で、なにが真実でなにがフェイクかという境界もあいまい。
そして格差は拡大する一方で、もし「親ガチャ」に外れてコネのない「一般国民」に生まれてしまったら、浮上は「無理ゲー」になる。
もしそう感じるだけの現実があるなら、人々が異世界への転生を望むのも無理はないことでしょう。
異世界ならば誰でも成功できる。今どきの情報商材的なウリ文句でいうならば「成功するのにセンスも、努力もいらない。誰でもかんたん英雄生活」といったところでしょうか。
もっとも、『異世界おじさん』のような「異世界に行ってもつらい現実が続く」という作品がヒットするということは、言うほどみんな心の底から異世界にハマっているわけではないのかもしれません。
ミゲル・デ・セルバンテスの小説「ドン・キホーテ」の主人公は、騎士道物語にハマりまくったあげくに現実とファンタジーの境界を見失い、風車小屋を魔物に見立てて突撃することになりました。

Kerrick / iStock
しかし現代の読者は、ファンタジーのお約束を共有し、楽しんでいるだけで、そこまでどっぷりハマっているわけではないのでしょう。
<POINT>
・周囲に合わせてアップデートせず、変なこだわりを捨てないと“浮く”
・柔軟性がないとカルチャーギャップ、ジェネレーションギャップを超えられない
・とはいえマイナス感情やストレスはチート的に消去してもいい
・マイノリティーゆえの強さで生き延びることも
・周囲に合わせてアップデートせず、変なこだわりを捨てないと“浮く”
・柔軟性がないとカルチャーギャップ、ジェネレーションギャップを超えられない
・とはいえマイナス感情やストレスはチート的に消去してもいい
・マイノリティーゆえの強さで生き延びることも
執筆:堀田純司
イラスト:瀬川サユリ(堀田氏プロフィール)
デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)
編集:奈良岡崇子
イラスト:瀬川サユリ(堀田氏プロフィール)
デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)
編集:奈良岡崇子