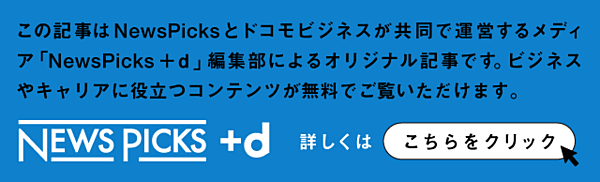2023/2/18
【新潟】ワクチン運搬庫、世界に先駆け量産化したウルトラC
新型コロナウイルス感染症のワクチンを、厳密な温度管理をしながら運搬・保管する専用冷凍庫「ディープフリーザー」。その製造元として全国的に知られることになったツインバード(本社・新潟県燕市)は、“金属加工のまち”新潟・燕三条地域にある社員300人の中堅家電メーカーです。
世界の大企業がこぞって研究して量産化できなかった技術を、なぜ地方のイチ家電メーカーが実現できたのか。そして、世界的パンデミックの真っただ中でワクチン運搬庫の大量生産をどう成し遂げたのか――その秘密に迫ります。(全3回)
世界の大企業がこぞって研究して量産化できなかった技術を、なぜ地方のイチ家電メーカーが実現できたのか。そして、世界的パンデミックの真っただ中でワクチン運搬庫の大量生産をどう成し遂げたのか――その秘密に迫ります。(全3回)
INDEX
- 国からの生産依頼に「決断」
- 「独自技術こそ製造業の未来」
- 5期連続赤字でも貫いた信念
- 海外展開する「ディープフリーザー」

野水重明(のみずしげあき) 1965年新潟県生まれ。ツインバード2代目社長・野水重勝氏の長男。出生地の燕三条地域で高校卒業まで過ごす。工学院大学(東京)卒業後、ツインバード入社。大手都市銀行に3年間出向し、長岡技術科学大学大学院で工学研究科情報制御学を専攻、博士号取得。海外勤務、営業、経営企画などを経て2011年に3代目社長に就任。現在、同社のリブランディングを推し進めている。
国からの生産依頼に「決断」
幅695ミリ×奥行き350ミリ×高さ460ミリのクーラーボックスのような機械――それが、ツインバードが新型コロナウイルスワクチンの運搬・保管用に、従来機をベースに新しく開発した「ディープフリーザー」です。重さ16.5キロとコンパクトサイズでありながら、1℃単位でマイナス40℃まで温度制御が可能。なにより、揺れや衝撃に強いというメリットがあります。
この夢のような機能を実現させたのが、搭載されている冷却機「フリー・ピストン・スターリング・クーラー(FPSC)」です。ツインバードは、FPSCの商用量産化に向けた技術開発を世界に先駆けて成功し、その技術を特許登録しています。

新型コロナワクチンを運搬する専用冷凍庫「ディープフリーザー」
「来年の2月までに1万台納品してください」――厚生労働省からディープフリーザーの生産依頼があったのは2020年夏のことでした。当時、新型コロナウイルス感染症が世界中に広がるなかで、日本国内のワクチン接種は大きく遅れていました。
ワクチンを国内に行き渡らせるためには、コンパクトで高性能な冷凍庫が必要。国にとって、その体制を整えることが急務でした。そこで白羽の矢が立ったのが、革新技術を持つツインバードだったというわけです。
しかし、それは地方のイチ中小企業にとって“無理難題”でした。野水重明社長が、当時を振り返ります。
「2カ月程度で生産設備を整えるとして、逆算すると納期まで4カ月程度。それまでの生産能力は年間3000台ぐらいですから、4カ月で1万台となると通年で約10倍、ケタ違いです。短納期というか、台数が多すぎるというか……だから、厚生労働省に呼ばれて行ったときも、最初は『無理だ』と伝えたんですよ」
新しく工場を造る時間はないため、既存の倉庫を改修して専用設備を導入するのに数億円。さらに、協力企業に緊急で莫大な量の部品を発注し、納期を通常より早めてもらい、生産人員も確保しなければならない。何兆円という売り上げのある大会社ならまだしも、年間120億円程度の売り上げ規模の会社で、それだけの設備投資や部品代、人件費のリスクを負うことは無理、というのが経営者としての判断でした。

それでも、厚労省からは「1億2千万人の命を守るためにやっている。唯一無二の技術なので、ツインバードしか作れない」と強く説得されました。もちろん、できることならやりたい。しかし……心の中で葛藤しながら、自社に持ち帰って役員や社員に相談したところ、「やりましょう」と全員の意見が一致。
「長年苦労してきた技術で、世の中のお役に立てるときが来たのではないか。リスクはあるけれど、二度とないチャンスじゃないか」
社内のこうした声に後押しされ、野水社長は重い決断をしました――。
「独自技術こそ製造業の未来」
新潟の家電メーカーであるツインバードに、なぜ最先端のFPSCの技術があったのか。それは1990年代、野水社長の父である先代の2代目社長・重勝氏が、シャープ元副社長で工学博士でもあった故・佐々木正氏から助言されたことがきっかけでした。
「家電もいいけれど、やはり製造業がもっともっと世の中のお役に立ち、成長することを考えるのであれば、唯一無二の独自技術を持つべきだ。技術のない製造業に未来はない」
佐々木氏は、シャープを世界的な電機メーカーに育て上げ、孫正義氏やスティーブ・ジョブズ氏に助言をしていたことでも知られる“レジェンド”。その佐々木氏がツインバードに勧めたのが、「ナノテクノロジー」か「スターリング・クーラー」の技術開発でした。
「当社はその当時、ペルチェ素子という半導体素子を使ったクーラーボックスを手掛けていました。業界としては先駆的な試みでしたが、電気代がかかるわりに氷が作れないなど効率に課題があった。そこで、スターリング・クーラーの技術を応用しようと先代社長が判断したんですね。最初は一般家電製品の冷却装置として着目したんです」(野水社長)

ヘリウムガスが充填されたシリンダーの中にある2つのピストンが、異なる周期で往復運動してガスを膨張・圧縮させることで冷却するFPSC。この基本原理は1816年、スコットランドのスターリング博士が発明しました。優れた冷却技術でありながら、量産化には技術面やコストなど課題が大きく、大手企業が商品化に失敗してきた歴史があります。
ツインバードが1998年にスタートした量産化への道のりもまた、困難を極めました。
「それまで小型家電のアイデア商品を企画・製品化してきましたが、コーヒーメーカーであればヒーター、電子レンジであればマグネトロンといったデバイス自体の開発は初めて。つまり、まったく違うアプローチだったということです。家電エンジニアの優秀な人材を20人以上抜擢して技術チームを編成しましたが、開発ノウハウもなく、技術的ハードルも高かったので、投資も時間もそうとうかかりました」(野水社長)
なによりも大きな課題は、求められる金属加工と組み立て技術の精密さでした。開発担当のSC開発製造部の小川利明部長が言います。
「ピストンとシリンダーの隙間がミクロン(0.001ミリ)単位。さらに、金属1枚を必要な深さまで正確にプレスする『深絞り成型』など、非常に精密な部品加工が必要になる。これを解決したのが、地元の燕三条地域に蓄積された“ものづくり”の高い技術力でした」

サンプル模型で説明する小川利明部長
地元企業と力を合わせ、この地域ならではの精密加工技術を活用しながら、試行錯誤の末、2004年に量産化技術が実現しました。
5期連続赤字でも貫いた信念
2000年に東証2部に上場したツインバードにとって、さらなる飛躍となる開発の成功――しかし、問題はそこからでした。量産化ができるようになったにもかかわらず、予想通りに利益を生まなかったのです。さらに理論上、計算した通りの性能が、実機ではなかなか実現せず、試行錯誤を繰り返すことに時間が費やされました。
時期を同じくして、1990年代から中国、韓国の家電メーカーが世界シェアを伸ばし、それまで成長を続けてきた日本メーカーは衰退の兆しを見せ始めます。ツインバードの家電事業も低迷し、かたや開発コストのかかったFPSC事業も利益が出ない。結果、5期連続で最終赤字に。
社内では「まだこれを続けるのか?」と議論になり、金融機関からは事業撤退を迫られました。それでも継続したのは、「この技術は絶対にツインバードの柱になり、世の中のお役に立てるという先代社長の強い信念があったからでしょう」と野水社長は語ります。
「赤字が続いてもブレませんでした。これは、うちだけの教訓ではありません。新しい事業に取り組むときには、強い信念と覚悟を持ったリーダーが先陣を切って困難を突破しなくてはいけない。苦しくても、諦めてしまったら新しいモノやコトは生み出せません。当時の状況で、私も経営者として同じことができるかと考えると……難しいかもしれませんね」

(提供:ツインバード)
“諦めなかった”背景には、まだ数字としては表れないニーズへの“手ごたえ”がありました。国内外から継続的にサンプル購入の問い合わせがあったことからも、市場ニーズを「感覚的につかんでいた」と野水社長は話します。先代社長たちの苦労に報いるためにも、事業の黒字化を早急に図る必要がありました。
問題のひとつは、開発チームが「ガラパゴス化」していたことでした。投資先行で赤字が続くなかで社内の意識が変わり、外部の市場環境も変わる一方、周囲の“進化”に取り残されていたのです。野水社長は、これらの課題を洗い出す特別チームを結成、市場ニーズを受け止める体制をつくっていきました。
その結果、FPSCは2009年、製造業に携わる優れた企業や技能者を政府が表彰する「ものづくり日本大賞」の特別賞を受賞。さらに転機となったのは、2012年に宇宙航空研究開発機構(JAXA)から宇宙用冷凍・冷蔵庫の開発依頼を受けたことです。社内で開発体制を構築し、宇宙で使うための条件をクリアするために地元企業や外部試験機関の協力を得ながら、約10カ月で実現にこぎつけます。

開発した宇宙用冷凍・冷蔵庫「FROST」は2013年、JAXA国際宇宙ステーション「きぼう」で稼働。「地方の家電メーカーが宇宙用冷凍・冷蔵庫を開発するとは、まるで小説『下町ロケット』そのものだ」と日本中で大きな話題になりました。
そうして2014年、FPSC事業は初の単体黒字を果たしたのです。
海外展開する「ディープフリーザー」
新型コロナのパンデミックという国難を救うため、ワクチンを運搬・保管するための冷凍庫「ディープフリーザー」の大量生産に乗り出したツインバードですが、もちろん簡単にことが進んだわけではありません。生産の陣頭指揮にあたったのは、前出の小川SC開発製造部長。「品質と納期は絶対でしたから、プレッシャーは相当なものでした」と言います。
部員を7人から35人まで増員し、アイデアを出し合いながら3週間で新たな生産設備を整備すると、野水社長以下、役員や担当者が県内外の協力企業を訪ね、納期短縮をお願いして回りました。こうして2020年11月までに増産体制を構築し、2021年2月にディープフリーザー5000台を厚生労働省に、4月に製薬会社へ5000台を納品することができたのです。
ディープフリーザーの大量受注によって、ツインバードのFPSC事業の規模は10倍以上に拡大、2020年度に約7億円、21年度に約9億円の営業利益を出して会社全体の収支も黒字回復しました。好業績を受けて、同社は「次の成長ステージ」を見据えています。

(提供:ツインバード)
ワクチン輸送ボックスは、アジア・アフリカ地域への海外展開も進んでいます。すでに国際協力機構(JICA)を通じて2021年6月には東ティモールへ、2022年4月にはモザンビークへ納品しました。
さらにコロナワクチンだけでなく、抗体医薬品、細胞治療薬など治療薬の「コールドチェーン構築」への事業拡大、そして、省電力・低排熱・フロン不使用というFPSC技術の特徴を生かした“環境に優しい冷却装置”としての売り込みも進めていく計画です。
「1万台増産」のために緊急の要請にもかかわらず、迅速に対応してくれた地元の協力企業は約30社。ものづくりのまち・燕三条地域だからこそできた体制です。野水社長は力強く語りました。
「ディープフリーザーには、この地域の技術が結集しています。この製品によって、燕三条地域や新潟県自体のプレゼンスを高めることに貢献できたのならうれしいですね」
※Vol.2に続く
取材・文:本間千英子
撮影:高橋信幸
編集:鈴木毅(POWER NEWS)
デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)
タイトルバナー:高橋信幸
撮影:高橋信幸
編集:鈴木毅(POWER NEWS)
デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)
タイトルバナー:高橋信幸
地方の家電メーカーが奮闘
コロナワクチンを全国に届けた冷却技術