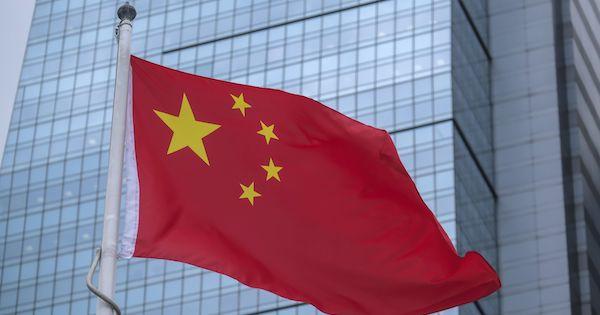中国がコロナ規制緩和、隔離期間短縮-本土・香港株急伸
コメント
注目のコメント
ざっくりと「海外入境者の隔離が10日から8日」と
ありますが、正確には以下になります
・①1次濃厚接触者/海外入境者は「7+3」→「5+3」
-つまり変更後は「5日の集中隔離+3日の自宅隔離」
(但し出張者は自宅がないため、8日の集中隔離)
・②2次濃厚接触者は「0+7」→ 管理せず
①は私たちのようなクロスボーダーで動く人間には
もちろん嬉しい限りですが、純粋な国内事情で言うと、
実は②のインパクトがかなり大きい気がしています
・1人の陽性者が、数千〜数十万人の自宅隔離を生み、
正常な経済活動に影響していたのはまさに②の方
海外からすると「まだやってるの...?」という感じが
否めないしょうが、中に身をおく者としては、ひとまず
嬉しい限りです
(逆方向に向かっている印象に怯えている方々もいたと
思いますが、ひとまずその懸念も払拭されたのは
良かったかと思います)
引いて見ると、過去2年は相当に良かった、今年は散々、
今後は時間が味方して収束
全期間が良かった地域は殆どなかったわけで、快適さを
かなり先取りしたグループはもう少しだけ我慢ですね...数日前から規制緩和のうわさが流れていましたが、正式に発表されました。
我々外国人にとっては水際対策が気になる所で、隔離期間は8日間(5日ホテル+3日自宅)になり、若干の緩和となりました。
朗報ではありますが、私のようなローカルで働く人間にとって最もつらいのが高止まりしている航空チケットです。往復旅券費+隔離ホテル費+入国手続き費(PCRなど)を合わせると、コロナ前の数倍となっています。特に北京往復は高いです。
会社が費用を負担してくれる駐在員と異なり、自腹で買うにはあまりにも高すぎて手が出ません。当分帰れそうにないです。健康コードのポップアップで上海に一か月以上も滞在しています。
仕事などはすべてテレワークできるわけではなく、ほんとうにたいへんな一か月でした。
しかも今もまだ継続しています。
いつ帰れるかわかりません。
緩和する双ですが、帰れない日が継続しており、どこまで緩和されるか不明です。