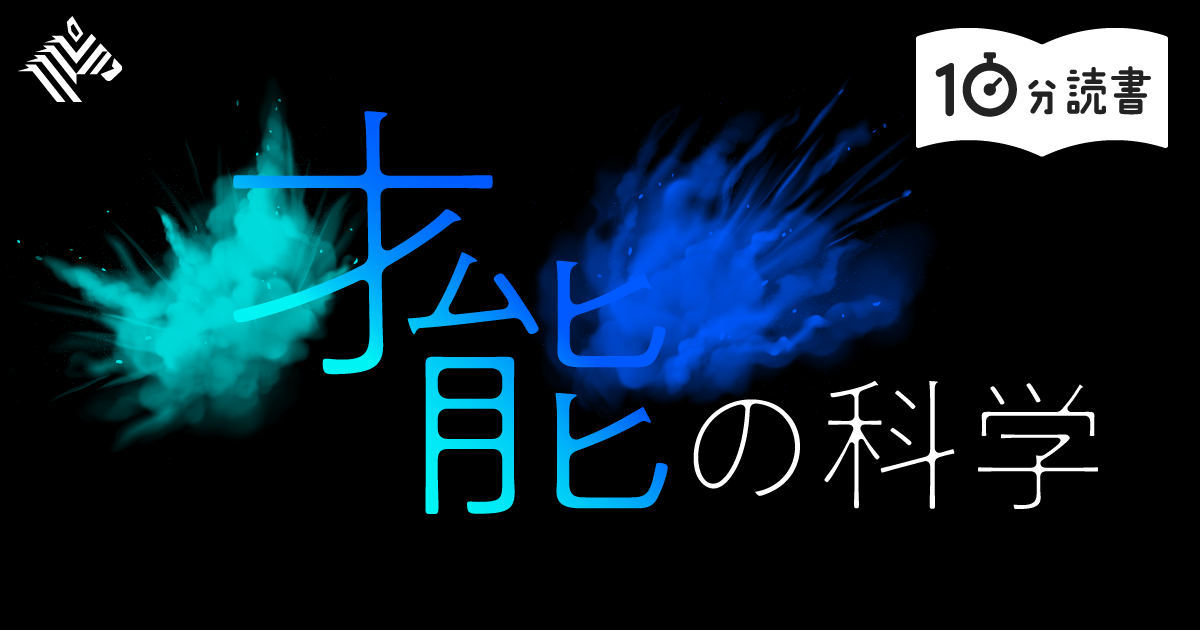【読書】生まれつきの「才能」より重要なものとは何か
コメント
注目のコメント
生まれ持った才能はあるものの、どれだけ頑張ったかで違いが出ることに、とても共感します。一方、頑張ってる人はどれだけ頑張っているかをあまり自己開示しないので、周りが気づかないのも事実です。だから、生まれつきの才能だと誤解しやすい。
例えば、プレゼンが苦手な人は、得意な人のことを「人前で話せる能力があるから」と片付けがちですが、意外と人一倍の事前練習をしっかりしています。どれだけの量の事前練習をしているかに気づくと、ハッとさせられるもの。
20代でアメリカ留学時、夜中まで大学の図書館で多くの学生が勉強している姿をみて、「母国語のアメリカ人ですらこれだけ勉強しているなら、自分は倍しないと!」と、ハッとさせられ猛反省したものです。
コツコツ努力をしている人は、努力の量を自己開示しないケースが多いので、そのことにいち早くどう気づくかが大切ですね。自分の努力次第で、道が開けることほど素晴らしいことはありません。可能性の扉の鍵は、自分が持っていますね。先日の「生まれが9割」と相反するような本を取り上げるのがニクイですね。
https://newspicks.com/news/7694798/body/?ref=user_4982505この記事と全く関係ない発言をお許しください。
私は若い方に向けて講演するチャンスが有るときには「人脈と体力」とずっと言い続けています。(もうすこし多く言っていますが)
AIの時代になろうと、一緒に仕事をする相手は人間です。全てがネットで完結しバーチャルなつながりだけでも生きていけるように見える時代の中で、自分自身は人脈はとても大事だと思います。私自身、人のつながりによって様々なチャンスを貰ったり助けられたりしてきました。自分が助けてあげられたこともあります。
そして、体力は言わずもがな。世界で活躍している人は皆さんビックリするくらいタフです。これは生存者バイアスがかかっており、才能があってもタフでない人が振り落とされた結果なのではないかと思っています。なので、学生に対しては「いま部活やサークルで運動をしている人は是非ずっと続けて。そうでない人も心配しないで。いまから始めればいいから。」と言い続けています。そんな偉そうに言う自分は大道芸サークルとアマチュア無線部だったので、運動しない典型でしたが。いまはカレンダーに運動のための時間を先に確保するようにしています。