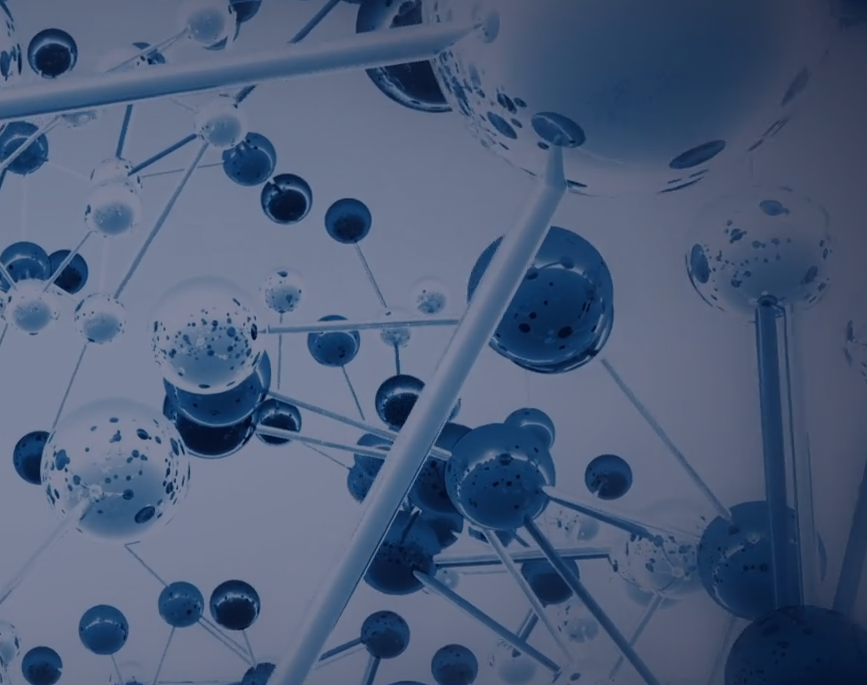
旭化成ファーマと最大359億円のライセンス契約した創薬スタートアップの正体
コメント
注目のコメント
記事に書かれているように、低分子医薬品の多くは「先発薬を改良」するイメージで作られますが、それらは「改良型医薬品」とも呼ばれます。先発薬とまったく同じ化合物の合成法を見出して作るジェネリックとは異なるものです。
一般には有望な多種類の化合物を大量に合成し、次いでそれをスクリーニング(ふるい分け)する方法で作ります。この創薬ベンチャー企業は、そのプロセスにノウハウを有する元製薬企業の研究者の方が創業しています。このカテゴリーの場合、バイオ医薬品のようにハイリスク、ハイリターンまではいかず、リスクもリターンも若干低めのミドルレンジを攻めます。
かと言って商品化に至る道のりは決して簡単ではありません。第1に先発薬がある場合、改良型は何かしらの点で優れる点に関する科学的データを出さないと認可されないためここを乗り切るアイディアと幸運が必要です。第2に一般論ですが化合物ができた後の臨床試験、ベンチャーで言うところの「死の谷」を乗り越える資金力が必要です。途中で資金が枯渇すればすべてが消えることになります。製薬企業とのライセンスは、このステージを乗り越えるために行われているはずです。紹介されている企業のステージからですと、臨床第1相試験から製品化までに予想される期間は最低でも5年、書かれている降圧を目的とする医薬品の場合は大規模な臨床試験が求められるはずですので、完成まで行く場合は数百億円の費用がかかる可能性があります。これを大企業側が負担し、完成すれば企業側にライセンスが移る代わりにベンチャー企業にマイルストーンが支払われるスキームが一般的です。
臨床試験には、改良型の場合は全体としては先発薬に劣らないなか特徴としての優れる点を出さないと認可に至りません。一方ジェネリックは先発薬との同等性を示す必要がありますが、主たる臨床試験は求められません。
製薬企業は、近年は自社の研究開発機能を縮小しています。それは企業内で実施するとリスクヘッジができないことと、コスト高になる傾向があるためです。研究者にとって製薬企業である程度の報酬を約束されながら自由な研究をする「企業内研究者」という職種はいまや狭き門です。逆に研究ベンチャー創業のチャンスが増えていると言えるかもしれません。アークメディスンは2019年にエーザイからカーブアウトした企業です。
代表取締役社長の田中圭悟氏がエーザイで23年間創薬合成に従事される中で業務の傍ら新規創薬合成プラットフォーム「HiSAP® (ハイサップ)」を開発していたことから設立されました。
今年後半から来年にかけて数十億円規模の資金調達を行い、24年のIPOを目指しているようなので、今後さらに注目されるスタートアップになりそうです。
アークメディスン:https://alchemedicine.com/
旭化成ファーマとのライセンス契約について:https://alchemedicine.com/upload_files/news/1654657319_9821.pdf
