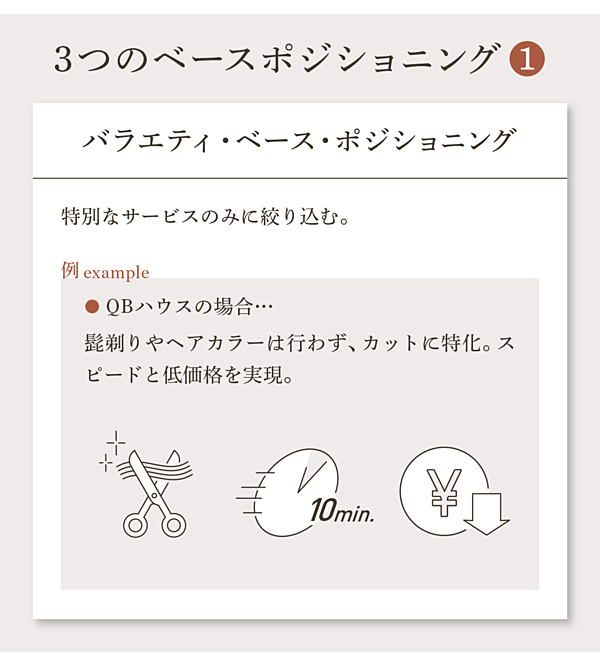2022/5/13
そこに正しい戦略はあるか? 間違ったDXは日本を滅ぼす
NewsPicks, Inc Brand Design Head of Creative
いたるところで取り組まれている「DX(Digital Transformation)」だが、それが「DXの本質」に根ざした取り組みになっているケースがいくつあるだろうか。
「誤った理解のままDXを進めていたのでは、日本が危ない」。そう現状を危惧するのは、ベイカレント・コンサルティングの小峰弘雅氏。同社が考える、あるべきデジタル変革のステップや、競争戦略の第一人者として知られる経営学者、マイケル・ポーターの主張をベースにしたデジタル適用の方法論について聞いた。
DXの認識を間違えると企業は衰退する
──ベイカレント・コンサルティングは、業界を問わずDXを支援していますが、日本企業の取り組み内容をどのように見ていますか。
小峰 大多数の企業が、DXの手前にいるのではないでしょうか。既存のビジネスモデルに対して、デジタルを部分的に取り入れ業務効率化や生産性向上を図る「デジタルパッチ」に取り組んでいる状況でしょう。
ただ、デジタルに関する一定の知識と経験がないと正しい変革は生み出せないので、DXにはこの助走段階は必要なことです。先行している海外でも、まずはデジタルパッチから始めています。
──多くの日本企業が進めているDXはまだ本来のDXではない、と。
そう捉えています。デジタルパッチの次のステップとして定義しているデジタル変革には、2つのモードがあります。それが、ビジネスモデルの要素を高度化する「デジタルインテグレーション(DI)」と、ビジネスモデルを転換していく「デジタルトランスフォーメーション(DX)」です。
例を挙げて説明しましょう。インターネット広告事業を手がけるサイバーエージェントにおけるDIは、クリエイティブ制作プロセスへのAI導入です。画像生成AIを使うことで、実在しない3DCGのモデル画像を生成して広告に使用しています。
インターネット広告事業の主要プロセス自体は変わらないものの、AIを使うことでモデル選定やスケジュール調整、撮影などのプロセスが不要に。また、広告効果を予測できるAIも用いることで、顧客企業やブランドに適した3DCGモデルを起用し、質の高いリード獲得につながりました。
一方、DXの代表例はダイキン工業です。ビルや商業施設に対して空調設備を売るのではなく、良質な空気そのものを提供するAaaS(Air as a Service)というサービスを始め、新たな価値を生み出しました。
これによって、単純なモノの売り切りモデルから、月額固定料金のサブスクリプションサービスへ利益方程式を変革したわけです。
DIにせよDXにせよ、市場の中で競争があって、自分たちのポテンシャルを最大限に生かしながら、持続的な競争優位を築いていくところは同じ。デジタルで業務を高度化するのか、それとも新たな価値を生むのかの違い。どちらかが良いというわけではなく、事業が置かれている競争環境に合わせて2つのモードを使い分けることが大切です。
──「競争優位」はよく使われる言葉ですが、改めてその定義を教えてください。
もっとも目に見える形では、同じ業界の平均的な業績を上回ることを意味します。具体的には、顧客にとって価値があるので高い価格を要求できるか、競合他社に比べて圧倒的に低いコストで事業を運営しているか、その両方か。
競争優位とは、他社と異なるバリューチェーンをいかに構築し、業界平均を上回る業績を確保するかということです。
デジタルパッチにとどまっている企業の多くは、先行している企業に追いつこうと、他社が導入しているソリューションを同じように求めるのですが、その後に業界を制したような企業を一つも知りません。
短期的な目先の利益だけは得られたけれども、中長期的に競争優位を築けたわけではない。隣りを見ながらRPAだ、データドリブンだと取り入れても、利益につながるようなインパクトを得ることはできません。
デジタルパッチ「だけ」をやっていても、あっという間に差が広がってしまうし、まねされてしまいます。
経営学者のマイケル・ポーターはこれを「競争の収斂」と呼んでいて、似たような企業が似たような価値を生んでいくと価格競争になり、その市場自体が価格でしか採用されず、どこも利益が得られなくなると論じています。勝者がいない戦いに陥るのです。
重要なのは、デジタルパッチをDXだと勘違いしないこと。そして、DXを目的にしないこと。デジタル変革の本質は持続的競争優位を築くことなのです。自分たちのビジネスがどうあるべきかを考えずにデジタルを求めたり、デジタルを業務改善の一助だと位置づけたりしたなら、企業は衰退していってしまうでしょう。
間違ったDXの認識が日本中にはびこったなら、日本が衰退してしまうかもしれない。あくまでも競争優位に重きを置いてほしいと思います。
DXのファーストステップ「戦略」の考え方
──DXを進めるためには、まず戦略からのアプローチが重要だということですが、改めて戦略とは何か教えてください。
ベイカレントでは、戦略を3つのレイヤーで捉えています。
次に、「競争」とは何なのかも正しく抑えておくべきです。
ポーターのいう競争とは、独自性を目指す競争です。ここでは価値がすべてになります。その上で、競争に勝つためには競争優位が必要で、ライバルとは異なる独自の活動をしなければなりません。特徴のある価値提案をするためにはポジショニングが重要で、3種類の戦略ポジショニングがあります。
1つ目がバラエティ・ベース・ポジショニング。ある業界の製品やサービスの一部を提供することでポジショニングするものです。
例えば、ヘアカット専門店のQBハウスでは、カットだけを突き詰めています。QBハウスの価値提案の一つは、10分で身だしなみを整えることです。最近は待ち時間がわかるようになっているのですが、最後に使うエアウォッシャーの電源がオフになったらカット終了のタイミングとして、カット時間を自動的に記録し、分析することで実現しています。
1人ひとりの所要時間もわかるため、標準レンジから外れている店舗やスタイリストを特定して対策を打つことにデジタルを活用し、安定的なサービスを提供し続けることに成功しています。
2つ目がニーズ・ベース・ポジショニング。これは古来マーケティングで用いられてきたもので、一定の顧客グループのニーズのほとんど、あるいはすべてのニーズを満たすサービスを提供するというものです。
代表的なのがIKEAで、価格感度が強い顧客グループに対して、どれを取っても満足する品揃えをしていますよね。DXの取り組みとしては、最近ではEコマースも展開するようになりました。
店舗で梱包し発送するフルフィルメントの機能を持たせているので、ニーズ・ベース・ポジションであることに変わりはないものの、オペレーションは激変しています。
3つ目がアクセス・ベース・ポジショニング。顧客の所在地や規模など、アクセスの方法の違いによってポジショニングができます。
例えば過疎地域では、スーパーに行けない人がいます。徳島県で生まれたサービス「とくし丸」は、地元のスーパーで商品を調達して軽トラックで運び、数十円を上乗せして販売しています。アナログに見えるのですが、要望にはないけれどお客さまが喜びそうな品ぞろえをAIがサポートすることに挑もうとしています。
こうしたポジショニング理論の上に価値提案を行い、その活動の要素にデジタルを組み入れるのがDXの正攻法だとベイカレントでは考えています。まず戦略があり、デジタルがある。
この順番が重要なのです。そうしないと、そもそもデジタルが武器になるかどうかもわからない。その経営戦略を実現するためにデジタルという武器を使って、現場の人たちを巻き込みながら実現していくのが、理想的な推進のあり方です。
──一方で、間違った進め方の特徴はありますか。
もっとも多いのは、現場だけで考えて施策を決めているケースです。トップは掛け声だけで丸投げし、予算も人も準備せずに、IT部門やデジタル部門に任せている。そうすると現場の課題を吸い上げて対処していくだけになるので、「デジタルパッチ」でしかない。「競争優位」まで考えていないことが多いのです。
「変革」に自信を持つベイカレントの特異な組織
──デジタル変革に関するさまざまな案件があると思いますが、ベイカレントのDXコンサルティングでは、何を重要視しているのでしょうか。
DXのXを重要視しています。大事なことは、デジタルを使ってどう変革していくか。オペレーションを変えるのか、社員の意識やモチベーションを変えるのか。「こうしたらいい」という支援ではなくて、社員の人たちが腹落ちできて、自分ごとにしてもらえるように支援することを大事にしています。
プロジェクト都度のお付き合いでは、現場を動かすことはできません。弊社では、複数チームを継続的にアサインし、1つのクライアントに対して数十名のコンサルタントで支援するケースが多いです。
これなら組織の隅々までコンサルタントがいるので、会社全体を動かすお手伝いができるのです。 Xをいたるところから染み渡らせ、実行も踏まえた戦略を作って実現していくのです。
ある老舗メーカーの例をご紹介しましょう。トップはDXを進めたいという意志を強く持っている組織です。2-6-2の法則がありますが、6割のマジョリティを変えるのがとても難しく、どう自分ごと化してもらい、実行に移してもらうかが課題です。
そこでご支援しているのは、DXの教育と実行の2つです。教育は全社員に対するDXセミナーで、DXとはどのようなものなのか、そして会社にとってどう重要なのかをコンサルタントのパートナー陣が説明しています。
実行においてはデジタルを活用した新規ビジネスの種を獲得するため、クライアントと共同提案を実施しています。例えば課題設定をベイカレントが担い、その後のサービス提供はベイカレントとクライアントが共同で行います。
このとき、知識・スキルが画一的なコンサルタントばかりでは、クライアントの課題を多面的に捉えることができません。ベイカレント社内では、ワンプール制という組織体制をとっており、さまざまな業界・テーマを渡り歩いて見出した共通知をクライアントに還元しています。
──業界ごとに部門が分かれている、一般的なコンサルティングファームとは真逆ですよね。
そうですね。DXのビジネスをやっていくと、老舗のメーカーであっても、相対する顧客が多様化してきます。ビジネスを横展開するときに、対象となる業界が変わってくる。そこでワンプール制を経験しているコンサルタントの力が生きるのです。
もちろん、フェーズによって体制を変えすぎるとクライアントは困ってしまいますので、軸となるリーダーは変えず、スタッフレベルを柔軟に入れ替えます。戦略フェーズでは戦略に強いスタッフ、実行フェーズは実行に強いスタッフ、あるいは希望するスタッフを配置するのです。
組織を動かすボタンを押せる
──新しいビジネスモデルだと業界を越境するような動きがあるので、いろいろな業界の経験を積んでいるコンサルタントが強みになるのですね。その上で、たくさんのファームがDXを支援している中にあって、ベイカレントが選ばれる理由は何でしょうか。
その会社のことを熟知する能力に長けているからだと自負しています。だから、組織を動かすボタンを押せるのです。
戦略策定の支援は当然大事ですが、クライアントが戦略を引き出しにしまってしまい、行動に移さないのであれば意味がありません。どの人から口説きにいけばいいか、どうやって現場に浸透させていくかを重要視していて、実際に動かせるのがベイカレントです。
これが可能なのは、先ほど説明したように組織の隅々までコンサルタントを配置しているからです。
加えて、現場とクライアントを知り尽くしたコンサルタントにデジタルの知見をプラスしていったことも、選ばれる理由でしょう。デジタル・イノベーション・ラボという組織はあるのですが、あくまで研究して知見を提供する役割に留めています。こうすれば、「デジタルありき」に陥って、戦略と順番が狂うことがありません。
──これからDXを本格化させる企業も少なくないと思います。どのようなアドバイスがありますか。
改めてお伝えしたいのは、まずは独自性を目指す戦略があってこそ、デジタルの力が発揮されるということです。事例探しに躍起になるのは、間違いだと思います。戦略は世界で1つ、その会社だけのものです。自分たちの価値を見つめ直した後に、最適なデジタルを入れていってください。
執筆:加藤学宏
撮影:森カズシゲ
デザイン:Seisakujo Inc.
取材・編集:木村剛士