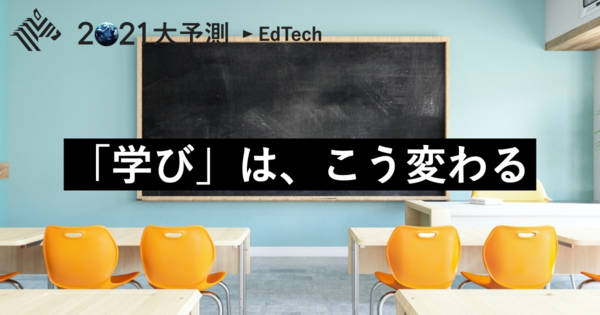
【2030年】イーロン・マスクも注目する「教育の最前線」
コメント
注目のコメント
イーロン・マスクと共に「Xプライズ財団」を立ち上げたVC、ピーター・ディアマンディスが構想する「教育の未来」をお届けします。VR、AI、5Gといった技術のかけ合わせは、教育にどんなイノベーションをもたらすのか。
さて、ディアマンディスの立場は「複数の技術のかけ合わせ(convergence)によって世界は飛躍的に前進する」というものですが、彼のこの世界観を支えているのが、マット・リドレーというイギリスの科学啓蒙家です。そんなリドレーがイノベーションの本質を解き明かした最新刊『人類とイノベーション』を、弊社から刊行します。私がリドレーの本を手がけるのは『繁栄』以来10年ぶり。ご期待いただければ嬉しく思います。https://www.amazon.co.jp/dp/4910063153/テクノロジーの進化を起点に書かれた教育記事ですが、やや注意が必要な内容だと思いました。
VRやAIの利用はたしかに教育を進化させます。様々な事象への理解を高める効果も様々にあると思います。ただし、知識理解に限定し、受動的に学んでいるままでは、学習の質はあまり進化していると言えません。
記事中の言葉を借りれば「豊かな学び」とは何か?ということへの言及が不足していると思います。
では、2030年にはどんな学びを期待しているかというと、テクノロジーが組み合わさることで
・教員主体ではなく、学習者主体の学びが実現される
・ICTを子どもたちが文具的に自由に使うことができる
・知識習得はAIによって、より個別最適化される
・知識習得の体験がよりリッチなものになる(VRはここ)
・AIと先生の合わせ技でよりきめ細やかなフォローができるようになる
・知識習得に限らず、探究的な学習でも個別最適化が進む
・探究が進むと、子どもたちが最先端の知識を作るレベルにまで至る
・ネットを介して学校の枠を超え、実社会とつながる学びが広がる
といったことが起きます。
知識理解ではなく、知識構築のレベルまで至る学びであり、その時、学習者は幼く知識を受容するだけの存在ではなく、一人の探求者として知識を作り社会を変えていく存在です。
2030年の未来では、テクノロジーの進歩だけでなく、学習観の進化がなければいけません。そうでなければ、昭和の時代の古い学習観がテクノロジーで焼き直されているだけになってしまいます。その点、私達大人がまずは留意せねばなりません。
ちなみに、パソコン一つとっても、管理型教育の価値観が変わらなければ、利用制限がガチガチについた「使えないパソコン」が学校に広がるだけです。そして実際そんなことが各地で起きていることには注意が必要です。
【参考記事】
【教育】コロナが生んだテクノロジーの「活用格差」
https://newspicks.com/news/5519593
iPad届いたのに制限だらけ 学校間で広がるIT格差
https://newspicks.com/news/5547462MITメディア・ラボ創設者のニコラス・ネグロポンテ氏が、エチオピアの僻地の子どもに、タブレットを渡したという話が面白い。
「子供たちは箱で遊ぶんじゃないか、と思っていました。だが4分も経たないうちに、一人が箱を開け、しかも電源スイッチを見つけ、電源を入れた。5日後には子供たちは1日あたり平均47個のアプリを使うようになっていた。2週間後には村中でABCの歌を唄っていた。そして5カ月後にはアンドロイド(のオペレーティングシステム)をハッキングしていたのです」
単なるゲーマーにしか見えない我が家の長男も、もうすぐハッキングとかできちゃうに違いない。
