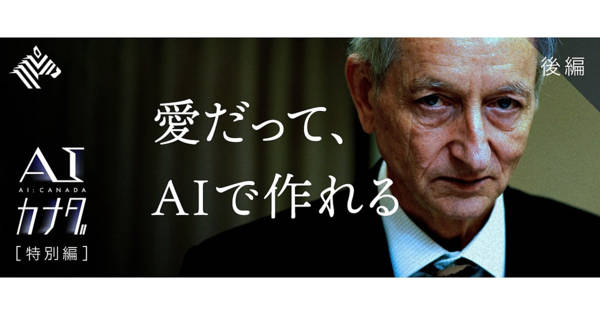【独白】AIの頂点に立つ男が語る、「優秀な才能」の条件
コメント
注目のコメント
あっという間に世界を圧倒的に変えてしまった「AIの源流」をグローバルに追い続けてきたNewsPicksの一大特集(https://newspicks.com/user/9670)もついに最終章を迎えました。
Google, Facebook, Appleをはじめ、世界の巨大テックでAI担当の幹部を勤めてるのは、ほとんど彼の門下生です。その彼が語る「優秀な人材」の条件とは?そして「知能」の限界とは?
どうぞ、皆さんお楽しみください。ヒントン氏は、~学がやりたかったわけではなく、自分の問題への答えを探したかった人だと思われます。その問題とは、人間の「心」を理解し、理解するために「人間の心」をつくってみることであったと思しいです。ニューラルネットワークは答えの一環でした。
ヒントン氏のキャリアは、ずっとコンピュータ・サイエンスを専攻してきた学生や、いわんや子供の時からプログラミングを教えられてきた人間が卓越したAI研究者になるわけではなく、自分の問題を持ち続けてきた人間が、たまたまAIの新しいアイディアにこだわり続けて、AIの新しいあり方の開拓者になった、ということを示しています。
歴史に名を遺す多くの学者は、ほとんどといっていいくらい、自分の問題を持っていました。それは、社会や国家の要請で与えられた問題ではなく、あくまで個人的に気になって仕方がない、といった問題です。その個人的なこだわりは、多くの場合、他者からはどうでもいいこと、くだらないことといわれます。
「人間(の心、魂)をつくりたい」という個人的な問題へのこだわりは、ヨーロッパでは非常に古く、ポピュラーなものです。古代ギリシアのピグマリオンの神話、中世に試みられた人造人間ホムンクルスの創造など、錬金術のような方法で、非常に多くの人間がこの問題に生涯を費やしました。
17世紀のデカルト以降、人間の人間たるゆえんは「意識」を持つことではないかと考えられるようになりました。以後、心とは、神が人間に与える与えるような神秘ではなく、人間という機械に組み込まれた仕組みと考えられるようになっていきました。「意識」が何であるのか、その仕組みが研究されるようになり、心理学もそこから出てきました。
20世紀になると、生化学による脳の仕組みの解明もあり、「意識」という仕組みを人体とは別に想定する必要は無いと考えられるようになりました。心理学や生理学で単に人間の心や脳を観測したり操作したりすることはまだ行われていますが、量子力学などによって、仕組みを説明し、人間の脳の働きを説明するモデルをつくったりするようにもなっています。
「人間(の心)をつくりたい」という2千年以上続くこだわりが、現代でたまたま数学と電子計算機の能力である程度再現できる条件が整っていたのは、ヒントン氏の幸運です。「私は当時、そして今も「教師なし学習」こそがあるべき姿だと思っています。」
氏はずっとおっしゃってますね。
Yann LeCun先生もCVPR19のkeynoteでやはり同じことをおっしゃっていました。
いま、深層学習の基本はConvolutional Neural Networks (CNN)ですが、氏はNeuroIPS17でカプセルネットという新しい概念を提唱し、下記のようにプーリング演算は「大失敗である」と述べています。
“The pooling operation used in convolutional neural networks is a big mistake and the fact that it works so well is a disaster.”
NNは完成したわけではなくて、いまもどんどん進化している。面白いですね。
Dynamic Routing Between Capsules
https://arxiv.org/abs/1710.09829