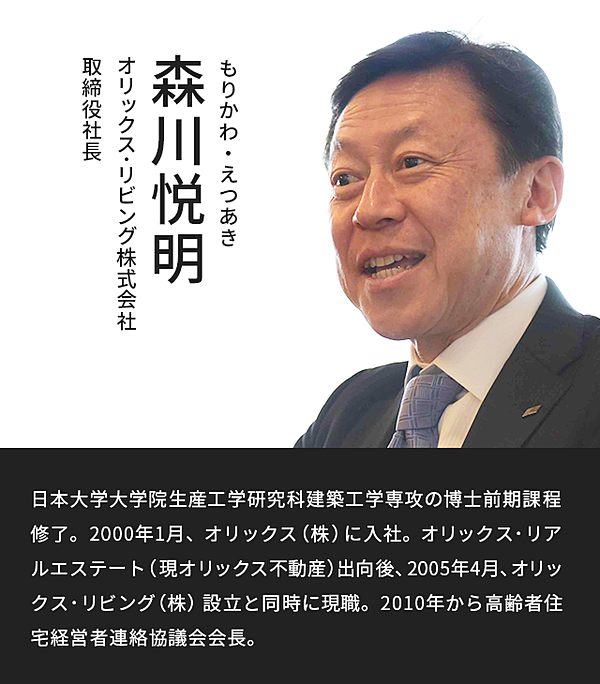「新しい介護の常識」を築くオリックスが運営する高齢者住宅とは
2018/6/4
経済環境やニーズの変化に対応し、新たな事業領域へとチャレンジを続けてきたオリックスは、1980年代に不動産事業に参入。投資や開発、施設運営などさまざまな事業を展開する中で、2005年にオリックス・リビングを立ち上げ、現在では2726室の高齢者住宅の運営を手掛けている。
介護従事者や高齢者受け入れ施設の不足など、問題が山積する少子高齢化の日本で、オリックスが目指してきた「新しい介護」とは。従来の「手厚い介護」とは異なる「よくする介護」とは何なのか。オリックス・リビング(株)取締役社長 森川悦明氏に話を聞いた。
街づくりからスタートした高齢者住宅事業
オリックスの高齢者住宅事業は、2000年頃から3世代が永続的に暮らせる「サスティナブルコミュニティ」をコンセプトにした街「マークスプリングス」(神奈川県横浜市)を開発する中で、医療機関の誘致に取り組んだことからはじまった。
森川氏は当時をこう振り返る。
「通常、クリニックなどの医療機関は、中学校区(1500世帯)規模の住宅を対象として採算が取れるといわれますが、マークスプリングスには700戸しかありませんでした。そこで街に高齢者住宅をつくり、高齢者医療をクリニックの収益源のひとつとする提案を受け入れました。
高齢者も安心して暮らすことができるうえ、マンションの住民にいずれ介護が必要になった際にも対応できます」
高齢者医療に着目したモデルを提案したのは、故春山満氏だった。
「車椅子社長」としても知られる春山氏は、24歳で進行性筋ジストロフィーを発症。
自らの経験を医療・福祉・介護の分野で生かすべく、オリジナル商品の開発や大手医療法人・企業のコンサルティングなど幅広く活躍。2003年、米ビジネスウィーク誌にて『アジアの星』25人に選出された人物だ。
「春山氏の提唱する実体験を通した『新しい介護のあり方』に強く共感しました。
その後、春山氏から紹介を受けて米国のCCRC(Continuing Care Retirement Communityの略。リタイアした人が第2の人生を健康的に楽しむためのコミュニティ)を視察した際には、教会や病院、ゴルフコースやプールなどを有する街で高齢者が生き生きと生活する様子に衝撃を受けました。
医療の必要性から考えられた街づくりのモデルでしたが、高齢者サービスと介護の必要性を深く考える機会となり、マークスプリングスの中にも高齢者住宅をつくることにしたのです」(森川氏)
近年では都心部にも有料老人ホームや高齢者住宅が増えてきたが、当時は一般的に「老人ホームは郊外につくるもの」と捉えられていた。「おしゃれな街づくりに老人ホームはいらない」と社内では反対の声も多かったという。
しかし実際に販売をはじめてみると、50代から60代を中心とした顧客から好評で、想定外の年齢層が購入してくれた。そしてオリックスはマークスプリングスで得た確信を生かして、その後も多くの高齢者住宅開発に取り組んでいく。
「介護施設」ではなく「高齢者住宅」を運営したい
現在、オリックス・リビングは高齢者住宅の開発から運営までを一貫して行っている。しかし、当初は開発のみを手掛け、運営は他社が担っていた。なぜ自ら運営を手掛けるようになったのか。
「当時は、入居している高齢者に門限や面会時間などのルールに従った生活を求める『施設』が一般的でした。たしかにそのほうがサービス提供者は管理しやすく、人件費もカットできるのだと思います。
しかし春山氏と関わる中で、弱者を世話するという発想の『施設』ではなく、入居者の身体と心と生活を支え、家族との絆と尊厳を守るサービスが備わった『住まい』を提供すべきだと考えたのです」(森川氏)
自分たちが手掛けるのは高齢者「住宅」であって、決して「施設」ではない。森川氏のこのようなビジョンを共有してくれるオペレーターを探すことは困難だった。そこで、思い描く「新しい介護」を実現するため、オリックス自ら高齢者住宅の運営事業に参入。
2005年4月にオリックス・リビングを設立し、2006年7月に第1弾となる「グッドタイム リビング 神戸垂水」の運営を開始。それ以後、有料老人ホーム「グッドタイム リビング」シリーズとシニア向け賃貸住宅「プラテシア」シリーズを展開していった。
苦難の時代も高齢者住宅事業から撤退しなかったオリックス
未経験の高齢者住宅のオペレーションに参入し、知識やノウハウがない中で奮闘するオリックス・リビング。大規模な物件を立て続けに開発した2007年春頃、大きな壁にぶつかった。
「組織をつくりながら同時にオペレーションも行う必要がありましたが、介護保険に関する手続き、介護職の採用活動、入居者を募集する営業活動まで、すべてが経験不足で手探りの状態でした。
入居者の尊厳を守り、街に輝きをもたらすような高齢者住宅をつくりたいという理想はあるものの、知識や経験をもつ人材の供給が追い付かなかったのです」(森川氏)
人材の不足に加え、入居も思うように進まず、経営は混乱を極めた。
「2008年の夏、新規で着工する予定の物件があり、パンフレットも完成している状況でしたが、断腸の思いで着工を中止しました。これ以上新規の物件を開発しても、私たちが理想とする高齢者住宅を運営することはできないと考えたからです」(森川氏)
それから2年間、新規物件の開発を中止。問題の解決に真摯に取り組みながら、ひたすら事業の基盤づくりに努める日々だったという。
「正直、もう辞めたいと何度も思いましたが、一度運営に参入したからにはサービスの提供を続けなければならないという責任と、自分たちが目指す新しい介護が社会からも求められているという使命感に突き動かされました。
『いつかは満室になる』『入居率が上がれば経営も安定する』と信じて、一歩ずつ前に進むしかありませんでした。結果的に2010年に黒字に転換するまで時間を与えてくれたグループの経営陣は、よく辛抱してくれたと思います」(森川氏)
「安心と賑わいのある暮らし」から、さらに新たなステージへ
もうどこにも移り住む必要のない、安心と賑わいのある暮らしを提供することを目指してきたオリックス・リビング。入居する高齢者を「ゲスト」、「ゲスト」の住まいを「ゲストハウス」と呼び、ゲストが自分の家のように過ごせる場所をつくりあげてきた。
ゲストが朝起きると、まずはスタッフが「今日はどのお洋服になさいますか」と問いかけるところから一日がスタートする。
たとえ身体が不自由なゲストでも、着替えさせやすい服をスタッフが選ぶのではなく、ゲストの意思を尊重することで活動意欲の向上につながると考えているからだ。

オリックスが運営する多くの高齢者住宅には施設内に美容室が併設されている。予約で埋まることもしばしば
「不自由を補う介助サービスを提供するだけではなく、そのゲストにとっての楽しい暮らし、喜びのある暮らしに主眼を置いたサービスを提供することが、身体機能の回復にもつながると信じています。
だからこそ以前からアクティビティには力を入れ、音楽やスポーツ、ゲームなど、ゲストの声を取り入れたさまざまなプログラムを用意しています」(森川氏)

共有スペースには、絵画や陶芸、クラフトなどのための専用アトリエやライブラリー、ビリヤードコーナーなどもあり、それぞれの楽しみを見つけられる
2015年からは、さらに次のステージに進むための新たなビジョンとして「よくする介護」「賑わい」「夢」の3つを掲げている。
「自らオペレーションを手掛ける中で介護の奥深さに気が付き、『個々のゲストにとっての最良のケア』を目指すようになりました。
まずはゲストをよく知る。そして、ゲストの能力や意欲を引き出し、自分でできることが増えていくようにスタッフがサポートする。その積み重ねによって、ゲストが成し遂げたい目標に向かっていく。そうした目標指向的介護を目指しています」(森川氏)
あるゲストは歩行器が手放せなかった。そのゲストの夢は「両親の墓参り」。ただし、道路から墓までは階段も多く、杖のみを使って歩く必要があった。
スタッフがゲストを担いでいけばすぐにでも実現可能ではあるが、スタッフは「自分の足で行けるようになりましょう」とゲストを励まし、やる気を引き出したという。数カ月かけてトレーニングを続けたこのゲストは、杖をついて自分の足で墓参りをすることができた。
「今、身体が不自由なゲストに何でもしてあげる『手厚い介護』ではなく、ゲストが自分でできることを増やしていく『自立支援』が求められています。
少子高齢化が進む日本の介護の現場では、これからより一層働き手の確保が難しくなり、施設を増やして収益をあげていく従来のビジネスモデルは成立しなくなる。『自立支援』につながる『よくする介護』は、介護される方の喜びを創出するだけでなく、本当の意味での介護に通じるものだと考えています」(森川氏)
オリックス・リビングは、さまざまな方法でサービスの合理化も追求している。
たとえばタブレット端末を導入し、これまで手書きで作成されていた書類を電子化したことで、スタッフの負担を軽減。ほかにも、シフトの見直しなどの働き方改革を推進し、スタッフの総労働時間を2年間かけて11%削減した。
「ICTをはじめとしたテクノロジーも積極的に導入しています。ベッドから起き上がった時点でスタッフの端末に通知が飛ぶ見守りシステムを導入し、ゲストの転倒防止につなげるだけでなく、日常生活の変化を知るために役立てています。
ほかにもベッドなどへの移乗時に利用する介護リフトを全拠点に導入し、スタッフの肉体的負担の軽減に役立てるとともに、ゲストが安心して介護を受けられる環境を整えています」(森川氏)
これまでの日本の介護現場では、職員が自らの手で行う移乗介護が温かみを醸成すると捉えられてきたが、実際は介護リフトを使用することで高齢者も気兼ねなく介護を受けられ、満足度も向上しているという。
「街づくりをはじまりとして、年を重ねても住み続けられる資産価値の下がらないマンションをつくりたいという気持ちから、高齢者住宅の開発に参入しました。そして介護の奥深さに気がつく中で、従来の有料老人ホームの枠組みにとらわれない挑戦を続けてきました。
高齢者住宅のオペレーションという面ではまったくの素人だったからこそ、常識にとらわれない発想ができたのだと思います。これからも新しい高齢者の暮らしと介護のスタンダードをつくりあげることを目指し、チャレンジを続けていきます」(森川氏)
(執筆:唐仁原俊博 編集:大高志帆 撮影:露木聡子 デザイン:星野美緒)