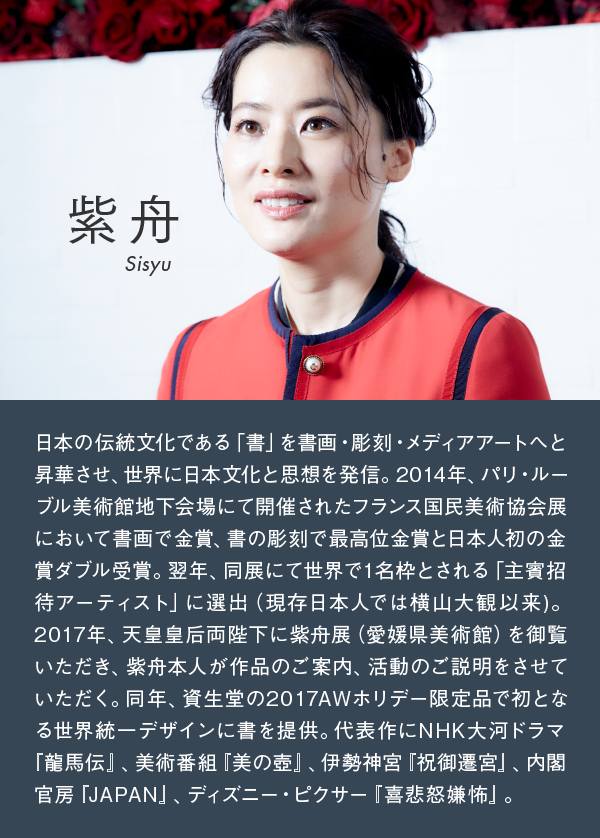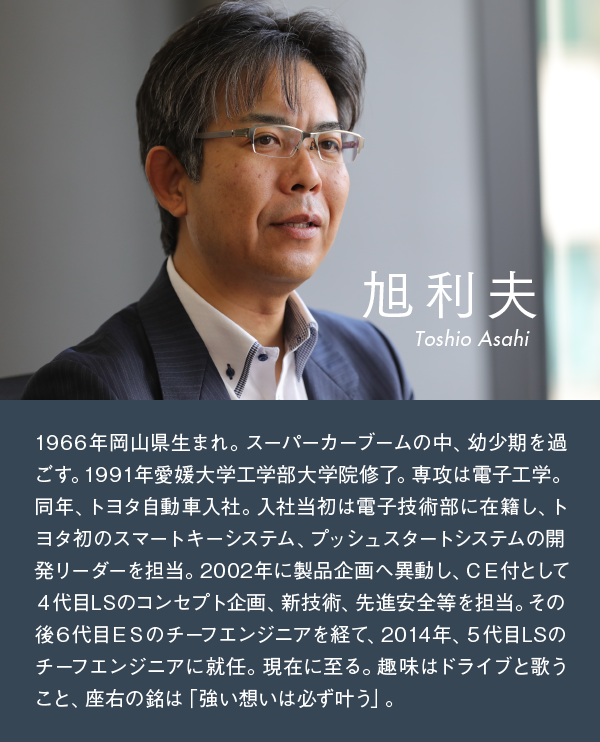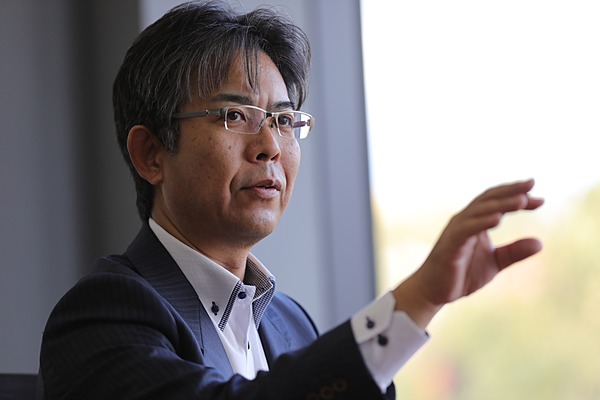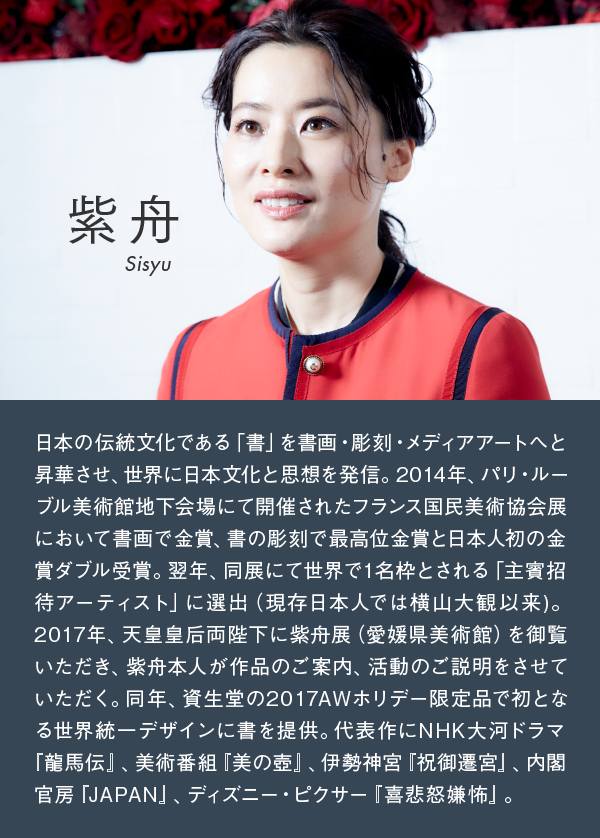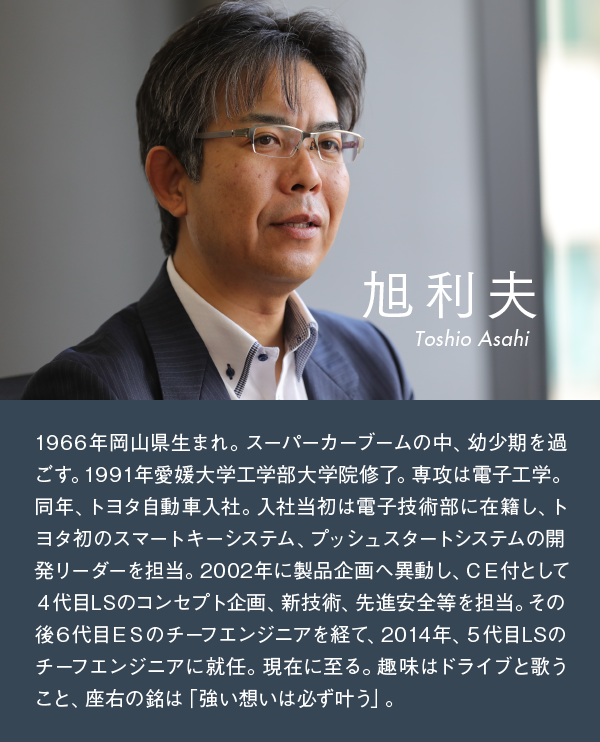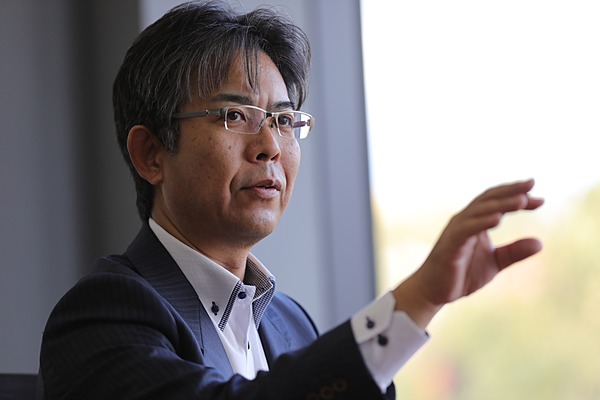テクノロジーと本能。感性が動き出す、満ち足りた瞬間とは
2018/1/27
AI化・機械化が進む社会にあって、人間には「より人間らしいこと」が求められている。“人間らしさ”の根幹にある感性や直感はどのように目覚め、磨かれるのか?
#1に引き続き、書家の紫舟氏と新生LSのチーフエンジニアである旭氏のインタビューから、その答えを導き出す。(全2回)
現代人の生活環境にはテクノロジーがあふれ返っている。それは我々に圧倒的な便利さをもたらしてくれた。しかし、そんな時代だからこそ“より人間らしいこと”が求められている、という流れも一方では存在する。AIなどに代表される機械が持ちえない、人間らしさの証左ともいうべき直感や感性=本能を磨くためにはどうするべきなのかを、世界的に活躍する書家の紫舟氏にうかがった。
インスピレーションの源よりも大切なこと
──紫舟さんにとってインスピレーションの源になるものとは何なのでしょうか。
講演会などを聴くことで、ふだん用いない言葉の刺激を受け、自分の中にすでに準備されているものと“つながり”、インスピレーションになることがよくあります。
名画から創作のヒントを得ることは元々少ないようです。今はむしろ発想力とは違ったところに重きを置くようになったという表現のほうが正しいかもしれませんね。
以前は、インスピレーションが人生や作品を自然と導いてくれるものだと信じていました。漠然とですが、そういうものが答えを教えてくれるのだと。
最近では、発想力やインスピレーション以上に、 制作を次のステップへと導いてくれる存在があることに気づくことができました。
──紫舟さんが重きを置いているものとは、具体的にはどういうものですか?
異次元の集中力でモノを“生み出す”領域です。
6歳から書の稽古で集中する訓練を継続したおかげで、私の集中力は他の人よりも高いらしいのです。
以前、ある実験で脳波を測っていただいたことがあるのですが、通常時でも「修行を重ねた僧侶が瞑想している状態」並みに集中力があるというデータとなりました。
経験を重ねて技術が上達してくると、それなりのクオリティのものを惰性や勢いで作れてしまいます。
書道だけでなく、専門性を求められるジャンルにおいては共通することだと思います。集中しなくても、小手先で見事に見える型を作れてしまう──言い換えると、それは本質的な意味での、成長が止まる段階です。
型は立派、技術も十分。ですが、それとヒトに感動を届けることや、ヒトの心を惹きつける何かを残す強さとは別次元のことだと思います。
心の存在から解き放たれることの重要性
──どういう状態が、より集中している状態といえるのでしょうか。
心の存在を手放している状態です。集中とは、心という鎧(よろい)から解き放たれるという意味と同義だと思います。
AIと人間の違いは「心」があるかどうか。心の存在が人間たるゆえんです。
心を奪われてしまうと、ヒトは感情に支配されてしまい、我を忘れます。心は美しく、一方では厄介でもあります。
心は我々を振り回し、コントロールすることは容易ではありません。過去の何かを悔い、未来を不安に思い、誰かを想い……。心は波立ったり瞬時に飛び回ったりと忙しいですね。
集中する状態に在るために、忙しい心をいったん横に置いてみる。心にとらわれず、心の存在から解放され、自由になり、たったひとつのことに意識を込められた状態なのだと感じます。

世界中から熱い評価を受ける紫舟氏の作品は、人知を超えた集中力によって生み出される。Photo by Tadahiko Nagata
これまで書を制作するときに見えているものは「余白」でした。子どものころは墨蹟をみて書いていましたが、その後は余白を見て書いていました。
もう一段階集中力が上がると、視野が広がるのではなく、毛先の命毛(筆の先端のこと)一本へと、どんどん視野が狭くなっているのがわかりました。
心の存在から解き放たれ、ひとつのことに意識を留めることができると、人の莫大な熱量がそこに注がれます。「火事場の力」が出せるようになるということかもしれません。
この集中力から生まれた作品は、展示するとすぐに完売します。鑑賞者も、目に見えるものと見えないもの、両方を感じているのだと思います。
特に、小さな子どもはこういった熱量の多い作品の前に座り込みます。幼稚園児が1時間も見ている作品もありました。
──その状態には創作時に常になれるものなのでしょうか?
そうなれるよう、日々の暮らしに節制を課しています。タイ仏教の修行僧の食生活に近い節度を保っています。
また、集中力の状態をチェックするために、行うことがあります。
創作活動に入る前に、特注筆(毛が細くて長くてこしのないとても柔らかい羊毛で出来た、扱うのが高難度の筆)を使い、試し書きをします。
その筆で、普段よりも10倍の遅さでゆっくりと「左はらい」を書きます。左に筆をはらうのは、筆に勢いとスピードがないと簡単に崩れるからです。
集中力が途切れると線が惰性になり、形にならない。いくつか書き、意識がその一筆に込められているかを確認します。
波立った心が凪(なぎ)になり、平安が訪れた状態で高い集中力のゾーンへ入る。その境地で作品に向き合えるかを、大切にしています。
直感や感性に嘘をつかない
──360°で鑑賞できる『書のキュビズム』に代表されるように、平面で表現する従来の書道の発想を覆すような作品も精力的に発表していますが、それはどこから生まれるものなのでしょう。
「自分自身との信頼関係」でしょうか。
たとえば、小さい頃に花を見て「キレイだな」「いい匂いだな」と思ってそれを周りの人に伝えたところ、否定されたとします。そうすると、自分の感覚にヒトはいとも簡単にふたをしてしまう。
自分の直感や感性を認めなくなる。信じなくなる。
素直な気持ちに背を向けることは、直感や感性に自ら心を閉ざすようなこと。
そのように自分を否定していると、直感や感性は自分に素直に訴えてくれなくなります。
自分が誰だかわからなくなり、自分のことなのに何が好きで、本当は何になりたかったのかわからなくなる……。

書のキュビズム「流水の香」 Photo by Tadahiko Nagata
書の既成概念を超えた『書のキュビズム』という表現に行き着いたことも、「世界中の人に書が伝わるふさわしい表現がある」という直感を信じた答えでした。最初の制作から5年がかりでした。
──ふさわしい表現とは、具体的にはどういうことでしょうか。
油絵など何度も筆で塗り足して完成する絵画表現を持つ西洋人にとって、ひと筆で完成する書は不思議なようで、「書はどうして1ストロークで書かなくてはいけないのか?」と疑問を抱くようです。
そのことから、書はひと筆でさまざまな線を生むことができるということを伝えるために「筆の動きや筆圧、そして描いた時間軸を立体的に可視化」したのが書のキュビズムです。
インスピレーションのその先、深い集中力のゾーンを保つために、自分の内側をちゃんと観てあげて、嘘をつかないようにする。そうすれば、直感や感性はきっと応えてくれると信じています。
相反するふたつの要素を、発想の転換や最新技術によって高次元で両立させる「二律双生」をコンセプトに掲げるレクサス。そのフラッグシップセダンに位置付けられ、新たに生まれ変わった5代目LSのチーフエンジニアを務めた旭利夫氏が考える、人間の感性を刺激する“ヒトとクルマの関係性”とは?
感性に訴えかけるために必要なこと
──ブランドとして「感性」をとても大事にしているレクサス。今回で5代目を迎えるLSは、先代から比べて大きく変化したように見えますが?
レクサスは人間を中心においたモノづくりをしています。お客さまの感性を刺激し拡張し、そして解放していくことで、心を揺さぶるような驚きや感動を提供することを心がけているブランドです。
感性に訴えるという観点で言うと、デザインや走りの部分がよりエモーショナルになっています。
フラッグシップセダンでありながら従来の高級車の概念や枠にとらわれない、4ドアクーペのような流麗なデザインを採用しながらも、居住性や乗降性も担保しています。
走りに関しても、高級サルーンとしての静粛性、乗り心地は確保しながらもドライバーズカーとしての気持ちよい走りにこだわり、プラットフォームを根本から見直しました。
また、従来のV8や大排気量と決別し、新たなユニットを提案しています。
単なるダウンサイジングではなく、高速燃焼技術を用いたV6ツインターボやエンジンとモーターの後段に4速変速機構を設けたV6マルチステージハイブリッドを採用することで、環境性能を高めることは当然のこと、パワフルでダイナミックな気持ちのよい走りを実現するスマートサイジング化したところも大きな変化です。
今回は、世界のトップの安全性を目指し、レクサスならではのヒトに寄り添う先進安全テクノロジー「Lexus Safety System +A」を導入した点も大きく進化した点と言えるでしょうね。

細かいこだわりを随所にちりばめながら完成させた新型LS
──お客さまの感性に訴えかけるために、具体的な目標値のようなものは設定したのでしょうか?
お客さまの感動するレベルってどのくらいなのか、という点をいろんなところで決めていきました。たとえば今回の新型LSは、エクステリアに「フラッシュサーフェイスウインドゥ」を採用しています。
通常のクルマではサイドウインドゥの前方と後方のドアの窓ガラスの間に「Bピラー」と呼ばれる段差がありますが、その段差を今回はなくし、面一化しました。
けれどクルマは工業製品なので、部品の精度やいろんな工程を経ていくなかで、どうしてもバラつきが出てしまう。フラッシュサーフェイスウインドゥにしても、結果的には段差が出てしまいます。
であれば、お客さまが段差を感じない、もっと言うと「感動してくれるレベル」とはどの辺なんだろう?というところをトライ&エラーで検証しました。
従来のドアの段差の半分以下にバラつきを抑えればお客さまに感動していただけると判断したんです。
私たちはそれを「感性の定量化」と呼んでいます。
それを明確にして目標数値に到達するために、さまざまな部門との折衝を重ねていく作業を繰り返しました。
インパネのステッチにつながりをもたせたり、インパネまわりのガタつきを可能な限り抑えたり、すべてが「お客さまはどこまでやったら感動してくれるのだろう」ということを検証しながら進めていきました。
──「ヒトとクルマとの関係からライフスタイルを提案する」というのはどういうことでしょうか。
いろいろと考え方はありますが、デザインの観点から言うと、今回「Time in Design」という概念を取り入れています。
これは、気持ちや環境で変わり続けるヒトとクルマの関係の変化をデザインで体現するというものです。
外観ひとつとっても、エモーショナルで抑揚があってセクシーなフォルムになっていますが、太陽の光や見る場所、映り込む景色でいろいろな陰影や表情に変わります。
内装も、心地よい広がり感のある、琴や茶筅をイメージしてデザインしたインパネのメーターフードの横に流れるメッキをあしらった曲線であったり、ドライバーを包みこむようなシートやアームレストの形状だったり……車に乗り込んだ時はあたかも自分のリビングで寛げるような空間や佇まいになっています。
しかしひとたび運転をし始めると、ステアリング周りに走行系のスイッチが配置されていて、ステアリング自体も少し小径になっていたり、フロントガラスに必要な情報が表示されたりと、アグレッシブに走れるようなドライバーオリエンテッドな空間にも変化します。
乗り込んだときと運転したときとで車の表情が変わり、走る時間や場所によってデザインがドライバーの感性を刺激する。そういった“ヒトと車の対話性”という意図から取り入れた概念が「Time in Design」なのです。

内装は、あたかも自分のリビングで寛げるような空間
押し売りではないテクノロジー
──ヒトとクルマの対話によって生まれるのはどういうものですか?
例えばシステム面においては、新型LSには「Lexus CoDrive」という高度運転支援系のテクノロジーが搭載されています。
これはレーダークルーズコントロール、レーントレーシングアシスト、そして、レーンチェンジアシストという3つの機能がパッケージになったものです。
このシステムを搭載したことで、高速道路上のコーナーや渋滞でも、お客さまの運転の意思に協調しながら熟練のドライバーが運転しているかのように自律的にレーンのセンターを走ることができます。また、レーンチェンジも安全性を担保した上で、快適に行うことが可能になります。
また、システムの状況を大型ヘッドアップディスプレイやメーターにわかりやすく提示することで、クルマとドライバーが対話をしながら走っているような状況が生まれます。
また、先進安全テクノロジー、プリクラッシュセーフティに関しても、世界初となる2つのシステムを開発しました。
歩行者と衝突の可能性がある場合、歩行者の存在を大型ヘッドアップディスプレイに自動的に警告してくれる機能と、衝突が避けられない場合、車がレーン内で回避スペースを見つけてくれてスペースがある場合は自動で避けてくれる機能です。
あたかもクルマがドライバーのベストパートナーとしてアドバイスやサポートをしてくれるように心掛けました。
「自分の運転がうまくなった」という実感
──最新のテクノロジーを搭載することは、運転がうまくなったと感じることにつながるのでしょうか?
今までフラッグシップセダンのような大きな車は「走ってもつまらない」ということで、なかなか積極的に外に出て行こうという気持ちになりませんでした。
新型LSに先端のプラットフォーム、先進安全、高度運転支援のテクノロジーが入り、クルマの絶対的な安心感や安定感、そして安全性が担保されたことでドライバーが「このクルマ、信頼できるな」とか「ちょっと自分の運転がうまくなったかもしれない」というふうに思うようになるのではないでしょうか。
安心して気持ちよく走れるため、外に運転して行きたくなるモチベーションになりますし、意のままに操れるという意味でも走りを楽しめるようになっていると思います。
──やはり純粋に運転を楽しむうえで、テクノロジーとは不可欠なものですか?
不可欠なものだと思います。積極的に運転するようになり、行動範囲や機会が増えることでどうなるか。
これまで見られなかったものが見えるようになり、会えなかった人に会えるようになり、できなかった経験ができるようになるなど、ライフスタイルが広がります。
その結果、感性がより刺激され、更に運転が楽しくなる。こういった好循環を生む意味でも、やはりテクノロジーは不可欠でしょう。
新型LSは、お客さまが走りを楽しみたいときもくつろぎたいときも、いつ何時も感性を刺激し、かつヒトに寄り添うベストパートナーを目指して作られています。
このクルマを経験することでライフスタイルがどんどん広がり、お客さまのかけがえのない一台になってもらえれば幸いです。
(編集:奈良岡崇子 構成:持田慎司 撮影:尾藤能暢<紫舟氏>、渋谷敦志<旭氏>)