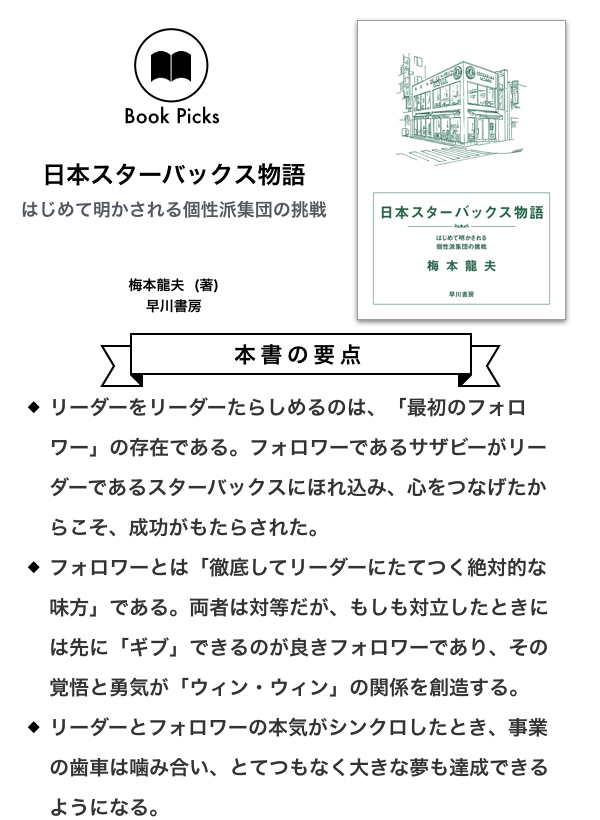要約で読む『日本スターバックス物語』
元サザビー取締役がつづる、日本のスターバックス誕生秘話
2015/12/14
時代を切り取る新刊本をさまざまな角度から紹介する「Book Picks」。毎週月曜日は「10分で読めるビジネス書要約」と題して、今、読むべきビジネス書の要約を紹介する。
今回取り上げるのは、サザビーで鈴木陸三氏の右腕として活躍した梅本龍夫氏がつづる『日本スターバックス物語』。生活雑貨やティールームを展開していたサザビーが、いかにしてスターバックスの日本進出を支えたのか。日本でほとんど知られていなかったスタバが、なぜ成功を収めることができたのか。鈴木氏の「イノベーターズ・ライフ」と併せて読めば、理解が深まること請け合いだ。
リーダーとフォロワーの出会い
「いいにおい」に惹かれて
スターバックスとサザビーの出会いは、当時サザビーの社長だった鈴木隆三の兄、角田雄二が、米国のスターバックスを訪れたことから始まる。
コーヒーのにおいだけでない、どこか懐かしい「いいにおい」を感じた雄二は、やがてその理由に思い至った。スターバックスの店舗デザインや、スタッフの醸し出す雰囲気が、サザビーで手がけていたアフタヌーンティーのものに似ていたのだ。
コーヒーと紅茶という違いはあれど、スターバックスもアフタヌーンティーも、「洗練されたライフスタイル」を提供するショップという点で一致していた。
すっかりスターバックスに魅了された雄二は、日本で展開できたら面白いのではないかと思い立つ。すぐに隆三に許可を取り、当時スターバックスのCEOだったハワード・シュルツに手紙を書いた。
「いっしょに日本での事業展開を考えませんか」。すると、シュルツ本人から電話で、シアトルへの「招待状」が届いた。シュルツもまた、日本での展開を考えて、パートナーを探していたのだ。
実際に会った3人は、すっかり意気投合する。話はとんとん拍子に進み、当時サザビーの経営企画室長であった著者がプロジェクトの総責任者として指名された。
その後、パートナーとしてのサザビーを不安視したハワード・ビーハー(スターバックス・コーヒー・インターナショナル社長)が日本を視察に訪れたが、アフタヌーンティーの店舗に招待することで、その不安は払拭(ふっしょく)できた。
「店舗に足を踏み入れた瞬間に状況を把握する」という伝説をもつビーハーは、アフタヌーンティーのセンスの良さ、ライフスタイルへの理解の高さを即座に見抜いたのだ。こうして、共通の魂を持つ「主人公」たちが集まり、日本でのスターバックス立ち上げプロジェクトはスタートした。
コーヒービジネスではなくピープルビジネス
立ち上げの後には、苦しいプロセスが待っていた。深い香りと味わいをもたらすダークローストのコーヒーと、魅力的な店舗によって、家でも職場でもないもう一つの居場所「サードプレイス」を提供することがスターバックスの理念だった。
しかし、当時日本のサラリーマンにとって、コーヒーの値段は1杯200円が限度であった。ドトールなどの従来のチェーンはあくまでコーヒーを飲むためだけの場所で、回転率も高い。それと比べると、スターバックスの店舗は効率が悪く、その値段ではペイしないことがわかっていた。
現在の日本では、米国スターバックスのような店舗で収益を上げることは難しい。そう報告すると、ビーハーは顔を真っ赤にして怒った。
「場の雰囲気、ジャズの音色、ほんもののコーヒー、パートナーたちの存在。そのすべてが特別なんだ。これはコーヒービジネスじゃない。ピープルビジネスだ。おれたちはスターバックス体験を提供しているライフスタイルショップなんだ!」
その言葉を受けて、著者たちは、「スターバックス体験」を具体的に想起できるような消費者調査を行った。
案の定反応の鈍かった男性たちに対し、ポジティブな反応を見せたのは女性たちだった。「本当にこんなサードプレイスができるなら、1杯500円以上払ってもいい」という声が6割以上を占めたのだ。こうしてスターバックスは、日本でブランドを確立するための「新たなタイプの顧客」を見いだした。
最後には譲るのがフォロワーの覚悟
「スターバックス体験」は必ず女性の心をつかめる。そう確信した両社は、合弁会社設立のための契約交渉に移った。しかしそこには波瀾万丈のプロセスが待っていた。
サザビーは、「持分50/50の対等な関係」に思い入れがあった。アニエスベーとの提携が「50/50」でうまくいっていたこと、隆三があくまで対等な関係を望んでいたことからの主張だった。
当初は、米国スターバックス側が株式の過半を握る「51/49」の持分を打診していたシュルツもこの提案を受け入れたが、具体的な契約に落とし込む段階では、いくつも調整すべき事項があった。
「徹底してリーダーにたてつく絶対的な味方」であることがフォロワーの使命だと信じる著者は、スターバックス側の言い分をうのみにせず、何度も腹を割って話し合うことで解決してきたが、最後に一つ、「意見が真っ二つに分かれ、デッドロック(こう着)状態になったときにどうするか?」という課題が残った。
両社は出店数と出店スピードの考え方において意見が分かれており、「成長なければ死あるのみ」という実感から、大規模でスピーディーな出店を主張していたビーハーにとって、ここで自社側の意見を通すことは切実な問題だった。
著者は交渉の着地点を探りながら、過去に受けた研修を思い出していた。その研修で行われたカードゲームは、全員が勝利するためには、誰かが最初に相手を信頼して「ギブ」する勇気が必要であることを示していた。
リーダーとフォロワーの関係は「ウィン・ウィン」しかない。それであれば、リーダーを信じて最初に「ギブ」するのがフォロワーとしての覚悟だ、と著者は考えた。
こうしてフォロワーのサザビーは、米国スターバックスの意向に近い「デッドロック条項」を受け入れ、退路を断った。
日本上陸、そして
共感の環を拡げる
米国スターバックスとの合弁会社設立を終えた著者を待っていたのは、サザビー社内の思わぬ反応だった。
宣伝や人の採用を頼んでも対応は冷たく、「いいね!」というリアクションはまったく得られなかったのだ。守秘義務を守ってきた結果、スターバックス立ち上げプロジェクトの存在が社内に周知されていなかったことが原因だった。
そこから社内にフォロワーをつくる過程で、著者は説明責任の3つの段階を実感した。
相手が「事実を正しく理解する」のは最低限で、そこには「納得感」が必要である。しかしその2つだけでは、「納得いかない」というマイナスをニュートラルな状態に戻したにすぎない。目指すべきは、一緒に考え、挑戦したいと胸を熱くするような、「心から共感する」状態である。
それに役立ったのは、スターバックスのコーヒー試飲だった。「米国のコーヒー屋をなぜうちが?」という社内の疑問を払拭するには、スターバックスの「ほんもののコーヒー」を味わわせるのが最も効果的だった。
会議前にコーヒーを入れ、リラックスしながら語り合う「スターバックス体験」を共有することで、共感の環はサザビー社内に広がっていった。
最初の注文は「ダブルトールラテ!」
スターバックス コーヒー ジャパンが設立されてから約10カ月後、銀座松屋の裏側に、スターバックスの日本1号店がオープンした。「A商業地域のB地点を狙え」という戦略通りに構えられた路面店の前には、広告宣伝の予算がなかったにもかかわらず、オープン当日たくさんのギャラリーが集まっていた。
いよいよ店がオープンし扉が開くと、1人の男性が笑顔でオーダーを告げた。「ダブルトールラテ!」。その言葉は、緊張していた新人スタッフたちの心を大いに盛り上げた。「ダブルトールラテ」は、スターバックスでの注文の特徴である「カスタマイズ」の定番だったからだ。
一躍有名になったこのエピソードだが、実はその注文者はシュルツ自身だった。ブランドのトップが、海外第1号店に自ら赴き、粋なオーダーを入れる。その振る舞いは、「スターバックス体験」の幕開けにふさわしい演出だった。
立ちどまるぜいたくはない
スターバックス1号店は、着実に客の入る店舗となった。喜ばしい反面、まだオペレーションに不慣れなスタッフたちにとっては試練の連続だった。
機械の故障やオーダーの取り違え、仕込み量の予測ミス……。しかし体制が整っていなくても、一度始動したらもう立ち止まることはできない。「人がいない」「休めない」「スキルがない」の「ないない尽くし」で、面接に来た人はとにかく全員合格にするような状況だった。
しかし、やがて「ラウンドテーブル」という有志座談会の制度が企画され、尊敬できるスタッフの振る舞いが共有されるようになると、スターバックスの価値観や「らしさ」を体現するスタッフが生まれていった。
彼らは決してリーダー・タイプではなく、本気で店舗をサポートするのが、自分たちの仕事だと考えるフォロワーだった。
雄二は、シアトルでのリーダーシップカンファレンスで、「フォロワーこそが主役」であると学んでいた。「日本が昔からもっていた良さをアメリカの会社に教えられた」と雄二は著者に語っている。
大きな夢を共有する
身の毛もよだつほど大胆不敵な目標
ビーハーは、『ビジョナリー・カンパニー』の著者であるジム・コリンズから、「BHAG(Big Hairy Audacious Goal)」という考え方を学んでいた。直訳すると、「大きくて身の毛もよだつほど大胆不敵な目標」となる。
コリンズは、「ビジョナリー・カンパニーは進歩を促す強力な仕組みとして、ときとして大胆な目標を掲げる」と述べた。それを受けてビーハーが考えたのが、「日本で1000店舗出店する」という目標だった。
それは著者にとってとてつもなく、現実感のない目標だった。「やれるかもしれないし、やってみたい」と考えていたものの、それが本当にふに落ちたのは、中期目標として「300店舗」を掲げてビーハーにいぶかしがられ、「成長か死か」の考えを説かれたときだった。本気で取り組まない目標はただのお題目にすぎないと悟ったのだ。
共通目標を掲げるのがリーダーの仕事なら、それを自分の目標とするのがフォロワーの仕事である。リーダーの本気とフォロワーの本気がシンクロして初めて事業の歯車はかみ合うのである。
「1000店舗」のビジョンに本気で賭けようと決心したとき、著者は失敗のプレッシャーから解放され、成長物語を楽しもうと思えるようになった。いつ実現するかわからないが、いつか必ず達成する。著者がそう決意したこのBHAGは、合弁事業設立から18年後に達成されることとなった。
本書の続きでは、その後の出店の様子や、山あり谷ありの展開、そして合弁事業解消までの様子が語られる。もちろん悲しい別れではないが、読むと胸が熱くなること請け合いだ。個性派集団の挑戦がどのように進み、成熟し、この先も続いていくのか、ぜひ実際の書籍で味わってほしい。
また要約内でも触れたが、スターバックス進出当時日本のコーヒー市場を席巻していたのはドトールコーヒーショップだった。このドトールの魅力にメスを入れた1冊、『なぜ気づいたらドトールを選んでしまうのか?』(上阪徹)の要約も、フライヤーのサイトで公開されている(NewsPicksの記事はこちら)。両社の戦略はどう違うのか、興味を持たれた方にはぜひ併読をおすすめしたい。
Copyright © 2015 flier Inc. All rights reserved.