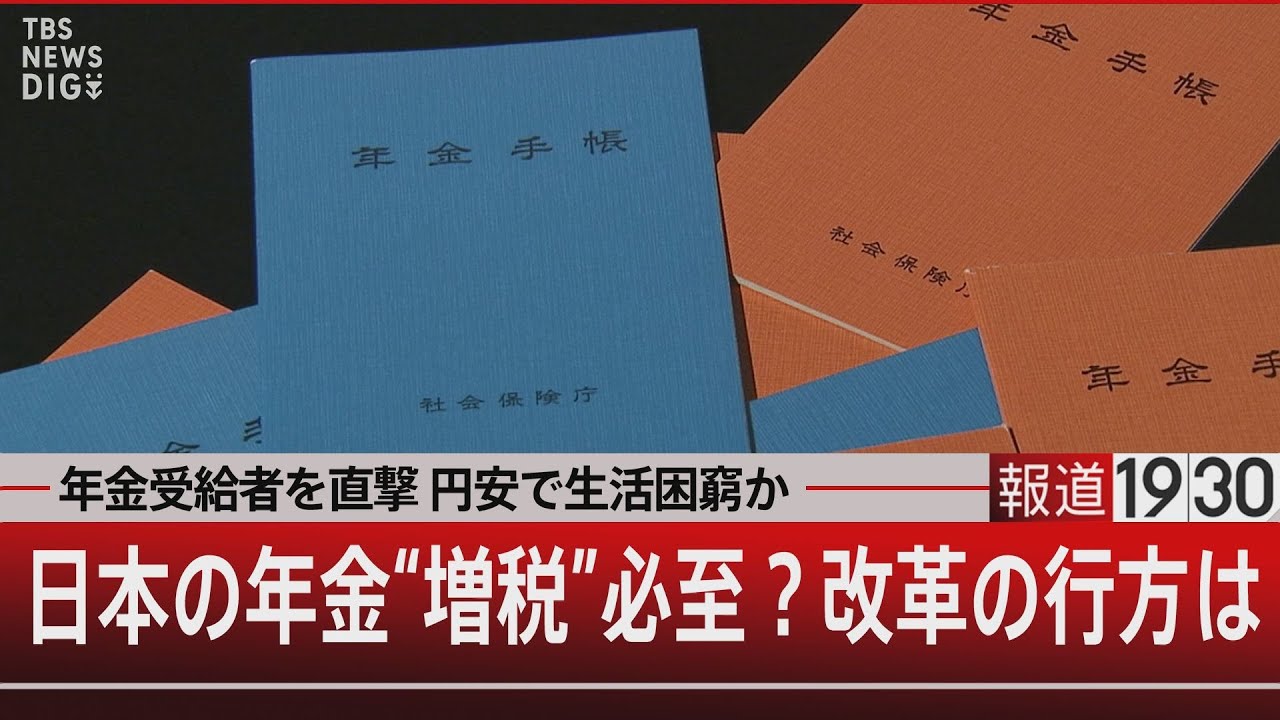
現役時代の給料7割保証 世界1位の年金王国に学ぶ?【報道1930】
コメント
注目のコメント
2019年の年金財政検証によれば、経済成長と労働参加が十分進む場合でも、30年後に年金を受け取り始める世代が受け取る年金は、今の8割程度です。経済成長と労働参加が一定程度なら、年金財政が安定するのは、支給額が今の高齢者の7割強まで落ちた時。
今の標準的な高齢者が受け取る厚生年金額はやや多めに見て22万円程度ですから、8割なら18万円、7割なら15万円で、厚生年金でさえ、夫婦二人が生活するにはかなり苦しい水準になるでしょう。いま6万8千円の基礎年金(≒国民年金)は更に悲惨で、経済が十分成長しても将来は5万円を下回ります。基礎年金保険料納付期間の延長は、将来の国民年金額が5万円を割り込まないようにするためです。どの時代に65歳を迎えても現役世代の所得の5割が貰える制度は既に破綻しています。
政府はいまの若い世代も、納めた保険料の2.3倍の年金が貰えると発表していますけど、実際には1.15倍と見るのが正解です。「収めた保険料」には企業負担分が含まれておらず、これだって本来なら賃金として貰える付加価値ですから、分母に含めないのは理屈に合いません。しかもこの1.15倍も、正社員の夫と年金保険料を納めずに済む専業主婦の二人を足した分が、夫が収めた保険料の1.15倍ということで、お一人様で65歳を迎えた場合、本人負担分と会社負担分を併せた保険料を生きているうちに回収するのは、今の若い世代にとって殆ど不可能です。同様に、現役世帯の所得の5割貰えるというのも、夫婦二人分を併せて現役社員一人分の賃金の5割ということで、お一人様であれば、確実に5割を下回ります。
パートや外国人の年金加入を増やして当面の年金保険料の支え手を維持し、年金は将来も安定しているという絵を政府は今年の年金財政検証でも多分描いてくるでしょう。しかし、その前提には多分に甘い予測が含まれています。年金制度の実態はこんな状況ですから、基礎年金保険料の納付期間の延長のみならず、年金の受給開始年齢を引き上げる、高所得者の年金保険料の上限を引き上げる、高所得者の基礎年金を減額する等々、様々な“改革”が遠からず打ち出されることは確実です。年金当局の大本営発表をそのまま報じるメディアに惑わされず、年金財政検証の前提条件と結果を自分の目でしっかり確かめて、何が起きるか想像力を働かせて将来に備えることが大切です。2024年現在、日本の年金の支給開始年齢(受給し始める標準的な年齢)は、基礎年金は65歳だが、厚生年金は男性64歳、女性62歳(目下支給開始年齢引上げ途中で、いずれこれらも65歳になるが今は違う)
https://www.mhlw.go.jp/nenkinkenshou/generation/50_60.html
年金のパフォーマンスがよいとされる国の支給開始年齢は、1位のオランダも2位のデンマークも3位のアイスランドも67歳。受給の開始を遅らせれば、それだけ年金給付は手厚くなる。
そして、日本では負担と給付の牽連性(結びつき)を重く見るがゆえに、年金保険料をたくさん払った人にはそれだけ多く給付するという度合いが強いし、(現役時代の所得が低いがゆえに)年金保険料を少なくしか払わなかった人にはそれだけ給付が少ない。確かに一旦納められた保険料収入をどう再分配するかは、制度設計次第だが、この牽連性の強さが、老後にもらえる人ともらえない人の差異を大きくする。> 「老後を貧しく過ごす人たちと老後を楽しんでいる人たちがいると社会の調和を壊す」
これはまさに政治的には正しい。経済というか資本主義の世界で生きてきた身としては努力した人が報われないと不公平だと強く考えてしまう。この「政治的」と「経済的」調整をできる政治家が不在なのか。また現在の日本では、この双方の側で平等が崩れてしまっている気がする。
まあ、これだけの異次元緩和などで将来世代に借金を先送りしているんだから当たり前かもしれない。
