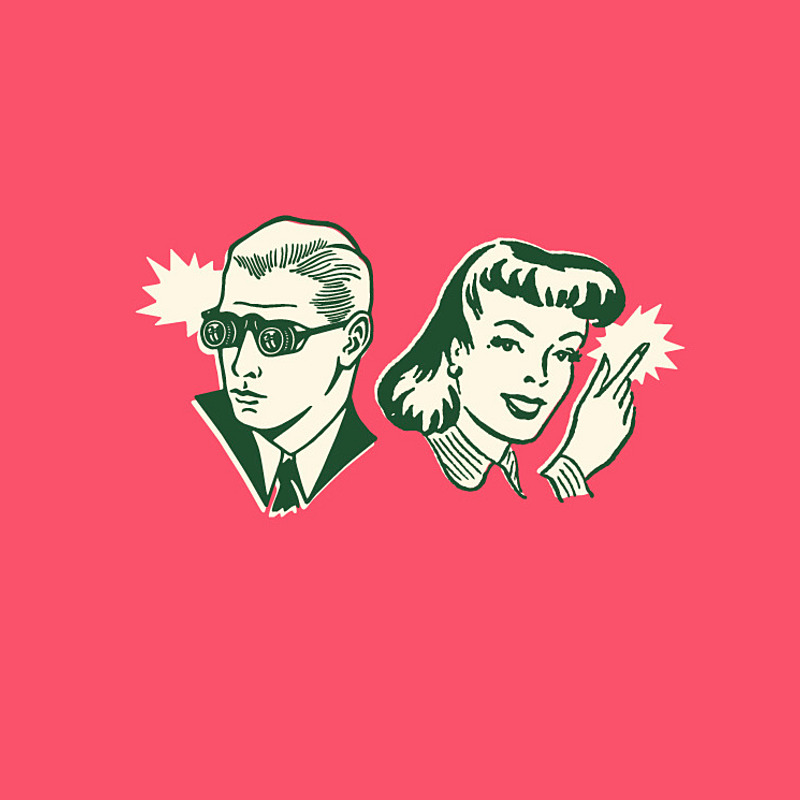
2024/5/8
次世代リーダーに求められる「オープンソース思考」とは
PwCコンサルティング | NewsPicks Brand Design
緊迫化する世界情勢やAIの進化、価値観の多様化など、ビジネスを取り巻く環境が目まぐるしく変化している。このような先が見えない時代において、企業の目指すべき道を示し、変革を牽引するリーダーの重要性はますます高まるばかりだ。
では、複雑化する時代を生きるこれからのリーダーには、どのような視点や考え方が求められるのか。
世界初となる自動運転のオープンソースソフトウェアの開発を通じて「自動運転の民主化」に挑む株式会社ティアフォーのCEO兼CTOの加藤真平氏、同社ジェネラルマネージャーの建川友宏氏、PwCコンサルティング合同会社の戦略コンサルティングサービスを担うStrategy&でディレクターを務める阿部健太郎氏が語る、自動運転の未来と次世代リーダーに求められる思考法とは──。
INDEX
- 「夢と現実」が交差する世界
- カギは「オープンソース戦略」
- モノよりビジョンを語れ
- 自動運転は、想像の10倍先の未来へ
「夢と現実」が交差する世界
──加藤さんは、コンピューターサイエンスの研究者を経て、2015年に自動運転のオープンソースソフトウェアを開発するティアフォーを創業されました。そもそもなぜ自動運転領域に着目したのでしょうか。
加藤 自動運転技術とのはじめての出会いは、米国のカーネギーメロン大学に研究員として在籍したことがきっかけです。
そこで自動運転技術を通じて車が無人で走っている姿を目にしたことで、「技術」「社会」「産業」の3つの観点から大きな可能性を感じました。
まず技術的な観点では、車が自動で動くためには無数の技術が必要であり、その現実的ではあるが難易度が高いテーマに、一研究者として好奇心を掻き立てられました。
社会的な観点では、人手不足の解消や交通事故の減少につながるなど社会に大きなインパクトを残せると感じたこと。最後に産業的な観点では、これから日本企業が世界のトップと肩を並べる可能性が残されたテーマであったことです。

神奈川県藤沢市⽣まれ。自動運転技術のためのオープンソースソフトウェアを進化させたパイオニア、コンピュータサイエンスの国際的な専門家。東京大学大学院情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻特任准教授としても活動。2012年から2016年まで名古屋大学大学院情報科学研究科の准教授を務め、世界初の自動運転オープンソースソフトウェア「Autoware」を開発。また、慶應義塾大学、東京大学、カーネギーメロン大学、カリフォルニア大学にて博士研究員として勤務。2017年には「科学技術への顕著な貢献」をした研究者として、文科省から顕彰を受賞。
この社会的価値と産業的価値を達成できる技術を開発することで、世界と戦いたい──。そう考え、2015年に自動運転ソフトウェア「Autoware」(※)をオープンソースとして公開し、事業化するために同年にティアフォーを設立しました。
(※)AutowareはThe Autoware Foundationの登録商標です。
──Strategy&でモビリティ領域を支援する立場から、2023年8月にティアフォーに転身された建川さんは、自動運転のどこに可能性を感じたのですか。
建川 コンサルタントとして働いていた時に「社会が変わる瞬間」に立ち会う機会が数多くありましたが、まさに自動運転にはそうした可能性があると感じました。
自動運転は、まだ誰も正解が分からない領域です。いま多くの企業が試行錯誤を重ねている現状ですが、ここを打破できれば世の中を大きく変えることができるのではないか。
そして加藤を筆頭に「自動運転革命を本気で起こす」という強い意志を持つメンバーが揃っているティアフォーにも可能性を感じてジョインを決めました。

ティアフォーの事業部門でジェネラルマネージャーを務める。自動運転システム・車両の開発や自動運転サービスの導入など顧客の目的に合わせたソリューションの提供を行う。2023年にティアフォーに入社する以前は、Strategy&のシニアマネージャーとして自動車・モビリティ業界、製造業等のクライアントに対し戦略立案、全社変革等のプロジェクトに従事。東京大学工学部社会基盤学科卒。
──Strategy&でモビリティ領域を中心に多くの企業の変革を支援する阿部さんの視点からは、自動運転の可能性をどのように感じていますか。
阿部 自動運転は、「夢と現実」が入り交じった領域だと感じています。
私は、10年程前に「自動車の3%が自動運転になることで移動の30%が変わる」ということを“夢”として語っていました。しかし、すでに米国では無人自動運転車の取り組みが加速していて、もはや自動運転は夢ではなく現実になってきたと感じます。
このまま進めば、自動運転は自動車産業だけでなく、まちや暮らしのあり方を大きく変えるでしょう。未来の夢を描くと同時に、現実の実装をいかに考えられるかが自動運転領域の面白さだと考えています。

PwCコンサルティング、Strategy&のディレクター。次世代モビリティ事業の企画・実行、海外進出に係る支援を中心に、業際領域において多様なコンサルティング経験を有する。大手自動車メーカーの経営企画部門への出向経験、東南アジア駐在実績を有し、ハンズオンの支援も豊富に行っている。米系コンサルティングファームを経て現職。東京大学工学部卒、同大学院新領域創成科学研究科修了。
カギは「オープンソース戦略」
──阿部さんは、戦略コンサルタントとしてさまざまな企業を支援するなかで、自動運転の社会実装を阻む壁をどのように捉えていますか。
阿部 規制や制度、安全性と品質の両立などさまざまな壁がありますが、やはり長期的な視点が必要な領域のため経済合理性の問題に直面している企業は多いです。
逆にいえば、そこをクリアできている企業は、長期的なロードマップと明確なゴールのイメージを持っている。そして、小さな成功を積み上げながら、巻き込む仲間を増やし、一歩一歩着実に前進している印象があります。加藤さんは実装の壁をどのように感じていますか。
加藤 私は、2つの壁があると考えています。
1つは、事故が起きた時の世間からの反応です。社会実装の過程で、事故が起きれば取り返しがつかなくなる可能性があります。
2つ目は、技術開発で海外企業に劣り、ティアフォーが産業的に厳しい立場に置かれる状態になる可能性があることです。

この2つの壁を乗り越えるためにも、私たちは無償でプログラムを公開するオープンソース戦略を取っています。
すべてを内製で自社開発した場合、もし事故が起きてしまったら、企業として立ち行かなくなってしまうかもしれない。しかし、オープンに開発を進めれば支援者が増え、リスクに備えることができます。
また自動運転領域で後発である私たちは、巨大IT企業と同じ方法で勝つことはとても難しいです。私は日本が自動運転領域において世界で勝てる可能性がある方法は、オープンソースによる開発だと考えています。
異なる強みを持つ企業が協力し合うことで、資金やリソースのある海外企業の単独による研究開発力に追いつくことができます。
阿部 自動運転は安全性が重要な競争軸になるため、これまで各社は内製で技術開発に取り組むことが当たり前でした。だからこそ自動運転システムをオープンソースで開発するという方法には本当に驚きました。

オープンソースで戦うと決められたことには、加藤さんのキャリアの背景も影響しているのでしょうか。
加藤 自動運転の世界で、私のようなコンピューターサイエンスのバックグラウドを持つ人は少ないと思います。
私はずっとOSを研究してきたので、「全取りしてこそ勝利」という考え方がベースにありました。たしかにそうしたオープンソース的な思考が、業界のなかでは新しい発想につながったのかもしれません。
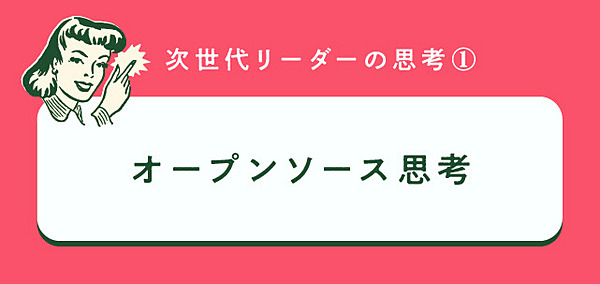
モノよりビジョンを語れ
──業界の慣習や常識に縛られず、変革を実現するリーダーの条件とは?
阿部 オープンソースという考え方で新しい価値を生み出す加藤さんは、ひと昔前とは異なる新しいタイプのリーダーだと感じます。
自分一人で何かを成し遂げようとするのではなく、周りの力を借りながら、世界に打ち勝とうとする。支援者とともに新たな未来を描こうとするスタイルのリーダーが、今後はさまざまな場所でもっと求められていくのではないでしょうか。
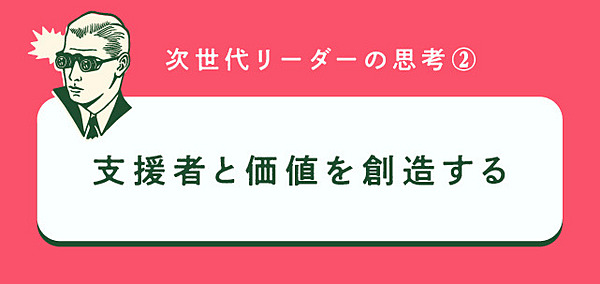
建川 自動運転は1、2年で成果が出るものではないので、長期間にわたり周囲を牽引することがリーダーに求められる。そのためにも言葉と行動で価値を伝えながら、周りを巻き込む力が必要になります。
またリーダーにも0を1に、1を10に、10を100にすることが得意なタイプがそれぞれいますが、加藤は0から1を生み出すこともできるし、道筋を立てることもできるリーダーだと思います。
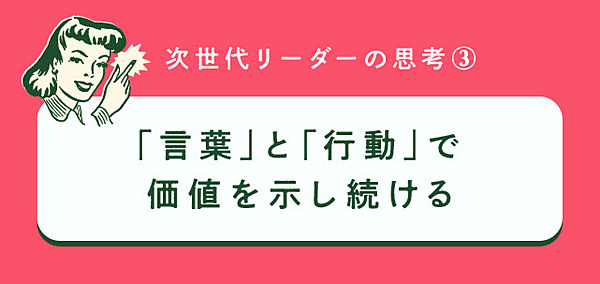
──加藤さんご自身は、リーダーとしてどのようなことを意識していますか。
加藤 リーダーにはミッションを示し、そこに行き着くまでの最も良い方法を描くことが求められます。
ミッションという目指すべき未来に旗を立て、そこまでの道筋をビジョンで示す。そしてその道を歩む人に求められる価値観をバリューで定義する。
もしミッションを定めることなく、いきなりビジョンにあたるコトやモノから事業を考えてしまった場合、自動運転のような長期的な取り組みが求められる領域では走り続けることができません。
また客観的に見て、「人がついてくること」はリーダーの条件の1つだと思います。リードできているということは、人がついてきているということ。逆にいえば、「ついていきたい」と思われなければ、良いリーダーとは言えないのではないでしょうか。
阿部 面白いですね。加藤さんが参考にしているロールモデルはいるのですか。
加藤 リーダー像は主観によるもので正解はないという前提で、参考にしている方はいます。
たとえば私の場合はビル・ゲイツ氏の著書を読んで、「OSで世界を取る」「モノではなくビジョンを売る」といった考え方に共感しました。彼の考え方がリーダーとして正解かどうかはわかりませんが、資本主義市場において成功を勝ち取ったといえるのは事実です。
それを知っていたから、製品としてモノを提供し始める前でも、自信を持って自分のビジョンを語れたのだと思います。
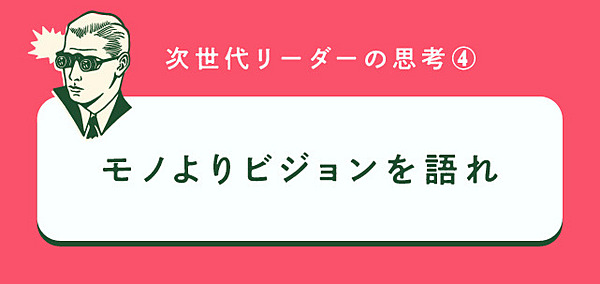
建川 逆にリーダーである加藤さんが、メンバーに期待することはありますか。
加藤 ミッションに依存すると思います。短期目標の場合は、処理能力を優先すると思います。
でも、ゴールが10年後に設定されているような長期目標の場合は、人間関係を大切にし、長くともに走り続けられる人を優先してチームをつくります。ティアフォーの場合は、長期的な取り組みなので後者になります。
自動運転は、想像の10倍先の未来へ
──最後に、改めて自動運転の民主化に向けた意気込みをお聞かせください。
建川 いまはようやく自動運転の社会実装がはじまった段階で、これから加速していくことは間違いありません。個人的には、自動運転技術で地方のバス路線をカバーする仕組みをつくり、日本の社会課題の解決に貢献したいと考えています。
戦略コンサルタントとしてさまざまな企業の現場に入り込み、実行支援をした経験を十分に還元していければと思います。
加藤 自動運転技術が変えるのは、自動車だけではありません。飛行機や鉄道などあらゆるモビリティ体験や暮らしをも変えるものです。また宇宙や海底探査の領域、ヒューマノイドにも応用できるかもしれない。
みなさんがいまイメージする自動運転が実現した未来予想図の10倍先の未来、その先の世界を私は実現したいと考えています。そのためにもオープンソース戦略を軸に、さまざまな組織と協業しながら、自動運転が民主化された新たな未来を描いていきます。
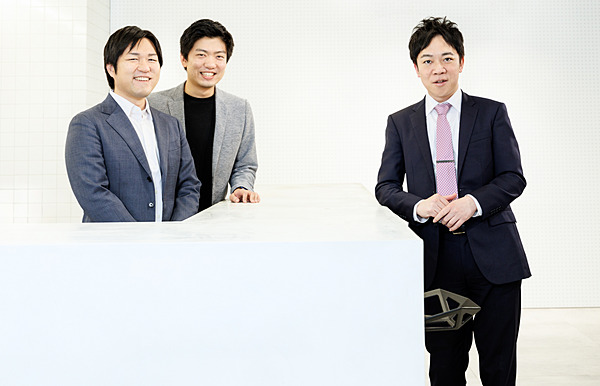
阿部 私はコンサルタントとして、大事な局面でクライアントから逃げないことが大切だと考えています。自動運転のような不確実性も抱えたテーマに取り組んでいると、大きな困難にぶつかることもあります。そういう肝心な時に頼りにならないコンサルタントにはなりたくない。
たとえお金が生まれないことでも、クライアントとの対話から「いま何をやるべきか」をともに考えながら、社会に新たな価値を生み出そうとするリーダーを支援したいと思います。
またコンサルタントには外から業界を俯瞰しながら、領域を越境するための支援が求められると考えています。たとえばモビリティ領域の場合、自動運転が実用化されることで移動手段が変わるだけでなく、都市設計や人々の暮らし、消費購買行動も変わっていきます。
波及する範囲が幅広いからこそ、私たちコンサルタントが貢献できることは多い。これからも領域を越えた視点を大切にしながら、クライアントとともに社会に新しい価値を生み出し続けることを目指していきたいと思います。
執筆:村上佳代
デザイン:小鈴キリカ
撮影:小林由喜伸
編集:君和田郁弥
デザイン:小鈴キリカ
撮影:小林由喜伸
編集:君和田郁弥
PwCコンサルティング | NewsPicks Brand Design


