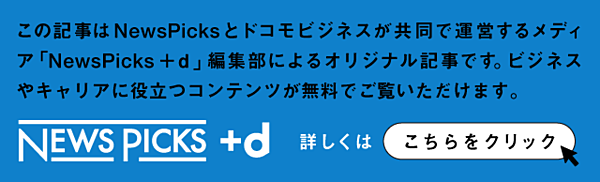2023/7/22
【コミュニケーション】オープンで風通しが良い組織のつくり方とは
餃子居酒屋のスタイルで人気の「肉汁餃子のダンダダン」が急成長を続けています。昨年4月には粉モンの本場・大阪にも進出。店舗数は全国で130を超え、急拡大を続けています。好調の秘密は「社員を元気にする組織づくり」にありました。(第1回/全3回)

井石裕二(いせき・ゆうじ)/1974年、東京都生まれ。大学を中退してゲームセンターでアルバイトをしていた時に、稲盛和夫氏の著書『心を高める、経営を伸ばす』を読み一念発起。会社員生活を経て、2001年に有限会社ナッティースワンキーを設立。2007年に株式会社化し、取締役社長に就任。2011年に「肉汁餃子製作所ダンダダン酒場」(現・肉汁餃子のダンダダン)の1号店を調布にオープン。2022年に「NATTY SWANKYホールディングス」に商号を変更した。
INDEX
- 社内交流を深める「鬼ごっこ」
- 社長が毎回参加の社員旅行
- 新入社員も社長を「裕二さん」と呼ぶ
社内交流を深める「鬼ごっこ」
にぎやかな活気あふれる雰囲気に誘われて暖簾をくぐると、ねじり鉢巻きに「餃」と書かれた前掛けをした店員さんが「いらっしゃいませ!」と笑顔で威勢よく出迎えてくれます。
オーダーは「餃子何枚、焼きますか?」からスタート。テンポのいいキビキビとした気持ちのいい接客は「肉汁餃子のダンダダン」の各店に共通するスタイルです。
飲食店は多種多様な人たちを迎え入れます。すべてが良い客とは限りません。お酒を提供する店ともなればなおさらです。難癖をつけてくるような酔客に当たることも少なくないでしょう。
それでも「ダンダダン」には、暗い表情をしているスタッフは皆無。はじけるような笑顔で楽しそうに働いています。
その秘密は、組織の風通しの良さ。社員やアルバイトも関係なく、たくさんの情報を共有し合います。思いついたプランやアイデアを、ちょっとしたことでも周囲に言いやすい雰囲気があるのです。

(提供写真)
そうした自由でオープンな組織づくりに一役買っているのが、社内イベントです。数多くある中でも特筆すべきは「鬼ごっこ」。
メンバーの1人が鬼になって他のメンバーを追いかけるおなじみの遊びとは少し違い、鬼の顔が描かれた「うちわ」を使ったオリジナルの全社を挙げたイベントなのです。
ルールは簡単。うちわを受け取った店舗は24時間以内に別の店舗に持っていかなければ「鬼」になります。ゲームが開催される期間は決まっていて、終了時点でうちわを持っていた店舗が鬼です。昨年は池袋西口店、千歳烏山店など8店舗が鬼になりました。
鬼になった店舗には罰ゲームも。昨年は当該店舗の社員全員が「平和の森公園フィールドアスレチック」(東京・大田区)に行き、強制的に体を動かし汗を流したそうです。
井石「手作り感満載のゲームなんですが、今はどの店が持っているとか、次はこの店に持っていきますとか、うちわに関する情報がリアルタイムで社内SNSにアップされる。
ものすごく盛り上がります。こうして社内に一体感が生まれることも重要なのですが、実はこのゲームの主眼は店舗間のコミュニケーションを深めることにあります。
チェーンの飲食店はどうしても横のつながりが薄くなりがちで、人間関係も店単位になりやすい傾向が。でも、うちわを持って店舗間を移動すれば、他の店舗との交流が生まれるので、各店舗の社員は孤立することがなくなります。
また、たとえ直属の上司には聞きにくいと感じることがあったとしても、ほかの店舗に接点があれば、そこの店長に話を聞けるかもしれません。鬼ごっこは楽しいだけでなく、組織活性化の効果があると感じています」

(提供写真)
社長が毎回参加の社員旅行
社員旅行も、コミュニケーションを深めるのに効果的なイベントです。
もともとは毎年、社員とアルバイト全員が参加して行われていました。今は社員が増えたことなどの理由により、全員が行くことは難しくなったそうですが、新しく入った人たちを優先的に参加してもらうようにしています。
最近は社員旅行を実施しない企業も増えています。産労総合研究所が実施した「2020年 社内イベント・社員旅行等に関する調査」によれば、社員旅行を行っている会社は全体の27.8%で、4社に1社ほどしかありません。
減っている要因としてもっとも指摘されているのが「社員に不評」だということ。
旅行先でオジサン社員から「昔の自慢話を聞かされる」「クドクドと説教をされる」「お酌をさせられる」「カラオケでデュエットを強要される」──こうしたことを強要され、苦痛を感じる女性社員も少なくないと聞きます。

monzenmachi / iStock
ダンダダンの社員旅行では、社長の井石さん自らホストに徹して社員たちを接待し、じっくり話をします。若手社員やアルバイトからしたら、社長と触れ合う機会もそう多くないでしょう。
彼らにとってもこれほど有意義な機会はなく、参加を嫌がるケースはほとんどないようです。
井石「参加者が一斉に休みを取れば店舗の営業ができなくなるので、社員たちを何班かに分けて実施しています。トータルの回数は増えますが、僕はその都度、必ず参加します。数年前に大阪のUSJに行った時は一人で10連泊ぐらいして、すべての班に参加しました」
東京近郊で開かれるバーベキューも恒例イベントで、昨年は7月に狭山市(埼玉県)の河川敷で3日間にわたって行われました。
毎日2回、昼と夜に開催されましたが、ここでも井石さんはフル参加。社員とキャッチボールをして遊んだり、これも恒例となっている「手作りカレー」を振る舞ったりしています。

(提供写真)
新入社員も社長を「裕二さん」と呼ぶ
一般に創業社長といえば、エキセントリックで圧が強いタイプも珍しくありません。しかし、井石さんは自然体でクセがなく、社員たちともフランクに接します。社長然として構えたり、偉ぶったりすることがありません。
これは本人のキャラクターにもよりますが、みんな身近に感じられるようです。社内SNSのプロフィール欄で、井石さんのことを「大好きです」と“告白”している社員も少なくないそう。
井石さんと社員たちの距離が縮まる仕掛けもあります。それが「呼称」のルール。
ダンダダンでは、井石さんを「社長」とか「井石さん」などと呼ぶ人は皆無です。みんな「裕二さん」。これは新入社員も同じで、入ったその日からファーストネームで呼びます。
井石「明文化された決まりではないのですが、昔から当たり前になっています。その方がお互いに壁もなくなりますよね?
僕も『社長』なんて呼ばれたくないですし、ほかの社員たちも同じで、肩書や名字で呼び合うことはありません。店舗で名札を見ていただければわかりますが、みんなファーストネームです。
違和感? むしろ社員からすれば、社外の人に向かって『井石が……』などと名字を口にしなければならない時のほうが変な感じがするみたいですよ」

(提供写真)
井石さんが接しやすいタイプの社長だとしても、このように社員たちの硬さをほぐし、なんでも話せるような関係になるのは、簡単なことではありません。
呼称のルールは、お互いを身近に感じられるキッカケになっているのです。
トップと若手の距離が詰まれば、両者に挟まれた格好になる中間層はギュッと押されて全体が密になります。その結果、日々の業務で気づいたことを話したり、新しい提案をしたりしやすい雰囲気が生まれるものです。
実際にダンダダンでは社員の提案で実現したものも少なくありません。
社外イベントへの参加もそうです。昨年のゴールデンウィークは、東京と大阪で開かれた餃子フェスに出店しました。

(提供写真)
井石「社外イベントはコストがかかるので、思うように儲かりません。むしろ赤字になることも多いのです。それでも、お祭りみたいに盛り上がれば、社員たちの気分転換にもなっていいかなって割り切っています。
いつも同じ店舗にいて、同じ仕事をしていると飽きてくることもありますからね」
ダンダダンでは、新メニューの開発よりも、すでにあるメニューをブラッシュアップさせていくことに注力しています。定番メニューを入れ替えたり変化をつけたりすることはほぼゼロ。
ただ、フェスなどの社外イベントでは通常のメニューにはない「手羽餃子」や「チーズ手羽餃子」も提供しました。
普段と違う場所で、普段と違う相手と、普段と違う作業に取り組む機会があることも、社員同士のコミュニケーションを活性化する効果があるようです。
(vol.2につづく)
取材・文:二口隆光
デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)
編集:奈良岡崇子
デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)
編集:奈良岡崇子