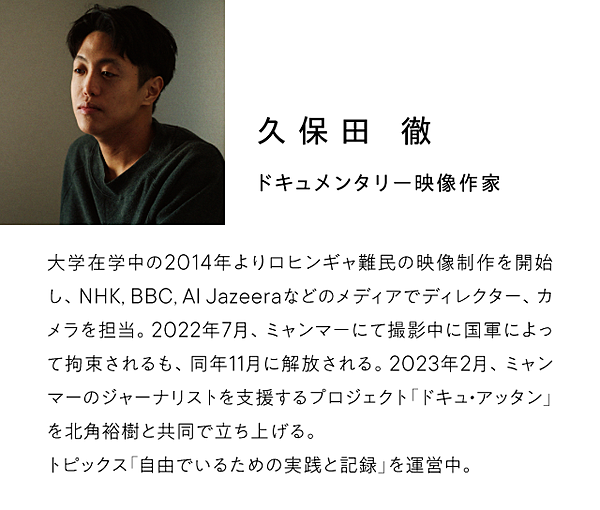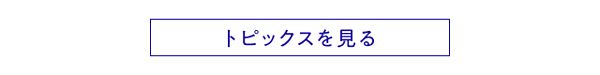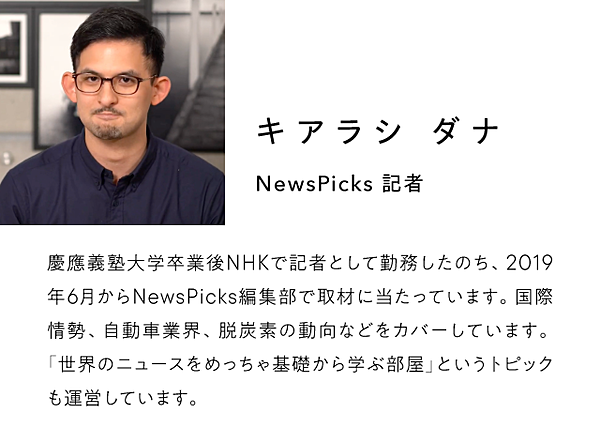2023/6/30
【久保田徹】ミャンマーでの拘束と強制送還の後に思うこと
6月1日からトピックス「
自由でいるための実践と記録」を運営されているドキュメンタリー映像作家の久保田徹さん。
昨年2022年7月30日、ミャンマーで撮影中に国軍に拘束され懲役10年を言い渡されるも、111日間の拘束を経て同年11月に日本に帰国しました。現在は日本を主な拠点として、ミャンマーの現状を知らせるため多くのメディアでの発信やドキュメンタリーの制作を行っています。
トピックスでは「実際に見たこと、経験したことを、読者が追体験できるような記事を書きたい」という久保田さんに、同じくトピックスオーナーでNewsPicks編集部の記者キアラシ・ダナと糸井あかりがミャンマー拘束中のこと、ミャンマーに渡った経緯、そしてこれからの活動についてお話を伺いました。
- 自分にしか撮れない友人の姿がある
- 「〇〇問題」からではなく、「人への愛着」から始まる制作
- 激動する社会の中で撮影するということ
- 声を奪われている人たちに、自分ができることを
自分にしか撮れない友人の姿がある
糸井 これまでの久保田さんの経歴やお仕事を拝見していて、「ベテランジャーナリストのような感じの方なのかな」と最初は思っていたんです。でも、よくよく見ると1996年生まれ。むしろ同年代で驚きました。
キアラシ 久保田さんは、慶応義塾大学在学中の2014年から、ミャンマーの少数派イスラム教徒であるロヒンギャに関するドキュメンタリー映像の制作を始めてらっしゃいますね。ロヒンギャの人々とどのような出会いがあって、この道に進むことになったんですか?
久保田 本当に偶然ですね。大学の先輩が取材プロジェクトをやっていて、日本にいるロヒンギャの人たちと出会えることになったんです。AO入試のときに実は「ロヒンギャを巡る民族対立の解決にソーシャルビジネスによって寄与する」という志望理由を書いて大学に入学したのですが、高校生のときには実行する覚悟を持っていたわけではありませんでした。でも、この偶然を逃してはいけないなと、ロヒンギャの人たちが住む群馬県館林市によく行くようになりました。日本で暮らすロヒンギャ難民の方々にご飯をごちそうしてもらったり、いろんなところに連れていってもらったり……今じゃ考えられないですけど、ミャンマーに連れていってもらったこともありました。
キアラシ トピックスの1回目で、久保田さんはご自身について「ドキュメンタリー映像作家」と名乗っています。
久保田 そうですね、僕は「ジャーナリスト」という肩書きで紹介していただくこともあるのですが、自分自身は「映像作家」だと思っています。元々はニュースレポート的なドキュメンタリーを作ることから始めたのですが、次第に1人の人間の姿を丁寧に映像に描くことを大切にしていきたいと思うようになりました。
2021年にミャンマーでクーデターが起こってから現地で多くの友人たちが被害にあいました。逮捕された友人や、行方がわからなくなった人も多くいます。その後、1年半が経っても現地に残っている友人のことが気がかりでした。多くのミャンマー人たちが国外へ逃れる中、彼はずっと現地で人道支援に携わっていました。彼の姿を映すことで、ミャンマーで起きている本当の窮状を伝えられるのではないかと思いました。それは「自分にしか撮れない、自分の友人の姿」でした。
キアラシ 久保田さんがミャンマーに渡ったのは2022年7月。デモ取材中にミャンマーの治安当局に拘束されて、独房に拘禁されていたんですよね。どういった日々だったのか、我々には想像もつかないんですが……。
久保田 デモを撮影していたところ、私服と思われる軍人に捕まってしまいました。銃をつきつけられて、手錠をかけられて。始めの1週間くらいは留置所に入れられて、ひどい現場でした。幸いにも、日本人であったために身体的な拷問を受けることはなく、刑務所に移送されてからは独房に入れられました。
そこから約3ヵ月半。形だけの裁判が行われて、10年の刑が言い渡されました。僕が罪に問われたのは、入管法と、電気通信法と、煽動罪の3つ。そのうち後者2つは軍事裁判の管轄で、裁判といっても弁護士もいれられないし、控訴もできません。さらに、裁判の根拠となる証拠をでっちあげられています。取り調べ中に、デモ隊が持っていたバナーを手に持たされ、写真を取られました。のちにその写真が「抗議デモに参加し、大衆を扇動した」という証拠として使われました。法治国家としての体裁すらないような状態で、結果を読み上げられて終わりです。
キアラシ なるほど……。アウンサンスーチーさんに33年の刑期が言い渡されていましたが、彼女に関しても、もちろんほかの国民の方々も、そういった状況下にあるということでしょうか。
久保田 はい、クーデター以降、不当に拘束されている人が2万人以上いると言われています。僕が言い渡された刑期は10年だったんですが、外国人の場合、判決を下したらすぐに強制送還されるパターンが多いので、おそらく10年刑務所にいることはないだろうと思っていました。でも判決がくだされてから1ヵ月ほど何も音沙汰がなく。次第に「これは最悪、本当に10年いることになるのかもしれない……」と考えるような時間でした。
糸井 「自分にしか撮れない友人の姿を撮りたい」とおっしゃっていましたよね。とはいえ、すごく危険なことが予想される中でも、ミャンマーでの取材に踏み切れた原動力はどんなものなんでしょうか?
久保田 何よりも、声が届きづらくなってしまったミャンマー国内で生きている人々の姿を伝えたいということが大きかったです。
都市部のヤンゴンにおいて、抗議デモや民主派武装組織との接触をすることのリスクは大きいです。ですので、あくまでも市政の人々の生活に着目し、密室で映すことに専念するつもりでした。現地の友人たちからの助言を得ながら安全管理をしていました。
しかし、現地に到着してしばらくすると、抗議デモの撮影をするべきだと考え始めました。クーデターから一年半が経過し、一見すると平穏を取り戻したかのように見える都市部ですが、見えないところで人々が弾圧されています。表面上は平和な街並みと、実際に抑圧されている人々の心情のギャップが、強く印象に残りました。現実に起きている弾圧の実態を伝えるために、抗議デモを撮らなければと考えてしまったんです。結果的に、人々が受けている弾圧を身をもって体験することになってしまいました。感情にながされ、事前に自分で決めたルールを破った形になります。そのルールを破らなければ、拘束される可能性はかなり低かったと思います。
「〇〇問題」からではなく、「人への愛着」から始まる制作
キアラシ 自分の中の課題として常々意識しているのが、人々の関心なんです。たとえばロヒンギャ問題やクルド人問題はずっと昔から存在していて、ミャンマークーデターやウクライナも、世界中の人が注目しました。でも、時間がたってくる中で、必ずしもトップニュースじゃなくなってくる。世界中でいろんな問題があるけれど、日本国内の人にとっては「遠くのこと」。久保田さんのように一次情報である人々の表情を撮って伝えることはできても、なかなかそれに関心を持ってもらえないときもあります。それを突破していくために、どういったことを意識しているのか、今日ぜひ聞いてみたかったです。
久保田 関心のギャップが生まれてくるというのは、ミャンマー国内でも起こっていると聞きます。まず、都市部と山岳部で起こっていることが違う。さらに都市部でも時間の経過で差が生まれつつあります。クーデター直後に捕まって、2年獄中で過ごして出てきた人は、「自分が出獄するころには、みんなが本当に戦ってくれているはずだと思っていた」と。でも、少なくとも都市部では、ゲリラ的なことは行えなくなっていて、これまで通り暮らしている人がほとんど。「心の中では革命に参加してるよ」とは言うけれど、獄中で過ごした人にとっては、「俺たちが獄中で過ごした時間はなんだったんだ」と感じるという……。
キアラシ それはつらい。外国からの介入が期待できない中で、どれくらい抵抗運動を続けられるかという、本当に難しい問題がある。
久保田 ウクライナと違って、他の国から安全保障上の脅威ではないとみなされていますからね。
キアラシ ウクライナは地理的にも歴史的にも、アメリカやイギリスやドイツといった大国から大変な興味関心を持たれている。でもミャンマーは地理的にそうではなく、興味関心を持たれていない。他国が介入など大きな動きをしないから、現状が続いている……これは残酷な構造だなと感じます。
久保田 理屈で言ったら本当にそうですよね。だからこそ、アジアの日本がちゃんと立場を示していかなければいけないという地理的背景も、ミャンマー国軍の礎を作ったのは日本帝国陸軍という歴史的背景もあります。
キアラシ G7で「アジアの代表」ということを誇りに思うわりに、意思表明や行動を取れていないもどかしさがありますね……。
久保田 ただ、最初のキアラシさんの質問に戻ると、僕自身は「問題」という視点から物事を考えるというよりは、始めに人がいて、その人に導かれて撮影が始まるという感じなんです。その人の実存が最も伝わる形で映像を作れたとき、その背後にある社会や問題が浮き彫りになるという形です。
たとえば、埼玉県・川口市に住むクルド人のアリさんを、2020年に「東京リトルネロ」(NHK)という番組で撮影しました。日本で「仮放免」の状態になっている人は、クルド人が一番多い。仮放免の人は県をまたいだ移動ができないことで知られています。この「居場所と移動の自由を奪われている」ということを、コロナ禍でロックダウンを全人類が経験したタイミングである2020年だったら伝えられるんじゃないかと思いました。
そんな中で出会ったのがアリさん。彼は埼玉から千葉に行く大きな橋を渡ることができない。そういう状態を映像にしました。それは「クルド人問題をやらなきゃいけない」というよりは、人と人でつながっていって、その人への愛着が生まれる中で、自然とやるべきことが見えてくるというような感覚です。
キアラシ なるほど。インタビュー冒頭でも少し触れましたが、久保田さんは「ジャーナリスト」と「映像作家」というのを分けて考えていらっしゃいますよね。どういった違いがあると考えているんでしょうか。
久保田 明確な違いを定義するのは難しいと思いますが、ジャーナリストは、「情報を入手して裏取りをして発信する」「ニュース性・今性を追いかける」という役割を担っていると思っています。自分は必ずしもそういったことを専門としているわけではありません。もう少し長いスパンで記録し、100年後に残っても意味がある映像を作りたいという思いです。
もうひとつは、被写体との距離の近さがあるかと思います。どのようなシーンを撮っていくかを被写体とともに考え、同じ目線に立って制作をします。
キアラシ 取材者と取材対象者で分かれているというよりは、もっと一体になっているようなイメージなんですね。
久保田 はい。もちろん、ジャーナリストを名乗っている人でも、そういうやり方をする人はいると思うんですけどね。英語だと「ジャーナリスト」と「フィルムメイカー」というように、役回りの違いが認識されているような気がするんですが、日本では線引きがあまり認識されていないように思うので、僕は映像作家を名乗るようにしています。
激動する社会の中で撮影するということ
糸井 トピックスのタイトルが「
自由でいるための実践と記録」ですよね。このタイトルに込めた思いを教えていただいてもいいですか?
久保田 自分は、中途半端なエリート育ちだと思っているんです。何かと頭でっかちな人間に育っていった部分があって、物事をどちらかというと論理のみで考えるような人間に育ちました。大学で映像というものを手にして初めて、そういった自分から解放されたというか、人間の感情がわかるようになっていったんです。
ドキュメンタリーを撮るごとに、映っている人の人生をちょっとずつもらう感覚ですね。その人の、痛みや苦しみ、ちょっとした口癖や言い回しが僕にうつる。これって結構面白くて、それまでの自分が崩壊して、ちょっと離れた新しい自分ができていくような感じ。視野が広がって、物事を見る視点を得ることで、ひとつずつ自由になっていると思うんです。
キアラシ なるほど……。少し久保田さんとは違うかもしれませんが、規格外の人の話を聞くと、「そんなものの考え方があるんだ」とはっとすることがあります。自分の中に落とし込むのは簡単ではないですが。
久保田 喋ることは言語的な知性ですが、映像を通じると、身体的な知性の存在にも気づきますね。なかなか言葉で表現するのは難しいんですが……顔を映さないようにして撮影していても、その人の感情や、空気感が伝わってくる人がいる。そういう人は、他人が考えていることもすぐにわかるんですよね。たとえば森本学園問題の撮影では、赤木雅子さんの感情を読み取る力のすごさを感じました。亡くなった夫の赤木俊夫さんの遺品を整理しているとき、いたわるような、丁寧に感情を見ているような、そういう空気感があったのが強く印象に残っています。
キアラシ ミャンマーの現場を見てから帰国し、政治や社会に無関心に見える東京の若者の姿を見てどう思いましたか?
久保田 ミャンマーの獄中では、大学生くらいの子たちが捕まっているんですよ。判決を下された彼らが「俺は3年だった」「俺は10年だった」と言い合っている光景は、まるでテストの成績を言い合っている学生のようでした。そういう年頃の子たちが、命がけで選挙の権利を求めている。日本に帰ってくると、そもそも選挙の権利が認識されていないというか、そういう力を持っていることを知らない雰囲気が社会に漂っていて、違和感はありましたね。
でも、なんとも言えないですね。民主主義というのはプロセスでしかないと僕は思います。選挙に行けばOKという話でもないし、社会問題をやっているから偉いという話でもない。それぞれがそれぞれの能力を持っていて、その能力を用いてどれだけ世の中を良い方向に変えていけるかを考え続けることなんじゃないでしょうか。その中で、僕は自分にできることをやり続けたいなと思っています。
キアラシ 「東京リトルネロ」をはじめ、久保田さんはコロナ禍まっただ中のころ、国内のさまざまな人を取材していましたね。
久保田 あの時は、今とはまた全然違う状況でしたよね。貧困や外国人差別など、これまで溜まっていた問題が噴出していた。社会運動も高まりがあって、そういうタイミングに現場に出て撮影した映像は、非常に貴重な記録にもなっていると思います。2021年の入管難民法改正案の見送りなどは、社会運動の成果のひとつだと思います。これまでずっと活動していた人に加えて、コロナの時期でデモに参加した若い人も多い。引き継がれていって、2年前よりもずっと大きな声が上がっている状態だなと感じています。
声を奪われている人たちに、自分ができることを
キアラシ いま、久保田さんが一番関心のある分野はなんでしょうか?
久保田 今回拘束されてしまったことで、ここ半年ほど「インタビューされる側」になってしまっている歯がゆさがありました。本来自分は映像で伝えたいという立場ですが、今回はそれができず、自分の体験を言葉で伝えることが多かった。そろそろ、自分の仕事である映像制作で伝えていきたいと思い、「
ドキュ・アッタン」というプロジェクトを始めています。
ミャンマーのジャーナリストの支援プロジェクトです。彼らの映像作品を翻訳してWebサイトに掲載し、視聴者が制作者に1000円から直接寄付できる仕組みです。彼らは今タイとの国境地帯に逃げているのですが、そこにいって彼らがいかに制作しているかを撮影してきて、編集を進めています。僕自身はミャンマー現地に入ることはできないので、現地周辺で活動している人々の状況を伝えていく、彼らが声をあげようとするのをエンパワーするような活動をしていきたいです。
キアラシ 「ドキュ・アッタン」のプロジェクトのアイデアは、どのタイミングにできたものですか?
久保田 以前からふんわりとは持っていましたが、拘束されていた3ヵ月半で考えた部分が大きいです。完全に閉ざされた場所にいることで、いかに声を奪われるかということを実感しました。もしここから出られるのであれば、同じく声を奪われている立場の人を応援することに意味があるし、筋が通っているんじゃないかと。帰国してから具体的に動き出して、ミャンマーのクーデターから2年にあたる2023年2月1日にリリースしました。
今はこのプロジェクトで手がいっぱいになってしまっているのですが、やはり難民の受け入れについてはもっと取り上げたいと思っています。日本は難民をほとんど受け入れていないけれど、すでにたくさん難民にあたる人が住んでいる。それを認識していかなければいけないなと。この間、在日ロヒンギャとミャンマー人が初めて共同で募金活動をしていたんです。大型サイクロンの被災者のためのものですが、これまで在日ミャンマー人はロヒンギャに対して排他的だったので、一緒にやっていることは本当に画期的なんです。そうした新しいうねりを追いかけていきたいですね。
執筆:青柳美帆子
編集:豊岡愛美
デザイン:九喜洋介