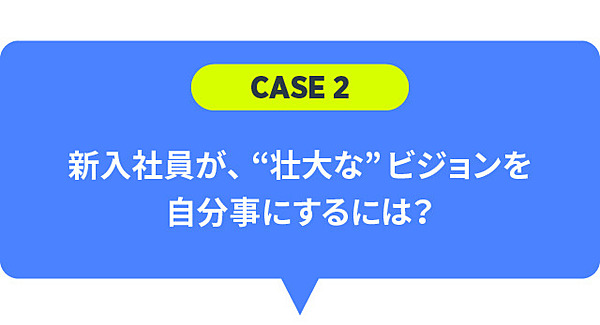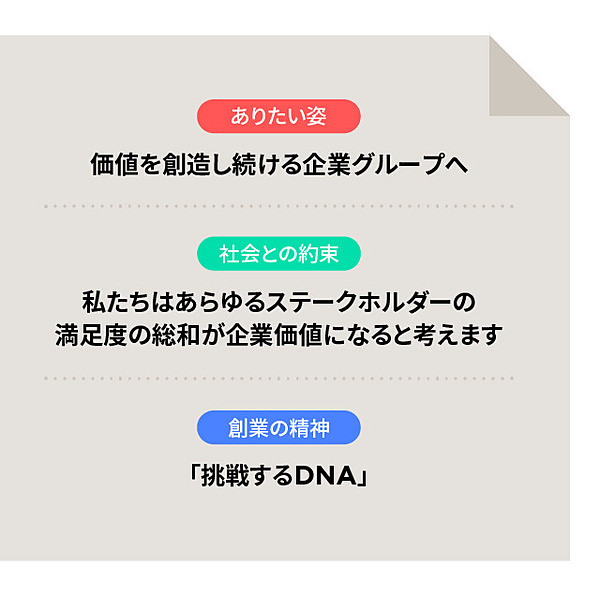2023/3/22
社員の“やる気がない”は本当か。対話から始める組織変革の実践
NewsPicks Brand Design editor
「企業のビジョンを社員に浸透させたい」「モチベーション高く働いてもらいたい」と一言で言っても、一人ひとりの社員を見れば、職種も世代も考え方も異なる。多様な社員の個性を活かしながら、同じ船に乗って一つの目標を目指すには、どんな組織づくりの姿勢が求められるのだろうか。
本記事で取り上げるのは、組織変革や理念浸透を目指した2社。創業110年を超える大手化学メーカー・三井化学と、不動産にまつわる幅広い事業展開をしている東急不動産ホールディングスだ。
研究開発部門での長年の課題に向き合った三井化学の葛藤や、幅広い事業展開がゆえに理念浸透に頭を悩ませていた東急不動産ホールディングス。2社の取り組みに伴走した、人材・組織開発支援を手掛けるセルムの働きかけとは。現場に話を聞いた。
研究者の顔を輝かせたい
研究者の自由な発想を起点に、数年から数十年にもわたる実験を重ねて、新たな素材や製品を生み出す化学の領域。
三井化学は、そんな化学領域のメーカーとして、110年以上の歴史を持つ老舗企業。その開発領域は多岐にわたり、医薬品から農業化学品、自動車部品まで、幅広い化学製品を世に送り出してきた。
しかし、2020年から同社の研究開発本部で本部長を務める柴田真吾氏は、大きな悩みを抱えていた。それは、三井化学の研究者に“元気がない”ことだったという。
「研究者の仕事には本来、自分の好奇心を追求できる面白さがあります。ですが、三井化学の研究開発本部のメンバーの顔は、正直何だか曇っていて。
研究に対するワクワク感が伝わってこない状況だったんです」(柴田氏)
かつて研究開発本部に勤めていた経験もある柴田氏は、その要因に思い当たる節があったという。
それは、30年以上も前に遡る組織改編。「研究開発部門」自体が研究の主導権を握る体制から、製品を販売する「事業部」が研究の主導権を持つ体制に変わったのだ。
「それこそ私が入社した1980年代の研究開発部には、『10年後』にビジネスとして成り立つ基盤技術や技術を開発していこうという、長期的視野に立った研究を歓迎する雰囲気がありました。
しかし組織改編が行われてからは、『その研究は3年後の売上につながるのか』という短期的な視点で、研究の良し悪しが判断されやすくなってしまったんです。
研究開発本部の社員のやる気がないという話ではなく、組織として長期的な視点でやり取りをしにくくなっていた。私はそう考えているんです」(柴田氏)
もちろん、事業部が研究をリードする体制が一概に悪いわけではない。
化学メーカーとして製品の売上と研究は切り離せないし、研究者としても自身の研究がプロダクトを通して世に広まる面白さもあるだろう。
一方で、事業部門や取引先からの要望に応えることに追われる日々では、「本当はこんな研究がしたい」「別の分野に挑戦してみたい」といった気持ちは、薄れてしまいがちだ。
「私自身は、長年研究開発本部から離れていたのですが、この状況にずっとモヤモヤを抱いていました。
だったら自分が研究開発本部に戻り、この組織風土を変えていこうと異動を決意。2020年に本部長に就任したのです」(柴田氏)
「人を見ていなかった」という反省
組織文化を変える上で、柴田氏が最も重視していたのは、研究者の一人ひとりの声に耳を傾けることだ。そう思うようになった背景には、柴田氏自身の反省があるという。
きっかけは、自身が受けたコーチングだった。
「コーチングを受けて得た最初の驚きは、『自分自身の人生のミッション』を問いかけられたことで、自分の心の奥に眠っていた想いが引き出されたことでした。
さらなる驚きは、組織を変えたい想いはあっても、その実現方法を考える際の私の姿勢が非常に『一方的』だったと気づいたことです。
それまでは、自分の理想や考えを押し付けるばかりでした。目の前にいる社員がどんな性格で、どんな想いを持って働いているかを、そもそも知らなかったのです。
目の前の人を見ないで、何が組織変革だ、何が場づくりだと。それまでの人との向き合い方を、すごく反省しました」(柴田氏)
この経験をもとに柴田氏は、上から理想を押し付けるのではなく、まずは社員一人ひとりの声を聞こうと対話の機会を設けていった。
「社員を知るための一丁目一番地として、まずは各研究分野のグループリーダー、そして次はチームリーダーとの1on1の対話の機会を設けました。
相手の話を聞きたいなら、まずは自分から自己開示すべきだと思い、自身の悩みから、経営に対する不満まで、包み隠さず正直に話しました。
すると、彼らもだんだんと心を開いてくれて。普段から抱えていた悩みや素朴な疑問、諦めかけていた想いを、徐々に話しだしてくれたのです」(柴田氏)
もちろん反発もあったという。「そんなことをやっている時間はない。現場の忙しさを分かっているんですか」と辛らつな意見をもらうこともあった。
それでも対話を重ねると、一緒に熱を持って取り組んでくれるリーダーが現れ始めた。その熱が、徐々に組織全体に伝播し始めたのだという。
1000人の「MYミッション」を創る
リーダーたちの、密かな熱意に火をつけることに専念して、約半年。
意識改革への芽を見出した段階を経て、2022年より組織全体の風土を変える取り組みに踏み出した。
とはいえ、三井化学の研究開発本部に所属する社員数は1000人以上。その全員の目線を合わせられるよう場を設計するのは、至難の業だ。
そこで、人材・組織開発のプロフェッショナルであるセルムと協業。
組織全体で、社員一人ひとりの「MYミッション」を創る試みが始まったのだ。
「『MYミッション』とは、自分の人生の目的や、人生において成し遂げたいことは何かということ。
MYミッションを軸にした1on1の対話を通じて、研究者が挑戦をし続ける後押しを行う。
さらに挑戦し続けることが組織風土となり、VISION2030(長期経営計画)の実現にもつながると考えています。
実際のプログラムでは、セルムとともに進めた場の設計とファシリテーションのもと、少人数のグループに分かれ、まずは互いがどんな人なのか、知り合うことから始めました。
その上で、自分自身を突き動かすMYミッションを創り、他者に伝えるセッションを重ねました。
研究者には、『幼少期からものづくりが好きで研究職を志した』なんて人も多い。
そんな自分の心の奥にある想いに向き合うことで、改めて自分は何をしたいのか、何ができるのかを考える。そんな機会にしてもらえたのではないかと考えています。
他の部門からも、『研究開発本部のメンバーが元気になった、前向きな提案が増えた』という声が聞こえてきています」(柴田氏)

この図のように自分の感情や価値観、原体験まで深掘りすることで、MYミッションを見出していく。
今回の取り組みで手応えを感じた柴田氏が次に目指すのは、MYミッションを仕事に結びつけてもらうことだ。
「1on1の対話やグループディスカッションを通じてMYミッションを作る先には、組織のビジョンと自分がすべきこととの重なりをどう見出していくかというフェーズがあります。
そのためには、MYミッションを軸にした対話のダイアログチェーンが永続的に続いていく必要があります。
今はまだ、各々のMYミッションに行き着いた段階。MYミッションを全員が意識し続ければ、挑戦する組織への改革は自ずと走り始めると考えています。
とはいえ、私も組織変革のプロではありません。そこに専門性を持つセルムの知見も借りながら、決して諦めることなく、やり続けていくつもりです」(柴田氏)
ビジョンとの距離が遠い新入社員
企業の理念やビジョンは、その性質上どうしても抽象度が高くなる。
特に、日々の仕事に精一杯の1年目の社員が、その理念やビジョンを自分事にするのは、かなりハードルが高いといえる。
そんな課題に向き合うのが、東急不動産ホールディングスだ。
東急不動産ホールディングスグループでは、幅広い事業を網羅する強みを持つ一方で、都市開発事業から戦略投資事業、管理運営業、不動産流通事業など事業が多岐にわたるからこその悩みも抱えていたという。
「ホールディングス全体として、10年後の未来に向けたありたい姿の実現のため、2030年に向けた長期ビジョン『GROUP VISION 2030』を策定しました。
ですが、ビジョンというものは、そもそも抽象的なものです。
新入社員には、『目の前の自分の仕事には関係のない、会社としての大きな話』と思われてしまい、本当の意味で社員一人ひとりにビジョンを届けることに、課題を感じていました」(堀口恭子氏)
そんな中で始めたのが、1年目の社員に「GROUP VISION 2030」の理解を深めてもらうための研修だ。
「たとえ抽象的なビジョンでも、長く在籍している社員なら、『自分の仕事を通してもっとこんな価値を発揮したい』と、自分の価値観と会社のビジョンが結びつく瞬間はあると思うんです。
ですが、働き始めて日が浅い社員がそんな心境に至るのは難しい。コロナ禍の影響もありグループ会社の同僚たちと対面で話す機会も減り、ホールディングスの一員であるとの感覚を持ちづらいのも現状でした。
だからこそ新入社員の皆さんが、改めて自分の想いと自社のビジョンに向き合う機会を作ろうと、動き出したんです」(堀口氏)
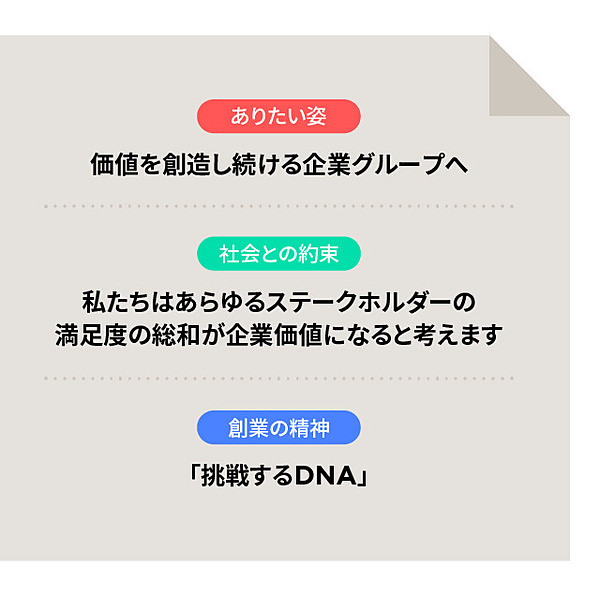
東急不動産ホールディングスグループの理念体系
押し付けではなく、問いかける
入社して10ヶ月の社員約400人が受講する、大規模なこのプログラム。
具体的には、異なるグループ会社で働く社員数人が一つのグループとなり、自分自身が大切にしている想いを発表し合う。
プログラムの設計において、アドバイスを求めたのが、人材・組織開発のコンサルティング会社であるセルムだった。
プログラムを設計する中でも、最も深く話し合ったのが、問いの設定だったという。
「入社1年目の社員にいきなり壮大な問いを投げかけて、『自分には関係ない』と思われてしまっては本末転倒。
そこで、セルムやセルムと協業する外部パートナーにアドバイスをいただき、『入社してからの10か月間で、最も心が動いた瞬間とは?』といった、自分事として考えやすい問いを設定しました。
また、マテリアリティなどの少し難しい話なども、一度会社の枠を取り払い、『自分が最も興味のある社会課題は?』など、Z世代だからこそ感じている個人の社会に対する想いも話しやすくしました。
その問いを深掘りすることで、自分が大切にしている価値観に気付き、会社のビジョンとの重なりを見つけてもらえるように、と。
理念を一方的に発信するのではなく、自分自身と結びつけてもらう意識を持つことに重点を置こうと、工夫しましたね」(堀口氏)
実際のプログラムでは、例えば普段の業務で関わりの薄いリゾートホテルで働く社員と、不動産賃貸営業の社員が、『どうやってお客様と関係を築いているの?』と相談し合うような場面もありました。
また『外国籍の方が日本でも入居しやすい環境を自分が創り上げたい』など、個人が感じている社会課題の解決への意見交換なども行われていました。
グループ内で全く異なる仕事をしている同期でも、共感する部分やヒントを得られる話題が多々あったようです。
互いの価値観を共有することで心の距離が縮まり、仲間意識が生まれていくのだと、私も改めて実感しました。
この仲間たちがいるからこそ挑戦していきたいという気持ちの醸成につながっていたように思います」(堀口氏)
悩みもシェアできる組織が健全だ
一方でこうした研修では、いくら正直に話していいと言われても、「人事が見ているから……」と取り繕った回答をしてしまう社員もいるのではないか。
当初はそんな不安も抱えていたというが、実際のプログラムでは、あっという間に社員の率直な意見交換が始まり、堀口氏自身も驚くほどだったという。
「当グループのカルチャーなのか、みんな本当に素直に自己開示するんです。人事の前でも、仕事の悩みや会社への不満を、どんどん言っちゃう(笑)。
ですが、密かに不満を抱えるよりも、『そんなこと思っていたんだ!』『みんな同じことで悩んでいるんだね』『どう改善していこうか』とシェアできる方が健全ですよね。
さらに発見だったのは、多様な事業に携わる多様な価値観を共有することで、ダイバーシティが進んでいくのではという期待を持てたことです。
普段の仕事の中で、心の奥底でどんなことを思っているかなんて、なかなか伝える機会はないですよね。
そんな互いの個性や考え方の違いをシェアすることで、属性や外見などとはまた異なる、“内側のダイバーシティ”の尊重や受容にもつながると思うのです」(堀口氏)
一方で、一度自分の心の奥にある想いに気付いても、仕事に追われるうちにまた忘れてしやすいもの。今後も、積極的に発信を続けていく予定だ。
「人生のライフステージによって、大切にする想いも変わるはず。そして、1年目に感じた想いはとても貴重です。
忙しさに追われる中でも、たまには立ち止まって、自分の人生と仕事のつながりを考えてみる。今後もそんな機会を提供し挑戦し続けられる組織を目指していきたいと考えています」(堀口氏)
執筆:田中瑠子
撮影:後藤渉
デザイン:久須美はるな
編集:金井明日香