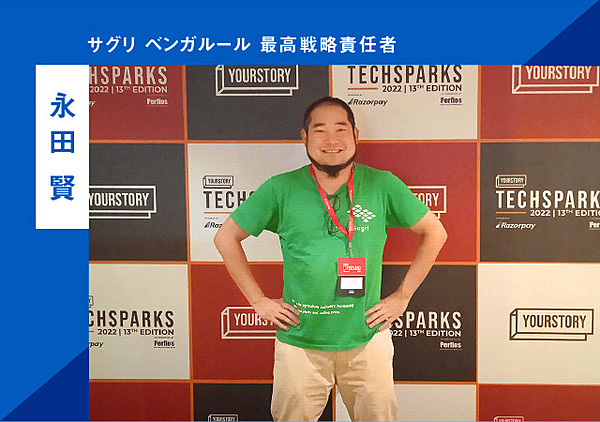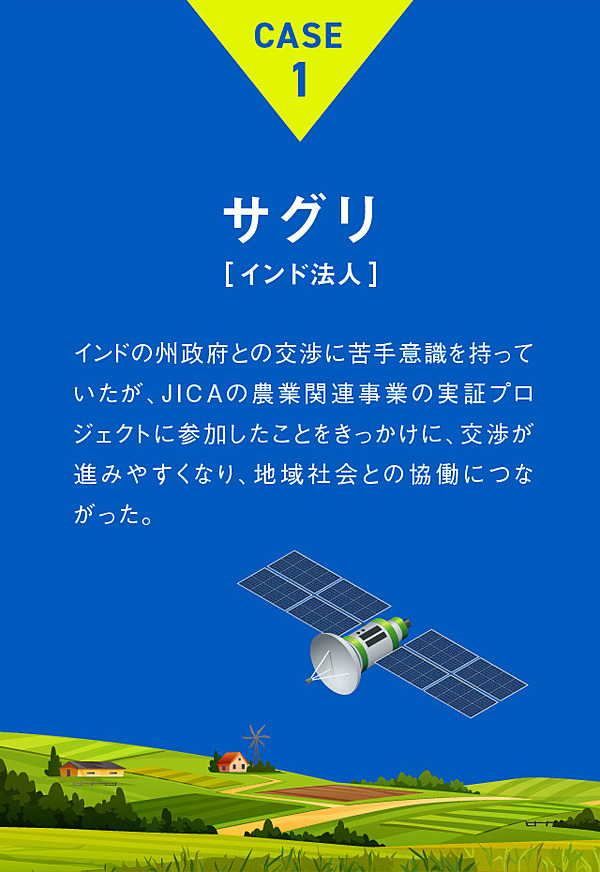2023/1/10
【奮闘】途上国課題は「ビジネス」で解決できるのか
NewsPicks Brand Design Editor
解くべき課題が山積する「開発途上国」は、日本企業にとっても、大きな可能性を秘めたビジネスフィールドだ。
一方、国内や先進国をメインに事業を行う企業にとって、途上国ビジネスの「リアル」は想像し難いもの。
現地で自社サービスのニーズはあるのか、言語や文化の壁はどう乗り越えればいいのかなど、懸念は尽きないだろう。
そこで今回は、開発途上国で事業や実証実験を展開する企業と、開発途上国の課題解決を目的に、民間企業との積極的な協働を行う、独立行政法人 国際協力機構(JICA)にインタビュー。
開発途上国でも大きな期待が寄せられるデジタル技術の話を中心に、JICAと民間企業との協働による、現地ビジネスのリアルを聞いていく。
- 企業との協働で「途上国課題」を解決
- ピボット、アイデア盗難。途上国進出のリアル
- 「専門人材」とのつながりが結果を生み出す
- 日本企業よ、巨大マーケットを目指そう
企業との協働で「途上国課題」を解決
SDGs(Sustainable Development Goals)という言葉が広く知られるようになって久しい。
しかし、このSDGsが2015年に国連総会で採択される以前、MDGs(Millennium Development Goals)、「ミレニアム開発目標」が存在していたことをご存じだろうか。
SDGsが先進国を含むすべての国を対象とする開発目標である一方、MDGsは極度の貧困と飢餓の撲滅など、主に開発途上国が抱える課題に関する目標として2000年の国連ミレニアム宣言を基に制定された。
このMDGsで一定の成果を収められたことが、2015年のSDGsの採択にもつながっている。

iStock:utah778
MDGsからSDGsへの転換のポイントは、対象国が広がっただけではない。
MDGsは国連や各国の開発協力機関など一部の伝統的なアクターによって達成されたが、SDGsは民間企業や教育機関、NPOなどを巻き込む「開かれた」開発目標として制定されたのだ。
このSDGsの達成に向け、日本でも積極的なアプローチを展開する機関の1つが、独立行政法人国際協力機構、通称JICAだ。
同組織は、日本のMDGsの達成においても中心的な役割を果たしたが、SDGsへの転換を受けて、民間企業や大学など共創の思いを同じくする外部のパートナーとの協働を含めた、オープンな取り組みを加速させている。
JICAと言えば「海外協力隊」でその存在を知る人も多いと思うが、その役割を一言で表すなら「開発途上国における社会課題の解決」。
歴史は古く、1962年に誕生した特殊法人 海外技術協力事業団にルーツを持ち、さまざま組織再編を経て2008年に現体制が確立された。
50年以上もの間、途上国の課題解決に向き合い続けてきた。
そんなJICAが、SDGsの達成を目指し、開発途上国の課題解決の手段として大きな期待を寄せるのが「デジタル技術」。
ITU(国際電気通信連合)によれば、2022年時点で約53億人、およそ世界人口の66%がインターネットを使用。開発途上国に限っても人口の56%がインターネットにアクセスできる状況にある。
こうした現状を踏まえ、JICAもデジタル技術の応用に力を入れる。
2020年6月にはデジタルに関する専門部署、STI・DX室を立ち上げ、医療や防災、農業といった注力分野を定めて、開発途上国の課題解決に関する取り組みを展開。
民間企業を中心とした外部のパートナーとの協働を念頭に、2022年4月にはデジタル技術に関連した連携を迅速かつ柔軟に促進するため、STI・DX室内に「DXLab」を新設すると発表した。
STI・DX室副室長の宮田真弓氏は、一連の背景をこう語る。
「開発途上国の課題は多岐にわたり、その一つひとつがあまりにも大きいため、私たちだけでは太刀打ちできません。だからこそ、民間企業の力が必要なのです。
昨今、ビジネスの世界においてはESG投資の拡大などを背景に、社会課題の解決を目標とする企業やサービスも増えています。
こうした流れを受け、国外への技術・ノウハウ展開などさまざまな面で民間企業とJICAが手を取り合い、シナジーを生みながら途上国の課題解決にもつながる仕組みを目指しました」(宮田氏)
ピボット、アイデア盗難。途上国進出のリアル
では、具体的に民間企業とJICAはどう協働しているのか。
まず注目したいのが、スタートアップ企業との事例だ。
兵庫県発のサグリ株式会社(以下、サグリ)は、人工衛星が撮影した映像データなどをもとに、農地の耕作状況や農地の生育・土壌状態を「見える化」するサービスを開発する企業。
2018年の創業以来、農業のDXに貢献している。
そんなサグリは、創業の翌年の2019年にインド南部のベンガルールに進出。JETRO(日本貿易振興機構)が現地で推進する「日印スタートアップハブ」第1号として採択された。
現地法人のトップを務める永田賢氏は、インド進出の経緯についてこう語る。
「インドの就農人口は約7〜8億人。人口の約3分の2は農業に従事している非常に巨大なマーケットです。
それにもかかわらず、ノウハウや技術が発達していないことで効率的な農業が行われていない上に、高利貸しの金融事業者に依存し、多くの農家の資金繰りがうまくいっていません。
そこで、自社が計測する農地のデータを応用し、農業従事者に小口資金を提供して、その利息によって利益をあげる『マイクロファイナンス』事業を立ち上げたいと考えました」(永田氏)
だが、結論から言えばこの計画は当初はうまくいかなかった。
サグリが事業を展開しようとしたタイミングで、政府がコロナ禍に端を発する借金のモラトリアム(支払猶予)を発令。これにより、資金回収の見込みが立たなくなってしまったのだ。
その後、現地の金融機関や農協などマイクロファイナンス事業者に農地データを提供する事業へとピボット(方針転換)。
今では、現地でスマート農業に関するデータ事業も立ち上げ、インド法人単体で年内には黒字化を見込めるまで成長した(2022年11月時点)が、道のりは平坦なものではなかった。

2022年現在のインド事業の様子。(提供:サグリ)
「途上国ビジネスではあるあるかもしれませんが、本当に困難の連続でした。
コロナ禍が続いてただでさえ事業が行き詰まっているのに、現地のスタッフと金銭トラブルになったり、創業メンバーが抜けてしまったり、事業アイデア自体を何回も盗まれたり……。
一時は、絶体絶命の状況でしたね」(永田氏)
事業ピボットが功を奏し、今でこそ現地のさまざまな機関と連携するサグリだが、当初は事業を円滑に進めるために欠かせない州政府との交渉にも苦労した。
何十州にもアプローチしたが、そもそもアポを取ることすらできず、運良く取れたとしても、まったく相手にしてもらえない。
そんなサグリに変化のきっかけをもたらしたのが、JICAだった。
2021年、JICAがインド北部のヒマーチャル・プラデシュ州で実施する、農業関連事業の実証プロジェクトへの参画が決定。
その後の提携がインドにおけるサグリの事業を好転させることになる。

インド現地での提携の様子。(提供:サグリ)
「振り返ると、僕たちは、政府などと交渉する際の『礼儀作法』がまったくわかっていなかったんです。
だから、交渉すらさせてもらえなかったのですが、JICAはその長年の経験から、どのように交渉を進めれば良いかを熟知している。
なので、実証プロジェクトは驚くほどスムーズに進みましたし、その実績を持って州政府との連携を取り付け、事業展開の活路を見出すことができたんです」(永田氏)
JICAのホームページに実証実験プロジェクトの概要が掲載されたことで、インドでの連携を視野に入れた日本企業との協業が開始。
また、UNDP(国際連合開発計画)が運営するデジタル技術についてのカタログにも事業が掲載され、国際的な評価と認知を得るきっかけにもつながった。
「現在、当社ではケニアでも事業を進めていますが、JICAの職員からケニアの研究機関に勤める方を紹介していただき、共同研究協定を締結する直前までこぎ着けることができました。
JICAが持つつながりと信頼があってのことだと思います」(永田氏)
「専門人材」とのつながりが結果を生み出す
JICAが持つ経験と知見は、大企業の新規事業の実証実験にも生かされている。
ソフトバンクの事業の1つである「e-kakashi(イーカカシ)」は、日本国内ですでに商用利用されている、アグリテックサービスだ。
田畑の温度や湿度、日射量といった環境データを「見える化」するだけではなく、作物を襲う病気の発生リスクを分析し、対応策などを提示。品質や収穫量の向上をサポートする。

ブラジルのほ場に設置された「e-kakashi」用ゲートウェイ。(提供:ソフトバンク)
海外でのサービス展開を目指し、現在ではエクアドル、ブラジルなど9カ国で検証を進めているe-kakashiだが、その第一歩となったのが、2017年に開始されたコロンビアでの実証実験だ。
きっかけは、JICAが実施の一翼を担う地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム、「
SATREPS(サトレップス)」に採用されたこと。
e-kakashiの事業責任者である戸上崇氏は、採用の経緯をこう振り返る。
「恩師からSATREPSプロジェクトを推進している方をご紹介いただいたのが、2015年の8月頃でした。
国内でe-kakashiの商用利用をスタートさせたのが2015年の10月ですから、事業を本格稼働させる前に、海外での実証実験のお話をいただいたことになります。
まだ事業が立ち上げられていない時点での打診だったので、驚くとともに期待をいただけていることにありがたさを感じました」(戸上氏)
その後、SATREPSやコロンビアの稲作団体のメンバーを招いた視察やディスカッションを繰り返し、2年後の2017年にコロンビアでの実証実験がスタート。
海外における初の実証実験だったが、意外にも「大きな困難はなかった」と戸上氏。その理由は、プロジェクトの進め方にある。
戸上氏によれば、データを活用した栽培支援プロジェクトの場合、最初のフェーズは「データ収集」で、2〜3年をかけ、データを集め、分析し、その後のアクションを検討していくのが「一般的な進め方」。
だが、コロンビアにおける実証プロジェクトでは、データを蓄積する前に、植物科学に基づいたアクションプランの仮説を構築。
その後、データを収集しながらプランを微調整することによって、約1年というスムーズな検証を実現したという。
スピーディーに事が運べた理由の1つとして、「共同研究だったことは大きい」と戸上氏。
実証実験では「高い専門性を持った人材の確保」ももちろん大切だが、国や組織の垣根を超えて、さまざまな知を組み合わせることの重要性を改めて感じたそうだ。
こうしたコラボレーションを起こしていく上で、鍵になったのがJICAだ。
「最終的には病害虫の発生予測にも取り組み、一定の精度を出せることが確認できました。
その際、協力してくれたのは、JICAとつながりのあるコロンビアの研究所のみなさんです。
現地の方々の協力がなければ、円滑に実験を進めることはできなかったと思いますし、JICAと連携して、そのコネクションを生かせる点はアドバンテージだと思いました」(戸上氏)
日本企業よ、巨大マーケットを目指そう
今後も、日本と開発途上国の「橋渡し役」が期待されるJICA。
今回取材した2社は農業関係だが、医療、水道、行政などさまざまな分野のデジタル技術支援に取り組んでいく予定だ。
だが、連携にあたって、企業にとってちょっとした弱点もある。それは、共同プロジェクトの企画や立案までのリードタイムが長いこと。
JICAのプロジェクトでは公的資金を使用するため、やや煩雑な手続きを精緻に進めることが求められるが、スピード感を重視する企業にとっては負担となる可能性もある。
だが、「JICAでは一連の手続きに要するコストを下げるための制度改善などを進めており、より短いリードタイムでプロジェクトを立ち上げられる環境が整いつつある」と先出の宮田氏は語る。
特にDXLabでは、よりスピーディーに企業との協働を進めるための体制を構築しており、早ければ数ヶ月で実際に海外での実証実験をスタートさせることができるそうだ。
無論、海外でのプロジェクトに取り組むとなると、当然それなりのリソースが必要になるだろう。
しかし、一定のリソースをかけてでも、成長性が期待される開発途上国に飛び込むメリットは大きい。JICAが提供するのは、そんな新たなマーケットへの「入り口」だ。
海外に約100か所の拠点を構え、JICAは50年以上もの間、各国の課題に向き合い続けてきた。その事業規模は1兆5,361億円(2021年度)にものぼり、現地との深いコネクションを持っている。
「これまでもJICAは、インドの首都・デリーの地下鉄建設やインドシナ半島4カ国を結ぶ東西経済回廊の整備など、国や地域に大きなインパクトのある案件に多く協力してきました。
これらには、1日あたり数万人・数万台単位のユーザーがいるため、デジタル技術やデータの活用の観点で見ても、多くの可能性を秘めていると思います。
もちろんプロジェクト内容や現地関係者の意向にもよりますが、こうした日本の協力アセットを活かし、社会課題解決を志向する企業や研究機関等とともに、我々との共創だからこそできる事例を創出したいですね」(宮田氏)
この半世紀ほどでマーケットはまたたく間にグローバル化した。
しかし、企業が「海外拠点を設立したこと」が、一定のニュースバリューを持っている現状は、海外進出のハードルの高さを逆説的に物語っている。
だが、今回取材した企業たちは、そのハードルを越えた。それには、各社の情熱と技術のみならず、海の向こうを知り尽くすパートナーの存在も大きい。
一筋縄ではいかない開発途上国への進出。だが、こうした連携によって、可能性はさらに広がっていくのだろう。
執筆:鷲尾諒太郎
撮影:小島マサヒロ
デザイン:zukku
編集:高橋智香